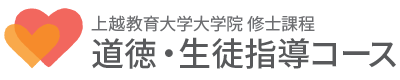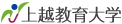修論
修士論文作成スケジュール

道徳・生徒指導コースでは、指導教員の指導を受けながら各自で修士論文を作成します。修論の指導は、各ゼミにおいて行います。本コースでは,入学直後から約2週間の研究室訪問期間を設定し,新入生にすべての教員の研究室を回ってもらいます。そのうえでゼミの所属希望を提出してもらい,コース教員会議において調整し,履修登録期限に合わせて決定します。
なお,1年次4月時点での所属ゼミ決定後も,院生の希望にもとづいて,ゼミを変更することが可能です(教員会議での了承が必要です)。

ゼミが決まったら,いよいよ本格的に修士論文作成に向けた研究が始まります。修士論文が正式に合格となるまでには,3回の発表会で発表したあと,論文を提出して審査を受け,口述試験に合格する必要があります。合格した修論については,最終の「修士論文発表会」で成果を発表します。
| 4月下旬 | 「研究計画調書」・「指導教員希望」提出 指導教員(ゼミ)決定 |
|---|---|
| 5月上~中 | M2第二次構想発表会・参加 |
| 6月下旬 | (全学)専攻・コース変更願受付 |
| 7月中旬 | 指導教員変更希望受付 |
| 10月上~中 | M2中間発表会・参加 |
| 11月上~中 | 第一次構想発表会 |
| 12月上旬 | (全学)専攻・コース変更願受付 |
| 2月下旬 | M2修士論文発表会・参加 |
| 5月上~中 | 第二次構想発表会 |
|---|---|
| 10月上~中 | 中間発表会 |
| 10月31日 | 「学位論文題目」提出 |
| 1月10日 | 修士論文提出 |
| 1月下旬 | 口述試験 |
| 2月上旬 | 口述試験(再試験) |
| 2月下旬 | 修士論文発表会 |
免P生(3年課程)の場合
長期履修(3年課程)の免P生に関しては,教員免許取得のための多忙さを考慮して,次のような2つの発表パターンを設定しています。指導教員と相談のうえ,各自のスケジュールを決定してください。
パターンA
(教育実習で多忙な2年次に,教職科目履修に集中するパターン)
| 1年次 | 11月 | 第一次構想発表会 |
|---|---|---|
| 2年次 | 11月 | (1.5次構想発表会:院生の自主企画) |
| 3年次 | 5月 | 第二次構想発表会 |
| 10月 | 中間発表会 | |
| 1月 | 修士論文提出 |
パターンB
(授業の多い1年次に,教職科目履修に集中するパターン)
| 1年次 | (修論関連公式行事を設定していない) | |
|---|---|---|
| 2年次 | 11月 | 第一次構想発表会 |
| 3年次 | 5月 | 第二次構想発表会 |
| 10月 | 中間発表会 | |
| 1月 | 修士論文提出 |
なお,「第二次構想発表」と「中間発表」は,原則として修士論文を提出する年度に行います。発表の間隔が空きすぎて,内容が大きく変化してしまっては,研究の進度をチェックできないからです。また,「第二次構想発表」・「中間発表」を済ませているのに,2年で修論を提出しなかった場合,3年次は「中間発表」を再度行ってください。(「第二次構想発表」は,ケースバイケースです。)
前期修了の場合は,「第二次構想発表」の際に中間発表をしてもらいます。
最近の修士論文タイトル
(道徳生徒指導コースは設置されたばかりです。ここに記載の論文タイトルは、これまで主として生徒指導総合科目群で作成されたものです。)
- 「高等学校公民科「倫理」の授業に関する研究―高等学校における道徳教育を視点として―」
- 「教師の仕事の意欲を向上させる「厳しい助言」の様相―中学校教師へのインタビューによる質的研究―」
- 「青年の友人関係を巡る学術的な言説形成についての哲学的考察」
- 「青年前期における友人関係と思いやりの関連」
- 「Philosophy of Childrenを取り入れた道徳授業の理論と実践」
- 「日本と中国の道徳教育に関する比較研究」
- 「教師と保護者による子どもの行動変容を促す連携に関する研究―交流分析を援用した学校教育相談に着目して―」
- 「中学校の生徒指導におけるコーディネーション機能の向上に関する研究―富山県カウンセリング指導員制度の有効性と課題に着目して―」
- 「中学校教師の指導行動とビリーフに関する研究―生徒指導上の問題を抱える生徒の事例を通して―」
- 「いじめ加害対応における学校と学外機関との連携に関する研究」
- 「大学生における「居場所がない」>と「実存的空虚感」との関連―実存分析による居場所の捉え方に着目して―」
- 「キャリア教育の視点を用いた高等学校物理教育に関する研究―物理教育の歴史的変遷に注目して―」
- 「中学校における部活動指導内容に関する研究―キャリア教育の「基礎的・汎用的能力」育成を視点として―」
- 「高等学校普通科における進路指導の充実に関する研究―キャリア学習プログラムカタリ場を通して―」