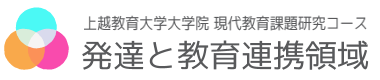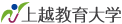入試
入試の概要
入試は,筆記試験と口述試験により行います。
筆記試験

以下に示す2領域にかかわる4問の中から自由に2問を選択して解答します。同じ領域から2問を選択することもできます。
1 教育学
(教育の制度・経営・社会・思想に関すること)
2 教育心理学
(児童生徒の学習と発達の心理的側面に関すること)
口述試験

主としてこれまでの教育実践及び入学後に取り組みたい実践的課題等について,入学希望等調書を参考にして試問します。
なお,筆記試験を課さない派遣教員及び教職経験者には,教育学・教育心理学に関する知識についても試問します。
配点
| 筆記試験 | 200点 |
|---|---|
| 口述試験 | 300点 |
各種制度への対応
| 教育委員会からの派遣教員及び3年以上の教職経験者 | 筆記試験を課しません |
|---|---|
| 機関長(学長又は学部長)から推薦を受け出願する者 | 筆記試験を免除します |
| 教員採用試験合格者 | 筆記試験を免除します |
※応募条件等,詳細は「学生募集要項」を参照してください。
なお,筆記試験を課さない受験者に関しては,口述試験の際,それぞれの制度に係る提出書類も参考にして試問します。
試験準備のポイント
筆記試験

筆記試験では,大学院での学修に必要な,教育学・教育心理学の基礎的知識と,それを論理的に記述する表現力を見ます。出題の際,私たちがおおよその目安としているのは,教員採用試験(教職教養)の教育学・教育心理学領域でよく出題されている程度の問題範囲と知識レベルです。
本学大学院には,学部段階で教育とは無関係の分野を専攻してきた学生も多く入学してきますので,入試段階でそれほど専門的な学力を要求してはいません。とはいえ,教育学や教育心理学の基本的なものの見方・考え方がわかっているかどうかは,入学後の学修に大きく影響しますので,教員採用試験レベルの勉強はしてきてください。
もちろん,実際に出題する問題はちょっとひねった問題にしてあります。しかし,筆記試験で求めているのはそのレベルの基礎知識だということを頭に入れながら,勉強を進めてください。
領域ごとに,もう少し具体的に書いておきます。
1. 教育学
- 教員採用試験の教職教養の本にひととおり目を通し,教職に関する基礎的な知識は知っておいてください。
- 新聞や白書等を読んで,最近の教育事情・動向を把握しておくとよいと思います。
2. 教育心理学
- 教員採用試験(教職教養)の教育心理の参考書に出てくる程度の基礎知識について勉強してきてください。
- 実験結果の表やグラフの読みとりもよく出しています。
口述試験

口述試験では,一般的な事項のほか,主に学校実習において取り組むテーマや領域についてお聞きします。入学希望等調書に記載した内容を参考に質問しますので,詳しくは,「入学希望等調書の書き方」を読んで,準備してきてください。
入学希望等調書の書き方

入学希望等調書は,口述試験のときに面接担当教員が参照し,それをもとに質問する重要な資料です。ですので,「その時点で可能な限り具体的に」まとめるようがんばって準備してください。
教職大学院での学修は,学校実習(学校支援プロジェクト)が中心となりますが,それは教育実習のような見習い,あるいはインターンシップではなく,連携協力校の先生方と一緒に教育実践をしっかりと見つめ,多様な視点から客観的・分析的に課題を追究する活動が主です。
ですから,「発達と教育連携」領域では,入学生にはできるだけ明確な研究テーマをもって入学してほしいと願っています。そのことはまた,支援校の決定の際にも重要な参考情報となります。
そこで,入学希望等調書には,現時点で自分がどのような問題に関心を持っているのか(問題意識),またそれをどのように明らかにしていこうと考えているのか(研究計画),がわかるように書いてください。
入学希望等調書には,「これまでの教育実践(教育実習等を含む)や教育研究で取り組んできたこと」と「入学後に取り組みたい実践的課題や伸ばしたい力」の2つの記入欄がありますが,次のように記載してください。
1. 入学後に取り組みたい実践的課題や伸ばしたい力
ここには,今述べた,入学後に追究したい研究テーマについて記入してください。「実践的課題」という制約には,特にこだわる必要はありません。最近の教育改革の流れに無理に合わせる必要もありません。現時点での自分の問題意識を,自分の言葉でしっかり語ることが,何より大切です。
2. これまでの教育実践や教育研究で取り組んできたこと
ここには,上記の研究テーマに関連したこれまでの取り組みに絞って,記入してください。卒業研究での取り組みや,これまでに読んだ本から何を学びどう考えてきたか,実際にどんな事例を経験しどう感じたかなど,具体的に挙げてください。
「現時点での自分の考え」でいいので,できる範囲内でしっかり考えて,調書を作成してください。不足している情報については,口述試験で詳しくお聞きします。