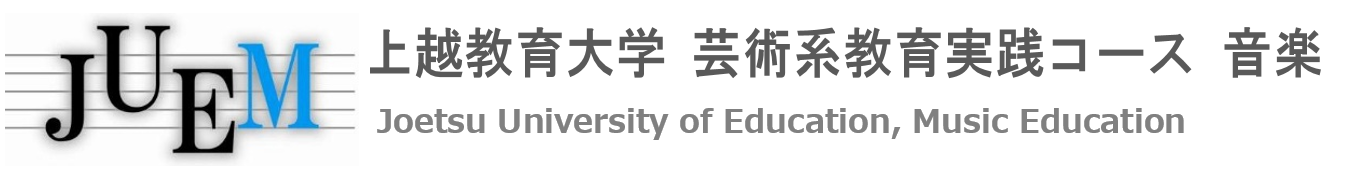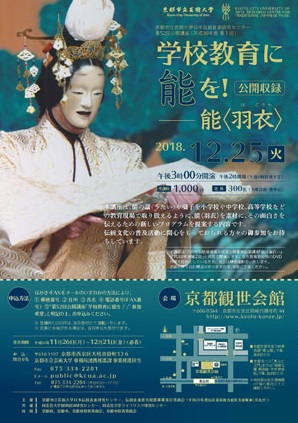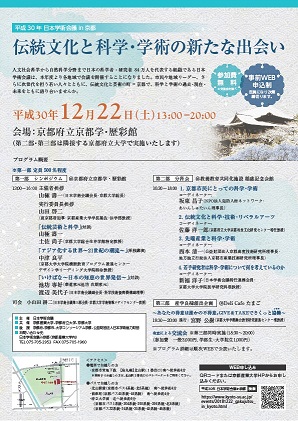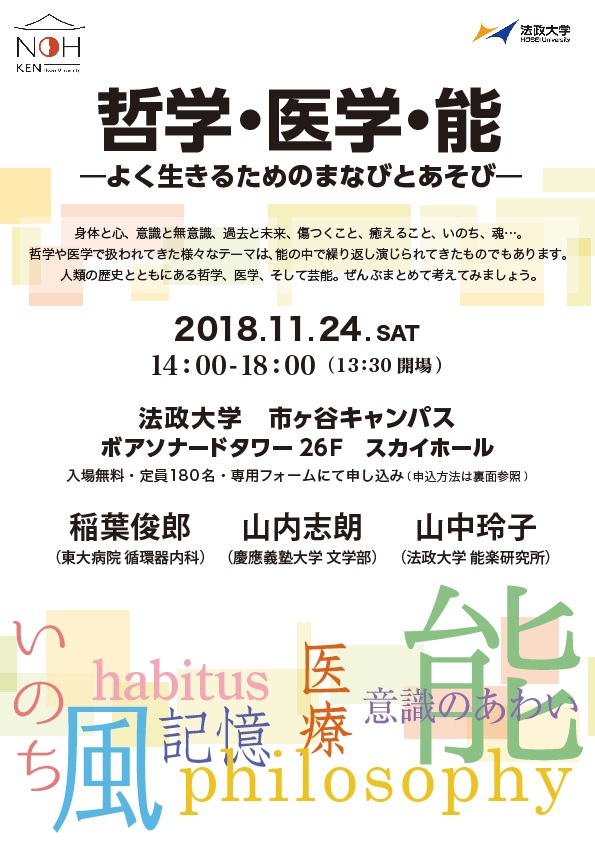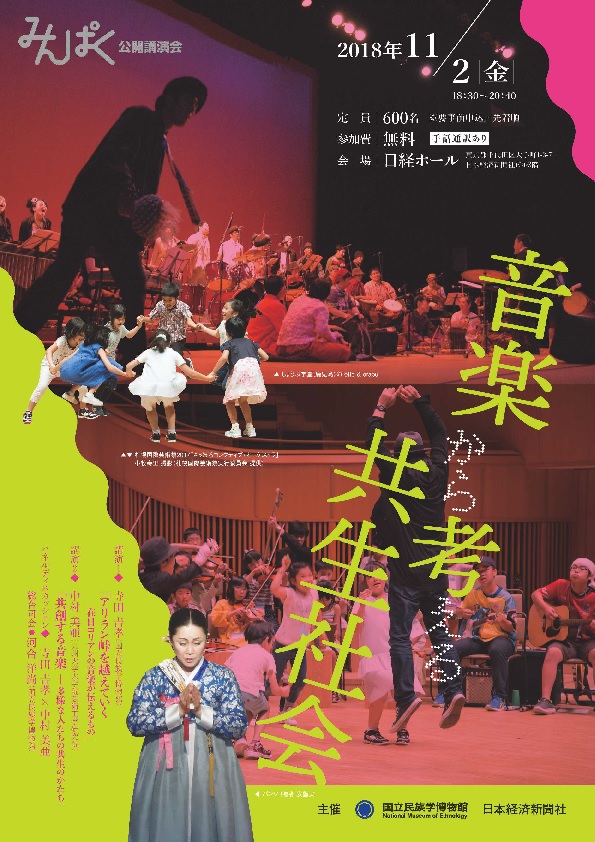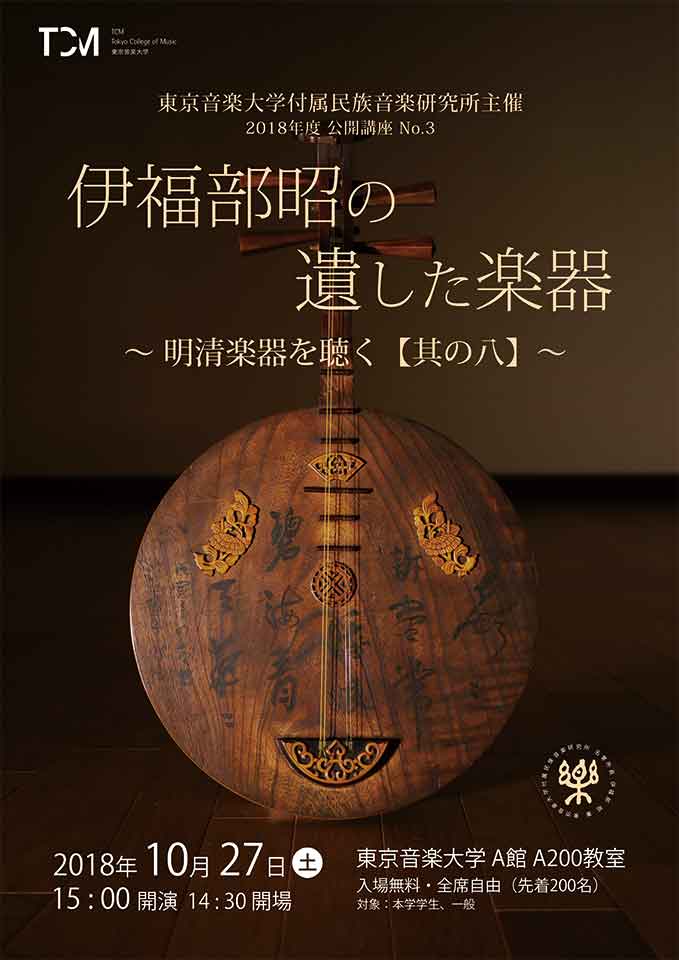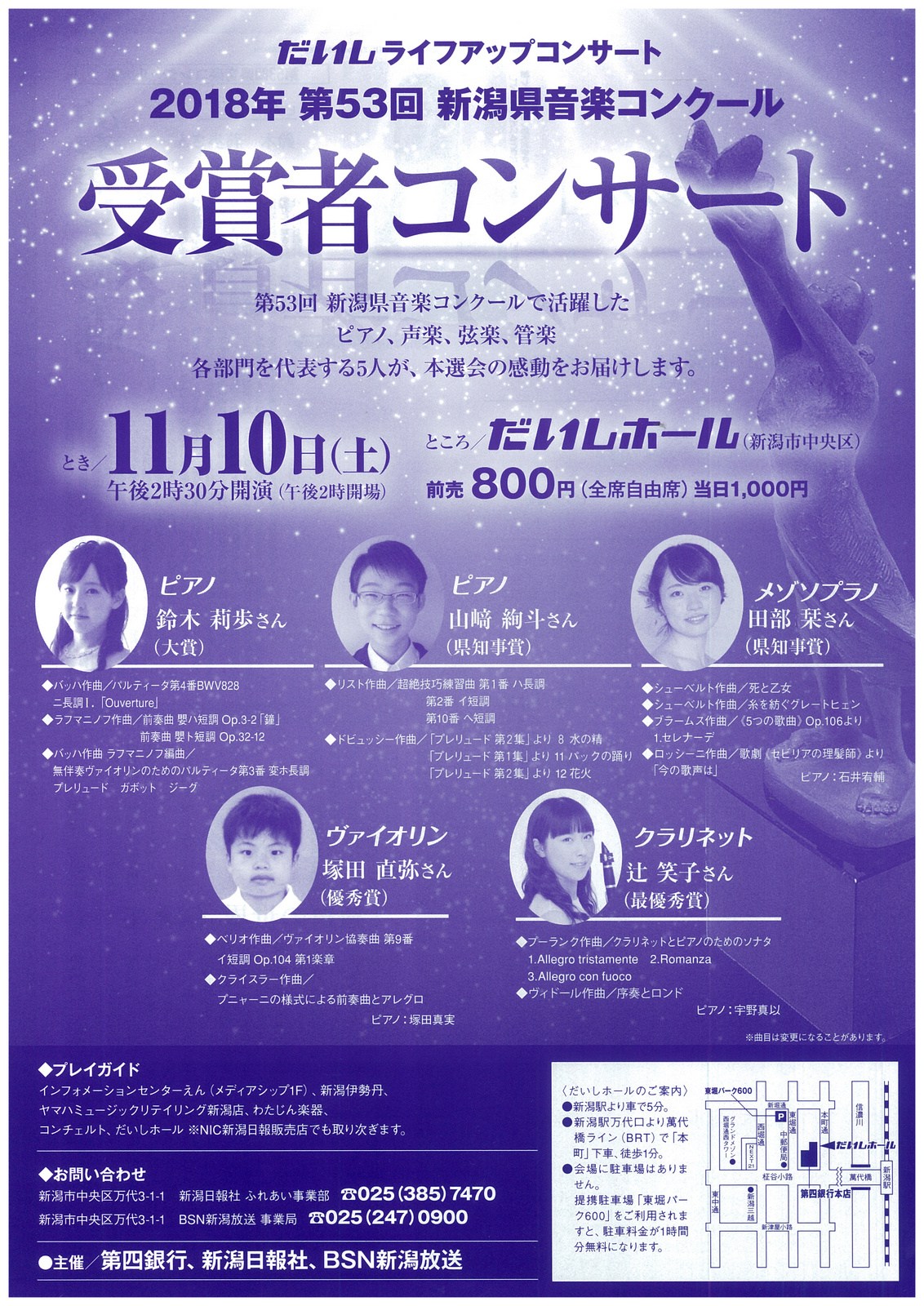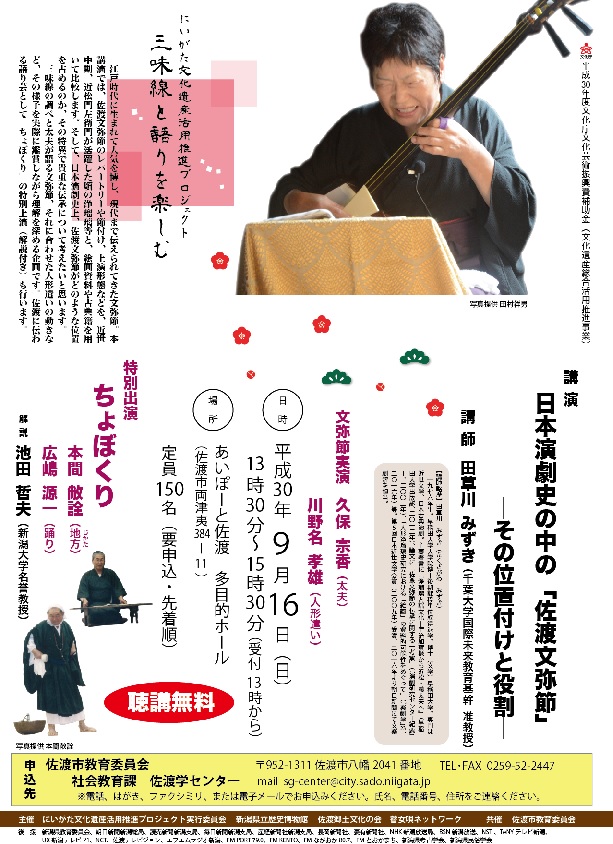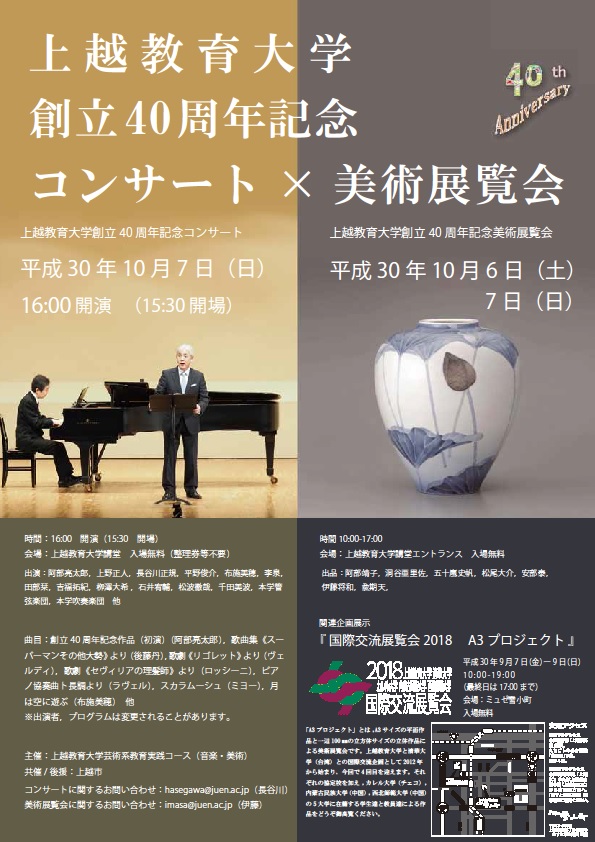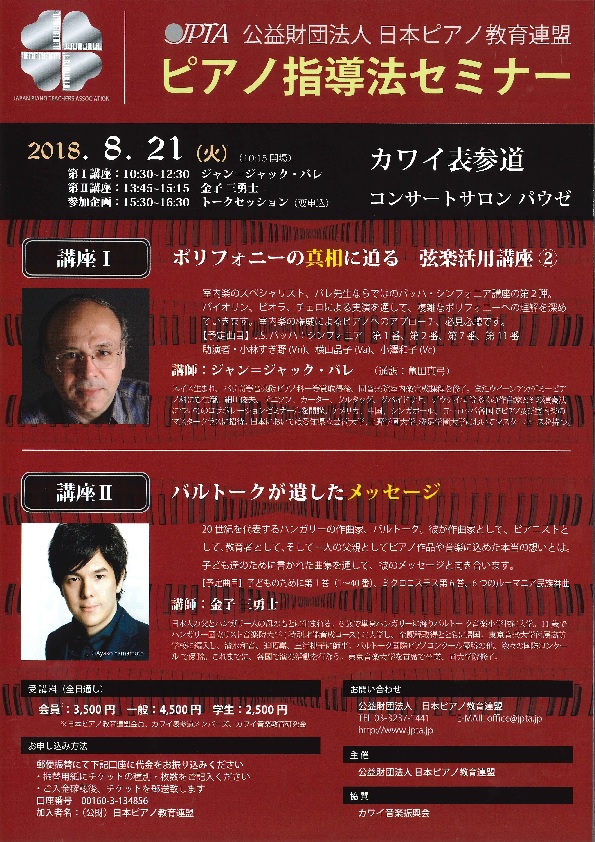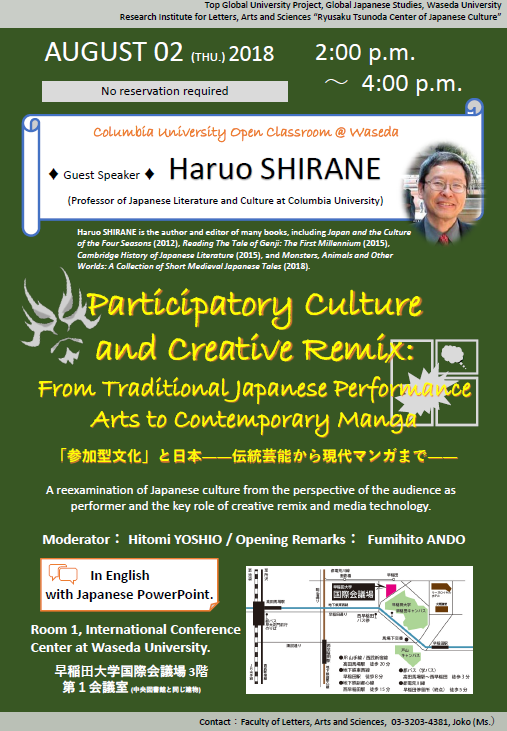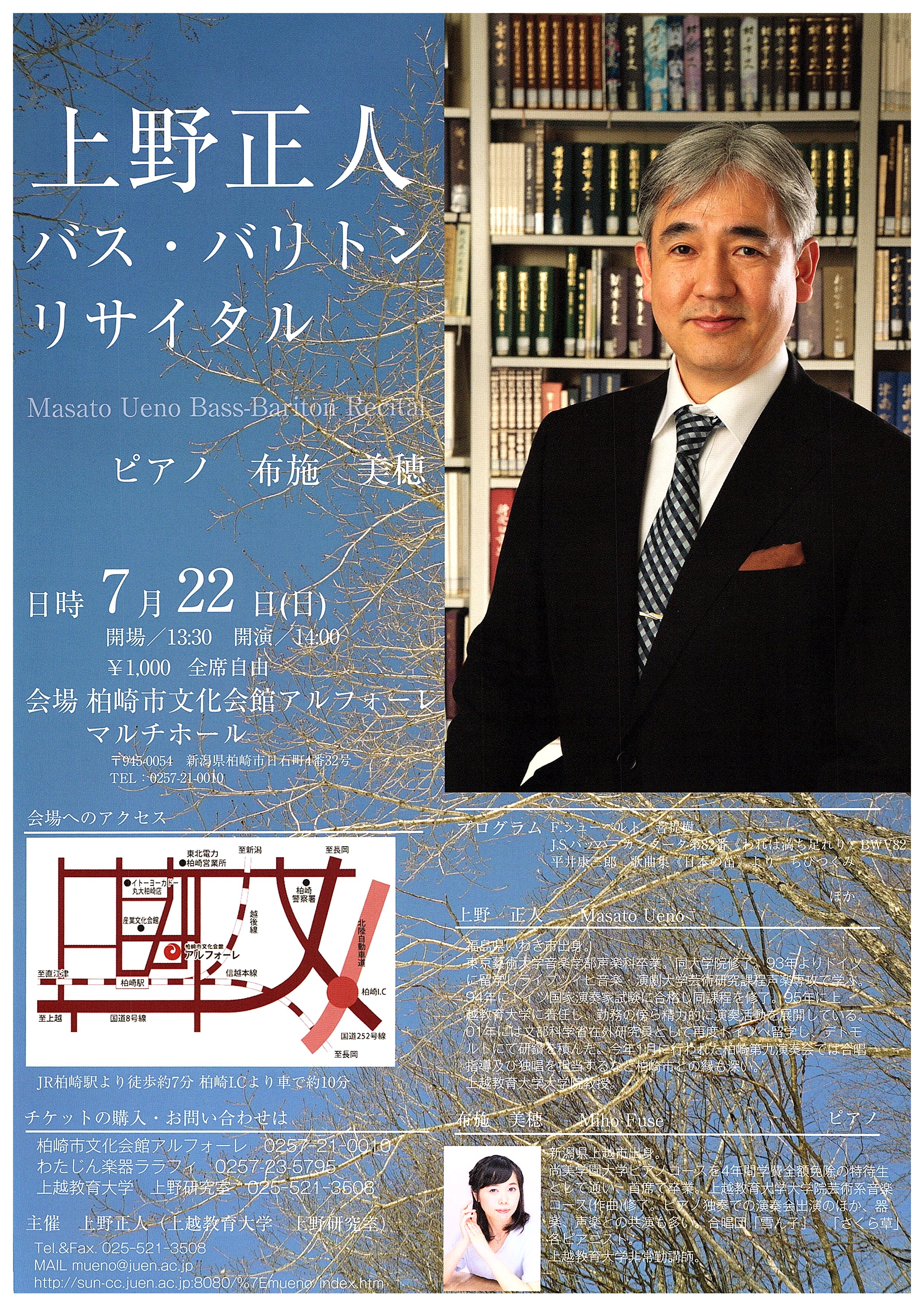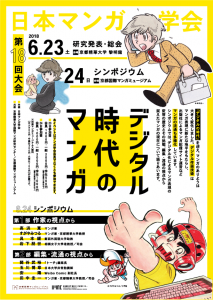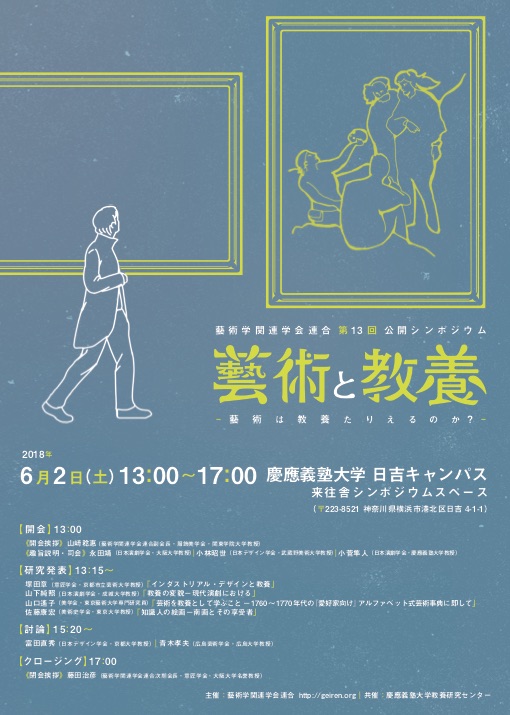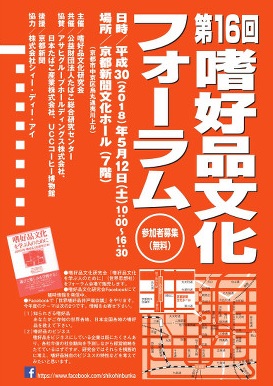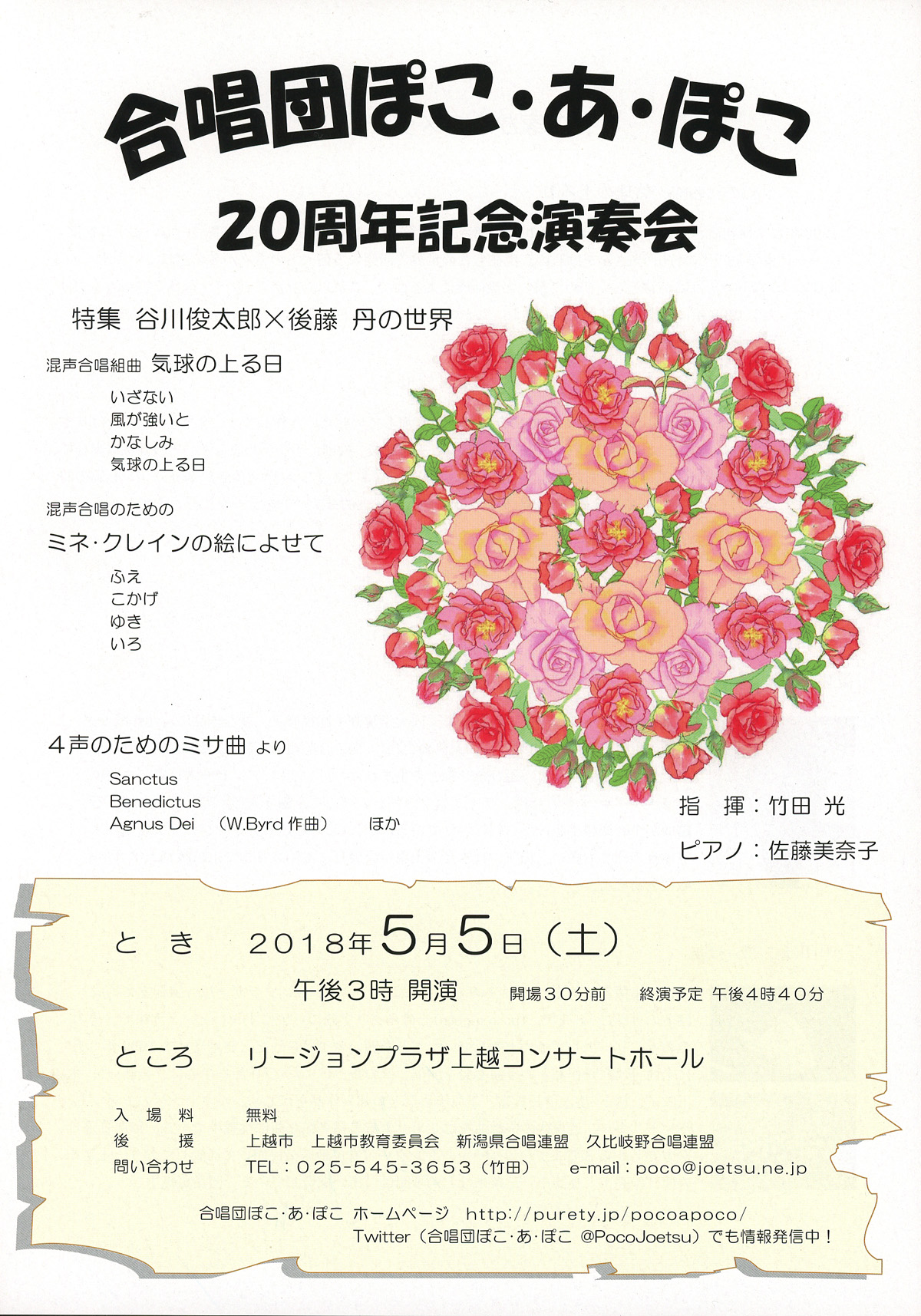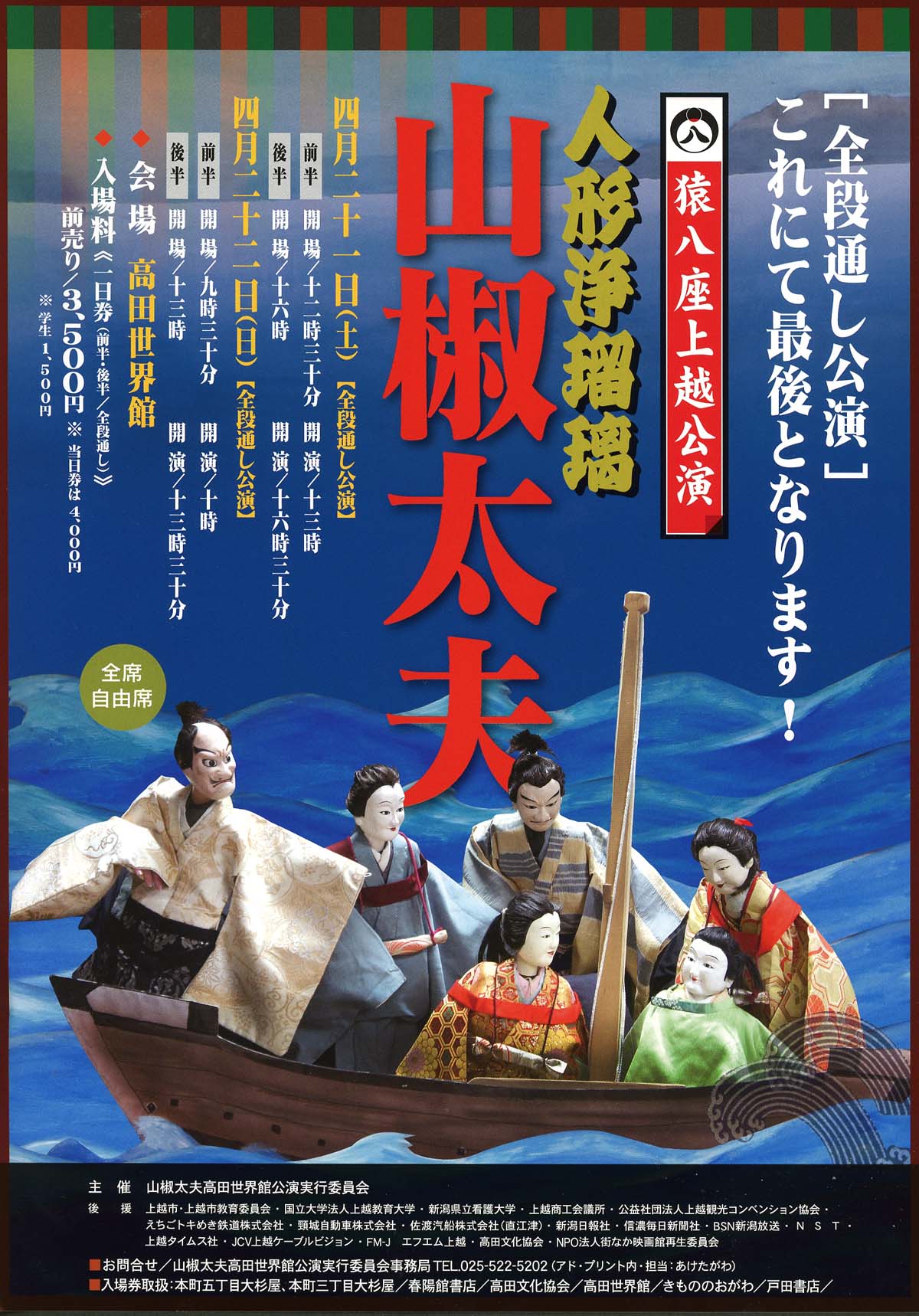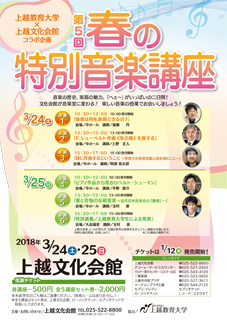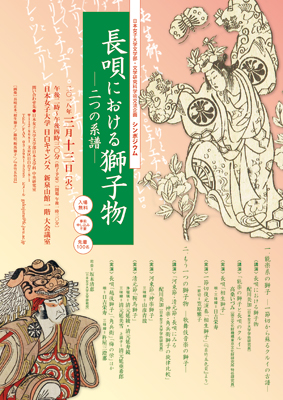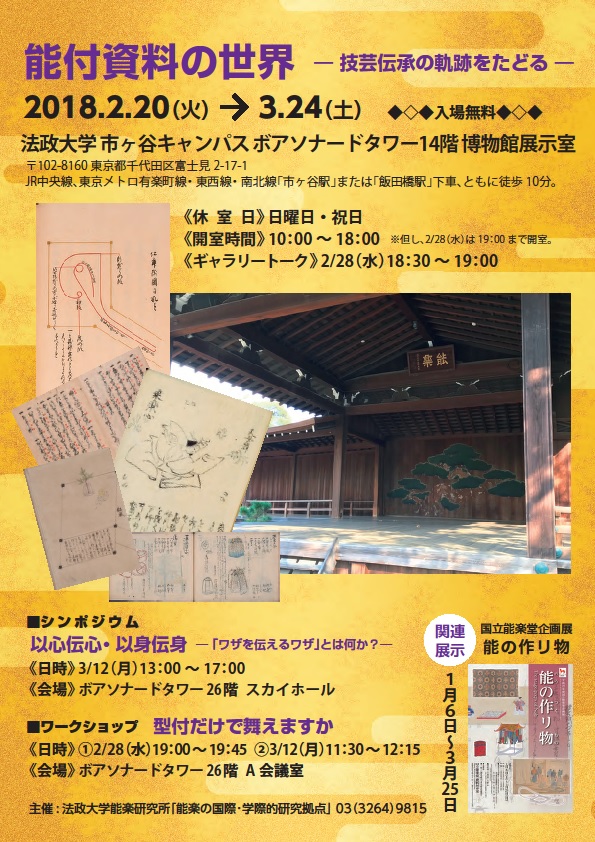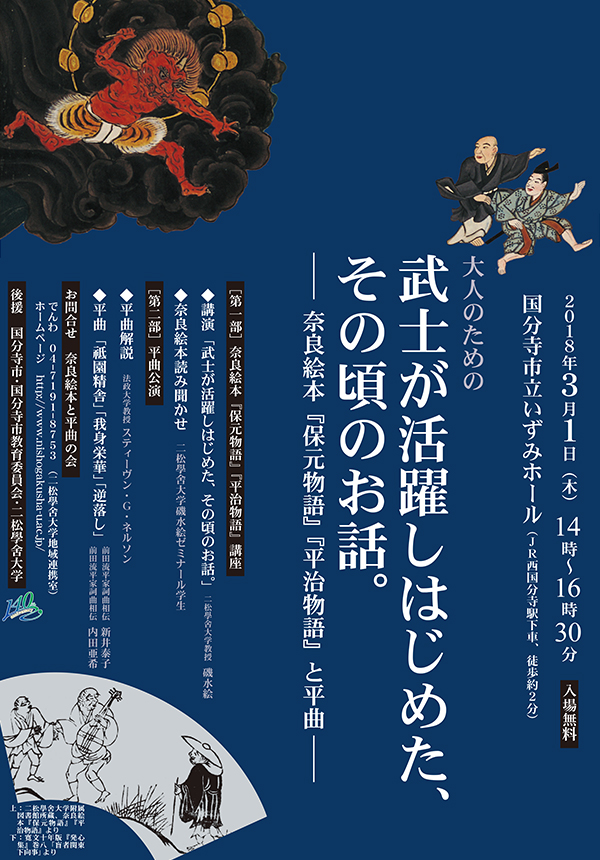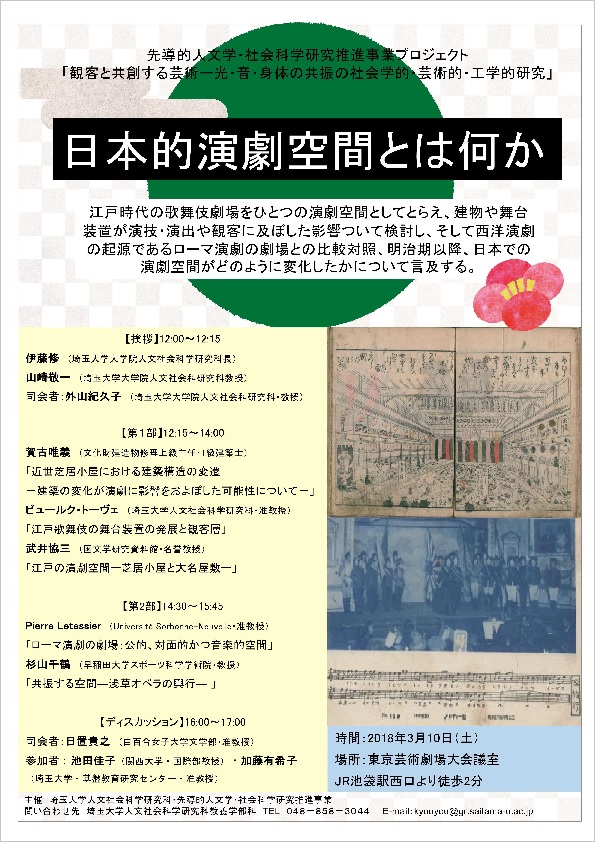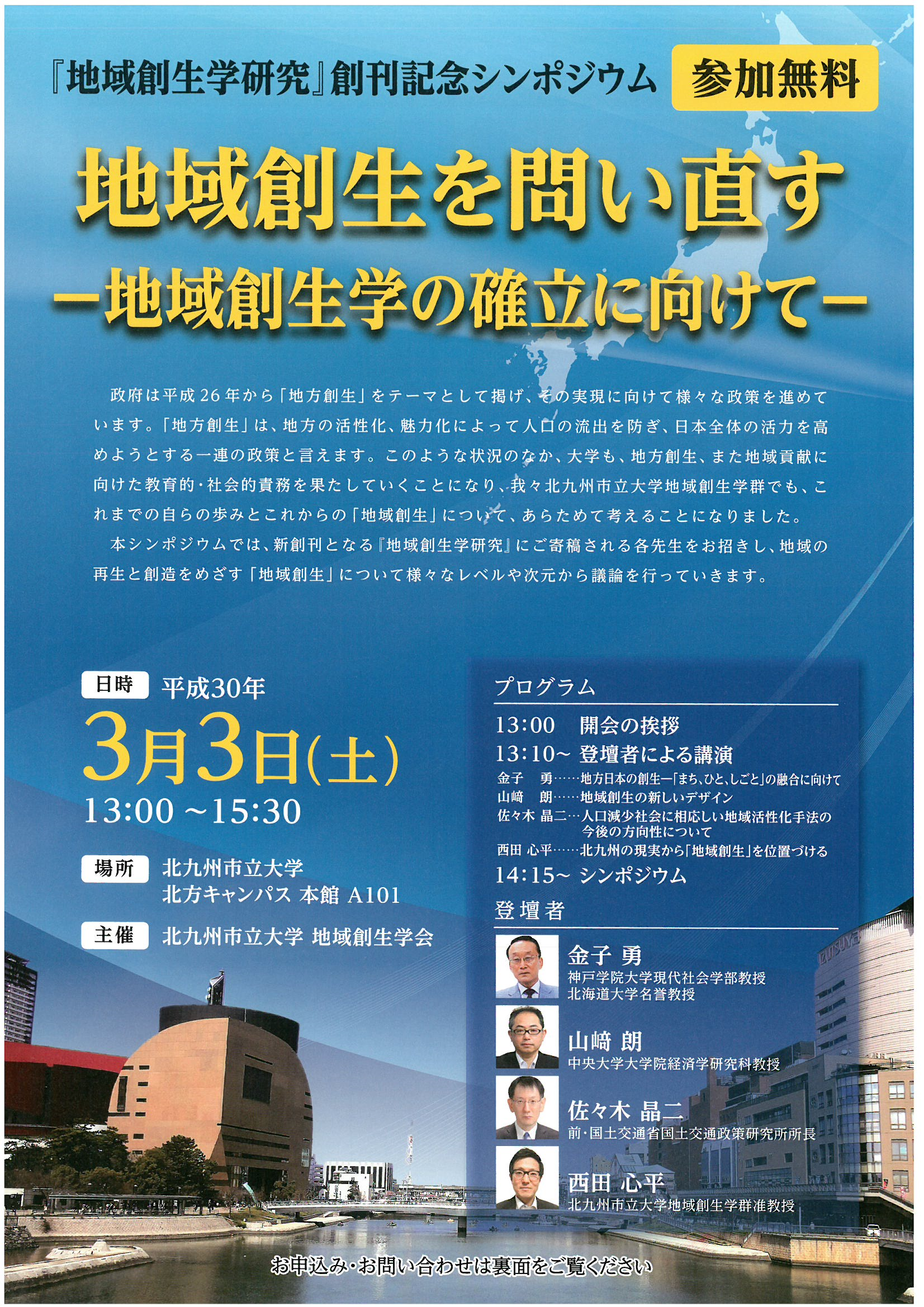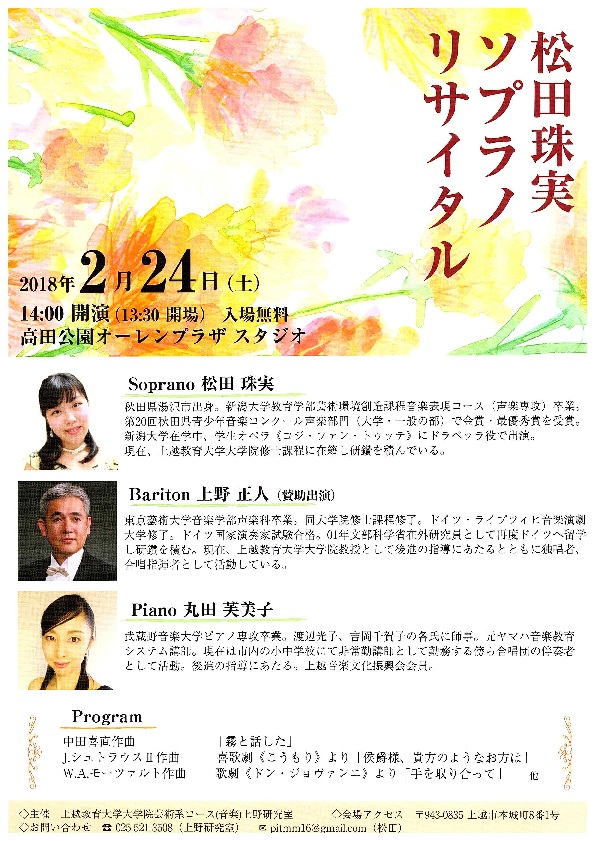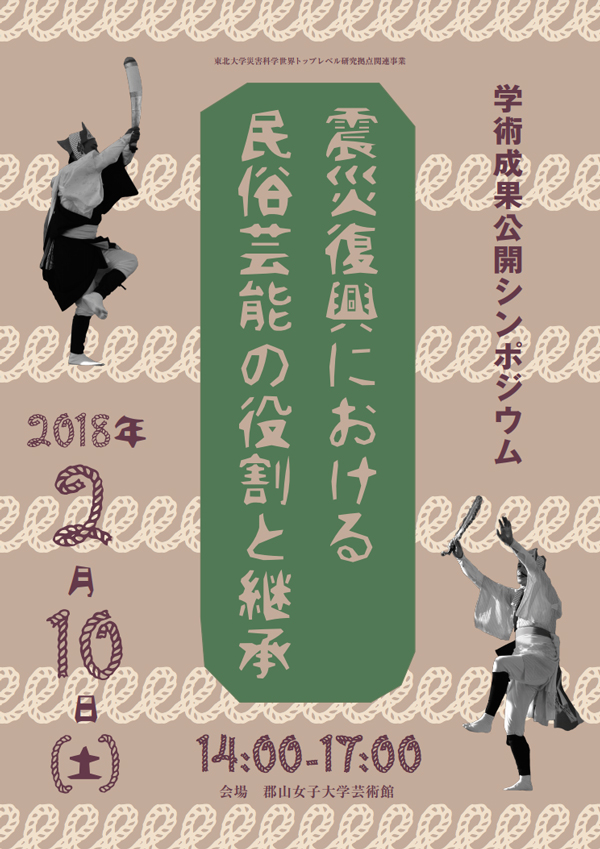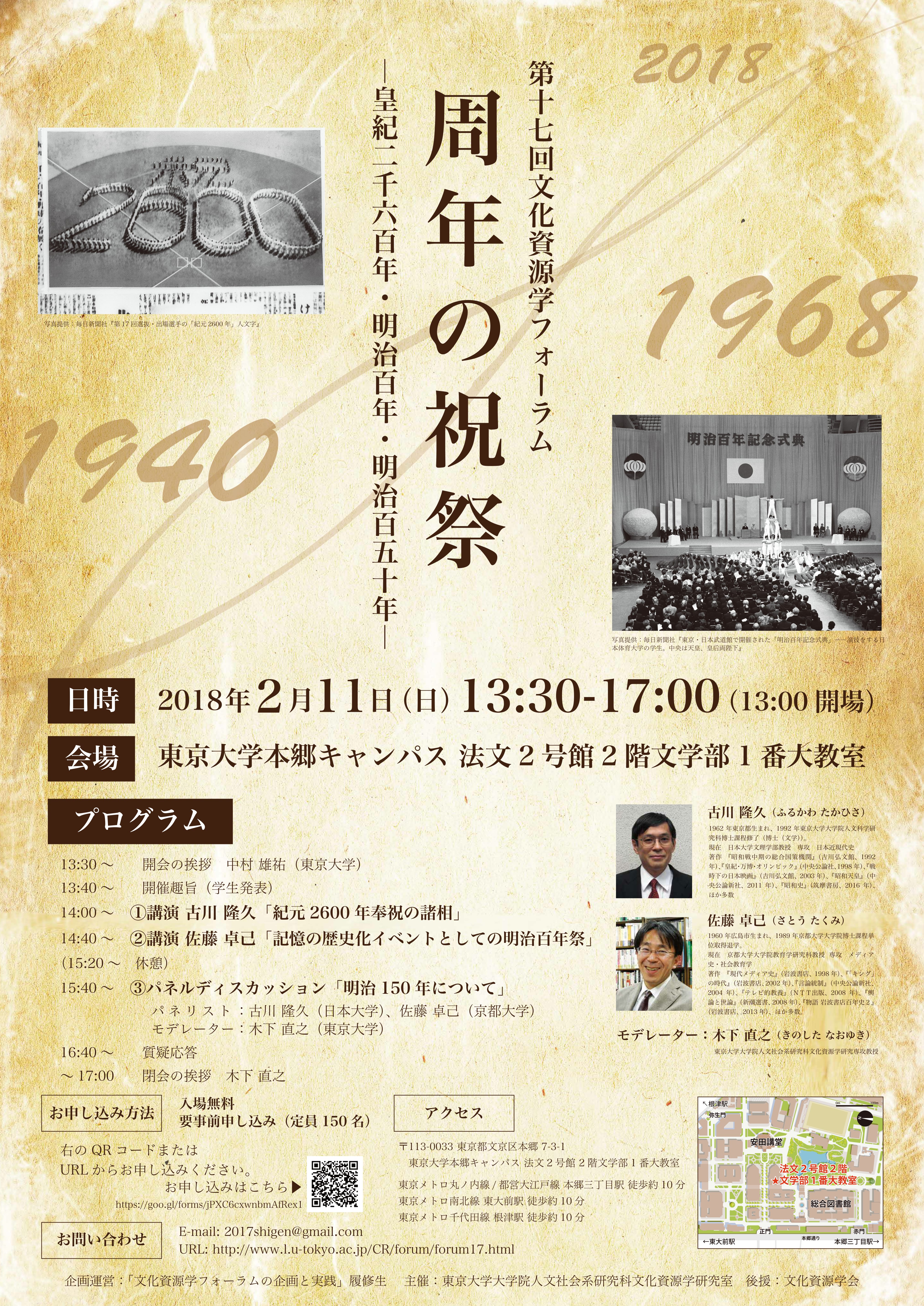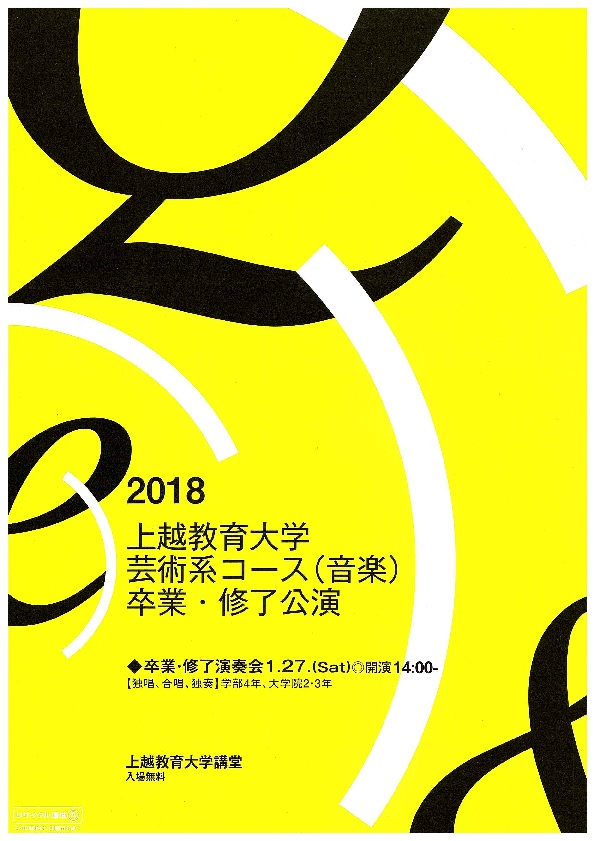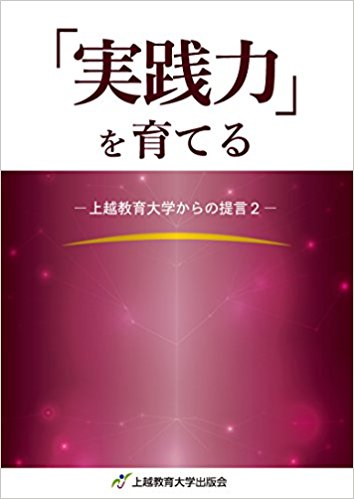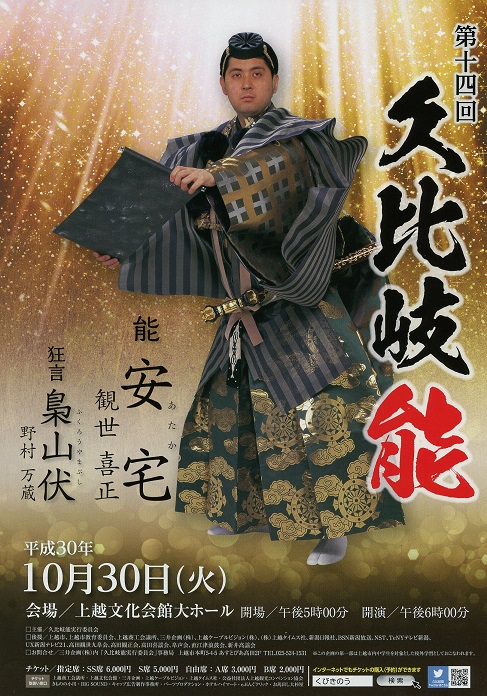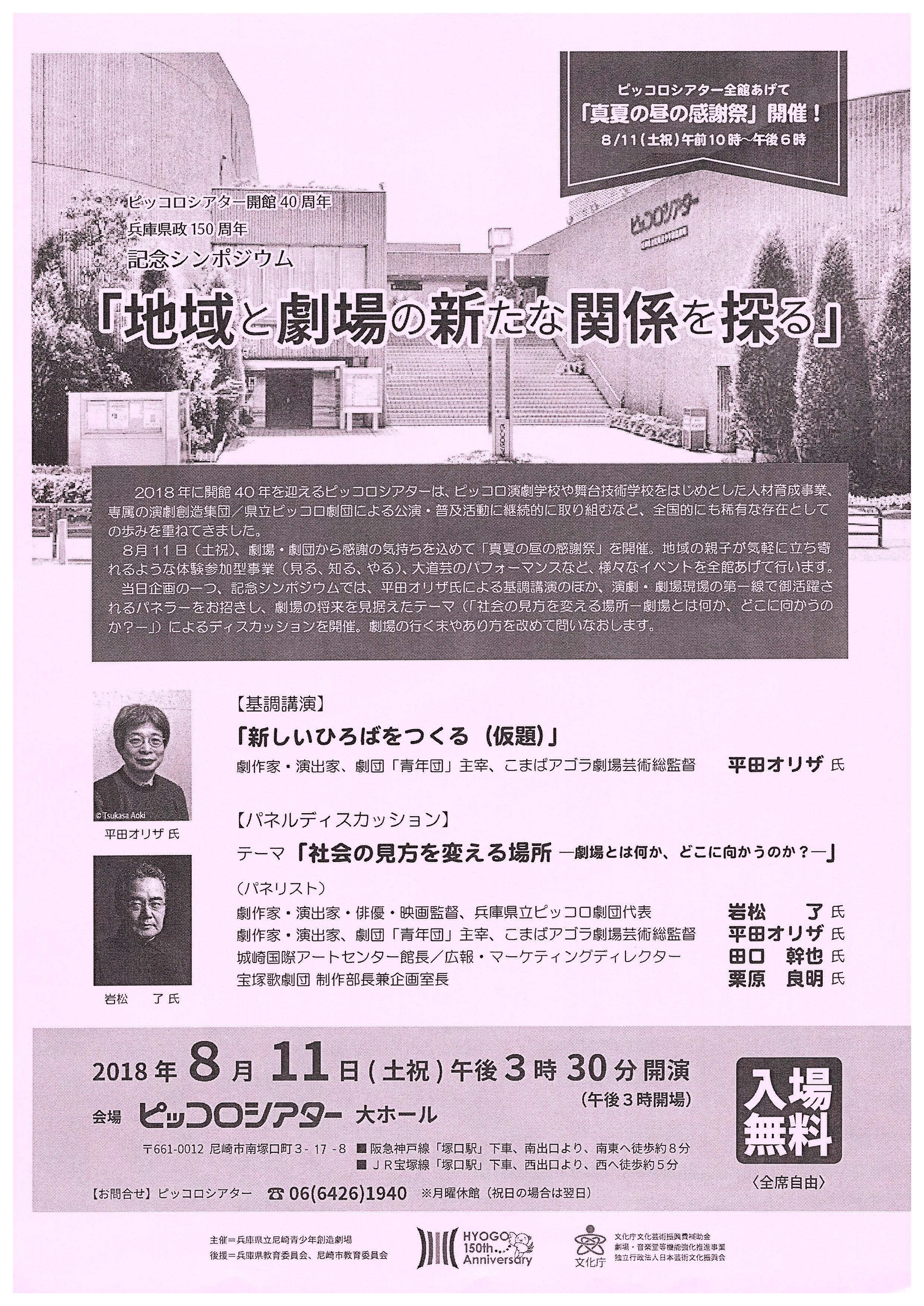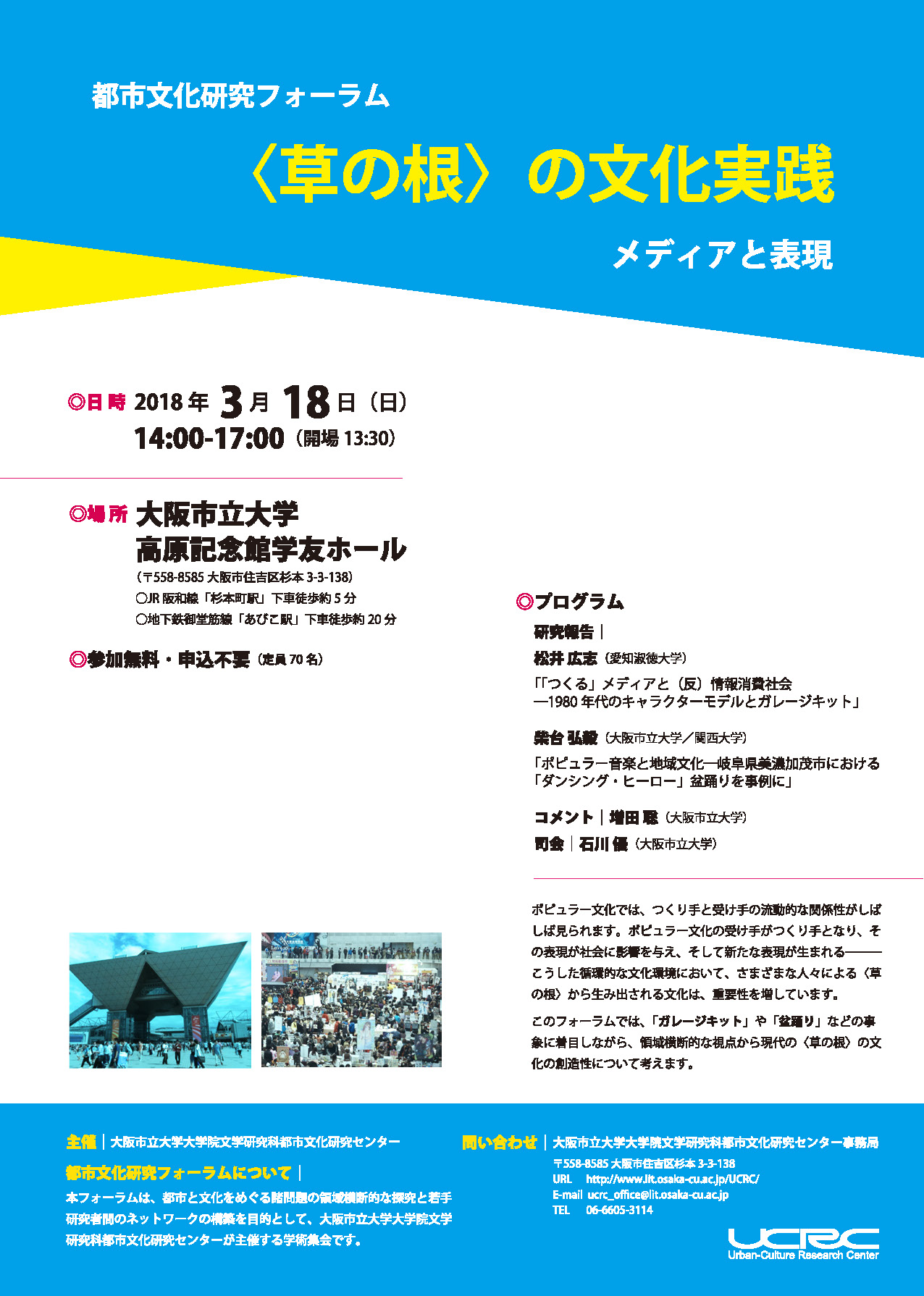|
News & Topics
�G���L�E�t�[�^���u����u���f�B�A�E�ړ��F�|�X�g�E�q���[�}�������̒���v�i2019�N1��7���i���j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j
�u���E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
hyosho-media.com/news/2018/1219_1-33.php
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�u���f�B�A�E�ړ��F�|�X�g�E�q���[�}�������̒���iMedia, Transportations, and the Challenges of Posthuman Culture�j�v
�u�t�F�G���L�E�t�[�^���iUCLA�����j
�����F2019�N1��7���i���j16:30�`18:00
�ꏊ�F����c��w�ˎR�L�����p�X36����581����
�@���\���s�v�A���ꖳ��
�i��E�����ʖ�F�h�~�j�N�E�`�F��
�i����c��w�����\�z�w���\�ہE���f�B�A�_�n�y�����j
��ÁF�h�~�j�N�E�`�F��������
���ÁF����c��w�����\�z�w���\�ہE���f�B�A�_�n
���₢���킹�Fcontact[at]hyosho-media.com
�i2018/12/21�j
�������`�����y���y���i�x�����Ɣ\�y�u���u�\�͖ʔ����v��52����J�u���i����30�N�x��1��j�u�w�Z����ɔ\���I�\�s�H�߁t�v�i2018�N12��25���i�j�A���s�ϐ���فj
�u���E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
rcjtm.kcua.ac.jp/events/openlecture...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
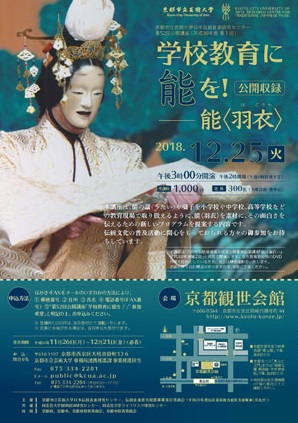
�����F����30�N12��25���i�j�ߌ�3���`6���i2���J��j
�@��2�������J���O�̎��O�v���[���e�[�V�������s���܂��B
���F���s�ϐ���فi���s�s�����扪��~����44�j
�@http://www.kyoto-kanze.jp/access/index.htm
�v���O�����F
�E��1�� �\�s�H�߁t�i�ϐ����F�r���ȗ��Ȃ��ʼn����܂��j
�V�e�i�V���j�F�͑����v�A���L�i���v�j�F�L���Ɉ�A���L�c���i���v�j�F���[�E���ѓw�A�J�F�X�c�۔��A���ہF��q�����Y�A��ہF�͑���A���ہF�O����́A�n�w�F�ϐ��c�V��i�n���j�ق�
�������߂������ƕ�ɂ��悤�Ǝ����A�鋙�v�E�����B�����ɓV��������A�߂�Ԃ��ė~�����ƌ����܂��B�����́A�߂��ޓV���ɓ���A�߂�Ԃ��܂��B�߂�g�ɂ����V���́A���̋{�̗L�l��\�����������A�t�̎O�ۂ̏������^�����A�V�ɏ����܂��B�s�H�߁t�́A�\�̑�\�I�ȍ�i�̈�ŁA�����Ώ㉉����܂����A����́A�����Ȃ��A�����āA�o�ꉹ�y�A�N���E�T�V�E�N�Z�ȂLj�؏ȗ��Ȃ��̊��S�łŏ㉉���܂��B
�E��2�� �\�s�H�߁t�Ŕ\����Ƌ��猻����Ȃ�
�i�u���ƃ��[�N�V���b�v�j
�H�߂ɂ��ā\����E�\�E�w�Z����
���L�ƃV�e�̖ⓚ�\�\�ƌ����̕\��
���[�N�V���b�v�\�w�A�^�A���q
��u���F1,000�~�i�S�Ȏ��R�A�v�\���j
����F300��
��u�\���ݕ��@�F
�E�\�����ԁF����30�N11��26���`12��21���K��
�͂����AFAX�AE���[���̂����ꂩ�̕��@�ɂ��A1.�X�֔ԍ��A2.�Z���A3.�����A4.�d�b�ԍ��iFAX�ԍ��j�A5.�u�w�Z����ɔ\���I�Q����]�v�Ɩ��L�̂������\�����݂��������B
������ɗ]�T������ꍇ�́A�����\�����t���܂��B
����u��1,000�~�͓�����t�ɂĒ��Ղ������܂��B
���\�������̏ꍇ�͒��I�Ƃ��܂��B
������ɗ]�T������ꍇ�́A�����\�����t���܂��B
�E�\����F���s�s���|�p��w�A�g���i�ہi���Ɛ��i�S���j
��610-1197���s�s�������}�B�|��13�|6
TEL075-334-2204�AFAX075-334-2281
�i�����ߑO8��30���`�ߌ�5��15���j
��ÁF���s�s���|�p��w���{�`�����y�����Z���^�[�A�`�����y���y���i���Ǝ��s�ψ���
���ÁF���u�Б�w���C�t���X�N�����Z���^�[�A�n���o�ό����Z���^�[
�㉇�F���s�{�A���s�s�A���s�{����ψ���A���s�s����ψ���@�@
�i2018/12/20�j
���c�����I�[�����v���U �N���X�}�X�E�t�F�X�e�B�o���i2018�N12��22���i�y�j�A���c�����I�[�����v���U�j
�Â��̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
joetsushisui.web.fc2.com/
www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza/gyouziyotei.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��22���i�y�j
�@�ߌ�1��30���J��A�ߌ�2���J���A�ߌ�4���I���\��
���F���c�����I�[�����v���U �R���T�[�g�z�[��
�����F��� 1,000�~�i����200�~���j�A���Z���ȉ� 500�~
�i���A�w������s�j
�o���F��z�s�����t�y�c�^�w�� �X�g���[�m�t����
�^���o���F��z�����y�c�E���F����c
���ʏo���F�Y���s�������y�c�E�Y���s�������c�̑I�������o�[
�ȖځF
��ꕔ ��z�s�����t�y�c
�E���V�A�̃N���X�}�X���y�@��
��� �Y���s�������y�c�E�Y���s�������c
�E�l���̃����[�S�[�����h
�E�I�y���u���S���b�g�v���s���S�̉́t�@��
��O�� ��z�s�����t�y�c�E���F����c
�E�T���^�����ɂ���Ă���@��
�������t
�E�N���X�}�X�E�t�F�X�e�B�o��
���ߌ�0������1��30���܂ŁA��z�����y�c�ɂ�錷�y�A���T���u���A���F����c����щY���s�������c�ɂ�郍�r�[�R���T�[�g����B���ꖳ���B
�v���C�K�C�h�F�I�[�����v���U�A��z������فA��t�y��A�w�����Y�J�t�F�A�˓c���X�A�����s�����z�[��
�₢���킹�F��z�s�����t�y�c�iTEL025-530-8013�j�A�I�[�����v���U�iTEL025-525-1311�j
�i2018/12/19�j
���{���y�w����{�x����44��i�ʎZ395��j���^���{�|�s�����[���y�w����n��2019�N�x��1�����i2019�N1��19���i�y�j�A���u�Џ��q��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia/msj/#395
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2019�N1��19���i�y�j14:00�`
���F���u�Џ��q��w���o��L�����p�X������3�K301����
�A�N�Z�X�F���s�s�c�n���S�G�ې��u���o��v�w���ԓk��5���A
�@����d�ԁu�o�����v�w�k��10��
�n�}�Fhttp://www.dwc.doshisha.ac.jp/access...
�V���|�W�E���u���E�@�B�E�g�́F���R�[�h���߂���A�[�g�̎��H�v
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�H�g�N���i���s���ؑ�w���u�t�j
�p�l���X�g�F���T�i��B��w�j
�Q�X�g�p�l���X�g�Fdj sniff�i�A�W�A���E�~�[�e�B���O�E�t�F�X�e�B�o�� �R�E�f�B���N�^�[�j
�@�f�W�^���@�킪�����̂ЂƂɂƂ��Đ����̈ꕔ�ƂȂ��Ă��錻�݁A���y�͕s���̃l�b�g���[�N��������ňړ�����f�[�^�̖z���ƂȂ��āA��C���ɏ[�����Ă���B���y�����I�Ɋy���ނɂ́A�I�[�f�B�I�@�킳�����͂�K�v�ł͂Ȃ��B�C���^�[�l�b�g�ɐڑ����ꂽ������PC���X�}�[�g�t�H������䂠��A�\���ł���B���̈���ŁA���R�[�h�i���Ձj��J�Z�b�g�e�[�v�Ƃ������ߋ��̃��f�B�A���ĕ]���������Ƃ����B�Ƃ�����Ύ������Ƃ��Ƃ�邱�̌��ۂ́A�������P�Ȃ���Î�ɂ����̂Ƃ͌���Ȃ��B�����ɂ́A���f�B�A�̕����������������w�i�ɂ��āA���y��t�ł�@�B�̋�̐���z�N���A�Ђ��Ă͂���ɐG���g�̂̊��o���Ȃ���_�@���܂܂�Ă�����悤�Ɏv���邩��ł���B
�@���������S�̂��ƁA�{�V���|�W�E���ŋc�_�̑�ނƂ��Ď��グ��̂̓��R�[�h���߂���A�[�g�̎��H�ł���B���R�[�h�̎��オ�I���������݂����炱���A���R�[�h�Ƃ͂����������Ȃ̂��Ȃ��A�n��Ɋ��p�����Ƃ͂܂��܂������Ă���B�{�V���|�W�E���ł̓��R�[�h�̕����j����������H�g�N�����i��i�s�߁A�p�l���X�g�Ƀf�W�^���@�����g���ă��R�[�h�̒�`�����V���Ă������T�A�Q�X�g�p�l���X�g�ɃC���v���r�[�[�V������ʂ��ă^�[���e�[�u���̉��t����T�����Ă���dj sniff�������}�����A���R�[�h�ɂ���ĐG������鉹�Ƌ@�B�Ɛg�̂̃_�C�i�~�b�N�ȊW���ɂ��čl���Ă݂����B
�i2018/12/18�j
����30�N�x���猤�����J�V���|�W�E���u�����E�\�͂̈琬�Ɍ������J���L�������E�}�l�W�����g�̐��i�F���ƂÂ���̎��_����v�i2019�N1��16���i���j�A�����Ȋw�ȁj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/sympo_h30/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2019�N1��16���i���j13:00�`17:00
�ꏊ�F�����Ȋw�� 3�K�u��
�i�����s���c�������3-2-2�����������ɑ�7���ٓ���3�K�j
�@�������g���u�Ճm��w�v11�ԏo������6�ԏo�����k��1��
�@�������g���u�����։w�vA13�ԏo�����k��5��
�i���قƐ��ق̊Ԃɂ��鋤�p���r�[���炨���肭������)
��ÁF�������琭����
����F300 ���i�Q�������j
�q�v���O�����r
�E12:30�` ��t
�E13:00�` �J��s���E�������A
��ՖL�i�������琭�������j
�E13:15�` ��1���F��u��
�u�V�w�K�w���v�̗̂��O�ƃJ���L�������E�}�l�W�����g�v
�V�}�i��t��w���C�����j
�E14:15�` ��2���F���H��
�u���H����J���L�������E�}�l�W�����g�̈Ӌ`�Ɖۑ���l����v
����i�Ɨ��s���@�l���E���x���@�\���C���͈��j�A�����ꐰ�i�V����������Z���^�[�w���厖�j�A�������i�L����w�����O�����w�Z���@�j
�E15:25�` ��3���F�p�l���f�B�X�J�b�V����
�u�J���L�������E�}�l�W�����g�Ǝ��ƂÂ�����Ȃ��v
�e�r�p���i�������琭��������ے��������j�A�c���m�q�i��㋳���w�����j�A�����n�i������w�����j�A����i�Ɨ��s���@�l���E���x���@�\���C���͈��j�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F���c�S�k�i�������琭��������ے������Z���^�[��b���������j
�E16:55�` ��s��
�q���\���݁r
�C���^�[�l�b�g�̏ꍇ�Fhttps://www.ifys.jp/nier-sympo/entry/
FAX�̏ꍇ�F�`���V���ʂ̎Q���\���p���ɂ��TEL03-5395-1206�܂�
���\���݂Ɋւ��邨�⍇���FTEL03-5395-1203
����30�N�x���猤�����J�V���|�W�E���\�������� ������ЃA�C�t�B�X��
(��t����9:30�`17:30�F�y�E���E�j���A12��29���`1��4��������)
�i2018/12/17�j
�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�u�O�����ƌ����y���ށv�i2019�N1��27���i���j�A�V���������j�����فj
�Â��̏��ł��B
����Î҃T�C�g�͂�����
nbz.or.jp/?p=19294
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2019�N1��27���i���j�@
���ԁF13:30�`15:40�i��t��13:00����j
���F�V���������j�����ٍu��
�i�����s����1���ڎ�������2247�Ԓn2�j
���u��
�u�q�������r�̌|�\�F�ڏ��S�̌���I�Ӌ`���߂����āv
�u�t�F�L���_��Y���i���������w�����ُy�����j
���ڏ��S���t
���t�F�{����q���A�������}���i�z���ڏ��S���̗t��j
���ځF
�E��t���S�@�⎺
�E�����j������
�E�Օ�����@�Γ��ہ@��i�E��i
�E�����S�@�ɐ�����������
����F150���i�v�\���E���R�ȁj
�����F����
�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�u�����A�����O�A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B
�\�����ݐ�F�V���������j�����ٌo�c����
��940-2035�@�����s����1���ڎ�������2247��2
TEL0258-47-6135�@FAX0258-47-6136�@E-mail:koryu[at]nbz.or.jp
�i2018/12/14�j
�S����w���y����w����n��w���30�N�x���������i2019�N1��5���i�y�j�A�O�؊y��J���فj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.nacome.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����31�N1��6���i���j13:00�J��
�@�i12:30�����t�A16:45����I���j
�ꏊ�F�O�؊y��J���فi���s������k�v��3-3-4�j
*��チ�g���䓰�ؐ��u�{���w�v���k��3���A���u�S���w�v���k��9��
������Q����F���1,000�~�A���2,000�~�A�w��500�~
�q�����������\�r13:15�`
1. ���{�����i���{�����S�㒹�����w�Z�j�u�����w�Z�̔\�ӏ܂ɂ�����̌��Ƌ����w�K�̌��ʂɂ��Ă̈�l�@�v
�q�������t���\�r13:45�`
1. �s�A�m�Ƒt �c�����q�i���s���؏��q��w�j�V���[�x���g��ȁu4�̑����ȁv��i90��� ��4��
2. �s�A�m�Ƒt ���J���q�i��։�Z����w�j �h�r���b�V�[��ȁu�f����1�W�v���u���̔��f�v
3. �Ə� �����K�i��㋳���w�j �c���i�i�E���c�쒼�u����������v�A�T�g�E�n�`���[�E���c�쒼�u�������H�݂����v�A�����ȏ��́u�~�i�F�v�A�ьÌk�E���c�O�u�l�ӂ̉́v�i�s�A�m�F�ۈ䗝�b�i��։�Z����w�j�j
4. ��i���\ �R�ݓO�i���L���X�g���Z����w�j�u�|�F�̍��i�͂Ȃ�����̂Ƃ��j�v�i�쎌�F�O�Y�Ǝq�A�Ə��F�ˎR�R���i���R��w�j�A�s�A�m�F�R�ݑ��b�i���ɋ����w�j�j
5. �s�A�m�A�e �v��ȑ��v�i����������w���É��L�����p�X�j�E���{��q�i���C�w����w�j ���[�c�@���g��ȁu�l��̂��߂̃s�A�m�\�i�^�vK.521����2�y��
6. �s�A�m�A�e �h���O���i���c�w�����q��w�Z����w���j�E�È����q�i���s�m�[�g���_�����q��w�j �r�[�[��ȁw���ǂ��̗V�сx��i22���u1 �Ԃ�v�u2 ���܁v�u12 ������v
7. �s�A�m�A�e ���{�R���i���ɑ�w�j�E�i�䐳�K�i���R��w�j �A�����X�L�[��ȁw�q�ǂ��̂��߂�6�̏��i�x��i34���u1 ���Ƃ��b�v�u5 �q����́v�u6 ���V�A�̎��ɂ��t�[�K�v
8. �s�A�m�A�e ���q���q�i���|�p��w�j�E�[�c���q�i��㑍���ۈ��w�j �h�r���b�V�[��ȁw���g�ȁx���u3 ���k�G�b�g�v�u4 �o���G�v
9. �s�A�m�A�e �씨���q�i���L���X�g���Z����w�j�E�R���M�q�i���a�Z����w�j �s�A�\����ȁE�R�{���q�ҋȁu���x���^���S�v
�q�u���r15:15�`
�E���E�u�w�y�������y�̊w�сx����w���y�̊y�����w�сx�ցv
���{�̉��y�w�K�͂���܂Łu�y�����v�ɏd�_���������悤�Ɏv����B�u���y�͊y�����Ȃ��Ă͂ˁv���O��ɂȂ��ăJ���L���������g������A���ނ��I��Ă����悤�Ɏv����B�e�퉹�y���ނ̒��ɒZ���̋Ȃ��]�茩���Ȃ��̂͂��̈�̕\��ł��邾�낤�B�u�y�������y�v�����߂錋�ʁA���y�ɂ��čl�����藝�����邱�Ƃ͂��낻���ɂ����B���ʂƂ��āA���w�Z1�N���́u���y�v�̋��ȏ�����ܐ������f�ڂ���Ă���ɂ�������炸�A�u�y�����ǂ߂܂���v�Ɖ��ʂ��Ȃ��q�ׂ��w����Љ�l���������͈�ĂĂ����悤�Ɏv����B �����A�O���̊w�Z��K���ƁA�q�ǂ��������u���y�̎��Ɓv�Łu�w�сv�����Ă��邱�Ƃɋ��������B�c�t�� �����g�̂�������A�̂����肵�Ȃ��特�y�̍\���ɋC�Â��A���̋C�Â������̊w�тւƌq�����Ă���B���{�̉��y����Ɖ����قȂ�̂��낤���B ����̌�����ł́A���̋@��Ɂu�y�������y�v�����łȂ��A�u�߂������y�v�u�C�������V�g�����鉹�y�v�u��肩����悤�ȉ��y�v�ȂǗl�X�ȉ��y���u�y�����w�ԁv���@�ɂ��Ă��Q���̕��X�ƈꏏ�ɍl���Ă݂����B
����ʂ̕��̂��\�����݁A���₢���킹��E���[���ɂĉ��L�܂ł��肢�������܂��B
�����ǒ��F�i�䐳�K m-nagai[at]osaka-aoyama.ac.jp
�i2018/12/13�j
���{�w�p��cin���s�u�`�������ƉȊw�E�Z�p�v�i2018�N12��22���i�y�j�A���s�{�����s�w�E���ʊفj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.scj.go.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
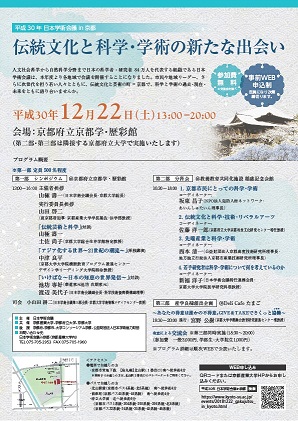
����30�N12��22���i�y�j13:00�`20:00
���F���s�{�����s�w�E���ʊفA���s�{����w
�@�Q������i�𗬉�������j
�@���OWEB�\�����i����ɂȂ莟�����܂��j
��ꕔ�F�V���|�W�E���i���s�{�����s�w�E���ʊفj13:00�`16:00
�E�Βk�u�`���|�p�ƉȊw�v�R�ɚ��i���{�w�p��c��E���s��w�����j�A�y�����q�i���s��w���������w�ٓ��苳���j
�E�P�ƍu���u�A�W�A�����鐢�E�F21���I�̒����v���×Ǖ��i���s��w��w�@���f����v���O�������i�Z���^�[�f�U�C���w���[�f�B���O��w�@���������j
�E�Βk�u�����ȁF���{�̒m�b�̐��E���M�v�r�V��D�i�ؓ��ƌ��r�V�����ƌ��j�A�n�Ӕ���q�i���{�w�p��c����E������������U���@�\�����j
�i��F���R�c�k��i���{�w�p��c��O������E���s��w�w�p��f�B�A�Z���^�[�����j
��F���ȉ�i���{���狤�����{�݈�L�O��فj16:30�`18:00
�E�u���s�s���ɂƂ��ẲȊw�E�w�p�v�Ⓦ���q�iNPO�@�l�m�I�l�ރl�b�g���[�N�E�����ソ�������j
�E�u�`�������ƉȊw�E�Z�p�E���x�����A�[�c�v�R�[�f�B�l�[�^�[�F�����m��Y�i���s�{����w���s�a�H���������Z���^�[���C�����j
�E�u��[�Y�ƂƉȊw�E�Z�p�v�R�[�f�B�l�[�^�[�F���{����i���v���c�@�l���s���x�Z�p�������������E�n���Ɨ��s���@�l���s�s�Y�ƋZ�p�������������j
�E�u��茤���҂͉Ȋw�E�w�p�ɂ��ĉ����l���Ă���̂��v�R�[�f�B�l�[�^�[�F�V���m�q�i���{�w�p��c���C�A�g����E���s��w��w�@��w�����ȏy�����j
��O���F�Y�w�lj��n�o���iDeli Cafe���܂��j18:30�`20:00
�u���Ȃ��̓��ӂ͒N���̕s���ӁBGIVE&TAKE�ł������Ƌ����i�R���{�j�v�i�s�F�{������i���s��w�w�ėZ�����猤�����i�Z���^�[�y�����j
��ÁF���{�w�p��c�@���ÁF���s�Y�Ƒ�w�A���s�{����w�A���s��w
�㉇�F���s�{�A���s�s�A��w�R���\�[�V�A�����s�A���v���c�@�l���{�w�p���͍��c
���₢���킹��F���{�w�p��cin���s�i���s�Y�Ƒ�w���j
TEL075-705-2953�@FAX075-705-1969
�i2018/12/12�j
��6��k�悤���̍ՓT�i2018�N12��23���i���j�A�V���s�k�敶����فj
�Â��̏��ł��B
�{�R�[�X�����A���J�삪�o�����܂��B
����Î҃T�C�g�͂�����
www.kitaku-bunkakaikan.com/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��2���i���j14:00�J���i13:30�J��j
���F�V���s�k�敶����كz�[��
�@�S�Ȏ��R ��l1,500�~�A���Z���ȉ�800�~
�G�߂ɂ���ĐF��ς���L��ȓc���A�������ɔ��邽������̓n�蒹�����\ ����ȕ��i�߂�Ƃ��ɁA�ӂƎv�������ԃ����f�B�B�k��̎��R�̒��Ő��܂������q�ǂ������ƁA���̎��R������Ă�����l�������ЂƂɂȂ�A���R��������C���������͂����܂��B
�q��1���r
1. �k�揭�N���������c�i�w���F�\�����q�A�s�A�m�F�c�������Y�j
�E���b�̃o���[�h �ق�
2. �k�悤���̍ՓT�����c�i�w���F���Y�ǎ��A�s�A�m�F�I�ї����j
�E���������h�i�E
�E�J���^�[�^�u�y�̉́v����u��n�]��v �ق�
�q��2���r�Q�X�g�X�e�[�W
�\�v���m�F�\�����q�A�s�A�m�F���c����
�E�I�y���g�[�߁h���u���̑厖�Ȃ�Ђ傤�v �ق�
�q��3���r�w���F���J�쐳�K
�����F�k�悤���̍ՓT�����c�A�k�揭�N���������c
�I�[�P�X�g���F�k�悤���̍ՓT���ʃI�[�P�X�g��
�E�����i�����j�����g�ȁu���߂��̂����v
�@��̂��� ���̂��� ���̂��� ���̂���
�E�~���[�W�J���u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v
�@�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N
�@���悤�Ȃ�A��������悤
�@���ׂĂ̎R�ɓo��
��ÁE���₢���킹�F�V���s�k�敶�����
��950-3323�V���s�k�擌�h��1-1-5
TEL025-368-6900�@FAX025-388-6901
http://www.kitaku-bunkakaikan.com
�i2018/12/11�j
���{���y�w����x������124���ጤ����i2018�N12��15���i�y�j�A���É��|�p��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.msj-chubu.org/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F12��15���i�y�j13��30���`
�ꏊ�F���É��|�p��w���L�����p�X5-301����
�i��F���q�֎q�i���É��|�p��w�j
�q�������\�r
1. �����߂��݁i���{�w�p�U������ʌ�����PD/���m�����|�p��w(��)�u�t�j�u�吳���̖��É��ɂ�����h�C�c���ؗ��̉��y�����F���A�K�u��̗����e���̎���Ɣ�r���āv
2. �d�H���e�B���e�B���i������w���ۊW�w���j�u�������i�e�B���e�B�������F�܍s�ƌܑ��ƌ܉��v
3. �n��Y�i�i���s������w�����Љ�w�������Љ�w�ȋ����j�u�_���̃|�s�����[�����F�^�C�ɂ�����O���[�o�����Ɠ`�������ۑ��E�����^���̂͂��܁v
�i2018/12/10�j
�����|�p�w���151�����i2018�N12��22���i�y�j�A����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
ethno-arts.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F12��22���i�y�j14:00�`17:00
�ꏊ�F����w�L���L�����p�X ���w�����ȁE�|�p������1�K�|3����
��ʁF��}��ː��u���v�w�i�k��15���j�A��ヂ�m���[���u�Ō��v�w�i�k��15���j
���]����҂Ƃ̑Θb�u�A�t���J���߂���v�l�̌��݁v�F
�E��������ׁi�w�U���ʌ������j�w�A�t���J���p�̐l�ފw�x
�@�@�]�ҁE�呺�h��i������w�j
�E����j���i������w�j�w�q�j�O���|�p�r�̎v�z�����j�x
�@�@�]�ҁE�֓��S��i����w�j
�S�������F��v�ۋ��q
�i2018/12/7�j
���{�����l�ފw��ߋE�n�挤�����k��i2018�N12��15���i�y�j�A���s�s���|�p��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jasca.org/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��15���i�y�j13:30�J���i13:00�J��j17:45��
���F���s�s���|�p��w�M�������[��KCUA
�@��604-0052 ���s�s�����扟�����H��238-1
�@���s�s�o�X�E���s�o�X�u�x���r�v���Ԃ���
�@���s�s�c�n���S�������u�����O�v�w����2�ԏo�����k��3��
�v���O�����F�V���|�W�E���u�l�ފw�ƃA�[�g�̋����v
�E13:30-13:40�@��|�����F�쐣���i���������w�����فj
�E13:40-14:25�@�����m�v�i���s�s���|�p��w�j�u�A�[�g���Ɓ��l�ފw���_�F���ݐG���I�ȃv���b�g�t�H�[���̌`���Ɍ����āv
�E14:25-15:10�@���×��i���s��w��w�@�A�W�A�E�A�t���J�n�挤�������ȁj�u�u�G�ꂽ��A���ʁv�F�l�ފw�I�T���ɂ�����f���C���X�^���[�V�����v
�E15:30-16:45�@��58�F�l�`�A�E�r�G���i�[�����۔��p�W�^���{�ٓW�������o�[ �Αq�q���i�H�c�������p��w�j�E�����_�V�i�H�c�������p��w�j�E������V�i���p�Ɓj�u���ّ̂̃R���|�W�V�����F���̈�I�����̎��H����v
�E16:45-17:45�@�������_�i���\�ҁA�R�[�f�B�l�[�^�[�j�A���^����
�{��́A���s�l�ފw������A���{�����l�ފw��ߋE�n�挤�����e��A���s�s���|�p��w�̋��ÂƂȂ�܂��B���s�l�ފw������͋��s�𒆐S�Ƃ�����̐l�ފw����ъ֘A����ɊS���������ҁE��w�@�������̌������ʂ�����ł��B
���O�̎Q���\��͕K�v����܂���B�ǂȂ��ł����R�ɎQ�����������܂��B�����͎�����Ƃ���200�~���������܂��B
�₢���킹��F���s�l�ފw���������
E-mail: kyojinken2018[at]gmail.com
URL: https://www.facebook.com/kyojinken/
�i2018/12/6�j
���x�w���70����i2018�N12��8���i�y�j�E9��(���j�A�����̐����q��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.danceresearch.ac/taikai/taikai.htm
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��8���i�y�j�E9���i���j
���F�����̐����q��w �i�Ŋ��w�F�n���S�ۃm����䪉גJ�w���k��7���A���͒n���S�L�y�����썑���w���k��13���^�y���͓�傪��̂��߁A����������p���������B�j ��ʈē��@http://www.ocha.ac.jp/access/index.html
�q�S�̃X�P�W���[���r
�E��1���ځF12��8���i�y�j
9:30�` ��t
10:00�`12:00 ��ʌ������\1
13:30�`14:30 70��L�O���ʊ��q���k��r���x�w��̂���܂ł�U��Ԃ�A�����ւ̓W�]��`��
14:40�`15:40 ��u���u�\�V�A���E�\�}�e�B�b�N�E�Z�I���[�̓W�]�v
15:50�`17:30 ���[�N�V���b�v�u�����̂����̂��H�v
�E��2���ځF12��9���i���j
9:30�` ��t
10:00�`12:00 ��ʌ������\2
13:00�`14:00 ����
14:00�`16:30 �q�V���|�W�E���r�u���x�ɂ�����g�̂ւ̕����I�Ȃ܂Ȃ����F���ҁA�U�t�ƁA�ϋq�̎��_����v
*�v���O�����ڍׂ� ������
���Q����F���2,000�~�A�w��1,000�~
�@��������F����3,000�~�A�w��1,500�~
��70�x�w������ǁF
��112-8610 �����s��������2-1-1
�����̐����q��w�@���x����w���莺��
���₢���킹TEL&FAX03-5978-5271�i����10�`17���j
Mail: buyogakkai2018[at]gmail.com
�i2018/12/5�j
���{���y��������12��w�p�W��in���s�i2018�N12��9��(���j�A���s��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://jmm12th.jimdofree.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��9���i���j9:55�`17:00
�ꏊ�F���s��w���ۉȊw�C�m�x�[�V������5�K�V���|�W�E���z�[��
�i606-8501���s�s������g�c�{���j
�e�[�}�F�q�ǂ��̔��B�Ɖ��y�Ö@
�q�v���O�����T�v�r
���v���O�����ڍׂ� ������
�E���ʍu���u�d�ǎ��Ɖ��y�Ö@�v13:40�`15:10
���厛�����È�a�@�x�a�����@���A������鉹�y�Ö@�m
�����F���s��w��w�@��w������ �����i����
�E�V���|�W�E���u��o���̏d���̉��y�Ö@�`���Ă̌���`�v15:20�`16:50
�R�`���������a�@�������Y����q��ÃZ���^�[����q�������A��r�������y�Ö@�m
��ʌ���������ÃZ���^�[�������Y����q��ÃZ���^�[�V�����Ȑ������������A�]�����G�q���y�Ö@�m
�w�蔭���F�Q�n����������ÃZ���^�[�������Y����q��ÃZ���^�[�ؓ������Ō�t
�����F���s��w��w�������a�@�����ȁi�V�����W�����Õ��j�͈䏹�F�a�@����
�E�J���e�b�g���t13:00�`13:30
�i2018/12/4�j
���{���y�w����{�x����54���ጤ����i2018�N12��8��(�y�j�A�������y��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.musicology-japan.org/east/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��8���i�y�j13:20�`16:50
�@���J�n�������ʏ�ƈقȂ�܂��̂ł����ӂ��������B
�ꏊ�F�������y��w3����114����
���[�N�V���b�v
�u���y�`���_�čl�FCaplin, Hepokoski, Webster��ǂށi������j�v
�i��E�R�[�f�B�l�[�^�[�F�ɓ��C�F�i���ۊ����w�j
�p�l���X�g�F�������i�������y��w�j�A�Έ䖾�i�c���`�m��w�j�A���쏺�i�����{�x���j
����̗��́A2007�N10��10�`14���ɁA�h�C�c�̃t���C�u���N�ōs�Ȃ�ꂽ�A��6�[���b�p���y���͉�c�iEuro-MAC�j��Formenlehre�Ɋւ���V���|�W�E�����܂Ƃ߂������ł���APieter Berge, ed., Musical Form, Forms, Formenlehre: Three Methodological Reflections (Leuven University Press, 2010)���ނƂ��āA���[�N�V���b�v�̃X�^�C���ōs�������Ǝv���Ă��܂��B�V���|�W�E���ɓo�ꂵ��3�l�̘_�҂̎咣���A����iBerge�j���܂Ƃߖ��ƂȂ�A�����iCaplin�j�A�Έ�iHepokoski�j�A�ɓ��iWebster�j�����ꂼ����ق��Ȃ���A�Q���ґS���Ƌ��ɁA���̕���̌���𗝉����A����̉ۑ�Ɏ��g�݂����ƍl���Ă��܂��B�����́u�O�����v�iLudwig Holtmeier�j�ɂ��A���̉�c�S�̂ł́A180�l�̔��\�҂�500�l����Q���҂������������ł����A���̒��ł��A���̃V���|�W�E���͉�c�S�̂̊j�ƂȂ���̂ł������悤�ł��B���̂��Ƃ́u�O�����v�ɂ��q�ׂ��Ă���A����܂ł̗l�X�ȁA�����Ƃ́A���邢�͓`�����Ƃ̘g�g�݂����z���āA�^�ɍ��ۓI�ȁA����̐��E�I�c�_�ɂȂ�����e�ł��邱�Ƃ���������Ă��܂��B���{�ł́A�c�O�Ȃ���A���̃e�[�}�ł���قǂ̎Q���҂��W�߂邱�Ƃ͓����������܂��A���݂������A11��3���ɊJ�Â��ꂽ���{���y�w��S������Session G�i�i��F�ɓ��C�F�j�ɎQ���������̔��\�҂����̌����iHaydn, Mozart, Schubert �Ɋւ�����́j�̎Q�l�����ɂ́ACaplin, Hepokoski��̌������܂܂�Ă���A����A18-19���I�̃��[���b�p�̉��y������ŁA�����ł��Ȃ�����ł���Ǝv���܂��B���ہA�C�O�ɂ����ẮA1990�N�ォ�璅���ɐi�W���Ă��Ă��镪��ł���A���{�̌����҂����̗ւ̒��ɎQ������Ӗ��ł��A������@��ɁA���{�̒x�����C�ɏk�߁A�w��Ƃ��Ă̗�����[�߂����Ǝv���̂ł��B�܂����A���̕���̂�����l�̗Y�ł���}�[�N�E�G���@���E�{���Y�̒���A�w�\�i�^�`���̏C���w�F�ÓT�h�̉��y�`���_ �iWordless Rhetoric: Musical Form and the Metaphor of the Oration�j�x�A�i���y�V�F�ЁA2018�N�j���y�c�p�O�Y���̖�ŏ㈲����A�x����Ȃ���A���{�ɂ����Ă��@���n���ė��Ă���悤�Ɏv���܂��B�\��Ƃ��ẮA�O���̑�1���ŁA����̑O�u���̌�A�����A�ɓ��A�Έ�̏��ł��ꂼ�ꂪ�S�������_�҂̎咣�̗v�_���܂Ƃ߂邱�Ƃɂ��܂��B�x�e������ŁA�㔼�̑�2���ł́A���삪�i����߁A3�l�̘_�҂��݂��̎咣�ɑ��Ē��������^���v�邱�Ƃɂ��܂��c�i�������������j
�i2018/12/3�j
���������w���8�m���擾�Ҍ������\����ѓ��ʍu����i2018�N12��8��(�y�j�A������w�{���L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
bunkashigen.jp/sympo/sympo03.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��8���i�y�j
���F������w�@��1����113����
�q�������\�r13:30�`16:00
�E�{���m�i���s�����ߑ���p�فj�u�n����s�̐������Z�Ɩ��S�ۑq�ɂ̔����@�������N�v�H�@���{�����Ƌ�s�����q�Ɍ��݉ߒ�����݂�n��Y�Ɣ��B�̋ߑ�I�����v�i���m���擾�F����c��w�A2017�N7���j
�E���m�f�i������w�j�u�A���n���N�ɂ�����ߑ�I��ԂƂ��Ă̌���Ɖ����E�v�i���m���擾�F������w�A2017�N10���j
�E���������i�É������|�p��w�j�u���{�����@��25���u�����v�T�O�̌����F�������icultural right�j�Ƃ̊֘A���v�i���m���擾�F������w�A2017�N7���j
�q���ʍu����r16:15�`17:45
�E�^�痤���Y�i������w�j�u�s�s�̏��̑������F�R�~���j�e�B�E�f�U�C���ւ̓W�J�v
�i2018/11/30�j
���w������30�N�x��4����i2018�N12��1��(�y�j�A��q��w�l�J�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��1���i�y�j13��00���`16��30��
�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�X1����408����
�@�A�N�Z�X�Fhttps://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access...
�@�������́A�k��͕債�Ă���܂��̂ŁA����������p���������B
�q�������\�r
�E��c�א��i��q��w�j�u�|�p�Ə@���̋��ԁF�V���[�y���n�E�A�[���w�ɂ����鐹�l��̈Ӌ`���߂����āv
�i��F�����z��Y�i���{��w�j
�E���ђ��q�i�����Y�p��w�j�u���w�Ɩ����FG.F.�}�C�A�[�i1718-77�j�̔��w�I��_���߂����āv
�i��F��}���m�i���R������w�j
�E�K���r��i��q��w�j�u���H���t�̘_���w�ƃo�E���K���e���̔��w�ɂ����鎩�R��`�ƐS����`�F�ߐ��ȍ~�̘_���w�̗��j�I�W�J�ɑ����āv
�i��F��}���m�i���R������w�j
�i2018/11/29�j
���m���y�w����{�x����106���ጤ����i2018�N12��1��(�y�j�A������w���L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
tog.a.la9.jp/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��1���i�y�j
�@I��15:00�`16:15�AII��17:00�`18:45
�ꏊ�F������w���L�����p�X
�@I�� 18����1�K���f�B�A���{2
�@II�� ���R�~���j�P�[�V�����E�v���U�k��2�K���y���K��
I�� �������\
�u�J�U�t�`�����y�̌l�w�K�Ɋւ���l�@�v
���c�͎q�i�����Y�p��w��w�@�j
�i��F�S�`�F�t�X�L�C�w���}���i������w�j
�U�� ���N�`���[��R���T�[�g
�u�A���b�|�̓`���Ŋw�ԃA���u���@�̊�{�v
���t�F���n���}�h�E�J�h���[�E�_���[���i�E�[�h�j�A�A�u�h�D�E�q���f�B�[�i�́j�A�T���[�t�E�o�N���i���b�N�j
����F�і�肳�i���{�w�p�U���� ���ʌ�����(PD)�j
�i��F�����p�C�i������w�����n�挤���Z���^�[�j
�i2018/11/28�j
����c��w�����l���Ȋw�����Z���^�[��������u�C���[�W�����j�v��Ã��[�N�V���b�v�q�}���K�̑̌��A���f�B�A�̑̌��r��2��u�}���K�Ǝʐ^�A�f��v�i2018�N12��1��(�y�j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/flas/rilas/news/2018/11/08/5557/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��1���i�y�j15:00�`17:30
�ꏊ�F����c��w�O�R�L�����p�X36����6�K681����
�E�O�����N�i�����H�|��w�����u�t�j
�u�}���K�̘_���A�@�B�̘_���v
�E���c�W��i�����ّ�w�u�t�j
�u�Î~�Ɖ^���A�܂��̓}���K�Ɖf���̐ړ_���߂����āv
���܂��܂Ȏ��o���f�B�A�Ƃ̑Δ�̂Ȃ��ŁA�}���K��ǂށ^����Ƃ����̌��̈Ӗ����l����A�����[�N�V���b�v�̑�2��́A�w�}���K�Ɖf��x(NTT�o�ŁA2014�N)�Ń}���K�����̐V������\���鑶�݂ƂȂ����O�����N����ƁA�f�����f�B�A�_�E�f���Z�p�_�̐V�����n�����J���w�Ȋw�҂̖Ԗ��x(�|�ЁA2017�N)�ɂ���đ����ʂ̒��ڂ��W�߂鑝�c�W�傳�o�ꂵ�܂��B�ʐ^��f��ɑ�\����铯����̉f���Z�p�Ɣ�r�����Ƃ��A�}���K���畂���яオ�鎋�o�̘_���Ƃ͂����Ȃ���̂�? �Z�p�Ƃ��Ẵ}���K�ɉ\�Ȃ��ƁA�s�\�Ȃ��ƂƂ͉��Ȃ̂�? ���o�����_�̍Ő�[�������ɂ���I
���⍇����F�����l���Ȋw�����Z���^�[��������u�C���[�W�����j�v
imagebunkashi[at]list.waseda.jp
�i2018/11/27�j
�����|�p�w���88�����i2018�N12��1��(�y�j�A������w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://ethno-arts.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N12��1���i�y�j14:00�`16:00
�ꏊ�F������w�r�ܖ{�فi1���فj2�K1201����
�@�e���u�r�܁v�w���ԓk����7��
�������\�F
�E���X�^���i�����O�����w�j�u��̂��|�p�ɂȂ�Ƃ��F��w�A���p�j�A�~���[�W�A���v
�E�Ñ��肠�i���ꌧ���ߑ���p�فj�u���p�ł��함�ł��Ȃ����́F���摜���t�B�[���h�ƃ~���[�W�A������l����v
�S�������F����K�� (�����Y�p�w���������minzoku.tokyo[at]gmail.com�j
�i2018/11/26�j
�y���w���101����i2018�N11��26��(���j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www1.odn.ne.jp/~gakugeki/reikai.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N11��26���i���j
�@�ߌ�6��30���`8��00���i�\��j
���F�@����w�s�J�L�����p�X �{�A�\�i�[�h�^���[25�KB��c��
�@JR�E�n���S�u�s���J�v�܂��́u�ѓc���v�w���ԓk��10��
�u������o���߂����āF�ċ�����w�]�ˎ��㉹�y�ʉ��x�܂Łv
���\�ҁF����������
�i2018/11/23�j
�|�s�����[���y�w���30����i2018�N11��24��(�y�j�E25���i���j�A�c��`�m��w���g�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://jaspm30.wordpress.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N11��24���i�y�j�E25���i���j
���F�c��`�m��w���g�L�����p�X
�Q����F��ʉ��3,000�~�i����3,500�~�j�A�w�����E�@�����2,000�~�i����2,500�~�j�A����3,500�~�A�V���|�W�E���̂ݎQ��1,000�~
���₢���킹��F������ �c��`�m��w���g�L�����p�X������449��a�c�r�V������ e-mail:tohwada[at]gmail.com
�q�v���O�����r
11��24���i�y�j��1��
�E13:00 �J��E��t�J�n�i��6�Z��1F612�����j
�E14:00�`16:50 �l�������\
�E17:00�`18:00 ����i��6�Z��2,3F623�����j
�E18:10�`20:10 ���e��i������2F�t�@�J���e�B���E���W�j
11��25���i���j��2��
�E9:00 �J��E��t�J�n
�E9:30�`12:30 ���[�N�V���b�v
�E14:00�`17:00 �V���|�W�E���i��6�Z��2,3F623�����j
�E17:00�`17:30 ��A
�q�l�������\�r
�l�������\A�i��6�Z��1F J611�j
�i��F�G�h�K�[�EW�E�|�[�v�A��������
�E�����i�������y��w��w�@���m����ے��j�u���a��O���̊֓��B���A�����ǂɂ�闬�s�̂̐������F���́u����v�ƎЉ�I�v���y�щe���ɂ��āv
�E���q���N�i���l�s����w��w�@�s�s�Љ�������Ȕ��m����ے��j�u�����m�q�H�ɂ�����u�D�̊y�m�v��ʂ����y���y��e�ߒ��̕��́F���t�v���O�����̋ȖڕϑJ������Ɂv
�E���������i�����Y�p��w��w�@���y�����ȉ��y�����w��U�C�m�ے��j�u�����{�W���Y�j�ɂ�����u�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���v�̈ʒu�Â��ɂ��āF��ォ��1970�N��㔼�ɏœ_�����Ăāv
�E�V�c����i�����Y�p��w��w�@���y�����ȏC�m�ے��j�u�{�y���A�O��ɂ����鉫�ꃍ�b�N�E�~���[�W�V�����̉��t�����̕ω��F�`�T�C���N���u�𒆐S�Ɂv
�l�������\B�i��6�Z��3F J631�j
�i��F�����ǖ��A�֓��T��
�ERodney A. Dunham�i��ˎR��w�j�uQueens of Noise: The Runaways as Jungian Archetypes in Japan and in America�v
�E����貁i�@����w��w�@�l���Ȋw�����ȓ��{���w��U���ۓ��{�w�C���X�e�B�e���[�g���m����ے��j�u�˂��ꂽ���̑��F�u���v�Ɍ��т���ꂷ�����u���{�̐S�v�v
�E���c���i���s����w�j�u�u�����\���O�v�̌n���F�j�b�|���n�|�b�v���������v
�E�����c���i���؏��q�Z����w�c���ۈ�Ȑ�C�u�t�j�uNHK����ԑg�u�݂�Ȃ̂����v�̐����Ɓu���������^���v�̊֘A���v
�l�������\�i��6�Z��3F J632�j
�i��E�{������
�E���ѓĖi�~���[�W�V�����j�u���C�u�ɂ�����A�����G���W�j�A�̖����A�n�����A�Z�p���Ɋւ���l�@�F���C�u�n�E�X��PA�G���W�j�A������Ɂv
�E�˓c���v�i����w��w�@���w�����Ȕ��m����ے��j�u�u�n�[���j�[�f�B���N�^�[�v�͓��{�̐��t�y���ǂ��ς������F�y��Y�ƂƊw�Z���y�����v
�q���[�N�V���b�v�r
�E���[�N�V���b�vA�i��6�Z��1F J611�j
�u�Ȃ肫�邱�Ƃ̑n�����A�~���[�W�V������(�ւ�)�����ω��v
�{�菮��i���m������w���j�A���V�B�j�i���R���w����w�j�A�L�����_�i���R���w����w�j�A���_�ҁF����h�́i���m�����w�j
�E���[�N�V���b�vB�i��6�Z��3F J631�j
�u��ʒ����̓|�s�����[���y�̉����ǂ��܂Ŗ��炩�ɂł��邩�F�W�������E�n�D�E�R�~���j�P�[�V�����𒆐S�Ɂv
��c����i������w�j�A�ؓ��R���i���R�w�@��w�j�A�i�䏃��i�_�ˎR���w�j�A���_�ҁF�ēc�K�O�i�a����w�j
�E���[�N�V���b�vC�i��6�Z��3F J632�j
�u�����{�ɂ�����\���Ƃ��Ẳ��y�����v
���J���i�i�����ّ�w�j�A���c����i�l�V������w�j���M�m�i�����ّ�w��w�@�j�A
�q�V���|�W�E���r
�E���{�|�s�����[���y�w��ݗ�30���N�L�O�V���|�W�E��
�i��6�Z��2,3F 623�����j
�u���{�ɂ�����|�s�����[���y�����F30�N�̕��݁v
�p�l���X�g�F�O��O�i�����w���_�����j�A���씎�i�i����w�j�A�א�����i���ۓ��{���������Z���^�[�j�A���M�q�i�哌������w�j�A�i��F�ї��ÍF�i�����Y�p��w�j
�i2018/11/22�j
�����|�\�w���30�N�x���i2018�N11��25��(���j�A�����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
minzokugeino.com/conf.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N11��25���i���j
���F�����w3���فi��157-8511�����s���c�J�搬��6-1-20�j
�E��t�J�n�F10:00�`
�E�J��A�F10:30�`10:40�@�����s�ψ��� �U�،�
�E�������\�F10:40�`12:40
�P�D�r�ؐ^���u�f����r�ɂ��|�ԕω��̈�l�@�v
�Q�D�ɓ����u�������q�������̃e�N�X�g�ƌ|�\���H�v
�R�D�����O�u�k����B�ɂ������̏㉉�F�`���E���ځE�������v
�S�D���c�Y���u�����|�\�`���̃v���Z�X�Ɏ���u���������^�L�^�F�f���Z�p��p�����`���x���̎��݁v
�E�V���|�W�E���F14:00�`16:20
�e�[�}�u�����|�\�����̐V�������_�Ɍ����āv
��|�����E�R�[�f�B�l�[�^�[�F�U�،�i�����w�j
�p�l���[�F��萐��i���{�w�p�U������ʌ������j�A��؍V���i����������w�@��w�j�A�ˌ��L���i����w�j
�E�{�c���������F16:30�`16:40
�E����F16:40�`17:30
�E��A�F17:30�`17:40�@��\���� ���R��
�E���e�� �F18:00�`20:00�@��� �����w7���ْn�����E���W
���Q����A�\�����ڍׂ� ������
�i2018/11/21�j
�V���|�W�E���u�N�w�E��w�E�\�F�悭�����邽�߂̂܂ȂтƂ����сv�i2018�N11��24��(�y�j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j
�u���E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
kyoten-nohken.ws.hosei.ac.jp...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
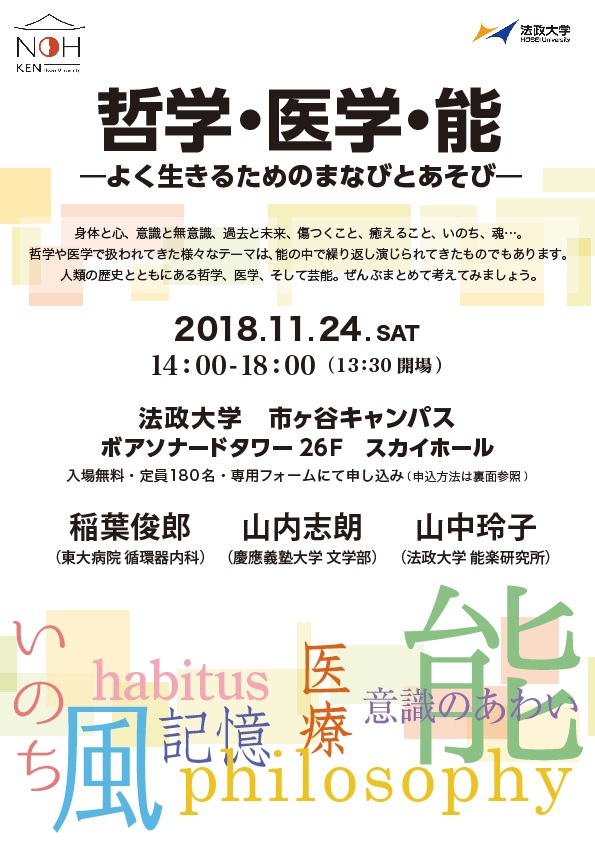
�����F2018�N11��24���i�y�j14:00�`18:00�i�J��13:30�j
�ꏊ�F�@����w�s���J�L�����p�X �{�A�\�i�[�h�^���[26�K�X�J�C�z�[��
���ꗿ�F����
����F180���i����ɒB��������ߐ�ƂȂ�܂��j
�\�����@�F�\����p�t�H�[�� �ɕK�{��������͂��A���\���݂��������B
�q�v���O�����r
�E14:00�`14:10�@��|����
�E14:10�`14:40�@�R����q�i�@����w�\�y�����������j�u���̊��o�E���̏ꏊ�̋L���F�����\�̂����݂Ɩ��́v
�E14:40�`15:30�@��t�r�Y�i������w�t���a�@�z����Ȉ㏕���j�u�\�y�ƈ�w�̐ړ_�@�ӎ��̂��킢�v
�E15:50�`16:40�@�R���u�N�i�c��`�m���w�������j�u���ƕ��Ɛ���Ɓv
�E16:45�`18:00�@�f�B�X�J�b�V����
�u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v�̑�����2019�N3���ŏI���܂��B�������͂���5�N���܂�A�\�y�����̃t�B�[���h���g����ׂ��A�����O�Ŋ��邳�܂��܂ȕ���̌����ҁE�����҂Ƃ̋��͂�A����������i�߂Ă��܂����B�R���s���[�^�ł̗w���́ACG�ɂ�鉉�\��Ԃ̕����A���{�b�g�f�U�C���ւ̉��p���A�V���������������o���Ă��܂��B����̍Â��́A�����������_�̊����܂��A���̃X�e�[�W�Ɍ����Ă���ɂ�������A���ݏo���Ă݂悤�Ɗ�悵�܂����B�u���̂��v��������w��u���v�ɂ��čl����N�w�̕��@�́A�\���l����ۂɂǂ̂悤�ȐV�������ĂĂ����̂ł��傤���B����L�����O��`���̂ɒ������\�́A�������̈ӎ��△�ӎ��A���̂��A���Ƃǂ����т��Ă����̂ł��傤���B��w�E�N�w�̕���ł��ꂼ��V���������N�����Ă��邨��l���}���A������Q���݂̂Ȃ��܂ƂƂ��ɗl�X�ȕ�������l���Ă݂����Ǝv���܂��B
��ÁE�₢���킹��F
�@����w�\�y�������u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v
��102-8160 �����s���c��x�m��2-17-1
TEL03(3264)9815�@FAX03(3264)9607
�i2018/11/20�j
���njd�t�c Brass Collection Concert�i2018�N12��2���i���j�A��z�����w�u���j
�Â��̏��ł��B
�{�R�[�X�����A���J�삪�o�����܂��B
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N12��2���i���j14:00�J���i13:30�J��j
���F��z�����w�u���i��z�s�R���~��1�j
�����ꖳ���A���O�\���ݕs�v
�q���t�\��ȁr
�E���Ƃ��̐X�i�����G���j
�EBRASS-ISM�i�O�V�c�j
�E�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�E�Z���N�V�����iR.���W���[�X�j�@��
Brass Collection �v���t�B�[���F
�x�R���o�g�̉��t�Ƃō\�����ꂽ���njd�t�c�B�ÓT�I�ȍ�i����|�s�����[�܂ŕ��L���W�������̉��y���v���O�����ɑg�ݍ���ł���B����܂łɏ��{���A�����O�a�A�Љ������A�����\�q�A�p�猫�A�����L�ƁA����M���A�M���듿�A�����G���A�����~�̊e���ɐV����Ϗ��E�������A���̕Ґ��̃��p�[�g���[�g��ɍv�����Ă���B�����̍�i�ɂ͏�����o�ł���L���e���܂�Ă�����̂������B2006�N���10��̒�����t����J�Â���ق��A�S���̊w�Z�ł̉��y�ӏ܋����⎮�T�̉��t�ł��������B��z�ł̌�����2011�A13�A14�A15�N�ɑ�����5��ڂƂȂ�B
��ÁF��z�����w�A��z�����w�U�����͉�
�㉇�F��z�s�A��z�s����ψ���A��z���H��c���A��z�ό��R���x���V��������A�V������ЁA������Џ�z�^�C���X�ЁAJCV��z�P�[�u���r�W�����A�V�������t�y�A���A��z�n�搁�t�y�A��
���₢���킹�F��z�����w���L��
�@TEL090-6274-5685�@kouhou[at]juen.ac.jp
�i2018/11/19�j
�T�N�\�t�H���E�s�A�m�E�G���N�g�[���ɂ�郏���R�C���R���T�[�g�i2018�N11��4���i���j�A���c�܂����nj𗬊فj
�Â��̏��ł��B
�{�R�[�X��w�@������ÁE�o�����鉉�t��ł��B
���ڍׂ͂�����
joetsucity.com/event/2018-11-4onecoin
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N11��4���i���j14:30�J���i14:00�J��j
���F���c�܂����nj𗬊فi����l��s���c�x�X�j
Program�F
�EJ. �J���g���[�u �I�[���F���j���̉̑�1�W�iSax�j
�EC. �h�r���b�V�[ �ʼn�iPf�j
�ED. �V���X�^�R�[���B�` �j�T���ȁiEl�j
�EG. �K�[�V���C�� �A�C�E�S�b�g�E���Y���ϑt�ȁiSax&Pf&El�j�@��
�@���Ȗڂ͂�ނ��ύX����ꍇ���������܂��B
�o���F���V���iSax�j�A��c���g�iPf�j�A�����쌪��iEl�j
��ÁF�T�N�\�t�H���E�s�A�m�E�G���N�g�[���ɂ�郏���R�C���R���T�[�g���s�ψ���
�㉇�F��z�����w�A��z�s�A��z�s����ψ���
���₢���킹�FTEL090-6274-5685
�@kenji.kosukegawa[at]gmail.com�i������j
�i2018/10/25�j
�݂�ς����J�u����u���y����l���鋤���Љ�v�i2018�N11��2��(���j�A���o�z�[���j
�u���E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.minpaku.ac.jp/research/activity
...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
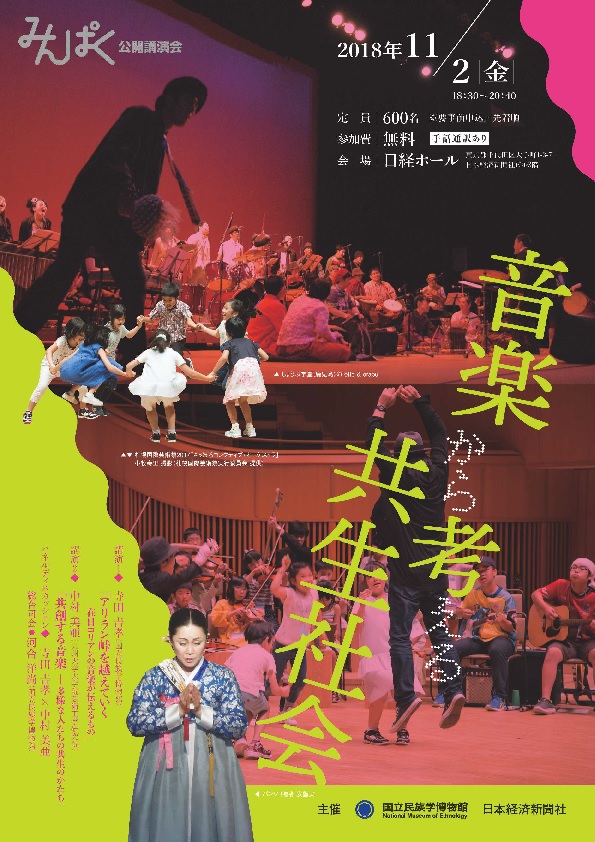
�����F2018�N11��2���i���j18:30-20:40�i�J��17:30�j
�ꏊ�F���o�z�[���i�����s���c���蒬1-3-7���o�r��3F�j
����F600���i�撅���j�@�Q����F�����i�v���O�\���j
����b�ʖ�
�\�����@�F�\���t�H�[���܂��͉����͂����ɂ�鎖�O�\����
�i�ڂ����� ������ �����Q�Ƃ��������j
��|�F
���E�e�n�Ŕr���I�ȍl���̑䓪���݂��錻��Љ�ł́A���l�ȏW�c�̋����͍ŏd�v�ۑ�̈�ł���ƍl�����܂��B�{�u����ł́A����܂ł̋��������ł͌y������Ă������y�ɏœ_�āA���������̂��߂ɉʂ�����������Ɖ\����T��܂��B
�v���O�����F
�E17:30-18:30 ��t
�E18:30-18:35 �J�� �����L�ցi���{�o�ϐV���Б��{�ЕҏW�Njǎ����j
�E18:35-18:40 ���A �g�c���i�i���������w�����ْ��j
�E18:40-19:15 ��|�����y�эu��1�u�A�����������z���Ă����F�ݓ��R���A���̉��y���`������́v���c�g�F�i���������w�����ً����j
�E19:15-19:50 �u��2�u���n���鉹�y�F���l�Ȑl�����̋����̂������v���������i��B��w��w�@�|�p�H�w�����@�y�����j
�E20:05-20:40 �p�l���f�B�X�J�b�V���� ���c�g�F�~���������@�i��F�͍��m��
�i2018/10/24�j
��14��v���\�i10��30���i�j�A��z������فj
�Â��̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jocci.jp/kubikinoh/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
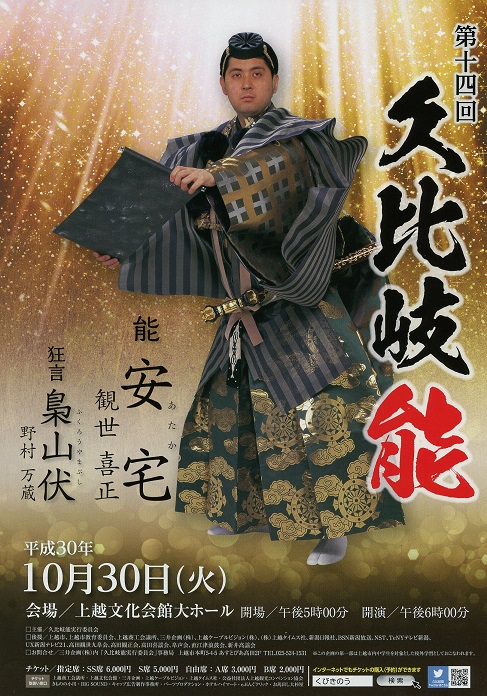
����30�N10��30���i�j
���F��z������ّ�z�[��
�J��F�ߌ�5��00���@�J���F�ߌ�6��00��
�@�i�I���\��ߌ�8��30�����j
�`�P�b�g�F�w��ȁ]SS��6,000�~�AS��5,000�~
�@�@�@�@�@���R�ȁ]A��3,000�~�AB��2,000�~
�ԑg�F
�E��� �ϐ��쐳
�E�d���u��➃N���q�v�����N�q
�E�����u���R���v�쑺�����A�쑺�C�I�A�㐙�[��
�E�d���u�J�V�i�v�ϐ���V
�E�d���u���c��v�i������
�E�\�u���� ���i�� �뗬�v�ϐ��쐳�A�������a�A����
�@ �|�s�w�A�K�M��A���쏲�ق�
�`�P�b�g�戵�������F��z���H��c���A��z������فA�O����A��z�P�[�u���e���r�W�����A��z�^�C���X�ЁA���v�Вc�@�l��z�ό��R���x���V��������A�����̂̏���ABIG SOUND�A�L���b�v�L�����쎖�����A�n�[�c�v���_�N�V�����A�z�e���n�C�}�[�g�Ae�ԂN���b�N�A���n�o���吙���@
���C���^�[�l�b�g�ł��`�P�b�g�̍w���i�\��j���ł��܂�
���⍇���F�v���\���s�ψ������
��z�s�{��5-4-5�����Ƃ҂����c2F�i�O���抔����Г��j
TEL025-524-1531
�i2018/10/23�j
��z�����w��w�@���y�R�[�X�w���ɂ�鉉�t��uAutunnale�v�i2018�N11��11���i���j�A��z�����w�u���j

11��11���i���j�A�{�w�u���ɂđ�w�@���ɂ��R���T�[�g�uAutunnale�i�A�E�g�D���i�[���j�v���J�Â��܂��B�@�����g�����E�^�c���s���A�����̌��r�̐��ʂ\����N�Ɉ�x�̋@��ł��B
�w�O�E�w�����킸�A�ǂȂ��ł������꒸���܂��B�����̕��X�ɕ����Ē����A��ᔻ�Ղł���Ǝv���܂��B���U�����킹�̏�A���Ђ��������������B
��z�����w��w�@���y�R�[�X�ɂ�鉉�t��uAutunnale�v
����30�N11��11���i���j ���F��z�����w�u��
�J��F13:00�@�J���F13:30�@
�����ꖳ��
�q���t�ȁr
�ER. �V���g���E�X�s8�̉̋ȁt��i10��� 1.���� 8.�����
�EL.v.�x�[�g�[���F�� �s�A�m�E�\�i�^��21�ԁu�����g�V���^�C���vOp.53 ��1�y��
�EC. ���C�l�b�P ���t�ƃA���O�� �A�p�b�V���i�[�g
�EF. �h�b�v���[ �A���_���e�ƃ����h
�EC. �h�r���b�V�[ �s���ƍ��Łt��� 2.���₩�ɈÂ� 3.�X�P���c�@���h
�E�O�P�W �nj��y�̂��߂̋��t��
��
�q�o���r
�╣�q�Ɓ@�Έ�G��@�c���x�@���R�仉ԁ@�����쌪��@���X�ʑ�
��c���g�@����ז��@���o���M�@���g�O�Ɓ@���V���@�g����I
����@���J�ā@�F��Ď��@�잊�K꤁@�є��؎q�@�Ð�t���@�Ð쏃��
�{�c�x���@�R������T�@�R���v�q�@�n糐�T
�����t�ȏ��s��
��Á^��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j
�⍇�킹�Fhirano [at] juen.ac.jp�i����j
TEL090-6274-5685�i�Έ�j
�i2018/10/22�j
�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�`���|�\�㉉��u�Ӑl�̌��|�F���ȁE�ڏ��S�E����߂̐��E�v�i2018�N11��3��(�y�E�j�j�A���n�s����R�~���j�e�B�[�Z���^�[�j
�Â��̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
nbz.or.jp/?p=18738
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�J���F2018�N11��3���i�y�E�j�j13:00�`16:00�i�J��12:30�j
�ꏊ�F���n�s����R�~���j�e�B�[�Z���^�[�i���n�s���240�j
���� �O�c�����Ɣ��i
��؍F�f���i����t���j�i�V����w���_�����j
�E�|��
����l�` �^����
�E�ߐ{�^�s���C���@�ܒi��
����F�r�c�N�v���i�V����w���_�����j�@
�ڏ��S �z���ڏ��S ���̗t��
����b�q���A����^���q��
�E��t���S�@�⎺
�E�Օ�����@���̗t�q�ʂ�
�E�ڏ����@������
����F�r�c���p���i�ڏ��S�l�b�g���[�N��j
�R�[�f�B�l�[�^�[�F���t�v���i���{�H�Ƒ�w�����j
����F200���i�v�\���E���R�ȁj
�����F����
�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�u�����A�����O�A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B
�\�����ݐ�F�V���������j������ �o�c����
�@��940-2035�����s����1���ڎ�������2247��2
�@TEL0258-47-6135�@FAX0258-47-6136
�@E-mail:koryu[at]nbz.or.jp
�i2018/10/18�j
�������y��w�������y������ 2018�N�x���J�u��No3�u�ɕ������̈₵���y��F�����y�������8�v�i2018�N10��27��(�y�j�A�������y��w�j
���J�u���̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.minken1975.com/kouza_exhibition
...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
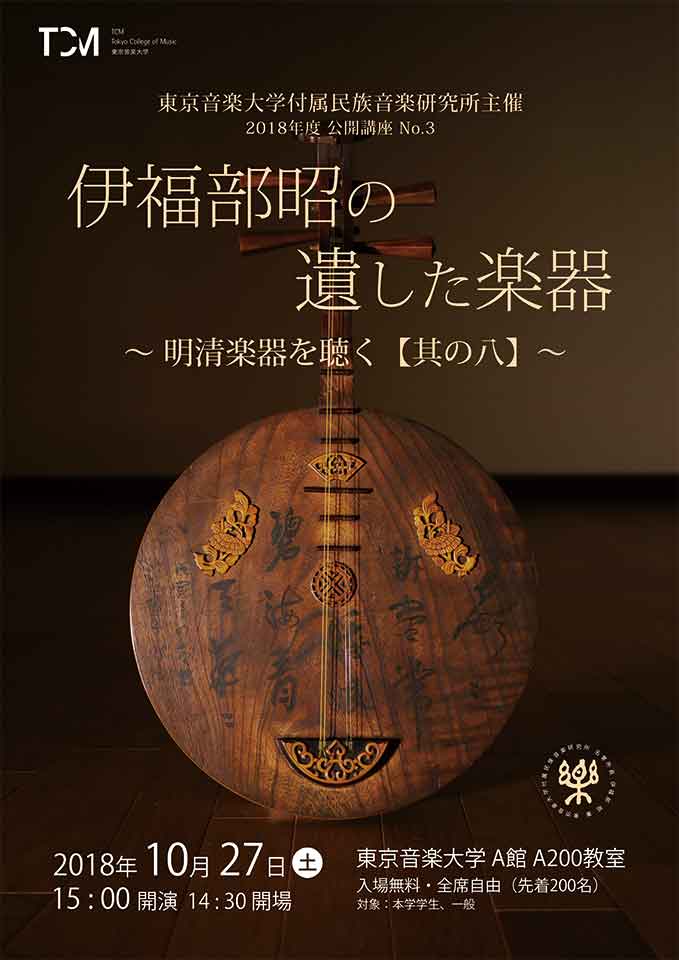
�J���F2018�N10��27���i�y�j15:00�J��
�ꏊ�F�������y��w A��A200����
�\���F���ꖳ���A�\��s�v
����F200���B�����撅���̂�����ƂȂ�܂�
�u�����e�F�́E�ɕ��������㏊�����N�W�����A�M�d�Ȗ����y��A�y���Ȃǂ̎��������J�����t����ȂǁA2011�N��薈�N�H�ɊJ���Ă��邱�̌��J�u�����A8��𐔂��邱�ƂƂȂ�܂����B���̓x�����肩�猳���薾���y�ۑ������̎R�c�c�q�A�Y�c�����������������A�܂��A�Րl�F��c���j���ɂ��u�Պw�v�̉��t�������āA����14���ɂ��A�Â���q�˂鉹�y�����������������܂��B
�@����ɍ���́A���N�����t�̉̐l�A�唺�Ǝ����a1300�N�̋L�O�̔N�ł����邱�Ƃ���A��4��̍u���̍ۂɃ\�v���m�Ɩ����y��ʼn��t�v���܂����ɕ������̔ӔN�̍�i�A�唺�Ǝ��E�唺���Y���̉̂ɂ��s�������t�̉̂ɂ���t�����Ȃ̕Ґ��ŁA�\�v���m�F�|�c�^���q�A�A���g�E�t���[�g�F����^���A��\�܌�ⵁF��c���q�q���̉��t�ł��������������܂��B�ǂ����A���y���݉������B
�i2018/10/18�j
���������w���8���� �V���|�W�E���u���������Ɓq���́r������v�i2018�N10��27���i�y�j�A�����̐����q��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
bunkashigen.jp/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N10��27���i�y�j13:00�`
���F�����̐����q��w ��w�{��306����
�E13:00�@�J��
�E13:30�@��|�����i��ؒ��G ���������w��E�����̐����q��y�����j
�E13:40�`14:40�@�u���u�A�[�g�i���p�j�ƃA�[�e�B�t�@�N�g�i�함�j�F���p�قƔ����ق̂������v�g�c���i���i���������w�����يْ��j
�E14:50�`15:10�@�R�����g�i�P�j���p�ق̗��ꂩ��@�؉����V�i������w�����A�É��������p�يْ��j
�E15:10�`15:30�@�R�����g�i�Q�j�l�Êw�̗��ꂩ��@�x���G���i������w�y�����E�l�Êw�j
�E15:30�`15:45�@�x�e
�E15:45�`16:45�@�p�l���f�B�f�B�X�J�b�V���� �g�c���i�A�؉����V�A�x���G���@�i��F��ؒ��G
�@2017�N1������n�܂����W�]�v���W�F�N�g�u���������̌��݁v���A���悢��ŏI����}���܂��B�ŏI��ł́A���������w�����ق̋g�c���i�ْ������������A���b�����������܂��B
�@����܂ł̌�����ł́A�w����ӂ肩�����Ƃ��s������Łi��1-5��j�A�u���������v�̌������Ղ��Ă܂���܂����B���Ȃ킿�A�������ɂ�����u���`�������v�i��2��j�̎��g�݂Ɓu�d�v���`�������ێ��ҁv�̌����i��3��j�A�n�������̂ɂ�����u���������v�ւ̎��g�݁i��4��j�A��w����ɂ�����u���������v�i��5�A7��j�A�w��Ǘ��Ґ��x�Ɣ����فE���p�فi��6��j�A�f�W�^���Z�p�ɂ��u���������v�̊��p�i��7��j�ł��B����ꂽ�ł������A�u���������v�ɂ�����鎖��L���݂Ă܂���܂����B
�@������������܂ł̋c�_���ӂ܂��A�ŏI��ł͂��炽�߂ĕ��������Ƃ����ϓ_����u���́v�ɂ��čl���܂��B�����l�ފw�A���p�j�w�A�l�Êw�ȂǁA�u���́v�������w��͂��낢�날��܂����A���ꂼ��̊w�╪��ō��x�ȋc�_���s����قǁA���̋c�_�Ŏg���錾�t�͑��̕���ł͒ʂ��Ȃ����̂ɂȂ��Ă����܂��B���������A�e�w�╪��ɂ�����u���v�i�����Ƃ����O��j���I��ƂȂ�̂��A�����فE���p�ق̓W����Ƃ����@��ł��B
�@���}������g�c���i�搶�́A����܂ŃA�t���J���t�B�[���h�Ƃ��镶���l�ފw�҂̂����ꂩ��u�ٕ����ւ̂܂Ȃ����v�W�A�u�A�W�A�ƃ��[���b�p�̏ё��v�W�A�u�C���[�W�̗́v�W�Ȃǂ��肪���Ă����܂����B���������A�����قƔ��p�قɂ܂����邲�����Ƃ������ɂ��Ă��b�����������܂��B�u<����>���ǂ̂悤�Ɍ���Ă������v�ɂ��Č��Ȃ���A���炽�߂āu���������v�Ƃ��������A����сu���������w�v�Ƃ����A�v���[�`�ɉ����\�Ȃ̂��l���Ă݂܂��傤�B
�i2018/10/17�j
�S����w���y����w��֓��n�敽��30�N�x��2����i2018�N10��20���i�y�j�A�\�����w�����q��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
www.nacome.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N10��20���i�y�j13:00�`17:00
���F�\�����w�����q��w�iJR��������V���w���k��8���j
�E12:30�`13:00 ��t
�E13:00�`14:30 �������\
(1)�u�o�C�G�������{�`���̊y�ȌQ�ɕt�����鎋�o�I�H�v�ƁA���ʓI�ȓǕ��w�K�ւ̃A�v���[�`�ɂ��āv�����R���q�i����������w�j
(2)�u�������y�ȋ���@�ɂ�������H�I�w���͂�L���鋳�t���琬������Ǝ��H�ɂ��Ă̌����F���w�Z�������u�]����w���ւ̉��y���Ƃɑ����ے����v���Ǝj�l�i���{�̈��w�j
(3)�u�Ȗځq���yII�r�̐U��Ԃ�Ɓq���y���H���KII�r�ւ̎��ƓW�J�ɂ��āF�U��Ԃ�V�[�g�̕��͂�ʂ��āv�Ԓˑ��Y�i����������w�j�A�{��m�q�i����������w�Z����w���j
�E14:40�`17:00 �u���{�̂��ׂ����v�ɂ��Ẵ��[�N�V���b�v�i���N�`���[���܂ށj�ƃ��E���h�e�[�u��
�e�[�}�F���ׂ�������n�߂鉹�y����
��1���F���[�N�V���b�v�i���N�`���[���܂ށj
�@�u�t�F�|�c���㎁�i�O���߂̂��ۈ牀�����j
��2���F���E���h�e�[�u��
�@�b��ҁF���g�֎q���i�쑺�w�����q��w�j
�@�t�@�V���e�[�^�[�F��{�I�q�i�\�����w�����q��w�j
�Q����F���1,000�~�A���1,500�~
��������F17:30�`10:30 ���5,000�~
�i2018/10/16�j
��53��V�������y�R���N�[����҃R���T�[�g�i2018�N11��10���i�y)�A�������z�[���j
�Â��̏��ł��B
�R���N�[���Ō��m���܂���܂�����w�@���̓c���x���o�����܂��B
����Î҃T�C�g�͂�����
http://www.niigata-nippo.co.jp/life/event...
http://www.ohbsn.com/event/2018
...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
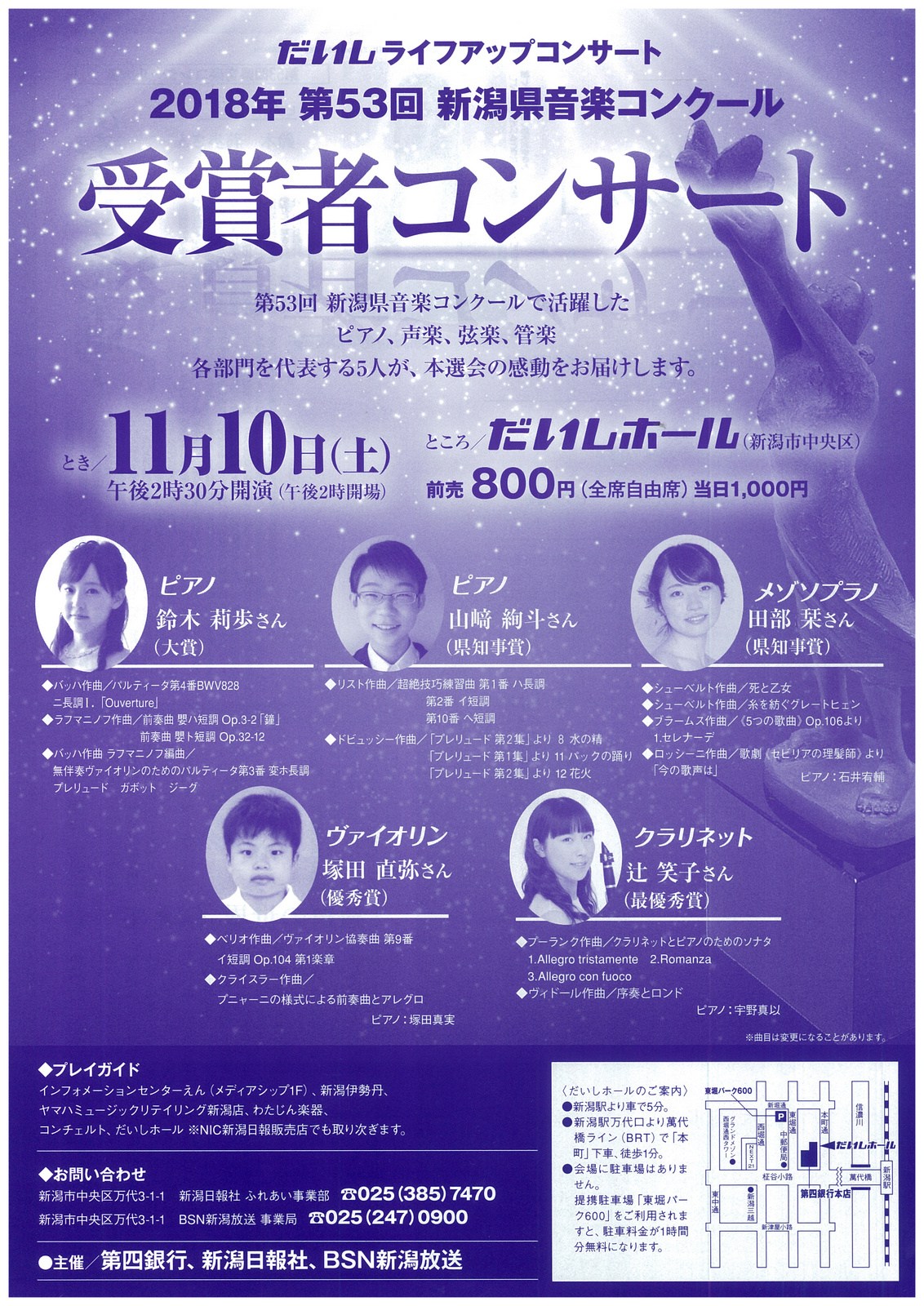
�J�Ó��F11��10��(�y)�@�ߌ�2��30���J���i�ߌ�2���J��j
�Ƃ���F�������z�[��(�V���s�����擌�x�O��7�Ԓ�1071-1)
���ꗿ�F�O����800�~�A������1,000�~
���仕�����i�s�A�m�E��܁j
�E�o�b�n��ȁ^�p���e�B�[�^��4��BWV828 I. Ouverture
�E���t�}�j�m�t��ȁ^�O�t��Op.3-2�u���v�AOp.32-12
�E�o�b�n��ȁA���t�}�j�m�t�ҋȁ^
�@�@�����t���@�C�I�����̂��߂̃p���e�B�[�^��3��
�@�@�@�v�������[�h�A�K�{�b�g�A�W�[�O
�R�舺�l����i�s�A�m�E���m���܁j
�E���X�g��ȁ^����Z�I���K�� ��1�ԁA��2�ԁA��10��
�E�h�r���b�V�[��ȁ^�v�������[�h��2�W��� 8���̐��A12�ԉ�
�@�@�v�������[�h��1�W��� 11�p�b�N�̗x��
�c���x����i���]�\�v���m�E���m���܁j
�E�V���[�x���g��ȁ^���Ɖ����A����a���O���[�g�q�F��
�E�u���[���X��ȁ^�s5�̉̋ȁtOp.106��� 1.�Z���i�[�f
�E���b�V�[�j��ȁ^�̌��s�Z�r���A�̗����t�t���u���̉̐��́v
�i�s�A�m�F�Έ�G��j
�˓c���킳��i���@�C�I�����E�D�G�܁j
�E�x���I��ȁ^���@�C�I�������t�ȑ�9��Op.104 ��1�y��
�E�N���C�X���[��ȁ^�v�j���[�j�̗l���ɂ��O�t�ȂƃA���O��
�i�s�A�m�F�˓c�^���j
�ҏΎq����i�N�����l�b�g�E�ŗD�G�܁j
�E�v�[�����N��ȁ^�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̃\�i�^
�@1.Allegro tristamente�A2.Romanza�A3.Allegro con fuoco
�E���B�h�[����ȁ^���t�ƃ����h
�i�s�A�m�F�F��^�ȁj
�v���C�K�C�h�F�C���t�H���[�V�����Z���^�[����(���f�B�A�V�b�v1F)�A�V���ɐ��O�A���}�n�~���[�W�b�N���e�C�����O�V���X�A�킽����y��A�R���`�F���g�A�������z�[���@��NIC�V������̔��X�ł���莟���܂��B
��ÁF��l��s�A�V������ЁABSN�V������
���₢���킹��F�V������Ђӂꂠ�����ƕ��iTel025-385-7470)�ABSN�V�����������ǁiTel025-247-0900)
�i2018/10/15�j
�S���{���y���猤����S������w���� ����30�N�x���i2018�N10��20���i�y�j�A������w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jsme.net/univ.htm
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N10��20���i�y�j
�ꏊ�F������w�iJR������ˉw���ԁA�k��5���j
��w������F�u���y���炪�����ɓ`������́v
�X�P�W���[���F
9:30�` ��t
10:00�`10:10 ���A��������
10:15�`12:30 �������\
13:45�`14:45 ���[�N�V���b�v
14:50�`15:45 ���}���t��
16:00�`17:30 ���Z�v�V����
�q�������\ ��1���r�i1321�����j
�E�g����ߎq�i�������y��w�j�u�����̌���\�����猩�鉹�y�I�n�����F���y�����ɂ�����O���[�v���b�X���̍l�@��ʂ��āv
�E�������ߎq�i�c�{�ّ�w�j�u�����E�ۈ�җ{���ے��ɂ����郊�Y���p�^�[���ɒ��ڂ����R�[�h�l�[���̊w�K�v
�E�����c�q�i�É���w�j�A���J��N��i��w�j�u�����{���ɂ�����s�A�m���Z��]�����邽�߂̃��[�u���b�N�쐬 �v
�E������q�i����w�j�A�����x���q�i�������y��w�j�u���y�ȋ���ɂ�����i���j���̂̋��މ��F�`�����y�Ɛg�̐��v
�q�������\ ��2���r�i1322�����j
�E���G�l�i���l������w�j�u���y�ȋ���ƒn��ނ̜�����ʂ����[���w�т̉\���F���w�Z�ɂ�����A�E�g���[�`�̊ώ@����v
�E�R�{�^�I�i������w�j�u�q���特�y�r�Ƃ����p��ɂ��Ă̗��j�I�l�@�F���p����O�l�ɒ��ڂ��āv
�E�e�n�q�q�i�ʐ��w�j�u������w�ɂ�����\���t�F�[�W������̎���ƍH�v�v
�q���[�N�V���b�v�r�i���f�B�A�z�[���E���r�[�j
�u�̕��ꍕ����y��̓W���ƃ��[�N�V���b�v�v
�Ύ�،��q�����A �Q�X�g�u�t�^�P�ߐ��v�i�M�y���q���j
�̕���̍�������y�Ɏg����l�X�Ȋy��̎��ۂ�W�����āA ���w�҂����R�ɑ̌�����R�[�i�[�����B�Ύ�؋����ƃQ�X�g�̖P�ߐ��v�u�t���M�y��̉��t���@�����Љ�A�Q���҂��������t�̌�����B������t����B���ł͉f���@��ŁA�y��̉��t�@�̈����������f���������Ă����\��B
�q���}���t��r�i���f�B�A�E�z�[���j
�u�����ɂ��Ƒt�A�Ə��v�k��X��(Fl)�A����q�q(Sop.)
�u����F�v�Ɗy���ދ��������̐��E�v����F�v�y����
�`���A������w���t�w�ȋ����ɂ��Ƒt�A�Ə������������������B���t�͖k��X���i�t���[�g�Ƒt�j�A����q�q�i�Ə��j�A�s�A�m�͐X���p�q�̊F����B �����Č㔼�́u����F�v�Ɗy���ދ��������̐��E�v�����y���݂��������B�Ŕ����̏���F�v�y�����̎w���ŁA�����{���R�[�X�w�������ɂ�鍇���̉��t�B����͊w���̍�������ɏ���搶�̍�Ȃ���������i�𒆐S�ɁA��̉\��������I�ڂ���B
�i2018/10/5�j
�@����w�\�y�����������W��u�\�y���������̉\���v�i2018�N10��21���i���j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
kyoten-nohken.ws.hosei.ac.jp/info/2018/3150/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N10��21���i���j13:00�`17:15�i�J��12:30�j
���F�@����w �s���J�L�����p�X�{�A�\�i�[�h�^���[26�K�X�J�C�z�[��
�����ꖳ���A���O�\���s�v
�{�����W��́A�u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v�����ɂ����Ȃ������������̂����A�e�[�}�����T�u�\�y���������������Ɋ�Â������w�I�E����w�I�����v�̑����Ƃ��āA�\�y���������̂��܂��܂Ȑ��ʂ\������̂ł��B�\�y���������ɂ͂ǂ̂悤�ȉ\��������̂ł��傤���B���{��w�E�����w�E�Ŗ{�����w�E���j�w�ȂǁA�]���̔\�y�����̘g�g�݂������L���A�v���[�`�Ɋ�Â��ŐV�̎��g�݂��Љ�A�\�y���������̍���̍s����W�]���܂��B
�E13:00�`14:00�u�]�ˎ���̔\���҂̗�������ǂށF�w�ߐ����˔\���җR�����W���x�̊��s�Ɍ����āv�{�{�\���i�@����w�\�y�����������j
�E14:00�`15:00�u�]�ˎ��㏉���o�Ŏj�̒��̗w�{�̏o�ŁF�Ê����ʉ��w�{�̕\����������ʂ��āv�������u�i�����w���������ً����j
�E15:15�`16:15�u�\��i�̕��������l����v�����I��i�c��`�m��w�����������z�����ɏy�����j
�E16:15�`17:15�u�\�y�`���ނ̍���w�I�����F�K�͂ƋL�q�̖��v�L�����V�i��q��w�����j
��Á^�₢���킹�F
�@����w�\�y�������u�\�y�̍��ہE�w�ۓI�������_�v
��102-8160 �����s���c��x�m��2-17-1
TEL03(3264)9815�@FAX03(3264)9607
�i2018/10/4�j
���{���ފw���30�����\���i2018�N10��20���i�y�j�E21���i���j�A���R��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.kyozai-gakkai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N10��20���i�y�j�E21���i���j
���F�w�Z�@�l���R��w�{�n�L�O��
�@�L�������R�s�۔V��1����2��40��
�@TEL084-932-6300�@FAX084-932-6354
���Q����F�����\2,000�A�Վ����\4,000�A�w��\1,000
�����E�����F
�E10��20���i�y�j ��t11:00�`
12:00�` ������
13:00�`13:50 �V���|�W�E���A��u��
14:00�`15:20 �V���|�W�E���A�������_
15:20�`16:00 ����
16:10�`18:15 �������\�A�����v���W�F�N�g�A�|�X�^�[���\
18:35�`20:35 ��������
�E10��21���i���j ��t8:30�`
9:00�`11:05 �������\�A�����v���W�F�N�g
12:00�`14:00 �����v���W�F�N�g
14:15�`14:45 �����E�l���E��B�x������
�E�V���|�W�E���F10��20���i�y�j13:00�`
��u���u�V�w�K�w���v�̂Ɋ�Â����ފJ���̐V���_�v
�吙���p�i�Ɨ��s���@�l���E���x���@�\�j
�E��������:10��20���i�y�j18:35�`
���R�j���[�L���b�X���z�e��
��������Q����F\3,000
�i2018/10/3�j
���{���Y���w���36����i2018�N10��6���i�y�j�A�t�F���X���w�@��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.japaninstituteofrhythm.cho88.com/taikai...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N10��6���i�y�j12:00�`17:30
�ꏊ�F�t�F���X���w�@��w6����631����
�i���l�s����R�蒬37�j
�E�u�A�j���E�Q�[���\���O�ɂ�����q�����I�Ȃ���partial connections�r�F�̎��ɂ�����gdestiny�h�̉��y�I�����ɒ��ڂ��āv��������i�_�ˑ�w�E���{�w�p�U������ʌ�����PD�j
�E�u���{�̃|�s�����[���y�ɂ������O�I�Șa���F�������̓v���O�����̍\�z�v�ēc�z��i��B��w��w�@�|�p�H�w�{�C�m2�N�j�E���c�h�q�i��B��w��w�@�|�p�H�w�����@�����j
�E�u���@�Ƃ͉����H�i��9��j�q�_��a���r�̉��f�ޕ��́F�X�N�����[�r���s�A���o���̈�t�t��i58�i1910�N�j�̕��́v���㏁�i���{���y���_������A���y���͊w������j
�E�u�C�X���[�����C���h�̃y���V���ꉹ�y���ɂ݂郊�Y�����_�̗Z���v���t���i���s��w�A�W�A�E�A�t���J�n�挤�������ȁj
�E�u�p�ꃊ�Y�����[�u�����g�̊T�O�Ǝ��H�v�ΐ�ǔ��i��ʎВc�@�l�p�ꃊ�Y�����[�u�����g����(ERMA) ��\�����j
�E�u�w�̃��Y���Z�@�ɂ�鎵�ܒ����͂̕ϗe���F�V�e���ܗ��h�̔�r��ʂ��āv�Ⓦ���q�i�\�y�ϐ����V�e���j
�E�u���m����7�̃��Y���p�^�[���͂ǂ�������őI��Ă���̂��v���c���i���y�w�ҁj
���e���\���e�̏ڍꗗ�y�[�W�́�����������
�i2018/10/2�j
���{���y����w���49�R���i2018�N10��6���i�y�j�E7���i���j�A���R��w�j
�w��E������̏��ł��B
�{�R�[�X�����̔���A�{�w�������w�Z�����̓��V��搶���������\���s���܂��B
�������T�C�g�͂�����
http://���{���y����w��.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N10��6���i�y�j�E7���i���j
���F���R��w���L�����p�X ����w���u�`���E�k���y��
�i�A�N�Z�X�Fhttps://edu.okayama-u.ac.jp/access/�j
�E10��6���i�y�j
9:00�` ��t
9:30�`11:30 �������\A�`I
11:30�`12:15 �|�X�^�[���\S
13:00�`14:30 �v���W�F�N�g�����A�������I�`III
14:40�`17:30 ���s�ψ�����i��u���A�V���|�W�E���j
17:40�`18:30 ����
18:30�`20:00 ���e��
�E10��7���i���j
8:30�` ��t
9:00�`11:30 �������\J�`R
12:00�`13:30 �@���t�H�[����
12:45�`13:30 �|�X�^�[���\T
13:30�`15:00 �������IV�`VIII
15:15�`16:45 �������IX�`XI
�E�v���O�������
�q���s�ψ�����r
�u��含���ɂ߂�E�a���E�q���v
�i10��6���i�y�j14:40�`17:25 �u�`��5202�j
�E��u��(1)�u���ۉF���X�e�[�V��������̒n�������w��C�̎B���ϑ��ƃf�W�^�����̒n���V�ɂ�鋳��E�A�E�g���[�`�����vꎓ������i���s��w��w�@���w������ �n���f���Ȋw��U�j
�E��u��(2)�u�x�ڐA�̌���v�員���G�i���R��w����ڐA��ÃZ���^�[�j
�E�V���|�W�E���u��含���ɂ߂�E�a���E�q���v�p�l���X�g�Fꎓ������A�員���G�@�i��F����e�q�i���R��w�j
�q�������\�r
�E���V��i��z�����w�������w�Z�j�u���ʊ����ɂ����鉹�y�̖����v�i�������\B-4�F10��6���i�y�j9:30�`11:30�A�u�`��5303�j
�E����S�i�i��z�����w�j�u�}�C�m���e�B�ւ̋��炩�琶�����ꂽ����J�N�Y�̉��y�q�Ö@�r�ρF�q���������r�̖ڕW�Ɠ��e�����Ȋw�K�ɔ��f�������y����v�i�������\C-1�F10��6���i�y�j9:30�`11:30�A�u�`��5304�j
�i2018/10/1�j
���{���y�w����{�x����43��i�ʎZ394��j���i2018�N10��13���i�y�j�A���s����w�~�c�T�e���C�g�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia/msj/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N10��13���i�y�j�@14:00�`16:00
���F���s����w�~�c�T�e���C�g �����𗬃Z���^�[��z�[��
�i���w�O��2�r��6F�j
�A�N�Z�X�Fhttps://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/university/access#umeda
�q�C�_���\�r
1. ���V���u�i�����ّ�w��w�@�j�u���{�ɂ�����q�����������m���y�r�ς̌`���F����20�N��̉��t��]�̓W�J����v
2. �c�ɉ��ߊG�i�{���[�j����w��w�@�j�u�V���p�����g�p�����y��ɂ��Ă̈�l�@�F�u�[�t�z���c�E�s�A�m�ƃv���C�G���̃��j�R�[�h�E�s�A�m�𒆐S�Ɂv
�q�������\�r
3. ���{����i���炩�ȃo�b�n�̉�j�u���炩�ȃo�b�n�v
�i2018/9/27�j
�����|�p�w���150�����i2018�N10��6���i�y�j�A���{���]�V�q�������|�p�n���Z���^�[�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://ethno-arts.sakura.ne.jp
/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F10��6���i�y�j 13��30���`17��30��
�ꏊ�F���{���]�V�q�������|�p�n���Z���^�[
�i���s����]�V�q��2����1��34���j
��ʁF�n���S����O���E���������g���w���ԁA8�ԏo�����琼�֖�150��
�V���|�W�E���u���L�����J��(�A���p�b�N�j����F�w�v���X�A���g�x���Ƃ����A�h�E�A�[�J�C���vUnpacking Kansai Advertising Materials�F�gPRES ARTO�h as ad archives
1930�N�ォ��70�N��܂Ŋ��Ŕ������ꂽ��i�t�L���E��`��]���w�v���X�A���g�x�̌����B�����ɕt�^���ꂽ�L���������悻6000�_�����ƂɁA���𒆐S�Ƃ������{�̍L���\���j���l����B
�ҁF�|���K�G�i���u�Б�w�j�A�A�،[�q�i���V���p�ٌ��ݏ������j�A������O�i���s���ؑ�w�j�A�F�q��сi���s���`�|�p��w�j�A�����P�F�i���É��|�p��w�j�A�֓��T��i����w�j
���֘A�W���F10��2���i�j�`10��13���i�y�j���F�����M�������[
�S�������F�����O
�A����F�{���������@mg_gakkai[at]yahoo.co.jp
�i2018/9/26�j
�w��z�����w�����I�v�x��38��1���i2018�N9���j
�{�w�����I�v�w��z�����w�����I�v�x�̍ŐV���i��38����1���AISSN:0915-8162�j�����s����܂����B�{�R�[�X�����i�����A����A�ʑ��j����уR�[�X�����w���E�C�����̘_�e���f�ڂ���Ă��܂��B

�q���^�_�����r
�E����S�i�A�v�ۓc�b���A�������q�u���y�Ȃɂ�����q�����I�ȕ����r�Ɓq����I�ȕ����r�ɂ��w������ : �������q�ق�����̂����r�i���w�Z��P�w�N�j��������H���v�i167-178�Łj
�E�ʑ����A���u�s�������̓��Ɂt�͖��Ȃ��H�v�i179-194�Łj
�E�������A���Ŏq�A�����I�q�u�Θb�I�E�����I�Ȋ����ɂ��[�߂�n��w�� : ���w���E�����{���ے��w����ΏۂƂ������H����v�i205-216�Łj
�{�w�����}���ك��|�W�g�� �őS�����{���ł��܂��BPDF�t�@�C���ł̃_�E�����[�h���\�ł��B����ǂ��������B
�i2018/9/25�j
����j�w���62����i2018�N9��29���i�y�j�E30���i���j�A�ꋴ��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://kyouikushi62.blogspot.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N9��29���i�y�j�E30���i���j
���F�ꋴ��w �������L�����p�X
�@��186-8601�����s�����s��2-1
�@http://www.hit-u.ac.jp/guide/campus/kunitachi.html
���Q����F��ʉ���E�Վ����3,000�~�A�w����������A
�@�w���Վ����1,000�~
�^�C���e�[�u���F
�E9��29���i�y�j
8:15�` ��t�i�{��1�K�z�[���j
9:00�` �������\�i�{��2�K22�E23�E24�E25�E28�ԋ����j
13:00�` ����E����������^���i�{��2�K21�ԋ����j
14:10�` �V���|�W�E���i�{��2�K21�ԋ����j
18:00�` ���e��i���L�����p�X�������H���j
�E9��30���i���j
8:15�` ��t�i�{��1�K�z�[���j
9:00�` �������\�i�{��2�K22�E23�E24�E25�E28�ԋ����j
13:00�` �������\�i�{��2�K22�E24�E25�E28�ԋ����j
15:40�` �R���L�E���i�{��2�K23�E24�E28�ԋ����j
�V���|�W�E���F
�����F9��29���i�y�j14:10�`17:40
�ꏊ�F�ꋴ��w �������L�����p�X�{��31�ԋ���
�e�[�}�F�u����j�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȋw�₩�F�u60���N�L�O�o�Łv�̌����܂��āv
��ĎҁF�u60���N�L�O�o�Łv�̐���҂̗��ꂩ��
�@���{����j�̈�@�ēc�r�F�i�����̐����q��w�j
�@���m����j�̈�@�{�{���s���i���w�@��w�j
�@���m����j�̈�@�V�ۓ֎q�i����c��w�j
�w�蓢�_�ҁF
�@��r����Љ�j�̎��_���� �≺���i�R�w�@��w�j
�@����̎Љ�j�̎��_���� �O�c���q�i��������w�j
�@���E���{�Ƃ̊֘A�̎��_���� ���ΐ��l�i�L���������q��w�j
�i��F�ؑ����i�ꋴ��w�j�A�R���~�i������w�j
�i2018/9/21�j
���J�u����u���여�ċz�@�̃��\�b�h�ƌ��ۂ͐l�̉Ȋw�ɂ����Ȃ�q���g��^���邩�H�v�i2018�N9��29���i�y�j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/flas
...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N9��29���i�y�j16:00�`18:00�i15:15�`��t�j
���F����c��w �ˎR�L�����p�X36����2�K382����
�Q����F����
�u���ҁF�јa�q���i���k��w���_�����E��t�j
�u���여�ċz�@�̃��\�b�h�ƌ��ۂ͐l�̉Ȋw�ɂ����Ȃ�q���g��^���邩�H�\�ċz�����̗��ꂩ��ċz��Fascia/Soma���l����v
�ċz�͐l�́iSoma�F�g�̂Ƃ�body�����A��U�w�I�i���_�I�ꊴ���܂߂��̌���g���j�ɂƂ��ĉ��̈Ӗ�������̂��HNHK�X�y�V�����u�l�́v�����Ă��u�ċz�v�̐����͂Ȃ��B�u�ċz�v�̖{���́A�����w�ł͗��j�I�ɖ��߂�ꂽ�܂܂œ�ł���B�u�ċz�v�͔x�Ƃ�������ƂƂ��ɁA�g�̑S�̂ɂ��`������B����͐Ғœ����i����Soma�ƌċz�^���i��C�k���ł͐��l�̏o���j�����i�����Ă�������ł���B�]���Čċz�@�ł́A�K�X�����ɂ������āASoma�ւ̓������������ƂȂ�B��������̂Ɏ~�܂炸�A����Soma�͌ċz��communication���ł���BAI��VR���O�ʂɂł�21���I����l�ԂƂ��āASoma�����߂�����́u�s�v�A���여�ċz�@�̎a�V�ȃ��\�b�h�ƌ��ۂ��Љ�A���̈Ӌ`���l����B
���ÁF�l�̉Ȋw��A����c��w�����l���Ȋw�����Z���^�[�i�u�s���E�Љ�E�����Ɋւ��鑽�p�I�A�v���[�`�v����j�A����c��w�S���w��
�i2018/9/20�j
�w���y����w�x��48����1���i���{���y����w��A2018�N8���j
�w��ŐV���̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://���{���y����w��.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�q�����_���r
�E�؉��a�F�E����y��u�T���v�����O�̎�@��p�����n�슈���̋���I�Ӌ`�F���f�ނ̉��H�A�n��p�\�t�g�̊��p�̊ϓ_����v1
�E���c���v�u���y����N�w�ɂ�����u�Љ�`�v�_�̒n���F�|�X�g�R���j�A����]�A�E�\�z�A���x�����Y���Ɋ�Â��c�_�̏����v13
�q�����r
�E����葾�Y�u���Y��`�̐����ɂ����鉹�y�̐�勳��F���h�C�c���勤�a���ɂ݂鐺�y����̎���v25
�q���]�r
�E�R�{�G�q���w���ۂ̕������x�i�c�������q�j36
�E�E�B���A���E�u���E�����A���~��w���i�w���E�v���X���[�̃s�A�m���b�X���F���y�E�̎����A�|�p�I�ȉ��t�ւ̃q���g�x�i�؉����j38
���� 40
ISSN:0289-6907
���s���F����30�N8��31��
���s���F���{���y����w��
�@�����ǁ@184-0004�����s������s�{��5-38-10-206
�@�@�@�@�@�d�b�EFAX042-381-3562�@Mail: onkyoiku[at]remus.dti.ne.jp
�i2018/9/19�j
��w�@��������J�Â��܂�
������9��22���i�y�j�ɁA��w�@��������J�Â��܂��B�{�w�̋��E�����ꓰ�ɉ�A�{�w�̋���E�����̓��F������̊T�v�A�C����̐i�H���ɂ��đ��k�������܂��B
��w�@�ւ̐i�w�����l���̕��A�{�w�̎��g�݂ɋ�����������̕��A�����w�������B�w���h�ɂ��͂��ߑ�w�������w����c�A�[�Ȃǂ�����܂��B�ʂ̎���₲���k�ɂ����������܂��̂ŁA���̋@��ɂ��Б������^�т���������Ǝv���܂��B

��z�����w ��w�@������
����30�N9��22���i�y�j13:00�`16:00
���F��z�����w�i�V������z�s�R���~��1�j
���k���V�����u��z�����v�w�Ƒ�w�L�����p�X�Ԃ��������}�o�X���^�s���܂��B�ڍׂ� ������ ���������������B
�����̑��ɓ����Ɩ��É��Łu��w�@���w���k��v�𐏎��J�Â��Ă��܂��B����ɂ��Ă� ������ �ł��ē����Ă��܂��̂ł������������B
���\���݁E���₢���킹
�E��z�����w���L��
Tel025-521-3626 / Fax025-521-3627
�E���y�R�[�X ��w�@������S��
Tel025-521-3514 / MAIL: tamamura [at] juen.ac.jp
��������\��̕��͎��O�ɂ������K���ł��B���L�����N�́u�y������zWeb�\���݂͂�����v���炨�\���݂��������B�������A�\�����݂Ȃ��ł��Q���ł��܂��B
�i2018/9/18�j
��z�����y�c��81�������t��i2018�N9��16���i���j�A��z������فj
�Â��̏��ł��B
�{�R�[�X�����̒��J�삪�o�����܂��B
�������T�C�g�͂�����
http://www5a.biglobe.ne.jp/~jsovn/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
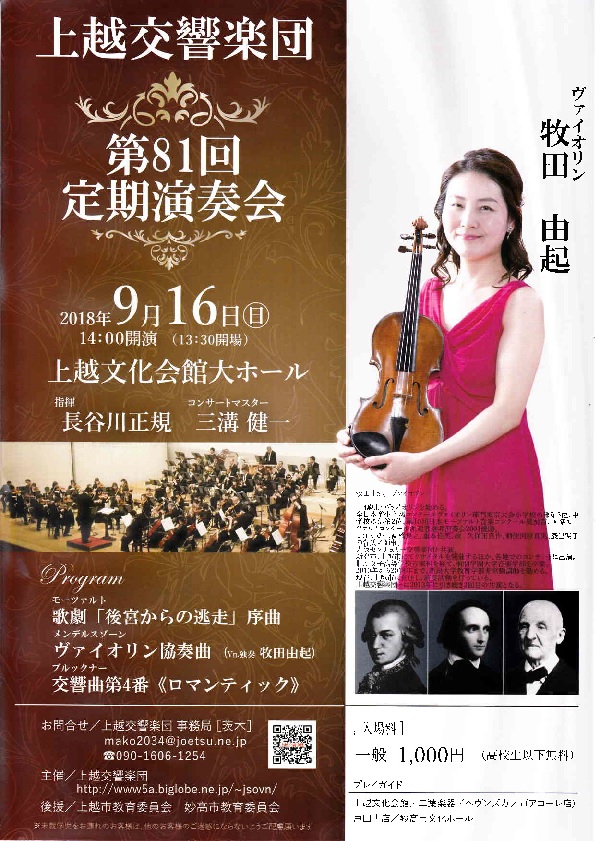
�����F2018�N9��16���i���j14:00�J���i13:30�J��j
�ꏊ�F��z������� ��z�[��
���ꗿ�F���1,000�~�i���Z���ȉ������j
�v���O�����F
�E���[�c�@���g �̌��u��{����̓����v����
�E�����f���X�]�[�� ���@�C�I�������t��
�E�u���b�N�i�[ �����ȑ�4��
�w���F���J�쐳�K
�R���T�[�g�}�X�^�[�F�O�a����
���@�C�I�����Ƒt�F�q�c�R�N
�v���C�K�C�h�F��z������فA��t�y��A�˓c���X�A
�@�@�w�����Y�J�t�F�i�A�R�[���X�j�A�����s�����z�[��
���⍇�킹�F��z�����y�c�����ǁm��n
�@�@mako2034[at]joetsu.ne.jp TEL090-1606-1254
�i2018/9/14�j
�㌴���L�q�����u����u�n������|��F�ߑ���{�N�w�̐��������ǂ��āv�i2018�N9��25���i�j�A����c��w�ˎR�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/flas/rilas/news...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N9��25���i�j15:20�`17:00
���F����c��w�ˎR�L�����p�X 33����16�K��10��c��
�@���Q�������A�\��s�v
�u���ҁF�㌴���L�q�i���s��w��w�@���w�����ȋ����j
�i��F�w��p���i����c��w���w�w�p�@�����j
�J�Î�|�F�u�ߑ���{�Ɠ��A�W�A�ɐ��������l���w�̌��v�ɂƂ肭��ł����������̌����O���[�v�ɂƂ��āA�|��E�|�ĂȂǂ�ʂ��ĉߋ���ٕ����̒m���������Ɏ�e����A�܂������ɐV�����l���w�̊w�m�̌`���ɍv�������̂��A�Ƃ������Ƃ͏d�v�ȉۑ�̈�ł��B����́A�ߑ���{�N�w���U����A���s�w�h�̓N�w�ɂ�����|��̖��ɂ����͓I�ɂƂ肭��ł���ꂽ�㌴���L�q�����ɁA���s�w�h�̖|��_�����Љ�������A�u�n���I�ȍs�ׁv�Ƃ��Ă̖|��Ƃ������Ƃ����b�����������܂��B
��ÁF������w�헪�I������Ռ`���x�����Ɓu�ߑ���{�̐l���w�Ɠ��A�W�A�������F���A�W�A�̐l���w�̊�@�ƍĐ��v
���ÁF�X�[�p�[�O���[�o����w�n���x������ ����c��w���ۓ��{�w���_�A����c��w�����l���Ȋw�����Z���^�[ �p�c����L�O���ۓ��{�w������
�i2018/9/13�j
���{���t����w���28�����i2018�N9��29���i�y�j�E30���i���j�A�����w�|��w������L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.u-gakugei.ac.jp/~jsste28/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�E�v���O����
9/28�i���j�F���Z���(1)���ƌ��J�i���������䏬�w�Z�j
9/29�i�y�j�F���R�������\�A�������i�E���𗬎x�����A���Z���(2)(3)(4)�A�ۑ茤��
9/30�i���j�F���R�������\�A���J�V���|�W�E���A���E���h�e�[�u��
�E���Z���(1)���������䏬�w�Z�̎��ƌ��J
�E���Z���(2)�u�Θb�^�͋[���ƌ�����v�̎����Ƃ�����߂�����
�P�ɖ͋[���Ƃ̂����̍H�v�Ƃ��������ƂɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��A���Ƃ̃��t���N�V�����̂�����A���Ƃ��߂���Θb�̂�����̕ϊv��ژ_�ށC�����w�|��w���E��w�@�́u�Θb�^�͋[���ƌ�����v�̎��g�݁B
�{�Z�b�V�����ł͉@���炪������������A������ӂ܂��āA������߂���f�B�X�J�b�V�������s���\��ł��B
�b��ҁF�n�ӋM�T�i�����w�|��w�j�A����Y�i�����w�|��w�j�A�␣�����i�y��z�w���A�������w�|��w�j�A���c�M�q�i������w�j�A���X�؍G�i�����s������䍂���w�Z�j
�E���Z���(3)�F�Љ�̕ω��Ǝq�ǂ��̑��l���Ɍ��鋳�t����ւ̊���
�Љ�̕ω��A���G���ɔ����q�ǂ��̑��l�Ȍ����ɁA����͂ǂ̂悤�Ɍ����������Ă����̂ł��傤���B
�{���ł́A�w�Z����ɂ����鋳�t�Ƌ���x���҂Ƃ̘A�g���Ⴉ��A�����ł̐��ʂ�ۑ�ɂ��Č������܂��B���t����W�҂Ƌ���x���W�҂̎��R�ȋc�_��ʂ��āu�`�[���w�Z�v�ւ̊��҂Ɩ��_���c�_���A���ꂩ��̋��t����ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B
�b��ҁF��|���o���i�����w�|��w���_�����j�A���r���i�J�q���ۑ�w����w���j�A�V�荑�L�i��㋳���w�j�A�����i�i�����w�|��w�j�A�N�ːm�F�i�����w�|��w�j
�E���Z���(4)�O���l�������k�������S�������̗{���E���C�̌��݁A�����āA���ꂩ��
�ߔN�̍ݗ��O���l�̑����ƍ��ЁE�n�擙�̕ω��ɔ����A���{��w�����K�v�Ƃ����O���l�������k���������������܂��B�{���ł́A���{�ꋳ��w������Ȋw�Ȃ���ϑ������u�O���l�������k�������S�������̗{���E���C���f���v���O�����J�����Ɓv�̎��{�҂���{���ƂɊւ�����s���܂��B�����ʂ��āA�����{���E���C�ɂ�����u�O���l�������k������v�̂��߂̎����E�\�͂Ƃ��̗{���Ɋւ��A�n��̎x���҂Ƃ̘A�g�̕K�v����A���t�̃L�����A�`���Ƃ������_���猟�����܂��B�����I���l���Ɍ��������o�����A���t�⋳�猻��ɂǂ̂悤�Ȑ����������炷�̂��A�܂��A���̐����̂��߂ɁA�{���f���v���O�����ɂ͉������߂���̂����c�_���܂��B
�b��ҁF�s���q�I�i�{�鋳���w�j�E�ɓ��S�Y�i�����O�����w�j�A�V���Ђ�݁i�����w�|��w�j�E�l�c�����i���s�����w�j�A�e���^�|�i���s���ی𗬋���j
�f�B�X�J�b�T���g�F�R�菀��i�w�K�@��w�j
�E���J�V���|�W�E���u���t���猤���̎˒���₢�����v
���e�[�}�u���t���猤���̎˒���₢�����v�ɂ��Ă̌��J�V���|�W�E�����J�Â��܂��B�����̕��ł��Q�����\�ł��B
�����F2018�N9��30���i���j13:00�`16:00
�ꏊ�F�����w�|��w ��u�`��S410����
�b��ҁF�������i���~�w����w�j�A���c�b���i�����w�|��w�j�A�S���c�^���l�i���E���x���@�\�j
�w�蓢�_�ҁF����a�q�i������w�E���{���t����w���j
�R�[�f�B�l�[�^�[�F��c�N�V�i�����w�|��w)
�i2018/9/12�j
�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�u�O�����ƌ����y���ށi2018�N9��16���i���j�A�����ہ[�ƍ��n�j
�Â��̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://nbz.or.jp/?p=18217
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
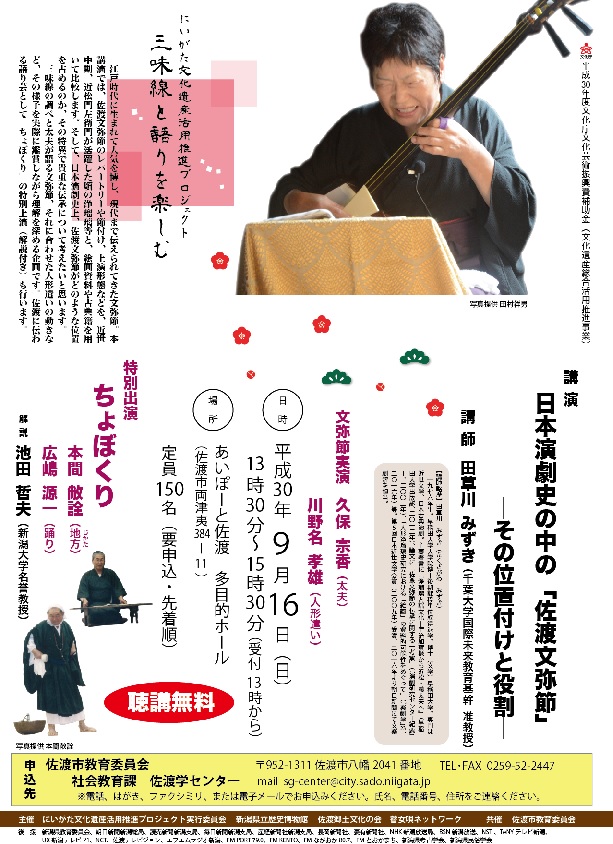
�V���������j�����قł́A�ɂ�����������Y���p���i�v���W�F�N�g�����{���Ă��܂��B���̊֘A�C�x���g�Ƃ��āA9��16���i���j�Ɂu�O�����ƌ����y���ށv�����n�s�ɂĊJ�Â��܂��B
�]�ˎ���ɐ��܂�Đl�C���A����܂œ`�����Ă�������߁B�{�u���ł͍��n����߂̃��p�[�g���[��ߕt���A�㉉�`�ԂȂǂ��A�ߐ������A�ߏ��卶�q�傪�������̏�ڗ��ȂǂƊG�掑����
�ÓT�Ђ�p���Ĕ�r���܂��B�����āA���{�����j��A���n����߂��ǂ̂悤�Ȉʒu���߂�̂��A���̓��قŋM�d�ȓ`���ɂ��čl�������Ǝv���܂��B
�O�����̒��ׂƑ��v����镶��߁A����ɍ��킹���l�`�����̓����ȂǁA���̗l�q�����ۂɊӏ܂��Ȃ��痝����[�߂���ł��B���n�ɓ`�����|�Ƃ��āu����ڂ���v�̓��ʏ㉉�i����t���j��
�s���܂��B���Ђ��Q�����������B
�����F����30�N9��16���i���j13:30�`15:30
���F�����ہ[�ƍ��n���ړI�z�[���i���n�s���È�384�|11�j
����F150���i�v�\���E�撅���j
�����F����
�E�u���u���{�����j�̒��́w���n����߁x�F���̈ʒu�t���Ɩ����v
�u�t�F�c����݂�������i��t��w���ۖ��������y�����j
�E����ߎ���
�v�ۏ@������i���v�j�A��얼�F�Y����i�l�`�����j
�E���ʏo�� ����ڂ���
�{�ԝƑF����i�n���j�A�L�����ꂳ��i�x��j
����F�r�c�N�v����i�V����w���_�����j
�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�����A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B
�\�����ݐ�F���n�s����ψ��� �Љ��� ���n�w�Z���^�[
�@��952-1311���n�s����2041�Ԓn
�@�d�b�EFAX0259-52-2447�@E-mail�Fsg-center[at]city.sado.niigata.jp
�i2018/9/11�j
�A�[�c�J�E���V���V���������X�y�[�X���̏�vol.12�u�_���X���n��łł��邱�ƁF�x�肽���H�x�肽���Ȃ��H�Љ�ɗx��͕K�v���v�i2018�N9��14���i���j�A�A�[�c�J�E���V���V���j
������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://artscouncil-niigata.jp/2269/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�o���G�A���{���x�A�R���e���|�����[�_���X�ȂǁA����ŗx����x��͉₩�ő�z�����Z�p������A�ς���̂��䂫���܂��B����A�������̕�炵�̒��ɂ́A��≃��̏�ȂǂŎp����Ă����x�������܂��B�ŋ߂ł́A�N���ʁA�_���X�o�����킸�l�X�Ȑl���Ƃ��ɗx��R�~���j�e�B�_���X�ƌĂ����g�݂��e�n�ōs����悤�ɂȂ��Ă��܂����B����́u���̏�v�ł́A�n��̒��ōs����_���X�ɏœ_�ĂĂ��b�����Ă��������܂��B�x�邱�Ƃ͐l�̒��ɉ��ݏo���A�ǂ�ȕω��������炷�̂ł��傤���H���{�e�n�ŃR�~���j�e�B�_���X�����{���A�O�����ی|�p�Ղœ��k�n���̗x��ɋr���Ă�NPO�@�l�W���p���E�R���e���|�����[�_���X�E�l�b�g���[�N�iJCDN�j�̍����͈ꂳ��ƁA�V�����ܐ�s�����_�Ƀ_���T�[�E�U�t�ƂƂ��Ċ������Ă���Lata��������}�����A���b���Ă��������܂��B
�J�����F2018�N9��18��(��)�@19:00�`21:00
�Q����F�����@����F20���i�撅�E�v�\���j
�J�Ïꏊ�F�A�[�c�J�E���V���V���������X�y�[�X
�@�V���s�����攒�R�Y1����613�Ԓn69 �V���s�J�����Љ��3F
�@���v���c�@�l�V���s�|�p�����U�����c���i�V���s�������ى��j
�Q�X�g�F
�����͈�iNPO�@�l�W���p���E�R���e���|�����[�_���X�E�l�b�g���[�N(JCDN)��\�j
Lata�i���x�Ɓ^�U�t�Ɓ^���K�u�t�j
���\�����ݕ��@�F�����E�d�b�ԍ��E���[���A�h���X���L�ڂ̏�AFAX�����[���ł��\���݂��������BFacebook��������\���݂��������܂��B�Ȃ��A���\���݂̍ۂɂ́u9/18�Q����]�v�Ɩ��L���Ă��������B
FAX025-234-4521�@Mail�Fartscouncil[at]niigata.email.ne.jp
Facebook�Fhttps://www.facebook.com/arts.niigata/
���₢���킹�FTEL025-234-4530�i�A�[�c�J�E���V���V���j
�@��t���ԁF�����ߑO8��30���`�ߌ�5��15��
�i2018/9/10�j
�V�G�i�E�E�C���h�E�I�[�P�X�g���~��z�s�����t�y�c�W���C���g�R���T�[�g�i2018�N10��14���i���j�A��z������فj
�Â��̂��ē��ł��B
�{�R�[�X�����̒��J�삪�o�����܂��B�{�w�n��40���N�L�O�Ƃ��ĊJ�Â���鉉�t��ł��B
���ڍׂ͂�����
www.joetsu-bunkakaikan.com/jisyu.html#�V�G�i
https://sienawind.com/concert_event/2018-10-14
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N10��14���i���j14:00�J�� (13:30�J��j
���F��z������ّ�z�[���i��z�s�V����1����9��10���j
�����FS��\3,500�AA��\2,500
�@�����A�w���̂�����͂ł��܂���B
�w���F�⑺�́^���J�쐳�K
���t�F�V�G�i�E�E�C���h�E�I�[�P�X�g���^��z�s�����t�y�c
Program�F
�q��1���r��z�s�����t�y�c�X�e�[�W�i�w���F���J�쐳�K�j
�E�S�N�Տ��ȁFJ.�o�[���Y
�E�uGR�v���V���t�H�j�b�N�E�Z���N�V�����F�V�쐳���@��
�q��2���r�V�G�i�X�e�[�W�i�w���F�⑺�́j
�E���[�t�@�E�X���}���T�i�A���L�v�F�Ζї����ҋȁj
�E���o�[�_���X�iB.�E�B�[�����F�o�C�e���n�C�X�ҋȁj
�E�l���̃����[�S�[�����h�i�v�Ώ��F�O�Y�G�H�ҋȁj�@��
�q��3���r��z�s�����t�y�c�~�V�G�i�@�����X�e�[�W�i�w���F�⑺�́j
�E�G���E�J�~�[�m�E���A���iA.���[�h�j
�E�f�B�Y�R�E�L�b�h�i���C�яC�j
�E�������u���[�}�̏��v���g�A�b�s�A�X���̏��h�iO.���X�s�[�M�j
�q�t�B�i�[���r�y��������ďW���I�ꏏ�ɉ��t���悤�I
�E�F�a��G���i�^���r�v�ҋȁj
�E��������i���Ȃ�i�X�[�U�j
���₢���킹�F
��z������ف@Tel025-522-8800�i�x�ٓ�������9:00�`17:00�j
�`�P�b�g��舵���F���[�\���`�P�b�g�iL�R�[�h�F33847�j�A�Z�u���C���u���i�Z�u���`�P�b�g�j
�i2018/9/3�j
���ۃV���|�W�E���u�~���[�W�A���̖����F�l�ފw�I�p�[�X�y�N�e�B�u�v�i2018�N9��28���i���j�A�O�����t�����g���j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.minpaku.ac.jp/research...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N9��28���i���j14:00�`16:30�i�J��13:00�j
�ꏊ�F�O�����t�����g��� �k��4�K�i���b�W�V�A�^�[
�i���{���s�k���[��3-1�j
�g�p����F�p��^���{��i�����ʖ�j
����F350���i�v���O�\���j
���F�u�l�ނ̕��������Ɋւ���t�H�[�����^���~���[�W�A���̍\�z�v�v���W�F�N�g�^�w�p���������J���Z���^�[
��|�F�����w�����ق́A19���I�Ɋe���Őݗ������悤�ɂȂ������Ƃ���킩��悤�ɁA�u������̐��I�v�̍l�����������������p���ł��܂��B�����A�l�ގЉ�͖��J�i�K����Y�ƒi�K�i�����A���ꂼ��̖��������͂��̊K��̓���̒��Ԓi�K�Ɉʒu������̂��ƍl�����Ă��܂����B���̐i����`�̍l�������́A20���I�ɂȂ�Ɨ��_�I�Ɍ�������̂Ƃ��Ċ��p����܂����A�~���[�W�A���́A�W�����Ƃ����āA����҂ƌ�����҂̂������ɔ�Ώ̓I�Ȍ��͊W���Đ��Y���Â��܂����B������21���I�ɓ��������݁A�����̖����w�����ق��A�W���Ƃ���Ɋւ�邳�܂��܂Ȋ����������āA���̌��͊W��E�\�z���悤�Ƃ��Ă��܂��B���̃V���|�W�E���ł́A�~���[�W�A���̂��炽�Ȗ������\�z���܂��B
�v���O�����F
�E13:00�`�@�J��
�E14:00�`14:10�@�J��̂����A�@�֗Y��i���������w�����ً����j
�E14:10�`15:10�@��u��
�u�|�X�g�����w�����ف\�\�����Â���q�g�ƃ��m�v
�W�F�C���Y�E�N���t�H�[�h�i�J���t�H���j�A��w�T���^�N���[�Y�Z���_�����j
�E15:20�`15:35
�u�\�[�X�R�~���j�e�B�Ɣ����َ����Ƃ́w�ĉ�x�v
�ɓ��K�i���������w�����ُy�����j
�E15:35�`15:50
�u�G�X�m�O���t�B�ƃG�C�W�F���V�[�v
�V����q�i���������w�����ُy�����j
�E15:50�`16:25�@�p�l���E�f�B�X�J�b�V����
�f�B�X�J�b�T���g�F�W�F�C���Y�E�N���t�H�[�h�A�ɓ��K�A�V����q�A�g�c���i�i���������w�����ْ��j
�E16:25�`16:30�@��̂����A
�i2018/8/31�j
���w�� �������30�N�x��3����^�������320�����i2018�N9��22���i�y�j�A������w�{���L�����p�X�^����w�L���L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
����30�N�x ��3����w�������
�����F9��22���i�y�j14��30���`18��00��
�ꏊ�F������w�{���L�����p�X�@�@��1����113����
�������\�F
�E�u�ጎ�Ԃ̎��w�v�쑺��
�i��F���ѐM�V�i����c��w�j
�E�u�~�P�����W�F���́u�����f�`�Q�v�F�f�`�̕��ނ���уL���X�g���ɂ����钤���I�|�ĂƎ��̕ϗe�v�V�q�T�E�iBunkamura �U�E�~���[�W�A���j
�i��F���R����i�c��`�m��w�j
�E�u�u����z(Mandylion)�v�̕ϗe�ƋA���F���I�i���h�́s�T�����@�g�[���E�����f�B�t�ƃt�����h���G��̊W�v�]�����i���m��w�j
�i��F���R����i�c��`�m��w�j
���w����� ��320�����\��
����30�N9��22���i�y�j�ߌ�1��30�����
����w �L���L�����p�X�@�o�u�`��2�ԍu�`��
�������\�F
�E�u�ۓc�o�d�Y�̔��p��]�F�W���b�g�_�𒆐S�Ɂv�������ǁi���s��w�j
�E�u�v���g���w�����x�̍\���ƌ`�������\�N���e�X���v�����r��i����w�j
�i2018/8/30�j
���{���y�w����{�x����53���ጤ����i2018�N9��29���i�y�j�A�c��`�m��w���g�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.musicology-japan.org/east/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N9��29���i�y�j14:00�`17:00
�ꏊ�F�c��`�m��w ���g�L�����p�X��8�Z��811����
�i��F�����]�i�c���`�m��w�j
���e�F�C�m�_�����\�A�������\
�q�C�m�_�����\�r�i���\������j
�P�D�u�F�����i�̉��y�\���F�ߓc���𒆐S�Ɂv�]���݂����i�����Y�p��w��w�@�j
�Q�D�u�h�r���b�V�[�́s�N�����l�b�g�ƃs�A�m�̂��߂̑�P�����ȁt�̍l�@�F�t�����X�nj��y�Ȃɂ�����N�����l�b�g�p�@�̕ϑJ�̎��_����v�|���j�i�������y��w��w�@�j
�q�������\�r�i���\������j
�P�D�u�v���̓���Ƃ��Ă̐��m�y��F������v�����ɂ�����͔͌��̑n��Ǝ�e�̍Č����v�쑩�N�i������w�j
�Q�D�u18���I�ɂ����鉹�y�Ɓu�����Ȋw�v�̊ւ��F�A�����j�J���߂����āv�c�������i���ۊ����w�j
�i2018/8/29�j
��z�����w�n��40���N�L�O�R���T�[�g�i2018�N10��7���i���j�A��z�����w�u���j
�Â��̂��ē��ł��B
�{�w�n��40���N�L�O�Ƃ��đ�w����уR�[�X����Â��鉉�t��ł��B
����w�����T�C�g�͂�����
www.juen.ac.jp/010pickup/2018/180820_1.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
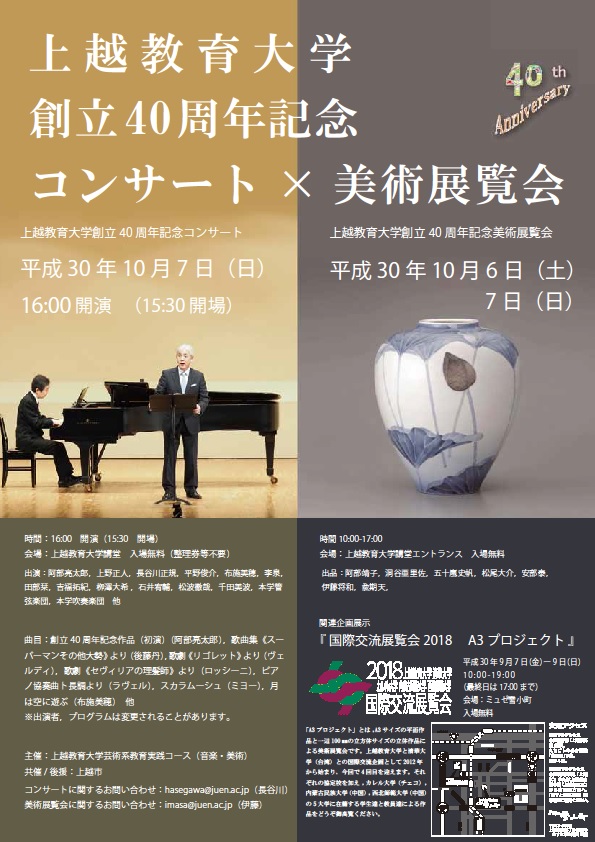
�����F����30�N10��7���i���j16:00�J�� (15:30�J��)
�ꏊ�F��z�����w�u���i�V������z�s�R���~��1�j
�@�����ꖳ���i���������s�v�j
�o���F���������Y�A��쐳�l�A���J�쐳�K�A����r��A�z�{����i�ȏ�{�w�����j�A����A�c���x�A�g����I�A������A�Έ�G��A���g�O�ƁA��c���g�i�ȏ�{�w��w�@���j�A�{�w�nj��y�c�A�{�w���t�y�c�@��
�ȖځF
�E�n��40���N�L�O��i�i�����j�i���������Y�j
�E�̋ȏW�s�X�[�p�[�}�����̑��吨�t���i�㓡�O�j
�E�̌��s���S���b�g�t���i���F���f�B�j
�E�̌��s�Z���B���A�̗����t�t���i���b�V�[�j�j
�E�s�A�m���t�ȃg�������i�����F���j
�E�X�J�����[�V���i�~���[�j
�E���͋�ɗV�ԁi�z�{����j�@��
���o���ҁA�v���O�����͕ύX����邱�Ƃ�����܂��B
��ÁF��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j
���ÁE�㉇�F��z�s
�R���T�[�g�Ɋւ��邨�₢���킹�F
hasegawa[at]juen.ac.jp�i���J��j
�����p�W����������J�Â��Ă��܂�
�����F����30�N10��6��(�y)�`7��(��)
�@�����Ƃ�10:00�`17:00
�ꏊ�F��z�����w�u���G���g�����X
���ꗿ�F ����
��ÁF��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���p�j
�i2018/8/28�j
���{�|�s�����[���y�w��2018�N�x��2����n����i2018�N8��29���i���j�A����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jaspm.jp/?p=1852
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N8��29��(��)14:00�`18:00
���F����w �痢�R�L�����p�X ��3�w�� A305����
�A�N�Z�X�F��}�d�S�u�~�c�v�w����A�痢���u�k�痢�v�s�Łu�֑�O�v�w���ԁA�܂��͋��s�u�͌����v�s�i�ʋΓ��}�������j�Łu�W�H�v�w���ԁA�u�k�痢�v�s�ɏ�芷���āu�֑�O�v�w���ԁA�k����5��
�n�}�Fhttp://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapsenri.html#map
�{�������́A2018�N6��9������10���ɂ����Ėk���ɂ��钆���`�}��w�iCUC�FCommunication University of China�j�ŊJ�Â��ꂽ�u6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference�i�ȉ��AIAPMS2018�j�v�Q���҂ɂ��ƁA����A���A�W�A���̃|�s�����[���y�����҂����Ƃǂ̂悤�ɘA�g���A���������Ɏ��g��ł������ɂ��Ă̈ӌ��������s���B
�����6��ڂ̊J�Â��}�����uIAPMS2018�v�ł́A�L�[�X�E�j�[�K�X�ɂ��L�[�m�[�g�E�X�s�[�`�A24�̃p�l���Z�b�V�����A�k���⍁�`�����_�Ɋ�������~���[�W�V���������ɂ�郉�C�u�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ��s��ꂽ�B�p�l���Z�b�V�����ł́A���ۊw��o���̑�w�@�����܂�10���ȏ��JASPM������������s���A�����A��p�A�؍��A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���ȂǓ��A�W�A���̃|�s�����[���y�����҂����ƌ𗬂�[�߂��B
�{�������ł́A�����������ۊw��Q���ɂ���ē���ꂽ���ʁE�m�������L���AJASPM����̍���̌��������Ɍq���Ă������Ƃ�ړI�ɁA���L��4���ɂ��Q�����s���B�đ�́uIAPMS2018�v�̊J�ÊT�v�Ȃǂɂ��Ă̕��s���B�����A�����́uIAPMS2018�v�ŏ��߂č��ۊw��ł̌������\���o��������w�@���̎��_����A�ǂ̂悤�ȏ������s���A�ǂ̂悤�Ȓm�����̂����A���\���e�̃T�}���[�Ƌ��ɕ���B�֓��́uIAPMS2018�v�Ɍ����Ă̎��g�̑�w�@�[�~�ɂ�������g�݂�w�����@�A���A�W�A���̃|�s�����[���y�����҂Ƃ̘A�g�̕K�v���⍡��̉ۑ�Ȃǂɂ��ĕ��s���B
��(1) �u6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference�iIAPMS2018�j�̊T�v�Ɠ��A�W�A���̃|�s�����[���y�����v�đ�O�B�i����w�E��㉹�y��w�ق����u�t�j
�{�́A�{�������̓����Ƃ��āuIAPMS2018�v�̊J�ÊT�v�A�p�l���Z�b�V�����ɂ����錤�����\�̓����A���{����p�l���X�g�Ƃ��ĎQ�����������҂̃R�����g�Ȃǂ��Љ����̂ł���B
�uIAPMS2018�v�ł́A�L�[�X�E�j�[�K�X�ɂ��L�[�m�[�g�E�X�s�[�`�A24�̃p�l���Z�b�V�����A�k���⍁�`�����_�Ɋ�������~���[�W�V���������ɂ�郉�C�u�p�t�H�[�}���X�Ȃǂ�2���Ԃɂ킽��s��ꂽ�B�p�l���Z�b�V�����ւ͓��{����̎Q���҂��܂�94���̌����҂��p�l���X�g�Ƃ��ēo�d���A�O���[�o���[�[�V�����A�Y�ƁA����A�W�F���_�[�A���C�u�p�t�H�[�}���X�A���{�̉��y�A�j���[���f�B�A�ȂǗl�X�ȃe�[�}�ŕ��s�����B�����͕҂��p�l���X�g�Ƃ��ĎQ�����A�e���r�_�ސ삪1970�N�ォ��1980�N��ɂ����Đ��삵�����y�ԑg�ɂ��āuThe backgrounds of music program from the 1970s to 1980s in japan: The Practice of "Young Impulse" and "Fighting '80s", that were produced by Television Kanagawa�v�Ƒ肷����s���A�e������̎Q���҂⌻�n�̊w���{�����e�B�A�����ƗL�v�ȋc�_�����킷���Ƃ��ł����B
�{�ł͂܂��A�v���O�����Ȃǂ̊e�펑����ʐ^�Ȃǂ������Ȃ���A�uIAPMS2018�v�̊J�ÊT�v�ƃp�l���Z�b�V�����ɂ����錤���e�[�}�̓������Љ��B�����ŁA�҂�2018�N8����{���牺�{�ɂ����čs���A���{����́uIAPMS2018�v�Q���҂�ΏۂƂ������[���A���P�[�g�̏W�v���ʂ��Љ�A�{�������ɂ�����c�_�̈ꏕ�Ƃ������B
��(2)�u�j�b�|���̉��y�́w�A�W�A�̉��y�x���H�Fthe 6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference 2018�v�������i����w��w�@���w�����ȕ����\���_��U���y�w���� �O�����m�ے�2�N�j
�{���\��2018�N6��9���E10���ɖk���E�����`�}��w�ŊJ�Â��ꂽ�����W��ł���Athe 6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference 2018 (6th IAPMS) �̑��Q���ł���B ���\�҂͑��J�Ó��̗����ɓn���ăV���|�W�E���E�p�l���Z�b�V�����֎Q�����A��������\���s�����B�ȉ� (1)���O���� (2)���\���e�Ȃ�тɎ��^���� (3)���֎Q�����Ă̏����A��3�_�ɂ��ĕ� ���s���B
���\�҂̍݊w�������w���y�w�������ɂ����ẮA�֓��T��y�����̎w���̂��Ɣ��\�v�|�E ���e�̎��O������v4��ɂ킽���ĊJ����A���̐��ʂ܂��Ĕ��\�҂͓��{�ɂ�����u�a�J�n�v ���y���[�u�����g������� �uWho Is Locating Shibuya-kei in Shibuya?: Musical Revival, Standardization, and Gentrification�v �Ƒ肵�����\���s�����B���̉ߒ��łǂ̂悤�ȋc�_�E���P ���ׂ��ꂽ�̂��A�܂����\�̌��ʂǂ̂悤�Ȏ��^�������s��ꂽ�̂��\����B�܂��{���� ���\�҂ɂƂ��ď��߂Ă̍��ۊw��ł���A�ڂɂ���S�Ă��V�N�ȋ����ł������B�A�W�A�Ƃ����L ��ŖL���ȃt�B�[���h�ł͂��܉����c�_����Ă���̂��A���̒��œ��{�Ȃ�тɓ��{�����͂ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă����ׂ��Ȃ̂��B���ɎQ�����邱�Ƃœ����������q�ׂ�B
��(3)�uIAPMS2018�Q���`�C�O�̌����҂�������{�̃|�s�����[���y�Ƃ����t�B�[���h�`�v�����R�����i����w��w�@���w�����ȕ����\���_��U���y�w���� ���m����ے�3�N�j
�{���\�ł́A���\�Ҏ��g�ɂƂ��ď��ƂȂ鍑�ۊw��ł̔��\�̕��s���B���\�҂́uIAPMS2018�v2���ڂ�Gender�̃Z�b�V�����ɂāuAmateur female music producers in otaku culture�FThe creativity of "diva" in dojin music�v�̃^�C�g���Ōl���\���s�����B���\�܂ł̓����͌������A����̕ǂƌ���ꂽ���\���Ԃ̒��Ŏ��g���咣�����������ǂ̂悤�ɂ��ēW�J���邩�A���̌v��͂Ƃ�킯������ɂ߂��B�������Ȃ���A���\�҂���������[�~�i����w���y�w�������֓��[�~�j�ł̓x�d�Ȃ�c�_��[�~�̃����o�[����̃A�h�o�C�X���邱�ƂŁA���ʂƂ��ē��e�����������ꂽ��ԂŔ��\���邱�Ƃ��o�����B�����āA���\��̎��^��������́A�C�O�̌����҂�������{�ɂ����鏗���̎��I�^�N�����̂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃɒ��ڂ��Ă���̂��Ƃ������Ƃ������яオ���Ă����B
�ȏ�̓_�܂��A�{���\�ł́A���ۊw��ł̔��\�Ɏ���܂ł̔��\���e�����̌o�܂ƁA���^�����⑼�̃Z�b�V�����ł̋c�_���������钆�Ŏ��g���������C�O�̓��A�W�A���|�s�����[���y�����҂ɂ����{�̃|�s�����[���y�y�у|�s�����[���y�����ւ̔F���ɂ��ďq�ׂ�B
��(4)�u�A�W�A�Ɓ^�̓��{�F���{�̃|�s�����[���y�����̖��Ƃ��Ắu�C���^�[�A�W�A�v�v�֓��T��i����w��w�@���w�����ȏy�����j
�{�ł́A�k�����ւ̊w���̎Q�����������サ���Ӑ}�Ƃ��̖��ӎ��ɂ��ĊT������B�҂́A2017�N�ɔ��N��p�؍݂��A����I�ȃ����F���ł̓��{������e�̐[���ƍL�����m�F���A�܂��A�����ҊԂ̓��{�̃|�s�����[���y�����̒~�ςւ̊S�ƁA���ꂪ����{�ꌗ�œK�ɏЉ��Ă��Ȃ����Ƃ�ɂ��ސ��������Ε������B�܂��A�h�C�c�̍��ۃ|�s�����[���y�w�����A�����J�������y�w��ɂ��Q���������A�����ł͓��{�̃|�s�����[���y�Ɋւ���ꕔ�̌����҂̊S�̍��܂�����������A�l�C�e�B���p�ꌗ�哱�̍��ۊw��ł́A����̕ǂ̍����݂̂Ȃ炸���@�_��c�_�̍�@�ɂ����鍷�ق�Ɋ����A�A�J�f�~�b�N�s��̉�ȃ|���e�B�N�X���ˌ������B
���������ϓ_����A�P�ɔ��R�Ƃ����u�O���[�o���v�Ȃ���̂̉��ʋ敪�ł͌����ĂȂ��A��̓I�ȃl�b�g���[�N�ł���A�w��I�ȕ��@�ł����肤��u�C���^�[�A�W�A�v�ɐϋɓI�ɎQ�^���邱�Ƃ�ڎw���A�v��������w���⌤���҂ɕВ[���琺������������ł���B
�̒��ł́A�����������S�݂̂Ȃ炸�A�{�ԂɎ���܂ł̋�̓I�ȍs���₻���ł̋c�_�ɂ��Ă��q�ׂ�B
���I����A���e���\�肵�Ă��܂��B
���₢���킹�F�i[at]��@�ɕς��Ă����M���������j
���c����i�����S�����������ψ��j otakenji[at]shitennoji.ac.jp
���M�q�i���������S�������j�@fwgd0462[at]mb.infoweb.ne.jp
�i2018/8/27�j
���{�d�q�L�[�{�[�h���y�w���14��S�����i2018�N9��9���i���j�A�����~���[�W�b�N�J���b�W���w�Z�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
jsekm.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N9��9���i���j
�ꏊ�F�����~���[�W�b�N�J���b�W���w�Z�i�{�فA�V1���فj
�@�����s������{��4-15-9
�@http://www.shobi.ac.jp/help/access.html
�Q����F���2,000�~�i�w��1,000�~�j�A����1,500�~�i�w��500�~�j
10:00�`�@��t
10:30�`�@���A
10:45�`�@��u��
11:30�`�@����
13:00�`15:00�@���E���h�e�[�u��
15:10�`17:00�@�������\�A�|�X�^�[�Z�b�V����
��u��
�uAI�Ɖ��y�Y�Ƃ̖����`�q�g�Ƌ@�B�����Ɋ�������鐢�E��ڎw���āv
�c�W����i���}�n������� �����J����������1�����J�������j
���E���h�e�[�u��
�E�u�A�R�[�X�e�B�b�N�y��Ɠd�q�I���K���̋����F�n�C���]���܂މ�������A���t���ʂ��Č����Ă����ۑ�Ə������v���\�ҁF�[�c�W�i��������j�A�Ԓ˔����i��������j�@�t�@�V���e�[�^�[�F�ēc�O�@���L�F���� �p��
�E�u�d�q�s�A�m�EICT���g�����y����̏�������Nj�����II�F�u�����X�g�[�~���O��ʂ��Ď��Ɠ��e��T��v���\�ҁF���m��i���Q��w�j�A�Ԓ×T�q�i�|�������ۈ�m�{�����j�A��ؑR�i������Ѓs�R���{�j�@�t�@�V���e�[�^�[�F�c������@���L�F���q����Y
�E�u�^�e�����E�����f�B�X�Ƃ͉���IV�F����E�ۑ�E�����v�ҁF�����r(�^�e���F��������)�A�V���N�V(�����F�؍X�Í���)�@ �b��ҁF�\���D�A���c�b���q�A���V�^�|�A���F�B��A���N��A�ˈ�����q���@�t�@�V���e�[�^�[�F�a�q�����@���L�F�V���N�V
�i2018/8/24�j
�����|�p�w���87�����i2018�N9��15���i�y�j�A�����̐����q��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
ethno-arts.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F9��15���i�y�j15���`17��
�ꏊ�F�����̐����q��w������w��2����110����
��ʁF�������g���ۃm����䪉גJ�w���Ԑ���܂�7��
�i������\���ɐg���ؖ����������������B���͕債�Ă��܂��j
�v���O�����F
�E���Ð�ˎq�i�����̐����q��w�j�u�吳���ɂ������ˉ̌��c�ւ̎����F�G���w�I�y���]�_�x�Ɓw�I�y���x�̋L������v
�E�R�������i�����̐����q��w�j
�u�������y�w����݂����{�̉��y�ȋ���̌���Ɖۑ�v
�A����F�����Y�p�w��������@minzoku.tokyo[at]gmail.com
�i2018/8/23�j
���{���ȋ���w���44��S�����i2018�N9��8���i�y�j�E9���i���j�A���{�̈��w���c�J�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.office-ga.site/jcrda2018/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N9��8���i�y�j�E9���i���j
���F���{�̈��w���c�J�L�����p�X
�����F
�E9��8���i�y�j
9:00�`�@��t
9:30�`10:40�@��ʌ������\1
10:50�`12:00�@��ʌ������\2
13:30�`14:45�@����
15:00�`17:00�@�V���|�W�E��1
17:30�`19:30�@���e��
�E9��9���i���j
9:00�`�@��t
9:30�`10:40�@��ʌ������\3
10:50�`12:00�@��ʌ������\4�A�|�X�^�[���\
13:15�`15:40�@�V���|�W�E��2
�E�V���|�W�E��1�i�w����j
�e�[�}�F�V�w�K�w���v�̂��������
�V���|�W�X�g�F����F�i�O�����Ȋw�ȏ�����������Nj���ے��ۉے��j
�@���ؐ��u�i�}�g��w�l�Ԍn�����j
�@�������K�i�L����w�������w�Z���@�j
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�p���d���i���{�̈��w�����j
�E�V���|�W�E��2�i���s�ψ�����j
�e�[�}�F���ꂩ��̋����{���̂�������l����
�V���|�W�X�g�F�n粒����i���s����ψ���璷�j
�@�Ⓡ���i�������琭��������ے������Z���^�[�����������j
�@�n��q�j�i��ʌ�����ǎs�����x���������w�Z�l���ۉے��j
�R�[�f�B�l�[�^�[�F�r��͒j�i���{�̈��w�����j
���Q����F
��ʉ��4,000�~�i����5,000�~�j
�w�����2,000�~�i����2,500�~�j
��ʔ���4,500�~�i����5,500�~�j
�w������500�~�i�����̂݁j
�i2018/8/22�j
���{����w���77����i2018�N8��31���i���j�E1���i�y�j�A�{�鋳���w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jera77.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
���ԁF2018�N8��30���i�j�`9��1���i�y�j
���F������w�@�l �{�鋳���w
�������F
�E8��30���i�j
�Ј�����i�w�����j�A���E���h�e�[�u���A���𗬉�
�E8��31���i���j
��ʌ������\A�A�e�[�}�^�������\B�A����A�V���|�W�E��I�A�ۑ茤��I�A���e��
�E9��1���i�y�j
��ʌ������\A�A�e�[�}�^�������\B�A�V���|�W�E��II�A�ۑ茤��II
�J�×\�蕪�ȉ�F
�E��ʌ������\
A-1���痝�_�E�v�z�E�N�w�AA-2����j�AA-3�w�Z���x�E�o�c�AA-4����s�����E����@�AA-5��r�E���ۋ���AA-6������@�E����ے��AA-7�����w���AA-8���ȋ���AA-9���B�Ƌ���AA-10�Z�p�E�E�Ƌ���AA-11�c������E�ۈ�AA-12�����E��������AA-13��������E�����㋳��AA-14���t����AA-15�Љ��E���U�w�K�AA-16 ����S���w�AA-17�J�E���Z�����O�E���瑊�k�AA-18���ʎx������AA-19�}���فE������w
�E�e�[�}�^�������\
B-1�s��������̉ۑ�AB-2�w�Z�̃��A���e�B�Ƌ�����v�̉ۑ�AB-3���E�̋�����v�����AB-4��҂̈ڍs�ߒ��ϗe�Ɗw�Z�AB-5�W�F���_�[�Ƌ���AB-6��������̉��v�����AB-7���t������v�̓����AB-8��㋳��j�̏����AB-9����w�̖₢�����AB-10�q�ǂ����Ƌ���E�����AB-11���E���f�B�A�E�e�N�m���W�[�Ƌ���AB-12�����{��k�ЂƋ���w�����AB-13�m�I���Y�̋��猤�����\�z���邽�߂ɁAB-14 Educational Issues from Global Perspectives�iEnglish Session�j
�E�ۑ茤��
(1)�ۑ茤��I �`�������₢�����i�S���F����N�E�������i�ψ���j
�@2016�N12���Ɂu�`������̒i�K�ɂ����镁�ʋ���ɑ������鋳��̋@��̊m�ۓ��Ɋւ���@���v�i�u����@��m�ۖ@�v�j�����z����A�������Ƃ������Ƃ͂ǂ��������Ƃ������߂Ė���Ă���B�����̓t���[�X�N�[���Ȃǂ̊w�Z�ȊO�̑I������ϋɓI�ɔF�߂Ă������Ƃ��铮�������������A�ŏI�I�ɂ͖@�Ă͑啝�C������A�����̊w�Z���璆�S�̍l���������P����Ă���B�������Ȃ���A���������@���̊�{���O��搂�����O���ɂ́A�u���A�n�������c�́A����@��̊m�ۓ��Ɋւ��銈�����s�����Ԃ̒c�̂��̑��̊W�҂̑��݂̖��ڂȘA�g�̉��ɍs����悤�ɂ��邱�Ɓv�ƋL���ꂽ�B�܂��A���O���ł́A�u�s�o�Z�������k���w�Z�ȊO�̏�ɂ����čs�����l�œK�Ȋw�K�����̏d�v���v���w�E����A�K�v�ȏ��̒⏕�����̑��̎x�����s�����߂ɕK�v�ȑ[�u���u���邱�Ƃ����߂��Ă���B
�@�����ŁA�{�ۑ茤���ł́A���ۂɓ��@�Ă̐����Ɋւ�����t���[�X�N�[���̑�\�҂ƁA���̖��ɂ��Č�����i�߂Ă��錤���ғ��������A���ꂩ��̓��{�Љ�ɂ����Ďq�ǂ��̋��猠���ǂ̂悤�Ȍ`�ŕۏႵ�Ă����ׂ��Ȃ̂��A�l�X�Ȍ��I�@�ւƃt���[�X�N�[�����͂ǂ̂悤�ɘA�g���Ă��������̂��A������߂�������╽���̊ϓ_���猻�݂̓������ǂ̂悤�ɕ]�����邩�Ȃǂ̘_�_�ɂ��Č�������B
(2)�ۑ茤��II�@education and politics in global age �i�S���F���ʏd�v�����E�������i�ψ���j
�@�O���[�o�������鐢�E�̒��ō������Ƃ�P�ʂƂ��Đ��x������Ă���������̂�����́A�ȉ��̓_�ŁA�傫���₢������悤�Ƃ��Ă���B���ɁA������ɂ����Ĉ琬�����s�������A�������Ƃ��\�����鍑������Ƃ�����̂ƁA�ږ����̑�����ӂ܂�����葽�����I�ŏd�w�I�Ȃ��̂Ƃ̊Ԃő傫���h�ꓮ���Ă���B���ɁAOECD ��PISA �ɏے������悤�ɁA�o�ς̃O���[�o�������w�Z����̕]����̃O���[�o�����𑣐i���A�i���̊g����ۂƔr�����߂���A�|���A�̖��ݏo���Ă���B��O�ɁA�n�����̕ϗe���Љ�̎����\�����O���[�o���ȉۑ�Ƃ��ĕ��コ���A�o�ϐ�����O��Ƃ��Ă�������̊T�O�̖₢�����𔗂��Ă���B
�@�{�ۑ茤���ł͈ȏ�̂悤�Ȗ����ӂ܂��A�O���[�o�������鎞��ɂ����鋳��Ɛ����̊W�����ۓI�Ȏ��_����_���A�V��������̃p���_�C�����\�z�����Ƃ��Ă��������B�Ȃ��A�{�ۑ茤���́A�ʖ�����Ȃ��p��݂̂̌`�ł̊J�Â�\�肵�Ă���B�܂��A2019�N�ɊJ�×\���WERA�i���E����w��j���{���̃v�����Ƃ��Ă��ʒu�Â��Ă��������B
�E���J�V���|�W�E��
(1)���J�V���|�W�E��I ���E�̍��x���ɂ�����u���_�Ǝ��H�̉��ҁv
�@�ߔN�A�������x�ɂ́A���E�̍��x����i�߂鐭��̉��A�����Ƌ��X�V���A���E��w�@���x�A�����琬���c��ɂ�鋳���琬�w�W�A���E�ȖڃR�A�J���L�������ݒ�ȂǑ傫�ȕύX���������Ă����B�����́A����19�N�A24�N�A28�N�ƒ�������R�c��̈�A�̓��\�ɂ����āA�w�ё����鋳�����̊m�����K�͂Ƃ���A���̋�Ƃ��Đ��x�����ꂽ�̂ł������B�����́A�����̗{���Ɛ����Ɋւ���āA�R���e���c����R���s�e���V�[�܂ł��܂܂��A�����āA��w�A����ψ���A�w�Z�̍���ɍL�͂ȉe�����y�ڂ���K�͂Ȑ��x�ύX�ł���A��A�̓����͈�̃X�e�[�W�ɒB�����Ƃ����邾�낤�B���̒��S�ł���w�ё����鋳���Ƃ́A�u���_�Ǝ��H�̉��ҁv���\�ł��鎑���\�͂�����邱�ƂƓ��`�ł���Ƒ����邱�Ƃ��ł���B����Ɂu���_�Ǝ��H�̉��ҁv�Ƃ́A��㋳�����x�̌����̈�ƂȂ��Ă����u��w�ɂ�����{���v�̋�ۂɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�u���_�Ǝ��H�̉��ҁv�ɂ��āA��w�݂̍�����Č��������ꍇ�A��w�l�͎����̐�傾���������A����͊w�K�҂��������H�ƌ��т���ɂ������Ȃ��Ɗ֒m�����̎p�����u�\�蒲�a�v�Ƃ��Ĕᔻ�I�ɑ����錩����A�Ƌ�����^���ɔ���E�ɏA���҂͋ɂ߂ď��Ȃ��i����25�N�x�̖Ƌ�����^������208,237�A�����w�Z�̗p�҂�31,107�l�j�Ƃ�������������B���_�Ƃ������ꍇ�ɁA�قȂ�w��w�i�����e���Ȃ����ׂċ����鏬�w�Z�����ɑ��ėL���ȗ��_�ł���̂��A�Ƃ����ۑ���c��B������̌���ɂ����Ē��ʂ��鑽��ɂ킽�镡�G�ȋ���ۑ�ɑ��A���_�Ǝ��H�����҂����Ȃ��狳�������z���Ă������Ƃ��ł��邩�A���̂��߂̊w������A��w�@����ƂȂ��Ă��邩�A���̎��������Ă������Ƃ��A���X�e�[�W�ɋ��߂��Ă���ƍl����B
�@�{�w����𒆐S�ɁA���X�e�[�W�Ƃ��Ă̐��x�ύX�ɂ��ẮA�J�����̗��O�A���Ɠ����A�葱�������r�Ƃ������_�ɂ����ċ^�`���悳��Ă���B�������Ȃ���A�p�č��ł́A���t���ʌ�������绂��A�����̎��i�⌤�C�͕s�v�Ƃ̓����������ł���B�����Ƌ����^���K���̉�Ɣᔻ���邾���ł́A�K���ɘa�̐�ɍT����A����ΏۊO�Ƃ����s���v���ɑΉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u���_�Ǝ��H�̉��ҁv�Ƃ͉����A�����ł��āA�ł��Ă��Ȃ������̂��A�����Ă��ꂩ��ǂ����ׂ��Ȃ̂��A�c�_���Ă��������B
�@��w�l�Ƃ��Ă̊����⌤���҂Ƃ��ċ����ė��w�p���_�̌n�ɂ����ėl�X�ȕ҂̔��\�����ƂɁA�u���_�Ǝ��H�̉��ҁv�̎��ۂƉۑ�ɂ��đ��ʓI�ɓ��c�ł���悤�ɂ������ƍl����B
(2)���J�V���|�W�E��II�u�q�ǂ��̕n���v�Ƌ���w�����̉ۑ�
�@�킪���ɂ����āu�q�ǂ��̕n���v�����ڂ𗁂т�悤�ɂȂ����̂́A2006�N��OECD �ȗ��ł��낤�B��i�����̒��ł��䂪���̎q�ǂ��̕n���������ʂł���Ƃ����V���b�L���O�ȕ��Ȃ��ꂽ���Ƃ͋L���ɐV�����B����ɑ��A���{��2013�N�Ɂu�q�ǂ��̕n����̐��i�Ɋւ���@���v�𐧒肵�A����Ɋ�Â��A2014�N�ɂ́u�q�ǂ��̕n����Ɋւ����j���߂��B�܂��A�w�Z�����n��Љ�A�s�����x���ɂ����Ă��A�A�g���āA�q�ǂ��̕n���ւ̗l�X�ȑL����������Ă���B�����A����s���w�A����Љ�w�A�Љ�w�A�o�ϊw�A���������w�A�Տ��S���w���l�X�Ȍ�������ɂ����Ă��A�q�ǂ��̕n�����������������Ă���B
�@�����ŁA�{�w��A����w�����҂ɂ��ł��傫�Ȋw��ł��邱�ƂɊӂ݁A�{�V���|�W�E���ɂ����ẮA�q�ǂ��̕n���Ɋւ��āA����w�����҂́A���̖��ɂǂ̂悤�Ɏ��g�݁A�����ۑ�Ƃ��Ă���̂��A�܂��A����ǂ̂悤�Ȍ����̉\���������Ă���̂��𖾂炩�ɂ������B�l�X�Ȍ������삩��s���Ă���u�q�ǂ��̕n���v�̎��ԂƉۑ�A�����āA����w�����̉\���ɂ��Ęb�����������Ǝv���B
�i2018/8/21�j
���{�������y�w���11�����y������i2018�N8��25���i�y�j�E26���i���j�A���ˎs�������{�Z���^�[�암��فj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://s-jfm.org/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N8��25���i�y�j�E26���i���j
�ꏊ�F���ˎs�������{�Z���^�[�암���
�@�X�����ˎs���ێO����3��6��
�e�[�}�F�~�x��̗R���ƕϑJ�`�i�j���h�������Ɂ`
��̑����X�A��藼���ɕ��z����~�̗x��i�j���h������̌����A���^�A�`�d�A�ϗe�A���ۂƂ̊֘A���A�T�O�`���A�l���A����A�`���Ȃǂ̖ʂ��瑽�p�I�ɖ~�x����������A���炽�߂Ė������y�̉̂Ɨx��̖��͂��l����B
�X�P�W���[���i�\��j�F
�E��1���ځF8��25��(�y)
13:00�`�@��t�J�n
13:30�`�@�J��E�����A�̌��i�i�j���h�����j
�@�����Y�����܂��ۑ���i�����Y�����܂��A�\�Z���A�T�T�i�j���h�����j
14:30�`�@��u��
�@����h�u�������y�̉̂Ɨx��̖��́v
15:15�`�@�V���|�W�E��
�@�ɖ�`���A���쎛�ߎq�A�鏊�b�q�A���X���p�A�O�菃��
16:30�@�I��
17:30�`�@���e��i��ꖢ��j
�E��2���ځF8��26��(��)
09:00�`�@�������\
11:00�`�@�����E���c
12:00�`�@�I���E���U
�Q����p���F
����F3,000�~�i1���݂̂̏ꍇ1,500�~�j
�����F4,000�~�i1���݂̂̏ꍇ2,000�~�j
���e���F5,000�~
�i2018/8/20�j
���m���y�w����{�x����282���ጤ����i2018�N9��16���i���j�A���s�����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/nishi/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N9��16���i�y�j14:00�`17:00
�ꏊ�F���s�s���|�p��w�V������7�K����1
1.�C�m�_�����\�u�ȕ���p�����V���߂̉��y���́F���{���풘�w�V���ȕ��l�x�̍l�@�ƌܐ���������Ɂv�ш�s�i���s�s���|�p��w�j
2.�������\�u�T���g�D�[���ɂ݂�y���V�����y�ƃC���h���y�̕����Z���̏����v���t���i���s��w�j
3.���N�`���[�E�f�����X�g���[�V�����u�k�C���h�ÓT���y�̉��F�F���[�K�ƃ^�[�����D��Ȃ��������t�v
����E�^�u���[�E�o�[���[�����t�F���t���A�T���g�D�[�����t�F��t�c�i�����j
�i��F�c�� �����q�i���s�����w�j
�i2018/8/10�j
���m���y�������34����i2018�N8��26���i���j�A�����s���y�v���U�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://stella.a.la9.jp/aok/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N8��26���i���j13:00�`16:30
���F�����s���y�v���U ��2�T��
�S���E�i��F�[�x�ʍ�
�������\�F
�E�R���^�G�q�u�w���}���E�V�F���փ����`���V���[�x���g���F�Љ��`�v�z�Ƃ̊ւ�肩��v
�E���}�R仁u�Z�U�[���E�t�����N�̏����t�@���^�W�[�̍\�����́v
���m���y������́A�����n��ɂ������̂��鉹�y�Ɋ֘A���錤���҂��A�������ʂ\���c�_�������A ��܂�������Ƃ��āA2014�N5���Ɍ�������܂����B ���y�ɊW����l�X�ȕ���̌����҂��ꓰ�ɉ�A���L������ōl�@���_��Ȏv�l�Ō�����W�J���Ă������Ƃ� �ڕW�Ƃ��Ă��܂��B�����́A1�`2������1��s���������\����S�ł��B���\�ɑ��Ĉӌ������̎��Ԃ����l�@��[�߂�悤�ɂ��Ă��܂��B�悫�c�_�E�����𒆕��n�悩�甭�M�������ƍl���Ă���܂��B��ɉ��y�Ɋւ��錤���҂��Ώۂł����A�ǂȂ������Q�����������܂��B�F�l�̂��Q�������҂����Ă���܂��B
�i2018/8/9�j
���y�w�K�w���14�����\���i2018�N8��26���i���j�A���R���w����w�����u�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://jsml.jp/home/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N8��26���i���j10:00�`�i��t9:30�`�j
�ꏊ�F���R���w����w �����u�L�����p�X����w����3F
URL�Fhttp://www.sugiyama-u.ac.jp/
�v���O�����F�ڍׂ����y�w�K�w��14th�v���O����.pdf�ɂ�
10:10�`10:10�@�J��A
10:00�`12:00�@�V���|�W�E��
12:00�`13:00�@�x�e
13:00�`13:30�@����
13:40�`16:40�@�������\
17:30�`19:30�@���e��i�\���w�H�ɂāj
�E�V���|�W�E��
�e�[�}�F�u�l���Ȃ���o�����Ƃ��Ẳ��y�̌��F���Ɖ��y�Ɗw�Z���y�̈Ⴂ��ʂ��čl����v
�V���|�W�X�g�F���䐽�u�i�G�C�x�b�N�X�E�G���^�e�C�������g������Ёj�@�i��E�w�蓢�_�ҁF���r���q�i��t�o�ϑ�j�A�|�����i����������j
�@����̏��E����Љ�ɂ����āA�������͗l�X�Ȏd���Ől�Ƃ̂Ȃ�������߂Ă���B�q�ǂ��������܂��A�����ۑ������ē����Љ�ɐ����Ă���B�������A���̂Ȃ�����ǂ̂悤�ɂ��邩�Ƃ����d���ɂ����āA������{�̎q�ǂ������́A�Ⴆ��SNS�⓮��T�C�g�ȂǁA�w�Z�̓���Ƃ͕ʂ́u���E�v���g���Ă���悤�ɂ݂���B�܂�����́A�ނ�̉��y�ɂ܂�������̎d���ɂ��\��Ă���悤�ɂ݂���B�����ł͂��̎��ۂɏœ_�āA���Ɖ��y�̐��E�Ő����Ă��邱�Ƃ��Ă�����ɁA�q�ǂ����������߂Ă��鉹�y�̌��̓������c�_���Ă݂����B���y�̎��Ƃ��q�ǂ��������Ȃ���o�����ɂ������Ɗ肤���t�ɂƂ��āA�{�e�[�}�͉��l����c�_���N�����\���������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�Q����F����E�������2,000�~�A�w������E����1,000�~�i���������E�҂������j�A���e��4,000�~
�i2018/8/8�j
���{�w�Z���y������H�w���23��S�����i2018�N8��18���i�y�j�E19���i���j�A���s�����w�j
�w��E������̏��ł��B
���{�R�[�X�����A���肪�������\���s���܂��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jassmep.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�J���F2018�N8��18���i�y�j�E19���i���j
���F���s�����w�i���s�s������[�����X��1�Ԓn�j
�A����F��23������� ��������i���s�����w�������R���w�Z�j
�@��612-0072���s�s�����操�R����ɉ��46
�@Email: shihojaasme[at]gmail.com
�Q����F���Q����4,000�~�A���e���4,000�~�A�u����Q����2,000�~
�����F
�E8��18���i�y�j
9:30�`10:00 ��t
10:00�`11:30 �u����
12:30�`15:00 ���R����1�`7
15:15�`15:45 ����
15:45�`17:45 �ۑ茤��
18:00�`20:00 ���e��
�E8��19���i���j
8:30�`9:00 ��t
9:00�`11:30 ���R����8�`14
12:30�`13:50 �x���v���W�F�N�gI�`III
14:10�`15:30 �t�H�[����I�`V
�E�u����u�]�Ȋw����݂����y����̈Ӌ`�v
�u�t�F����p�����i������Г������쏊���_�t�F���[�j
�@�{�w��ł́A����܂Łu�����������Ƃ���21 ���I���y�J���L�������v���J�����A�����Ƃ��ẴJ���L�����������H�ɂ�茟������ߒ���ʂ��āA���y�Ȃň琬���ׂ��\�͂�Nj����Ă��܂����B�܂����A�V�w�K�w���v�̂���������A���ׂĂ̋��ȓ��ɂ�����ڕW�y�ѓ��e���@�m���y�ыZ�\�A�A�v�l�́A���f�́A�\���͓��A�B�w�тɌ������́A�l�Ԑ����̎O�̒��ōč\�z�����ȂǁA�m���̗����̎������ߎ����E �\�͂���ށu��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�сv�̎�����ڎw���A�u�����ł���悤�ɂȂ邩�v�m�ɂ���Ƃ����V���ȕ�������������܂����B�����ŁA���̋@��ɁA�]�Ȋw�̕���ɂ����Đ��E�I�Ȏ���Ō���������A���ɐl�Ԃ̐����ɂ����鉹�y�E���p���̌|�p�̏d�v�����w��I�Ɍ������A�����_���⒘���Ƃ��Ĕ��\����Ă��鏬��p�������u�t �ɂ��������A�]�Ȋw����݂����y����ɂ��Ă��u�������������Ƃ� ���A�w�Z����ɂ����鉹�y�Ȃ̈Ӌ`�ɂ��āA�V���Ȏ��삩�痝����[�߂Ă��������ƍl���܂��B�ӂ���Ă��Q�����������B
�E�ۑ茤���u���y�Ȃň琬���ׂ������E�\�͂Ƃ��̕]���F�����̌����Ɋ�Â����y�Ȏ��Ɓv����3 �����E�\�͈琬�̂��߂̃X�^���_�[�h�̍l����
�i��F���m�K�Y�i��茧����������Z���^�[�j
�u���ꂩ��̎���ɋ��߂��鎑���E�\�́F���y�Ȃ̏ꍇ�v�P��w�i�����Ȋw�ȏ�����������Nj���ے��ۋ��Ȓ������j
�u���y�Ȃɂ����鎑���E�\�͈琬�̂��߂̃X�^���_�[�h�̍l���� �X�^���_�[�h�̘g�g�݁v�����S���q�i���s�����w�j
�u�p�t�H�[�}���X�E�X�^���_�[�h�̋�̓I�Ȏp�v�q�����q�i�E����w�j
�p�l���f�B�X�J�b�V�����u���y�Ȃň琬���ׂ������E�\�͂ɂ����ăX�^���_�[�h�͂����ɗL���ɋ@�\���邩�v
�E���R�������
���R����12-5�u�w�K�w���v�̉����ɔ������y�ȋ���ɂ�����u�������k�v�ς̍čl�F�}�C�m���e�B�ȗ���̎q���ւ̊w�͕ۏ�̑������v����S�i�i��z�����w�j
�i2018/8/7�j
�S����w���y����w���34��S�����i�����j�i2018�N8��23���i�j�`25���i�y�j�A���K�[�f���p���X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.nacome.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
���e�[�}�F�g�L���Ȋ����̈炿���特�y�\���ցh
�����F����30�N8��23���i�j�`25���i�y�j
���F���K�[�f���p���X�i���s�{����։��l����1��5���j
�q��1���ځF8��23���r
13:00�`15:00 ��C�ψ���
15:00�`17:00 ������
17:00�`18:00 �n��40���N�L�O���ƈψ���i���j
18:30�`21:00 �������������
�q��2���ځF8��24���r
9:30�`10:00 ��t
10:00�`10:30 �J�
10:30�`11:30 ��u��
11:30�`12:00 ���̎��A�{���Z�͂ǂ��Ώ������̂�
�@�@�@�@�@�@�@�`�����{��k�Ђ�U��Ԃ�`
13:00�`15:00 �V���|�W�E��
15:30�`17:30 �������\�i�������\�j
17:30�`18:30 �����I�v�ҏW�ψ���
18:30�`20:30 ��������
�q��3���ځF8��25���r
9:00�`10:20 �������\�i��i���\�j
10:30�`12:30 ���ʍu��
11:30�`12:00 �
�E��u���u�]�Ȋw���猩���q���̔]�̈�ݕ��v
�쓇�������i���k��w�����w�����������j
�E�V���|�W�E���u�����̈炿����R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Ẳ��y�\���� �\���������珉������܂ł����ʂ��ā\�v
�p�l���X�g�F�u���m�q�i��ʑ�w���_�����A���{�Ԃ����w���C�����A���{�q�ǂ��w����j�A�{���Ŕ��i�����̐����q��w�����A�����旧�����̐����q��w���ǂ��������j�A�茴�a�q�i�]�ː��w�����j�@�i�s�F���i�N���i�S�R���q��w�Z����w���u�t�A��ʑ�w�����j
�E���ʍu���u�̏��ɂ�����I���`�����v
������q���i�{�鋳���w�y�����j
�i2018/8/6�j
���v���c�@�l���{�s�A�m����A�� �s�A�m�w���@�Z�~�i�[�i2018�N8��21���i�j�A�J���C�\�Q���j
�Â��̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jpta.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
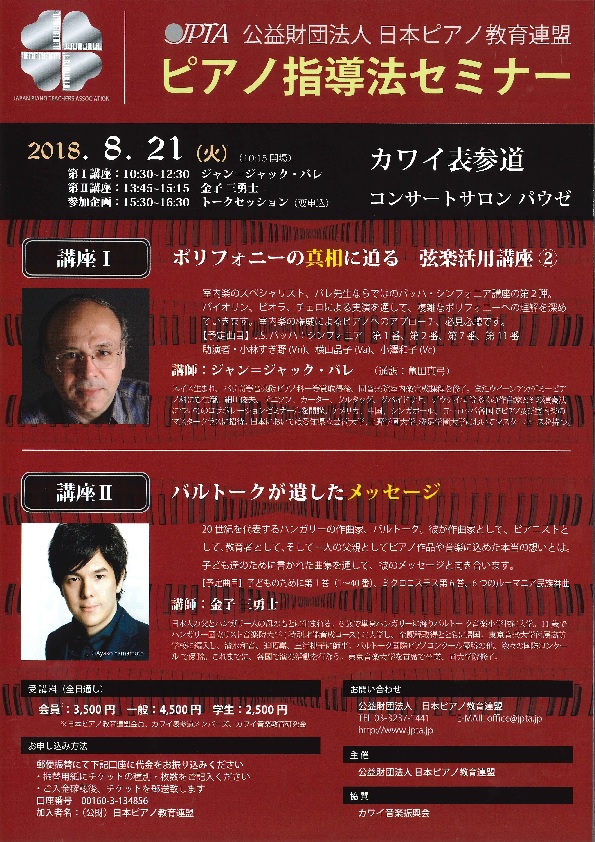
�����F2018�N8��21���i�j�i10:15�J��j
�@��I�u�� 10:30�`12:30 �W�������W���b�N�E�o��
�@��II�u�� 13:45�`15:15 ���q�O�E�m
�@�Q����� 15:30�`16:30 �g�[�N�Z�b�V�����i�v�\���j
�ꏊ�F�J���C�\�Q�� �R���T�[�g�T�����p�E�[
�E�u��I�u�|���t�H�j�[�̐^���ɔ��� ���y���p�u���i2)�v
�u�t�F�W�������W���b�N�E�o��
�����y�̃X�y�V�����X�g�A�o���搶�Ȃ�ł͂̃o�b�n�E�V���t�H�j�A�u���̑�2�e�B�o�C�I�����A�r�I���A�`�F���ɂ�������ʂ��āA���G�ȃ|���t�H�j�[�ւ̗�����[�߂Ă����܂��B�����y�̌��Ђɂ��s�A�m�ւ̃A�v���[�`�A�K���K���ł��B
�\��ȖځFJ.S.�o�b�n�F�V���t�H�j�A��1�ԁA��2�ԁA��7�ԁA��11��
�����ҁF���т�����iVn�j�A���R���q�iVa�j�A���V�a�q�iVc�j
�E�u��II�u�o���g�[�N���₵�����b�Z�[�W�v
�u�t�F���q�O�E�m
20���I���\����n���K���[�̍�ȉƁA�o���g�[�N�B�ނ���ȉƂƂ��āA�s�A�j�X�g�Ƃ��āA����҂Ƃ��āA�����Ĉ�l�̕��e�Ƃ��ăs�A�m��i�≹�y�ɍ��߂��{���̑z���Ƃ́B�q�ǂ��B�̂��߂ɏ����ꂽ�ȏW��ʂ��āA�ނ̃��b�Z�[�W�ƌ��������܂��B
�\��ȖځF�q�ǂ��̂��߂ɑ�1���A�~�N���R�X���X��6���A6�̃��[�}�j�A��������
��u���i�S���ʂ��j�F
���3,500�~�A���4,500�~�A�w��2,500�~
��ÁE�⍇���F���v���c�@�l���{�s�A�m����A��
TEL03-3237-1441�@MAIL: office[at]jpta.jp
�i2018/8/2�j
��53��V�������y�R���N�[�� ���ʔ��\
7��29���ɑ�53��V�������y�R���N�[���{�I��s���A�{�R�[�X��w�@���̓c���x�����m���܁A���J�Ă���Ɩ������D�G�܂���܂��܂����B
�{�I���ʂ͉��L�̂Ƃ���ł��B�i�h�̗��j
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�q��܁r
���仕��i�s�A�m�A���炵����z��j
�q���m���܁r
�R�舺�l�i�s�A�m�A��z�����t�����j
�c���x�i���y�A��z�����@�j
�q�ŗD�G�܁r
�ҏΎq�i�NJy��A�������y��j
�q�D�G�܁r
�E�s�A�m
�ߓ��R�s�i�����������j
���{�܂䂩�i�V���V�ʏ��j
�������P�i�V���T�c���j
�����I�ԁi�V���������j
��������i�V���������j
�����݂̂�i�V���������j
���J�āi��z�����@�j
�E���y
�˓c����i�V�����R���j
�E���y
�~��䂫�́i�V���������j
�������W�i�����w�|��@�j
�E�NJy
���_�����i�V���������j
���R�O�l�i�V���������j
������i��z�����@�j
�q����܁r
�L�I�i���y�A�V���������j
�i2018/8/1�j
��������Z�~�i�[�u�Œ艻�ȑO�̋����F�����펞�ォ�玺�������܂Łv�i2018�N8��8���i���j�A��������فj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
nohgakugakkai.cside.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F8��8��(��) 13:30�`17:00�i��t�J�n13:00�j
���F��������فi�ߓS�ޗljw�����D���o�Ď�������2���K�i�E�G�X�J���[�^�[��3���K�i����k���B�܂��́AJR�ޗljw���ޗǎs���z�n���o�X��5���A�u�����O�v���Ԃ����j
�E�J��̎� 13:30�@�\�y�w���\ �O��q
�E��|���� 13:35�@��c�G�Y
�E��u�� 13:40�`14:30
�u�����̌`���v�c���a�v
�E�� 14:40�`15:40
�u�����Ɖ̗w�v�A�ؒ��q
�u�������̐��b�Ƌ����v����F
�E�S�̓��c 15:50�`17:00
�i��F��c�G�Y
�E���e�� 17:30�`19:30
��C�O (�ޗǎs�Ђ����ނ����X�X)
�Z�~�i�[�Q����F1,000�~
���e���F4,000�~
����������Z�~�i�[�֘A�s��
�i�P�j��������@8��8���i���j10:00�`11:00�@���F��ގ��i�ޗnj����S�c���{���厚���ԁA�ߓS�u��a���v����^�N�V�[�Ŗ�20���j
�i�Q�j������E�T�|���M�`�����W�ρ@8��7���i�j13:00�`15:00�@���F��R���i�ޗnj�����s�A�ߓS�u����v����ߓS����P�[�u���u��R���v���ԁj�@�Q����F1,000�~
�⍇����F�\�y�w�����
��169-8050�V�h�搼����c1-6-1 ����c��w���������ٓ�
TEL03-3208-0325�i���T���j��10:00�`16:00�j
http://nohgakugakkai.cside.com/
�i2018/7/27�j
�|�s�����[���y�w��2018�N�x��3��֓��n����i2018�N7��28���i�y�j�A�哌������w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jaspm.jp/?p=1839
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��28��(�y) 14:00�`17:00
���F�哌������w�哌�������3�KK-302
�@����������������n�w�k��5���i�X�N�[���o�X�ɂ͏��܂���j
�@�A�N�Z�X�}�b�v�Fhttp://www.daito.ac.jp/file/block_49512_01.pdf
���\1�F���{�̃|�s�����[���y�ɂ�����W�������̐����ƕϗe�Ɋւ���Љ�w�I�l�@
�\70�N��̃t�H�[�N�A�j���[�~���[�W�b�N�𒆐S�Ƃ��ā\
����T�i�i�ŋ���w��w�@�Љ�w�����ȁj
���\2�F�{�y���A�O��̉���ɂ����郍�b�N��e�Ƃ��̓W�J
�\A�T�C���N���u�Ɗ�n���N���u�Ƃ��̎��ӂ�ΏۂɁ\
�V�c����i�����Y�p��w��w�@���y�����ȁj
���\3�F�����{�ɂ�����u�W���Y�E�t�F�X�e�B�o���v�̎�e�ƒ蒅�ߒ�
���������i�����Y�p��w��w�@���y�����ȁj
���I����A���e���\�肵�Ă��܂��B
���₢���킹�F
�������ށi�֓����S�����������ψ��jshuutou.yoshiki[at]gmail.com
���M�q�i���������S�������jfwgd0462[at]mb.infoweb.ne.jp
�i2018/7/26�j
�s�b�R���V�A�^�[�J��40���N�L�O�V���|�W�E���u�n��ƌ���̐V���ȊW��T��v�i2018�N8��11���i�y�E�j�j�A�s�b�R���V�A�^�[�j
�Â��̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
hyogo-arts.or.jp/piccolo/40kanshasai/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
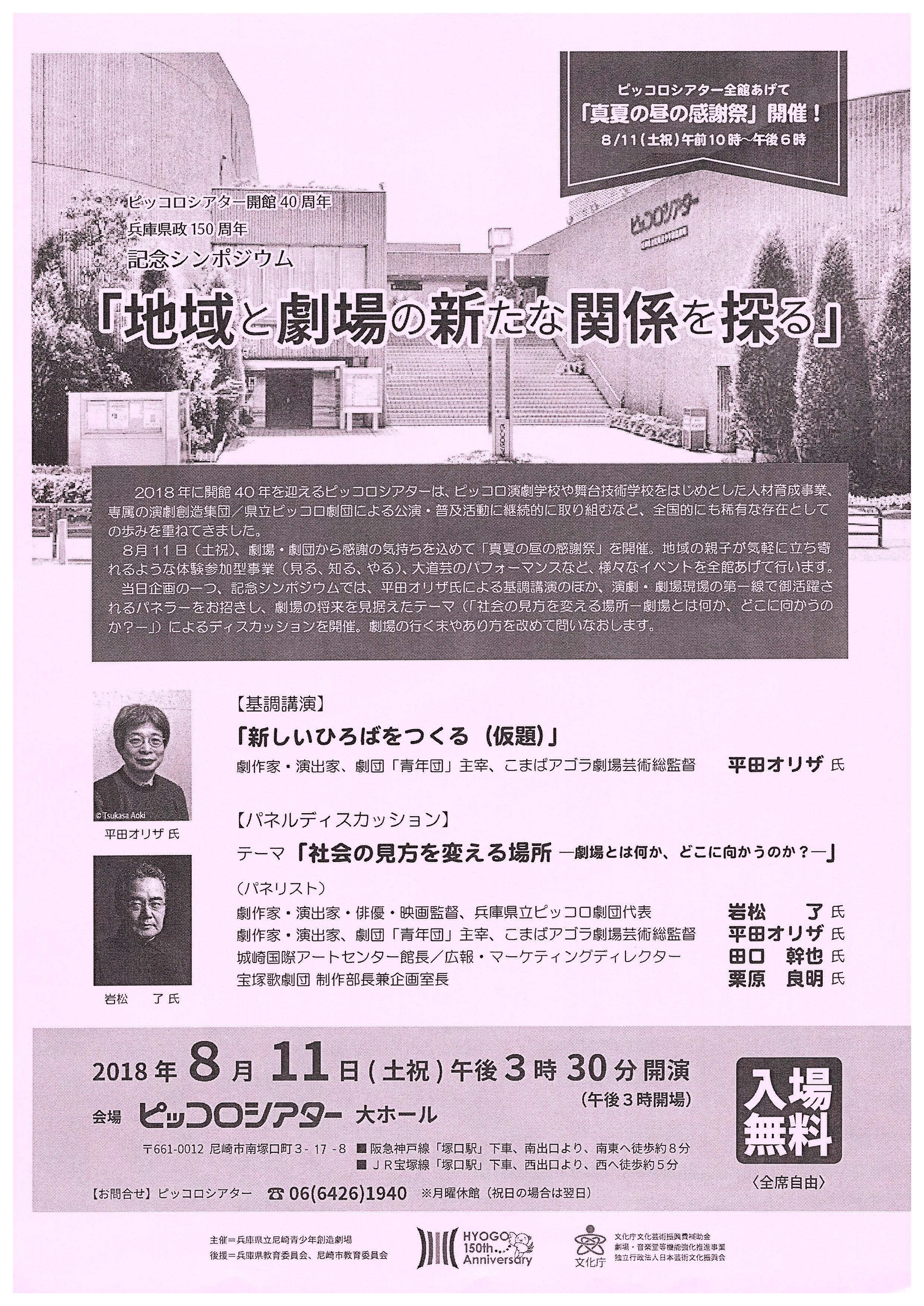
2018�N8��11���i�y�j�j�ߌ�3��30���J���i�ߌ�3���J��j
���F�s�b�R���V�A�^�[��z�[��
�@���Ɍ����s��ˌ���3-17-8
�@��}�_�ː��u�ˌ��v�w���ԁA��o�����쓌�֓k����8��
�@JR��ː��u�ˌ��v�w���ԁA���o����萼�֓k����5��
���ꖳ���i�S�Ȏ��R�j
���₢���킹�F�s�b�R���V�A�^�[
�@TEL06-6426-1940�i���j�x�فA�j���̏ꍇ�͗����j
�E��ꕔ�@��u���@�ߌ�3��30���`�ߌ�4��15��
�u�V�����L�������F21���I�̌���̖����v
���c�I���U���i����ƁE���o�ƁA���c�u�N�c�v��ÁA���܂A�S������|�p���ēj
�E��@�p�l���f�B�X�J�b�V�����@�ߌ�4��30���`�ߌ�6��
�u�Љ�̌�����ς���ꏊ�F����Ƃ͉����A�ǂ��Ɍ������̂��H�v
�⏼�����i����ƁE���o�ƁE�o�D�E�f��ēA���Ɍ����s�b�R�����c��\�j �A���c�I���U���i����ƁE���o�ƁA���c�u�N�c�v��ɁA���܂A�S������|�p���ēj�A�c�����玁�i��荑�ۃA�[�g�Z���^�[�ْ��j�A�I���ǖ����i��ˉ̌��c ���암������掺���j
�i�s�F�{�c��b�q�A��ؓc����i����������Ɍ����s�b�R�����c���j
�i2018/7/25�j
���{�w�Z����w���33�����i2018�N8��4���i�y�j�E5���i���j�A�����w�|��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jase.gr.jp/2018_taikai/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N8��4���A5���@��t�F08:30�`
�ꏊ�F�����w�|��w�k�u�`���iN���j�i�A�N�Z�X�A�L�����p�X�}�b�v�j
���������F
��1����
8:30�`�@��t�@N��1�K
9:00�`11:50�@���R�������\�@N���e�u�`��
12:50�`13:50�@�������@S410����
14:15�`17:00�@���J�V���|�W�E���@S410����
�@�u�n��ɂ����鋳��g�D�A�w�Z�g�D�A����ے��̐V�����W�̑n��
�@�@�\�@�\�T�O�Ƃ��ẴJ���L�������E�}�l�W�����g�\�v
17:30�`20:00�@��������@���ނ����̃z�[��2�K
��2����
8:30�`�@��t�@N��1�K
9:00�`11:50�@���R�������\�@N���e�u�`��
13:00�`15:30�@�ۑ茤���@S410����
15:40�`17:00 ���E���h�e�[�u��
�E�u���H�����_���ɒ��킵�悤�|�����̖��S�������Ƃ��Đ��������邽�߂Ɂ|�v�i�@�֎��ҏW�ψ���j
�E�u�����Ƌ���\���B�S�c�L�[�ƃf���[�C�A���㋳�痝�_�̒ꗬ����\�v�i��F�����T���i�����w�|��w�j�@�ҁF���ԋF��Y�i������w�j�A�������i�����w�|��w�j�A�É��b���i�����w�|��w�j
�����J�V���|�W�E��
�u�n��ɂ����鋳��g�D�A�w�Z�g�D�A����ے��̐V�����W�̑n���\�@�\�T�O�Ƃ��ẴJ���L��������}�l�W�����g�\�v
�V�w�K�w���v�̂́A�u�J���L��������}�l�W�����g�v�̏d�v�����w�E���Ă���B�J���L��������}�l�W�����g�Ƃ́A��ʓI�ɁA�w�Z����̂ƂȂ��āA�w�Z����̖ړI��ڕW��B�����邽�߂ɁA����̓��e���q���̐S�g�̔��B�ɉ����A���Ǝ������Ƃ̊֘A�ɂ����đ����I�ɑg�D���A����ے���Ґ����邱�Ƃ��Ƃ����Ӗ��Ŏg�p����Ă���B�������A�n��ɂ����ẮA���q���ɂ��w�K�W�c�̕Ґ��݂̍���A�����̔z�u��g�D����}�l�W�����g�݂̍���A�w�Z��Z���������ے��݂̍�����A�����ɒNj�����Ă���A�u�J���L��������}�l�W�����g�v�́A�u�w�Z�v�u����ے��v�����L��������������̂Ƃ��Č�������Ă���B���J�V���|�W�E���ɂ����ẮA�ߑa���Ɛl���W���ւ̑Ή��A�����̓����ɂ����錠���̍Ĕz���ƒ����A�w�Z��������ے��̍\�z�A�V�����w�Z�}�l�W�����g�V�X�e����Nj����Ă��钷��s������Ƃ��āA�@�\�T�O�Ƃ��ẴJ���L�������A�}�l�W�����g�ɂ��Ă̋c�_��[�߂邱�Ƃ���|�Ƃ��Ă���B
�V���|�W�X�g�i50�����j�F�ɓ��w�i���i���v���c�@�l�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���Z���g�D�ψ���`�[�t�E�t�B�i���V�����E�I�t�B�T�[�������ǒ��A�O�����Ȋw�ȏ�����������Ǎ����ے��A�O���쌧���璷�j�A�ސ{���T���i��q��w�����l�ԉȊw�������A��������R�c���ے�������������啔��ψ��j�A�R�l������s���͂���w�Z�Â��茟���ψ���ψ����A�O�M�B��w�w���j�@�i��i�s�F���{�݂���i�����w�|��w���E��w�@�����j
���������\���
�E���V��i��z�����w�t�����w�Z�j�u���y�W��̗��_�Ǝ��H�F�g�̐��ƌ��ꐫ�����鉹�y�ƏW�c�v�i���R�������\2�F8��4��9:05�`9:35�AN102�j
�E���ы��q�i�ڔ���w�j�u���w�Z���y�Ȃɂ�����u��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�сv�F�䂪���̓`���I�Ȕ��̑��������w�Ԏ��Ƃ�ʂ��āv�i���R�������\7�F8��5��10:40�`11:10�AN101�j
�i2018/7/24�j
Prof. Haruo Shirane from Columbia University Open Classroom@Waseda�u�q�Q���^�����r�Ɠ��{�F�`���|�\���猻��}���K�܂Łv�i2018�N8��2���i�j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/inst/sgu...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
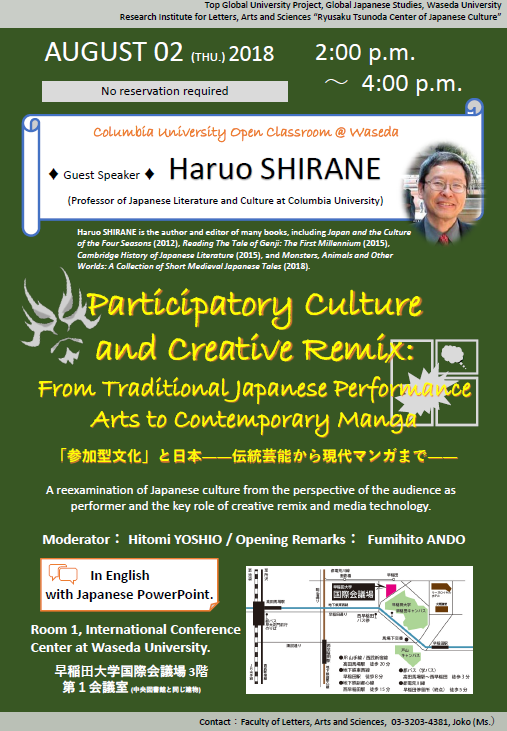
�����F2018�N8��2���i�j14:00�`16:00
�@�n���I�E�V���l�����ɂ��u���ɑ����A���[�N�V���b�v���J�Â��܂�
���F����c��w���ۉ�c��3�K��1��c���i�����}���ُ�j
�e�[�}�F�u�Q���^�����v�Ɠ��{�F�`���|�\���猻��}���K�܂� Participatory Culture and Creative Remix: From Traditional Japanese Performance Arts to Contemporary Manga
�J�Î�|�F�V���l�����ɂ��u���ɑ����A�I�[�v���N���X�`���Ńf�B�X�J�b�V�����������Ȃ����Ƃɂ��A���{���������̍őO���̓��e�ɂ��ċ����Ɗw�����Ƃ��ɎQ�����A�Ƃ��ɍl���A�c�_���s�����݂ł��B
�u������F�p��
���^�����F�p��E���{��
�p���[�|�C���g�����F�p��E���{��
�Q���ҁF�w���O�w���A��ʁ@�i�ǂȂ��ł����Q�����������܂��j
�i��F�R�����i���w�w�p�@�y�����j
�J��̎��F�������l�i���w�w�p�@�����j
�i2018/7/20�j
�����|�p�w���149�����i2018�N7��28���i�y�j�A���s�����m�������p�فj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
ethno-arts.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��28���i�y�j�@13�F00�`15�F30
�ꏊ�F���s�����m�������p�� �u��
�@�n���S�䓰�ؐ��E����{���u�������w�v1���o�������400���[�g��
�@�i���s������������j
������ɂ��A��ꂪ�u��c���v�ɕύX�����\��������܂��B�ē��\���Ȃǂɂ����ӂ��������B
�������\�F
�P�j�ؐ��痢(�����w�j�F�u�A���o�[�g�EC.�o�[���Y�̃A�t���J�|�p��������l�@����1920�N��̃A�����J�̔��p�j�ρv
�Q�j����j��(������w�j�F�u�����҂������݂��q�A�[���E�l�[�O���r�F1910�N��́u�A�t���J�`���v�̊����𒆐S�Ɂv
�S�������F��v�ۋ��q
�A����F�����Y�p�w��{���������@mg_gakkai[at]yahoo.co.jp
�i2018/7/19�j
���{���y�w����x����123���ጤ����i2018�N7��28���i�y�j�A������w���É��L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.msj-chubu.org/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N�i����30�N�j7��21��(�y) 13��30���`
�ꏊ�F������w���É��L�����p�X 5����4�K544����
�@�i���É��s���a�攪���{��101-2�j
�q�������\�r
1. �X��_�R�i���É��s����w��w�@���m�O���ے��j
�u�����Љ�ɂ����鉞�p���y�ɂ��Ă̌����v
2. ���ؖΕv�i������w���ۋ��{�w���j
�u�L�c�s�}���ّ��]�ˊ��ʖ{�w���C�x�Ɋւ����b�I����
�\�\���{�G�ǁw�R����v���x�Ƃ̊W�ɂ��āv
�q���ʍu���r
�}���N�E�o�e�B�G�iProf. Marc Battier�@�\���{���k��w���_�����j
�u�f�W�^�����y�w�̖��ɂ��āv
�������y�w(Computational Musicology)�́A�l�H�m�\�̏����W�J�Ɠ��������A���Ȃ킿1960�N��Ɍ��ꂽ�B �T�C�o�l�e�B�N�X�̏��������̉e�����A�R���s���[�^�Ȋw�����y�w�ɗL���ȃc�[������邾�낤�Ƃ��� �M�O���A1970�N��ɂ́A����ɁA�R���s���[�^�x�����y�w(Computer-Assisted Musicology)���Ă������B �����A�f�W�^���l���w(Digital Humanities)�Ƃ����p��́A�R���s���[�^�E�x�[�X�̗l�X�ȃI�y���[�V������ ���p�Ɋւ��āA���E�ɒʂ���ď̂Ƃ��Ďg�����Ƃ��ł���̂ł���A���L������ɐZ�����Ă��Ă���B���ꂪ ���y�w�ɂƂ��Ăǂ̂悤�Ɋւ���Ă��邩���l���邱�Ƃ́A�����n�܂�������̌����_�ɂ����ďd�v�ł���B ��X�̌����ɂƂ��ẴR���s���[�^�E�f�W�^���c�[���ɂ����č������g�����h�Ȃ̂��B����A�����x���� �R���L�E���ɂ����āA���y�w�҂̊F�l�Ƃ��̖������L���Ă��������B
�i��F���ؖΕv�i������w�j
�ʖ�F����݂��q�i���É��s����w�j
�i2018/7/18�j
��쐳�l�o�X�E�o���g�����T�C�^���i2018�N7��22���i���j�A����s������كA���t�H�[���j
�{�R�[�X�����A���̎�Ì����ł��B
�����T�C�g�͂�����
http://www.artforet.jp/event/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
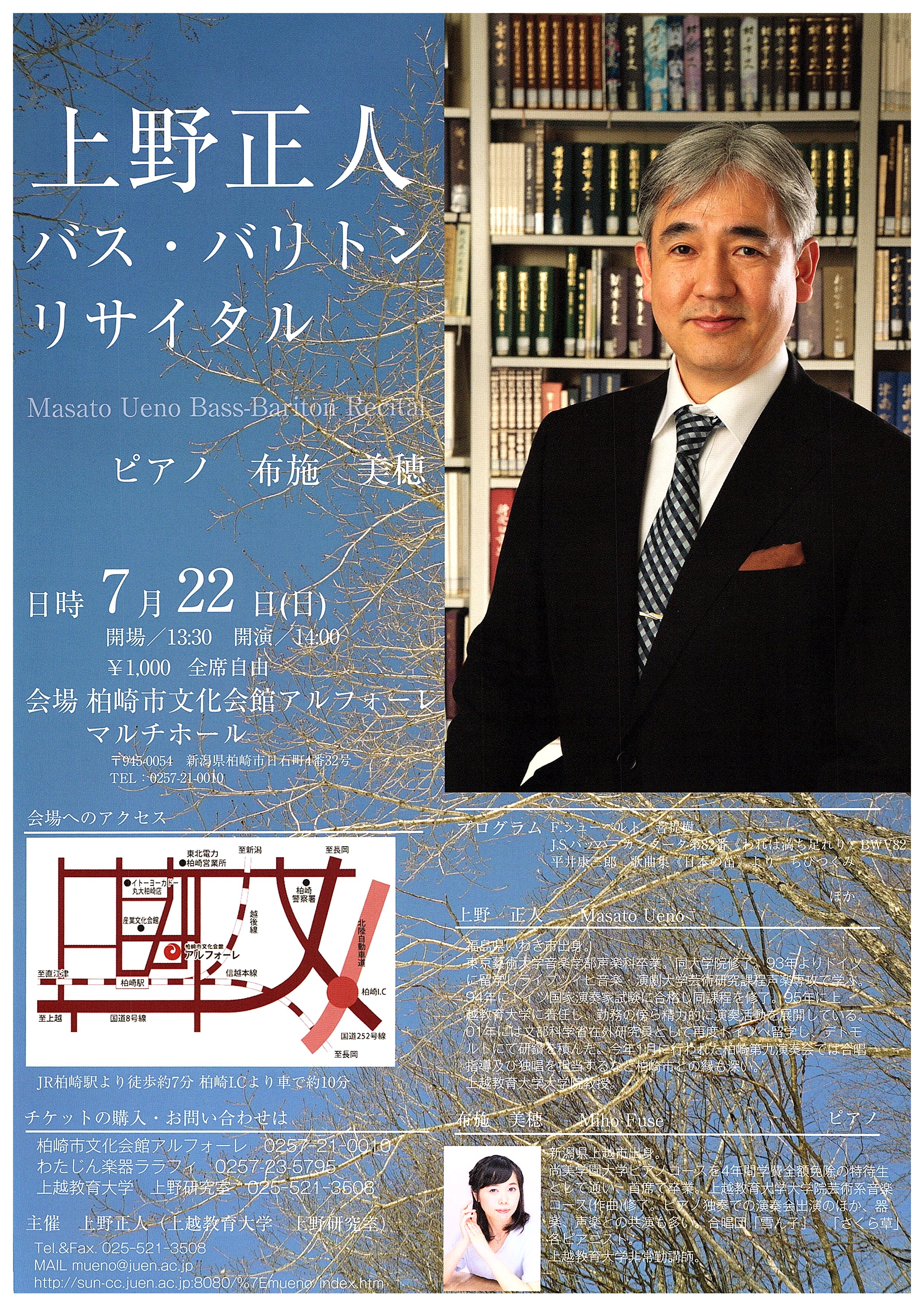
�����F2018�N7��22���i���j14:00�J���i13:30�J��j
�ꏊ�F����s������كA���t�H�[�� �}���`�z�[��
�@����s����4��32���@TEL0257-21-0010
�����F�S�Ȏ��R1,000�~
�q�v���O�����r
�EF.�V���[�x���g ����
�EJ.S.�o�b�n �J���^�[�^��82�ԁs���͖��������t
�E����N�O�Y �̋ȏW�s���{�̓J�t��� ���т��݁@�@�ق�
�s�A�m�F�z�{����
�`�P�b�g�̍w���F���蕶����كA���t�H�[���A�킽����y�탉���t�B�A��z�����w��쌤����
��ÁE���₢���킹�F��z�����w��쌤����
�@TEL025-521-3508�@Mail: mueno[at]juen.ac.jp
�@http://sun-cc.juen.ac.jp:8080/~mueno/index.htm
�i2018/7/17�j
���{���y�w����{�x����52���ጤ����i2018�N7��28���i�y�j�A�D�y��J��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.musicology-japan.org/east/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N�V��28���i�y�j14�F00�`17:00
�ꏊ�F�D�y��J��w �����z�[��
�i��E�R�[�f�B�l�[�^�[�F��t ���i�D�y��J��w�j
�V���|�W�E���u��펞��̉��y���l����v
�p�l���X�g�F�����~�q�i�����Y�p��w�j�A����Y�i�i�˕��w����w�j�A
�~�ËI�Y�i�H�w�@��w�j�A��t��
�i2018/7/13�j
��36���[�|�p���y�n��w��i2018�N7��29���i���j�A�����ё�w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://jssa.info/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
����: 2018�N7��29��(��)
�ꏊ:�����ё�w���c�L�����p�X ���X��4�K408����
�@��194-0294�����s���c�s��Ւ�3758
�@https://www.obirin.ac.jp/access/machida/
�@https://www.obirin.ac.jp/about/campus/machida.html
��29���i���j�ɃX�N�[���o�X�͉^�s����܂���B�_�ސ쒆����ʂ̘H���o�X��JR���l���u����Ӊw�v�k���i�����т܂�8���j�Ə��c�}���u���c�w ���c�o�X�Z���^�[�v�i25���j����^�s����Ă��܂��B�u�����ъw���v�u�����ъw�����v�u�����ъw���O�v�̂ǂ̃o�X��ʼn��Ԃ��Ă��������Ă����v�ł��B
�E13:00�`13:50 ��ʃZ�b�V����1 (25��)
����q (��s��)�u��ԉ����ɂ��g�̃C���[�W�̕ω���p�����C���X�^���[�V�����`quad�`�v
������n (��s��)�u�N���V�b�N���t�Ƃ̃W���Y���t�R�s�[�ɂ����郊�Y���E�t���[�Y�c���̒���
�E
14:00�`14:20 ��ʃZ�b�V����2 (20��)
����݂��q (��s��)�u�d�q�������y���ی������EMS2018�v
�E14:40�`15:40 ���ҍu����� �l�H�m�\�Ɖ��y
�����S�F (�����w�����y��)�A��J�I�q (�����s�s��)
�E16:00�`17:00 ���ҍu�����
Mara Helmuth (��ICMA��AUniversity of Cincinnati)
�i2018/7/12�j
�w���w�x��69��1���i�ʊ�252�A���w��A2018�N6���j
�w��ŐV���̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�E�y�c�k�u�q�����炵�r�^�q�߂Â炵�r�F�����a�̂Ɍ��鉿�l���f�̕ϑJ�Ɓq�Ƒn���r�̏o���v1
�E�Ï�p��u�Ñ㗝�_���ߑ�v�z�Ɏd���Ē����F�W���[�����E���[�C�̌|�p�̌n�_�v13
�E�R�����G�q�u�t���[�h���q�E�V�����[�Q���̏����v�z�ɂ�����q�t���r�v25
�E����������u�V�F�����O�̕��i��_�ɂ�����C���v37
�E�ɓ������q�u���|�p�͎��R�ɑ�����I���J�Ƃ�����̂��F���|�p���߂���ϗ��I���ɂ��āv49
�E���䐟�q�u�q���f���r�̓`�d�F�n���X�E���������N��s�_���̎O�A��t�ƃC���O�����h�ɂ�����t�����h�����p�̎�e���߂����āv61
�E�O�䖃���u�t���[�h���q�E�V���P���ɂ��x�������������ّ����lj�Ɋւ���l�@�v73
�E�Ð�^�G�u�A���t���[�g�E�N�[�r���ɂ����閲�ƋL���F1909�N�ォ��1930�N��̍�i�ƌ����𒆐S�Ɂv85
�E�������}�u�W�����E�f���r���b�t�F�G��ɂ����镨�������߂����āF1920�`40�N��t�����X�ɂ�����|�p�E�v�z�̏����v97
�E�|���L�q�u�N���X�g�t�@�[�E�h���b�T�[�čl�F���̃W���|�j�X���ƃ��_�j�Y���̊W���߂����āv109
�E�������q�u�o���G�ɂ�����A���x�X�N�ƃO���e�X�N�v121
�E�����N�G�u���[�g���B�q�E�m�[���́s�~�T�E�\�����j�X�t�_�F�q�t�����X�g�r�x�[�g�[���F���̋���y�v133
����30�N6��30�����s �@ISSN:0520-0962
�ҏW���s�F���w��@���s�s������g�c�����B��46����c�L�O�ٓ�
�@���s��w������̖��������Z���^�[ �g��������
�i2018/7/11�j
��53��V�������y�R���N�[���{�I��i2018�N7��29���i���j�A�V���s���|�p������فj
����w�@������яC�������\�I���ʉ߂��{�I��ɏo�ꂵ�܂��B
�{�R�[�X���������s�ψ��Ƃ��Ċւ���Ă��܂��B
�������T�C�g�͂�����
www.pref.niigata.lg.jp/bunkashinko
...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�J�����F7��29���i���j10:30�`
�ꏊ�F�V���s���|�p������فi���[�Ƃ҂��j
���ꗿ�F���1,500�~�A�����w��400�~�@���S�Ȏ��R
�@�i�������1,800�~�A�����w��500�~�j
����53��V�������y�R���N�[���{�I�o��ҁi�h�̗��j
�y�s�A�m����z
�E���w1�A2�N�F�������сi��z�����t���j�A�Έ�ː��i�V���c��t�j
�E��3�A4�N�F��◮�l�i��z�����t���j�A�����u���i������c��j�A�����G�K�i�V���㏊�j�A���{�܂䂩�i�V���V�ʁj�A�R�c�L仁i�V���T�c�j�A�ߓ��R�s�i���������j
�E��5�A6�N�F�������P�i�V���T�c�j�A���q�@��i�V���V���j�A�~�l�i�V����t���V���j�A����ԉ��i�����哇�j
�E���w���F�R�舺�l�i��z�����t���j�A���N���i��z�����t���j�A����ő��i�V����t���V���j�A���{�l�l�i�V�����ցj�A���{����i�V���Ԓˁj
�E���Z���F�|���D�P�T�i���c�j�A���c�Ήԁi���c�k��j�A���R�甎�i���c�j�A�����݂̂�i�V�������j�A�����I�ԁi�V�������j�A��������i�V�������j
�E��ʁF���仕��i���炵����z��j�A���J�āi��z�����@�j�A���їD���i�V����j�A�ˌ����T�i���{��@�j
�y���y����z
���o�C�I�������˓c����i���w���E�V�����R�j�A���ь��i���w���E�V���։��j
���`�F�����R�c�d�i��ʁE�˕��w����j
�y���y����z
�E�W���j�A�F�L�I�i�V���������j�A�~��䂫�́i�V���������j�A����^�F�i�V�����u��������j
�E��ʁF�c���x�i��z�����@�j�A�k�����}�i���{�L���s�A�C�����j�A�����^���i�����s���n��j�A�������W�i�����w�|��@�j
�y�NJy����z
�E�W���j�A�F
���t���[�g�����_�����i�V���������j�A���c���i�V���������j�A���R�O�l�i�V���������j
���N�����l�b�g�����c�挎�i�V���������j
���g�����{�[�������q���i�V���������j
�E��ʁF
���t���[�g�����ĉԁi���a���y��j
���N�����l�b�g���ҏΎq�i�������y��j
���T�N�\�t�H����������i��z�����@�j
�i2018/7/10�j
�w��剹�y�w��x��15���i����w���w���E����w��w�@���w�����ȉ��y�w�������A2018�N5���j
�w�p���ŐV���̏��ł��B
�����s�@��HP�͂�����
https://musicologyosaka.wordpress.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�E�u�q�ǂ��ƃx�[�g�[���F���F�ߑ���{�̋��猻��ɂ������b�q�����̋ȁr�v�R�{�k���@1
�E�u�\�A�Łs�V���f�����t�ƃv���R�t�B�G�t�̃o���G���y�F�q��ՓI�Ȓ�r�̕`�ʂ��߂����āv�e�Ԏj�D�@19
�E�u�쐼�h�C�c�̊������琢�E�̊X�H�ցF���v�t�@���c�̏o�҂��y�t���y�����j���������v�H�R�Ǔs�@25
�E�u���ꉉ�t�Ƃ�����Ȃ����t����ۂ̉��t���x�̐e�ߐ��F���[�[���^�[���ƃz�t�}���ɂ��V���p���s�����cOp.42�t�̕����^���̉��t��r�v�h�쏲�q�@37
�E�������V�� ���̉��Ɛl 2016.4.-2017.3.
ISSN:1348-0456
���s���F����30�i2018�j�N5��25��
���s���F����w���w���E��w�@���w�����ȉ��y�w������
�@��560-8532���{�L���s�Ҍ��R��1-5
�i2018/7/6�j
�J���`���[�g�[�N Creators@Kamogawa�i2018�N7��7���i�y�j�A�Q�[�e�E�C���X�e�B�g�D�[�g�E���B������j
�Â��̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.minken1975.com/kouza_exhibition...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

2018�N7��7���i�y�j15:00�`
���F�Q�[�e�E�C���X�e�B�g�D�[�g�E���B������
���ꖳ���@�\���s�v
��1���F�V�����y��̒a��
�W�����E���������i��ȉƁj�A�O�����O�i��ȉƁj
�×��A�l�X�Ȋy�킪�l�X�ȕ����ɐ��܂�Ă��܂����B�葫�Ȃlj�X���g�̐g�̂Ɏn�܂�A�ΓJ��|��y����o�āA�e���ɓ`���nj��Ŋy��܂ŁB�ߔN�ł͓d�C�y���d�q�y�����������A���b�N��e�N�m�ȂǐV�������y�W�������̐����Ɉ���Ă��܂��B�����A��ʂ�ʐM�̔��W�ƂƂ��Ɂu�ٕ����̔����v���������A���镶���ɌŗL�̊y���t�@���A�L�����L�����P�[�X�������Ă��Ă��܂��B�O���[�o���[�[�V������IT�̎���ɂ͂ǂ̂悤�Ȋy��Ɖ��y�����܂�A�Љ�ɂǂ�ȕω��������炷�̂��B���Ƃ̍�ȉƂ���荇���܂��B
��2���F�h�L�������^���[�����̗�
�n���X�����F���i�[�E�N���[�W���K�[�i���o�Ɓj�A���M�[�l�E�h�D�[���i�f��ēA��Ɓj�A���R���i���o�Ɓj
1960�N�ォ��70�N��ɂ����āA�e����\�͂��������������^�����������B�Љ�ɐ[�����Ղ��c���ƂƂ��Ƀ��[���b�p������傫���ϊv���܂����B�����̌|�p�Ƃ����̎��ɊS�������A�h�C�c�ł͓����̎����ɍނ�������f��≉�������������Ă��܂��B���{�ł����ẮA�w���^���Ȃǂ����Ƃ����i�����삳��܂������A�ŋ߂ł͂��܂茩���Ȃ��͗l�ł��B���j�A�����A�W���I�L���Ȃǂ��e�[�}�Ƃ���|�p�\���̖����Ƃ́H �V���ȁu�����̋G�߁v�ɁA�h�L�������^���[�����ɐ[���ւ��n��҂R�l���ӌ������킵�܂��B
����N�Ɓi�i��E�\���j
�i2018/7/5�j
�������y��w�������y������2018�N�x���J�u��No.2�u���w��ȉƂ̐��E�F���c�O���璆�R�W���܂Łv�i2018�N7��18���i���j�A�������y��w�j
�u���̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.minken1975.com/kouza_exhibition...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
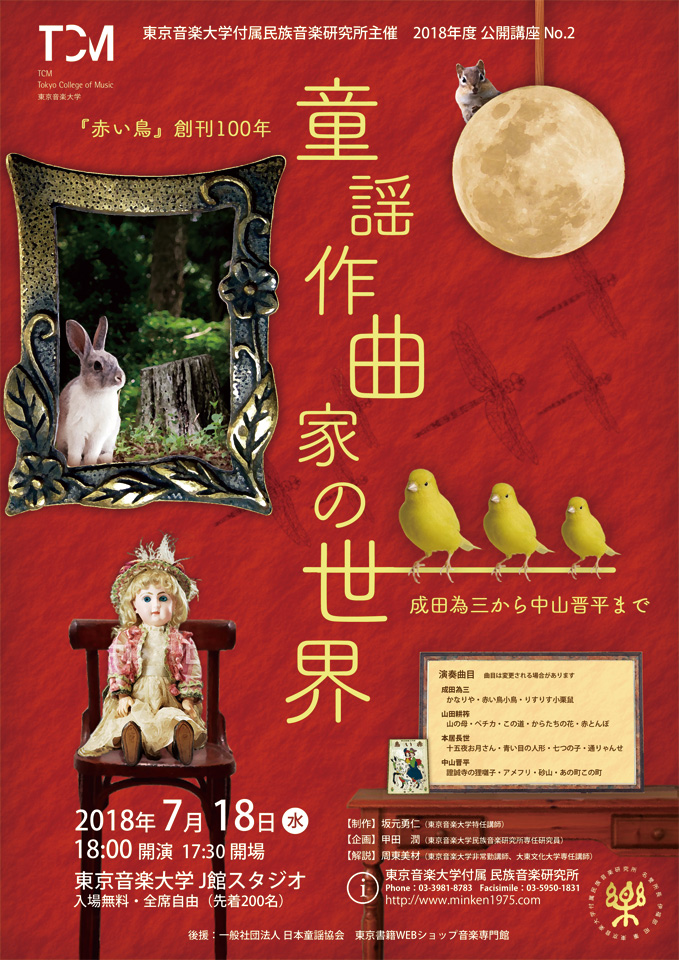
�����F2018�N7��18���i���j
�ꏊ�F�������y��wJ�كX�^�W�I
���ꗿ�F���ꖳ��
�\�����݁F�\��s�v�B�����撅���̂�����ƂȂ�܂��B
����F200��
�u�����e�F���w���̊y�ȁs���Ȃ��t����Ȃ��w�Ԃ����x���w�̑b��z�������c�O�B���|�I�ȋZ�ʂőO�q�I�Ȍ|�p���y�Ǝq�ǂ��̗̉w�Ƃ̗Z����}�����R�c�k⩁B�×��̓��{���y�̓`���ɐ[���w��ŐV���ȉ��y�̋��n���J���{�������B�����āA�e���݂₷�������f�B�[�ň��|�I�Ȑl�C��������������R�W���B���w��100�N�̗��j�̂Ȃ��ł��A����4�l�̌��͂Ƃ�킯�ٍʂ�����Ă��܂��B���w�̍�ȂɎ��g�݂Ȃ���A�ނ�͂ǂ̂悤�ɂ��̎��͂����A���ꂼ��̐����������f�B�A���ƑΛ����Ă������̂ł��傤���B����̃R���T�[�g�ł́A�ނ�̍�Ȗ@�̓������킩��₷��������Ȃ���A���ꂼ��̌��̈Ⴂ�������Ղ�Ɩ�����Ă����܂��B
�i2018/7/4�j
���w����� ����30�N�x��2����i2018�N7��14���i�y�j�A�c��`�m��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F7��14���i�y�j14��30���`17��00��
�ꏊ�F�c��`�m��w�O�c�L�����p�X ��Z��4�K454�ԋ���
�@�����ē��Fhttps://www.keio.ac.jp/ja/maps/mita.html
�@��Z�ɂ́u�L�����p�X�}�b�v�v���A��������Ă�����(6)�̌����ł��B
�q�������\�r
�j�R���E�v�b�T���́u���Ƒ��v
�\�\1650�N�O��̃t�����X�ł̃v�b�T����e����|����Ƃ��ā\�\
�]���T�q�i�c��`�m��w�j
�i��F�ؑ��O�Y�i���{��w�j
�A�[�����g�̎����_�Ɓq���̎��w�r�͘a���ł��邩
�\�\�u�����I���v�̗ތ^�_�̔ᔻ�I�č\���\�\
�N��ꐬ�i���{���q��w�j
�i��F���ѐM�V�i����c��w�j
�i2018/7/3�j
�\�ە����_�w���13����i2018�N7��7���i�y�j�E8���i���j�A�_�ˑ�w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.repre.org/conventions/13/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��7���i�y�j�E7��8���i���j
�ꏊ�F�_�ˑ�w�Z�b���2�L�����p�X
�@�i�����_�w���L�����p�X�^��}�_�ː��Z�b�w���k��15�����x�j
���F7���͖����A8���͔����̂�1,000�~
�@�i���O�\��s�v�j
��7��7���i�y�j
13:30-16:30�@�V���|�W�E���@�ꏊ�F���L�O�w�p�𗬉��2�K���c��
�V���|�W�E���u�t�@�b�V������]�͉\���H�v
�b�c�T�j�i���s���ؑ�w�j�A���F�T�q�i�_�ˑ�w�j�A�q����āi���s�����ߑ���p�فj�A�O�Y�N�Ɓi�R�w�@��w�j�@�i��F��ъx�j�i����w�j
17:00-18:30 �p�t�H�[�}���X�@�ꏊ�F�_�ˑ�w�S�N�L�O�فi�Z�b�z�[���j
�wRADIO AM�_��69���Ԑk�Е̋L�^�x���[�f�B���O�㉉
���E�\���F�x�c���A���o�F�ɓ���A�����F�������I
���ÁF����w�����w�p�����فu�L���̌���vTELESOPHIA�v���W�F�N�g�A���́F�ǎ��w�@��w�Љ�w��
��7��8���i���j
10:00-12:00 �������\�i�ߑO�j�@�ꏊ�F�l���w������B��
�p�l��1�@�ᔻ�I���s�w�h�̋Z�p�_�������̌���I�܈ӂƉ\���iB135�j
�E�|��̐��Ǝ������ˍ⏁�́u�Z�p�I���_�v�^���쑾�i������p�H�|��w�j
�E�Z�p�Ɛg�̂̓��ƊO�����ؑ��f�ʂ��ēǂ���^���R���Y�i�Ռ��w�����q��w�j
�E����-�@�B�̗��j���ݘ_���������Б��Y�N�w�̐����^�ҏ��͋v�i���l������w�j
�R�����e�[�^�[�F�w�_���Ɓi����w�j�@�i��F���R���Y�i�Ռ��w�����q��w�j
���p�l���@�wRADIO AM�_��69���Ԑk�Е̋L�^�x���[�f�B���O�㉉���߂����āiB132�j
�Γc�\�q�i�_�ˑ�w�j�A��ÏG���i�����w�j�A�]�����o�i������w�j�A�x�c���i�㉉���^�ǎ��w�@��w�j�A�ɓ���i�㉉���o�j�@�i��F��ъx�j�i����w�j
12:00-12:45 ����i����̂݁j�@�ꏊ�F�l���w������B��B331
14:00-16:00 �������\�i�ߌ�P�j�@�ꏊ�F�l���w������B��
�p�l��2�@���W�I�Ƃ������ꄟ�����W�I�S�����ɂ�������̏����iB231�j
�E�u��l�̒P���v�̌��Ƃ������������I�[�\���E�E�F���Y�̃��W�I�E�h���}�ɂ��ā^�������Ɓi����c��w�j
�E�~���[�W�J���̌���@�ƃ��W�I�̊W�����w�t�@���E�E�B�Y�E�U�E���������[�Y�x�ɂ�������Ɖ̂̋@�\���́^�ҍ��ێq�i����c��w�j
�E���W�I�����̉\���������C�u���ƕ��ꐢ�E�̍\�z���߂����ā^�m��c��G�i����c��w�j
�R�����e�[�^�[�F�쓇���i���u�Б�w�j�@�i��F�m��c��G�i����c��w�j
�p�l��3�@���z�̃��f�B�E���ƃt���[���iB132�j
�E���E���߁A���E�\�z�Ƃ��Ă̌��z�̐}�I�\������J. -N. -L.�f�������w��r���z�}�W�x�𒆐S�Ɂ^���V���q�i�a�m���q��w�j
�E�������E���݂�E�ό`�������z�Ɠ��䔎���̌��z�h���[�C���O�^�˓c���i����H�Ƒ�w�j
�E�g�����镽�ʐ��E�g�����X���f�B�A�����R���X�^���g�̃j���[�o�r�����^���R�a�i������w�^�f���t�g�H�ȑ�w�j
�R�����e�[�^�[�F�㓡���i�㓡�����z�v�������j�@�i��F�K�c�����i������w�j
�p�l��4�@�f���ɂ������Ԅ����ӎ����ꂸ���R�����ɂ��������̂Ƃ�����Ԃ́A���̐��N���߂����āiB135�j
�E�L�����N�^�[�̂���ꏊ�������y�Ƌ�Ԃɂ��ā^���c�ˈ�i�鐼��w�t���鐼���w�����w�Z�j
�E�����F�Ƃ��Č����鉜�s���ɂ��ā^�Y����i�ꋴ��w�j
�E�����^�z���̃��[�����g�����w�}�������̗z���x�ɂ����鎚���ƃz���C�g�A�E�g�̌W���𒆐S�Ɂ^���R�c�����i�ꋴ��w�j
�R�����e�[�^�[�F�����C�o�i�ꋴ��w�j�@�i��F�����m�q�i�ꋴ��w�j
16:30-18:30 �������\�i�ߌ�Q�j�@�ꏊ�F�l���w������B��
�p�l��5�@20���I���m�̐l�`�E�͑��E���g�������_�j�Y���|�p�ɂ�����q�ё��r�̏����iB135�j
�E�I�X�J�[�E�R�R�V���J�̃A���}�E�}�[���[�l�`�����ё���Ƃ̊֘A����̈�l�@�^�Ð�^�G�i���s���`�|�p��w�j
�E���S�Ȍ������o���G�w�ؒ���̉��q�x�ɂ����镪�g�Ƃ��Ắu�l�`�v�̖����^���{���q�i������w�j
�E�N���\�E�X�L�[�ɂ����郍�x���g���^�{�c�i���i������w�j
�R�����e�[�^�[�F����h�i������w�j�@�i��F�I�]�G���i���s���ؑ�w�j
���]�p�l���@���c����w�n�C�f�K�[�Ɛ������̖��x�iB132�j
�A�����i����w�j�A����^���i�Q�n�������q��w�j�A���c����i����c��w�j�@�i��F��t���i�����ّ�w�j
�i2018/7/2�j
���m���y�w����{�x����281���ጤ����i2018�N7��14���i�y�j�A���s�s���|�p��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/nishi/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��14���i�y�j14:00�`17:00
�ꏊ�F���s�s���|�p��w�V������7�K����1
���e�F�u���A�������\
�q�u���r
���ρu�����嗤�������y�����̗��j�ƌ���v
�i�������y�w�@�����A�����j
�q�������\�r
���c�����u����T���w�����̐��̋Z�F���̐g�̐��x��ǂށv
���S���F�����b���q
�i2018/6/28�j
�k��t�B���n�[���j�[�nj��y�c��7�������t��i2018�N7��1���i���j�A�V���s�k�敶����فj
�Â��̏��ł��B
���{�R�[�X�����A���J�삪�o�����܂��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.kita-phil.net
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N7��1���i���j�@�J��13:30�A�J��14:00
���F�k�敶����كz�[���i�V���s�k�擌�h��1-1-5�j
�����F��l1,000�~�i����1,200�~�j�A���w���ȉ�500�~�i����600�~�j
�@���S�Ȏ��R
�q���t�ȁr
�EE.�t���p�[�f�B���N �̌��u�w���[���ƃO���[�e���v���O�t��
�EF.�V���[�x���g �����ȑ�7��D759�u�������v
�EA.�h���H���U�[�N �`�F�����t�� ��i104
�w���F���J�쐳�K�@�\���X�g�F�Ж���
���₢���킹�F�k��t�B���n�[���j�[�nj��y�c
�@http://www.kita-phil.net�@Mail:kitaphil2017[at]excite.co.jp
�i2018/6/27�j
���{���ȓ��e�w���5�����i2018�N6��30���i�y�j�E7��1���i���j�A���R���w����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.jsssce.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N6��30���i�y�j�E7��1���i���j
���F���R���w����w����w��
6��30���i�y�j
�E������ 11:00�`12:00�i����w��D-314�j
�E��t 12:00�`12:30
�E�J��s�� 12:30�`12:50�i����w��B-307�j
�E�V���|�W�E�� 12:50�`17:50�i����w��B-307�j
�u���ȓ��e�w�̋��ʊ�Ղ����߂āF��Ղ���e���ȓ��e�\���̋�̉��ցv
�P�D��|���� 12:50�`13:00
�Q�D��u�� 13:00�`15:50�i170���j
(1)���J�_�V�i�����Ȋw�ȏ�����������Nj��E���ۋ����Ƌ���掺���j
(2)���F���F�i�_�ސ��w�j
�u�J���L�������_���猩�������{�����ȓ��e�w�����̎��_�v
(3)�p���d���i���{�̈��w�j
�u���ȓ��e�w�̋��ʊ�Ղ����߂āF���ȋ���w�̌��n����v�i50���F���^�܁j
�R�D�V���|�W�X�g��� 15:50�`17:00
�i��F�ɓ��m��i���R���w����w�����j
�v���W�F�N�g�F�����{���ɂ����鋳�ȓ��e�w�����\�u�e�ȋ��ȓ��e�\���v�Ȗڂ̊J���\�ۑ�ƊJ���̕��@:�����F�M�i�勳���w���_�����j
������
(1)����E�Љ�n�A�Љ�ȁF�����r�s�i��z�����w�����j
(2)���R�n�A���w�ȁF���� ���i�勳���w�����j
(3)�|�p�n�A���y�ȁF������Y�i�M�B��w����w�������j
(4)�����E���N�n�A�̈�ȁF�r�؏G�v�i������w���_�����j
�S�D�p�l�����_ 17�F00�`17�F50
�i��F�ɓ��m��i���R���w����w�����j�@�p�l���X�g�F���F���F�A�p���d���A�����r�s�A���� ���A������Y�A�r�؏G�v�@�w�蓢�_�ҁF����O�v�i������w���w���j
7��1���i���j
�E��t 9:00�`
�E�������\ 9:20�`11:20 �|�X�^�[���\�i����w��D-313�j
�E���� 11:30�`12:00 (����w��B-307�j
�E�ۑ茤�� 13:00�`16:00 (����w��B-307)
�e�[�}�u�v���W�F�N�g�����̕Ɠ��c�F�����{���ɂ����鋳�ȓ��e�w�����\�u�e���ȓ��e�\���v�Ȗڂ̊J���\�v
��|�����F�����F�M�i�勳���w���_�����j
�i��F����O�v�i������w���w���j�����F�M�i�勳���w���_�����j
���ȁF���g�Ո��i�勳���w�����j
�����p�ȁF�V��m���i������w����w�������j
������ȁF���c�i���i������w����w�������j
���p��ȁF���{�V��i�ǎ��w�@��w���ۋ��{�w�������j�A
���ƒ�ȁF���c�����i�L����w���_�����j
���Z�p�ȁF�e�n�́i�勳���w�����j�i�����̂݁j
���S���Ȃ���Ղ������ȓ��e�̌����F�Q��K�F�i���R���w����w�����j
���������\�̎Љ�ȁA���w�ȁA���y�ȁA�̈�Ȃ͓��c�ɂ����Đ����Q��
�i2018/6/26�j
��4��n����w����t�H�[�����u����ڑ��̎��_����݂��O���[�o�����̗���Ƒ�w����v�i2018�N7��14���i�y�j�A�n����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.soka.ac.jp/fd/events_fd/2018/03/2779/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�J�����F2018�N7��14��(�y) 13:00�`17:10�i12:30 ��t�J�n�j
���F�n����w�i�����s�����q�s�O�ؒ�1-236�jS201����
�Q����F����
�q�v���O�����r
�E13:00�`13:10�@�J������@�n��P�v�w��
�E13:10�`14:00�@��u���i�P�j
�u�O���[�o��������Љ�ɂ�����R�~���j�P�[�V�����v
���c�I���U���i����ƁA���o�ƁA����wCO�f�U�C���Z���^�[���C�����j
�E14:10�`15:00�@��u���i�Q�j
�u���ۃo�J�����A���炪��Ă�n���s���v
�唗�O�a���i�������w����w�������AChiyoda International School Tokyo, Head of School�j
�E15:10�`16:00�@�{�w�̎��g�ݏЉ�
���H��(1)�u���n�����Z�̃X�[�p�[�O���[�o���n�C�X�N�[���̎�g�v
���H��(2)�u�n����w�̃X�[�p�[�O���[�o����w�n���x�����Ƃ̎�g�v
�E16:10�`17:00�@�V���|�W�E��
�E17:00�`17:10�@������@�c���������w��
���O�\���F2018�N7��11��(��)�܂łɁA�����O�E�������E���A��������L���̏�AFAX�܂��͓d�q���[���ɂĂ��\�����݂��������B (1)Fax042-691-6941 (2)E-mail�Fseedfd[at]soka.ac.jp
���₢���킹��F�n����w�����w�K�x���I�t�B�X�w�K�x����
�@TEL042-691-7009�@FAX042-691-6941
�i2018/6/25�j
�y���w���26����i7��8���i���j�A�����\�y���j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www1.odn.ne.jp/~gakugeki/taikai.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��8���i���j10:30�`17:20�i�\��j
���F�����\�y�� ��u�`���i�����s�a�J���ʃ��J4-18-1�j
�@JR�������u��ʃ��J�v�E�n���S��]�ː��u�������Z��v���k��5��
�@JR�R����E�������u��X�v�E�n���S���s�S���u�k�Q���v���k��5��
��ꕔ�@�������\��i10:30�`11:50�j
�E�u��ߐ؎ڔ��̌����w�@�����ڔ��萔�����̖ژ^�x(1622)��ʂ��āv�������Â�
�E�u���S�́u�N���C�v�čl�v���K���Â�
��@����@�i12:50�`13:20�j
��O���@���J�u����q�y���ƕ��ƕ���r�i13:30�`17:20�j
�E��|�����@�E�c���q
�E��u���u�������w�Ƃ��ẴC�����������F�w�V���[�E�i�[���i�����j�x�Ɓw���ƕ���x�v������
�E���Ɖ��t�w�_�����Ɂx�w���Ŋ��x�w�ߐ{�^�s�x��蔲���@ �e���Y�i�E�c���މ���
�E�V���|�W�E���u�y���ƕ��ƕ���v�ɊC�F�[�i�\�y�j�A���c�^���i�ߐ������j�A������q�i�ߐ��M�y�j
�i2018/6/22�j
�@�@
���m���y�w����{�x����105���ጤ����i2018�N7��7���i�y�j�A�������y��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/higashi/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��7��(�y)�@14:00�`16:30
�ꏊ�F�������y��w A��200�����i�A�N�Z�X�j
���e�F�������\
�P�D��b�ʼn̂��Ƃ�������
�\�|��Ƃ��Ă̎�b�̂Ɋւ��郁�^��p�_�I���_�\
�@�y�c�܂ǂ��i������w��w�@�j
�Q�D�t�����c�E�G�b�P���g�̒����A�}�[���G�̎��`����ǂݎ������
�@�S�`�F�t�X�L�C�w���}���i������w�j
�i��F���R�����q�i����������w���u�t�j
�i2018/6/21�j
��w���y����w��k�C���n�敽��30�N�x������i2018�N7��7���i�y�j�A�Ƃ����v���U�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.nacome.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N7��7���i�y�j10:45�`16:45
���F�Ƃ����v���U 2�K�����o��
�@�i�k�C���эL�s��4���13����1�j
�E10:00�@��t
�E10:45�`11:45�@����
�E12:15�@�������t
�E12:45�`12:50�@�J��̈��A
�E12:50�`14:20�@�u��
�u�q�ǂ��Ƌ��t������ׂ����F�эL�Ђ܂��c�t���̊��Â���v
�u�t�F�����݂䂫���i�эL�Ђ܂��c�t�������j
�E14:30�`15:30�@���[�N�V���b�v
�u�\�̖��́F���E�R�g�o�E�g�̂ɂ�鉹�y���v
�u�t�F�����ѐD���i�k�C�������w���H�Z�y�����j
�E15:40�`16:40�@�������\�i�����j
1.�F��ρi�k�C�������w����Z�j�A�R���F�t�i�k�C�������w��w�@�j�u�����{���ے��̎��Ɓw���w�Z���y�Ȏw���@�x�ɂ������u�҂̊S�E�ӗ~�Ɋ� �����l�@�F��R���̒ጸ�ƈӗ~�̌�����N�����H�v�v
2.�ؑ��M�I�i�k�C�������w����Z�j�u�e���̂��̊w�K�ɍۂ��Ẵ\���t�F�[�W���I���ʁv
3.�ጴ�^�R�q�i�����w�����w�Z�j�u�����ۈ玞�ɂ����鉹�y����̎��݁F�ۈ�҂�ی�҂̈ӌ������ƂɁv
4.����L���A�V�c�x�q�i�k�đ�w�j�A������x�q�i�k�đ�w�j�u�w���̊w�K���ɍ��킹���A�s�A�m�w�K�̂��߂̓���쐬�ƌ��ʂ̌��v
�E16:40�`16:45�@��̈��A
�E18:00�`20:00�@��������
�Q����F���3,000�~�i�����̕������Q�����������܂��j
�@����������4,500�~
�i2018/6/20�j
�O�c�N�w��u����u�����ƃR�~���j�e�B�v�i2018�N7��3���i�j�A�c���`�m��w�O�c�L�����p�X�j
�u����̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
mitatetsu.keio.ac.jp/conference.html...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��3���i�j13:00�`14:30
���F�c��`�m��w�O�c�L�����p�X ��������223��
�u�t�F�֍��~�q�i�o�D�E���o�ESPAC�É�������|�p�Z���^�[�j
��ÁF�c��ABR�A�O�c�N�w��
�֍��~�q�����SPAC�É�������|�p�Z���^�[�����̔o�D�ł���ASPAC�̕���߂����ŁA���o�Ƃł�����܂��B���c �@���T������ɁB�����t�ƈ�l�ŋ���g�ݍ��킹���u���y����v�̊�����W�J���Ă��܂��B����͉����̂��͂��R�~���j�e�B�Ƃ̂������ł��b���������܂��B���p�����A���c�̃A�E�g���[�`�A���邢�̓R�~���j�e�B�����A�G�X�m�V�A�^�[�Ƃ��������݂����钆�ŁA�֍�����̎��g�݂Ȃǂ��Љ�Ă��������A�Q���҂Ƌ��ɁA�����I�\���̉\���ɂ��čl���܂��B
�i2018/6/19�j
���j���������w�����Ȍ��J�u���u�����́u�ߑ�v���߂���A��O�̂��ƁF���{�̎��Ⴉ��v�i2018�N7��4���i���j�A�_�ސ��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.kanagawa-u.ac.jp/event/details...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N7��4��(��)�@15�F00�`17�F00
���F�_�ސ��w���l�L�����p�X 3����406�u��
�u�t�F���c���� �� �i���{���q��w�l�ԎЉ�w�������j
���Q�������E���O�\���s�v�B�ǂȂ��ł����Q�����������܂�
����́A�l���Ȋw�Ƃ��Ă̗��j�w�̉\�������������ł͂Ȃ��A�g���h��g�L���h�����Ώۂɂ��ĐV���ȗ̈���J��Ă������c�搶�����}�����܂��B�������ł��鉹�����炢���Ȃ���j�����a���o�����ł��傤���B
��ÁF�_�ސ��w���j���������w������
���ÁF�_�ސ��w���{�햯����������
���₢���킹�F�_�ސ��w ���쌤����
�@TEL045-481-5661�i��j
�i2018/6/18�j
���{�J���L�������w���29����i2018�N6��30���i�y�j�E7��1���i���j�A�k�C�������w����Z�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
jscs.b.la9.jp/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��30���i�y�j�E7��1���i���j
���F�k�C�������w����Z
�Q����F�����3,000�~�A�w�����2,000�~�A�Վ����3,500�~
�q�v���O�����r
�E��1���i6��30���j
9:30�`�@��t�i�k�C�������w����ZP�����ցj
10:00�`12:00�@�ۑ茤��
�@I �J���L�������̕]���ƃ}�l�W�����g���߂����āF�u���ʌ��v�𒆐S��
�@II �w�Z����Ƃ̋����Ɋ�Â��J���L�������������ǂ��i�߂邩
13:00�`15:15�@���R�������\I
15:30�`18:00�@���J�V���|�W�E��
�@�u�q�ǂ��̎�̓I�Ȋw�т��x����w�Z�Â���v
�E��2���i7��1���j
9:30�`�@��t�i�k�C�������w����ZP�����ցj
10:00�`12:15�@���R�������\II
13:30�`15:30�@�ۑ茤��
�@III �u�����E�l�����v���ǂ������邩�F
�@�@�����E�\�͂̈琬�Ƌ��Ȃ̖{���̒Nj��Ƃ��Ȃ�
�@IV ���܉��߂đ�������`�̋�����l����
�i2018/6/15�j
���{�}���K�w���18����i2018�N6��23���i�y�j�E24���i���j�A���s���ؑ�w�E���s���ۃ}���K�~���[�W�A���j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.jsscc.net/convention/18
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
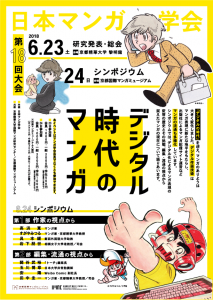
�����F2018�N6��23���i�y�j�E24���i���j
�ꏊ�F���s���ؑ�w��q�L�����p�X�i23���j�A
�@���s���ۃ}���K�~���[�W�A���i24���j
���Q����F���1,000�~/1���A���2,000�~/1���A
�@�w���i�v�w���ؒA��w�w�����ȉ��j1����500�~�E2����1,000�~
���{�C�x���g�̓}���K�w�����łȂ��Ƃ��Q���ł��܂��i���O�\���s�v�j
��2���ڂ̓}���K�~���[�W�A�����ꗿ���ʓr�K�v�B
�q�����r
�E6��23���i�y�j�F����ɂ�錤�����\�^����^���e��
12:15�`12:45�@�Q����t
12:45�@�J��錾
13:00�`16:55�@�������\�^���E���h�e�[�u��
17:15�`18:30�@����
19:00�`20:30�@���e��
�E6��24���i���j�F�V���|�W�E���u�f�W�^������̃}���K�v
10:00�`10:30�@�Q����t
10:30�`12:30�@��1���u��Ƃ̎��_����v
14:00�`16:00�@��2���u�ҏW�E���ʂ̎��_����v
16:00�@�
�q�������\�r
�E��1���F�t����L-101
[13:00-13:30]�u�l���l�Ԃ�����g�ɂ��鎞�\�\�l���l�ԃL�����N�^�[�̐g�̑����猩��}���K�ɂ�����l�H���̋[�l���v���ߋ��m���É���w��w�@�l���w�����ȁn
[13:35-14:05]�u�u�^���C�x���gSF�v�Ƃ��Ẳi�䍋��i�\�\�u�n�����`�w���v�����1970�N�㔼�܂ł́w�T�����N�}�K�W���x�A�ڍ�i�̌����v�X���B�m����������w�l���w���n
[14:10-14:40]�u�}���K�w�i�ɂ�����u���̃m�C�Y�v�ƃ��A���e�B�\�\��삢�ɂ���i�ɂ�����d���Ɠd����\�������w�i�̌��ʂɂ��āv�X�R�����m��ʁn
[14:45-15:15]�u�C�O�}���K�|��ɂ�����@���e�[�}�̈����\�\�������w�������ɂ�����x��ΏۂƂ����|���r�v��˖G�m��t��w��w�@�l�������w�{�n
[15:20-15:50]�u���{�}���K�ɂ�����`�n�c�镺�n�ڊZ�b�f�U�C���̓`�d�v�������Õv�mNPO�O���u�t�H�[�����n
�E��2���F�t����L-102
[13:00-13:30]�u�}���K�v��\�͑���e�X�g�V�X�e���̊J���v�|���r�F�m����������w����w���^����e�X�g�����Z���^�[�n
[13:35-14:05]�u�������݂��}���K�̓ǂ݂̌l���\�\�u���o�^�E����^�v�F�m�X�^�C�����_�Ɋ�Â���l�@�v�a�c�T��m���k��w��w�@���Ȋw�����ȁn�^�O�Y�m�u�m���D��w���㕶���w���n�^�E�r��m���k��w��w�@���Ȋw�����ȁn
[14:10-14:40]�u�܂ƋL�^�v�@���f�q�m���s�A�[�J�C�u�Y�n
�E��3���F�t����L-103
[13:00-13:30]�u�g�������낢�h�w�ׂ�}���K���ނ̍쐬�\�\�����狳�ނ̍쐬��ʂ��āv���c���k�m������w��w�@�V�̈�n���Ȋw�����ȁn
[13:35-14:05]�u�؍��ɂ�����q�w�K�}���K�r���\�\����ƒ�ɂ�����w�K�}���K�́q�ꏊ�r����|����Ɂv�R����b�m���s�Y�Ƒ�w����Љ�w���n
[14:10-14:40]�u��w�ɂ�����}���K�ɂ�闯�w���Ɠ��{�l�w���̋��C���Ɓ\�\�������𗬉Ȗځu�����Ƃ��Ă̓��{�}���K�v�̎��H�ƕ]���v���їR�q�m�k�C����w���ۘA�g�@�\���ۋ��猤���Z���^�[�n
[14:45-15:15]�u���{�����ɂ�����S�R�}�}���K�̗��p�\�\�Z�����w����ΏۂƂ�����H����v�r�V���q�m����w�@��w���w���ʉȁn
�q���E���h�e�[�u���r
�E��1���F�t����L-101
[15:55-16:55]�u�J�[�g�D�[���\�ۂɌ���푈�ƃi�V���i���Y���̍�p�\�\�펞���̓��{�̖���̎�̎҂͉���`�������v���i���h�E�X�`�����[�g�m�i��A�哌������w�Љ�w���n�A����ˉ���m���s���`�|�p��w�����N�w�������n�A���c�g���mFECO:���E����ƘA���n�m�i��A��������w]
�E��2���F�t����L-102
[14:45-15:50]�u�}���K�ƈ�Á\�\�O���t�B�b�N�E���f�B�X���̓����ƃ}���K�����̉��p�\���v���_�P���Y�m�i��A��C��w���w���n�A�����ām���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn�A���c�K�q�m���茒�N������w�l�Ԕ��B�w���n�A�����_���m�����w�|��w����w���n�A�������u�m�f�B�X�J�b�T���g�A��Ðl���o�Ŏ�SCICUS��\�n
[15:55-16�F55]�u�����}���K�����̔�r�v���╖�m�i��A���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn�A�����q�m���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn�A���n���m���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn�A�����ʁm���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn�A�C�G�m���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn
�E��3���F�t����L-103
[15:55-16�F55]�u�j���[�E�F�[�u�v�����̐����Ƃ��̏����\�\�u����m�F�R���N�V�����v�Ɋւ��钲�������ƂɁv�G�ꒉ�G�m�i��^���\�A���s���ؑ�w���ۃ}���K�����Z���^�[�n�A�ɓ��V�m���s���ؑ�w���ۃ}���K�����Z���^�[�n�A�������ׁm���s��w��w�@�l�ԁE���w�����ȁn
�q�|�X�^�[���\�r 6��24���i���j12:30�`14:00
���F���s���ۃ}���K�~���[�W�A��1�K�@���ړI�f���z�[��
�u���{�ꋳ�t�������p���Ďw������ۂɕ�����s���v��c�Čh�m���a���{��w�@�n
�u���v���͂��猩�������E���N�}���K�v�f�̑���_�\�\�����Ə��N�}���K�G���̓��v���͂��番���邱�ƁE����Ȃ����ƁvMia LEWIS (�~�A�E���C�X)�m�X�^���t�H�[�h��w��w�@���{���w�����ȁn
�u���������̍�i���特�g�̏����ɂ��Ă̍l�@�v���╖�m���s���ؑ�w��w�@�}���K�����ȁn
�q�V���|�W�E�� �u�f�W�^������̃}���K�v�r
[10:30-12:30]��1���u��Ƃ̎��_����v
���l���m�}���K�Ɓn�A������݂�m�}���K�Ɓ^���s���ؑ�w�}���K�w�������n�A��{�Q�m���O�����w�O����w�������n�A�≺�����m���͏��q��w�w�|�w���y�����n�^�i��
[14:00-16:00]��2���u�ҏW�E���ʂ̎��_����v
�֒J���T�m�w�g�[�`�x�ҏW���n�A�ʐ씎�́m���{��w���u�t�n�A���z�mWeibo Comic ���В��n�A�c���\��m���s���ؑ�w�}���K�w�������n�^�i��
�i2018/6/14�j
�u�z���́v������i�����l���Ȋw�����Z���^�[��������u����Љ�ɂ�����q�z���́r�̑����I�����v�j2018�N�x��2����i2018�N6��22���i���j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/flas...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��22�� 18:30�`19:45
���F����c��w�O�R�L�����p�X
�@33����16�K��10��c��
�b��F�u����w�Z�����ɋ��߂���q�z���́r�F����͐l���n�w���ŗ{���\���H�v�������i����c��w�����j
�����̌�����͌��J�ōs���܂��̂ŁA�ǂȂ��ɂ����Q�����������܂��B
�A����F��q�đP�V�������imikoyuki[at]waseda.jp�j
�i2018/6/13�j
�S����w���y����w��֓��n�敽��30�N�x��1����i2018�N6��16���i�y�j�A���}�n������Ёj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.nacome.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N6��16���i�y�j13:00�`16:30
���F���}�n������Ёi�������ցj1F�v���[���e�[�V�������[��
�@�i�s�c�n���S�� ��x���wA3�o���k��1���j
�����F
�E12:30�`13:00�@��t
�E13:00�`13:40�@����
�E13:40�`15:10�@�u��
�E15:30�`16:30�@�������\
�E17:00�`19:00�@��������
�u���F
�u���E�̉��y���炩��䂪���̉��y������l����`���[���b�p�A�A�����J�A�A�W�A�̊w�Z�����ʂ��ā`�v���쏹�����i���l������w����w�������j
�������\�F
(1)�u�������y�Ƌ���@�ɂ�������H�I�w���͂�L���鋳�t���琬������Ǝ��H�ɂ��Ă̌����v���Ǝj�l�i���{�̈��w�j
(2)�u�R�_�[�C�E�A�v���[�`�ɂ��\���t�F�[�W���̎��H�F�ۈ�m�{���^�c�t���E���w�Z�����{���̎��Ƃ���v���g�֎q�i�쑺�w�����q��w�j
(3)�u�ۈ���e�q�\���r�̎��Ɠ��e���l����F�ĉے��F��ŋ��߂�����@��̊��p�Ɨc���̕]���ɂ��āv��{�I�q�i�\�����w�����q��w�j
������Q����F���1,000�~�A��ʎQ��1,500�~
����������F5,000�~
�i���F�f�C�i�C�g �����s�`��O�c3-10-1�A�[�o���l�b�g�O�c�r��1F�j
�i2018/6/12�j
�`���|�\�㉉��u���n�l�`�ŋ��㉉��v�i2018�N7��1���i���j�A�V���������j�����فj
�Â��̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://nbz.or.jp/?p=16571
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�������j�����قł́A7��1���i���j�ɁA�u���n�l�`�ŋ��㉉��v���J�Â��܂��B���d�v���`�����������Ɏw�肳��Ă���u���n�̐l�`�ŋ��v�̏㉉��ł��B�ߑO�̕��ł́w���Ə��쓇�x�A�ߌ�̕��ł́w�����G�X�q�܁x���㉉���܂��B�ߌ�̕��̖`���ł́A�����ւj�[�N�ȁu�̂�ܐl�`�v���㉉���܂��B���Ђ��̋@��Ɍ������j�����قɂ��z�����������B

�����F2018�N7��1���i���j
���ԁF�ߑO�̕�11:00�`12:30�@�ߌ�̕�13:30�`15:00
���F�V���������j������ �u��
�o���F���n �^����
�����F�����A����e��150���i�v�\���j
�\�����ݕ��@�F�d�b�A�͂����A�t�@�b�N�X�܂��̓��[���ʼn��L�܂ł��\�����݂��������B�u�����A�����O�A�Z���A�d�b�ԍ��L���Ă��������B
�\�����ݐ�F�V���������j�����ف@�o�c����
��940-2035�@�����s�����P���ڎ�������2247�ԂQ
TEL0258-47-6135�@FAX0258-47-6136
E-mail:koryu[at]nbz.or.jp
�i2018/6/11�j
�����|�p�w���149����i2018�N6��16���i�y�j�A���H���q��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://ethno-arts.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��16���i�y�j 14:00�`16:30
�ꏊ�F���H���q��w �a�J�L�����p�X�n��120���N�L�O��
��ʁFJR�E�������g���E���}�u�a�J�v�w���k��10���A�������g��������^��������^���c���u�\�Q���v�w���k��12��
���n��120���N�L�O�ٌ��։E��̎�q�������ŁA�������������L���̏�A���\�������ɂȂ��āA�蓮�����炨���肭�������B
�������\�F�e�[�}�u�����̖L�����v
�P�j�_�����݁i���H���q��w��w�@�j�u�����ܗt�́u�\���v�F�G��Ƒ���̊W�v
�Q�j��������i�u�b�N�f�U�C�i�[�j�u�u�b�N�f�U�C���Ƃ����d���v
�S�������F�Z�l�����T
�A����F�����Y�p�w����������i�����̐����q��w�E�i���b�O�������j
E-mail: minzoku.tokyo[at]gmail.com
�i2018/6/8�j
��r�v�z�w���45����i2018�N6��16���i�y�j�E17���i���j�A���{��w�����w���j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jacp.org/conv/conv01/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��16���i�y�j�`17���i���j
���F���{��w�����w���L�����p�X �S���N�L�O��
�@��156-8550 �����s���c�J����㐅3-25-40
�q�v���O�����r
��1���F6��16���i�y�j
�E��t�@13:00�`
�E�l�������\�@13:30�`15:15
�E�p�l���f�B�X�J�b�V�����@15:30�`17:30
�E����@17:30�`18:00
��2���F6��17���i���j
�E��t�@9:00�`
�E�l�������\�@9:30�`11:15
�E��u���E�V���|�W�E���@12:30�`15:30
�q�l�������\ ��1���r
�E��1����i���ۉ�c��j
1. �ѓc�������i�����̐����q��w�j�u�j�[�`�F�Ǝ��R��`�Ƃ̋����F�a�ғN�Y�u�j�C�`�F�����v����|����Ƃ��āv
2. ���c�a�F�i�����n�������w�������j�u�ᔻ�I�ȃR�X���|���^�j�Y���F�a�ғN�Y�ƃA���t���[�g�E�V���b�c�v
3. E.�c�O���b�Q���i�n����w�j�u�q���Y�[���̎v�z���Q�[�e�̗։�ςƍ�i�ɗ^�����e���ɂ��āv
�E��2����i��c��2�j
1. ����C�i�����w�|��w�j�u�A�V���[�J���J���_�n���蕶�ɂ�����A�N���V�A�T�O�F�|���Ƃ��ẴM���V�A��������āv
2. ���ь�i���k��w�j�u���@�x�̖��|�_�ƕ����v�z�F�E�B���A���E�����X�Ƃ̔�r�Ɍ����āv
3. ���V����i���J��w�j�u����F��́u�P�����̙֑ɗ��v�ʼn���\�����悤�Ƃ������F�Z�t�B���g�Ƃ̔�r�v
�q�p�l���f�B�X�J�b�V�����r
�u�����w�̃t�����e�B�A�Ɣ�r�v�z�v
�E��R�^��i�M�B��w�j�u��r�v�z�Ƃ��Ă̕����F���_�v
�E�t�Ύ��i�ԉ���w�j�u����_�I�W�J�ȍ~�̓��A�W�A���������̎��݁v
�E���ؕ����m�i���ۓ��{���������Z���^�[�j�u���{�����Ɋւ���펯�ւ̒���v
�q�l�������\ ��2���r
�E��1����i���ۉ�c��j
1. ����M�F�i������w�j�u�����̘Z�c�d�\�ρF��s��^�Ƃ̔�r��ʂ��āv
2. ���c���H�i�ŋ���w�j�u�{���钷�̌���ςƋ�ɁE�B���v�z�v
3. �n�ӗ����i�吳��w�j�u�ΒÏƎ��̏��@�����_�ɂ������̐��̌����F�ʏ�N�l�Y�̋c�_�Ƃ̔�r��ʂ��āv
�E��2����i��c��2�j
1. �D�c�a���i����w�j�u��S�C���̐��̓N�w�Ɠc�ӌ��̎��̓N�w�v
2. �����O�Y�i���s��w�j�u���J�[���ɂ�����u�@���I�v���v�F���c�����Y�Ƃ̔�r����v
3. �����W�i���w�@��w�j�u�֍����Y�ɂ�����u���{�I�L���X�g���v�Ƃ��̎˒��F�쌴�ɂƂ̌����ƕ���𒆐S�Ɂv
�q��u���E�V���|�W�E���r
�u�g�̘_�F����ɂ������ґz�E�F��E�J���̈Ӌ`�����߂āv
�E�i��u���j�ؑ������i������w�j�u�C�s�Ɛg�́F�����̎v�z���肪����Ƃ��āv
�E�������q�i������w�j�u�g�̂̎��w�F�V���[�k�E���F�C����D.H.���[�����X�v
�E���c�G�s�i���{��w�j�u������s�h�̐g�̘_�ƑS�l�i�I�v�Ҙ_�v
�E�v�ۗ��i�i�R���w�@��w�j�u�ō_�w�ɂ�����S�g�_�I�ۑ�Ɣ�r�v�z�I�W�J�ɂ��āv
�i2018/6/7�j
���m���y�w����{�x����280���ጤ����i2018�N6��16���i�y�j�A���s��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/nishi/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��16���i�y�j14:00�`17:00
�ꏊ�F���s��w�l�ԁE���w������233���K���i�l��2�K�j
���e�F�C�m�_�����\�A���m�_�����\
�q�C�m�_�����\�r
�g���ϗT�u�ߑ�ɂ�����^�������̕ω��F��R�i���𒆐S�Ƃ��āv
�q���m�_�����\�r
�R�c�~���u�ߐ���y�����̌������Ƃ̉�y��e�𒆐S�Ɂv
�i2018/6/6�j
��r�����������154���ጤ����i2018�N6��15���i���j�A�_�ސ��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://hikakuminzok.html.xdomain.jp...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��15���i���j16:00�`18:00
�ꏊ�F�_�ސ��w���l�Z��9����9-212
�@���n�}�Fhttp://hikakuminzok.html.xdomain.jp...
���\�ҁF�����G�Y���i�����w�@�����w�����������j
��ځF�n��Љ�̓`���Ǝ����̊W���ɂ���
�@�@�\���ݕ}���I���s�A���L���Y�̔�r�����Ɍ������\���I�l�@
���O�̎Q���\�����݂͕s�v�ł��B
���\��ɂ͑�w�߂��̂��X�ɂč��e����J�Â������܂��i�Q�����R�j
�i2018/6/5�j
���{���y�w����{�x����51���ጤ����i2018�N6��9���i�y�j�A�����쉹�y��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.musicology-japan.org/east/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��9���i�y�j14�F00�`17�F00
�ꏊ�F�����쉹�y��w�]�Óc�L�����p�X S502
�i��F����Y�i�i�˕��w����w�j
���e�F�C�m�_�����\5��
1. 1920�`30�N��̒����ɂ����鐼�m���y�o��
�@�\�\�h���a�ƒ��؊y�Ђ𒆐S�Ɂ\�\
�@�A �ŗ�i�����Y�p��w��w�@�j
2. �O�B�h�E�A�h���[�̗l���_�čl
�@�\�\���y�w�̌n�ɂ�������w�̈ʒu�\�\
�@���쏫��i�c��`�m��w��w�@�j
3. �W���[���E�}�X�l�s���I�[���̉��t(1877)
�@�\�\�X�y�N�^�N���v�f�ւ̍�ȉƂ̍v���\�\
�@���щ��D�i�R�w�@��w��w�@�j
4. �]�˒����̎�w�҂ɂ�鉹�y�����ᔻ�Ɖ����h�q
�@����D�q�i�����Y�p��w��w�@�j
5. �t�H�[���̋Ȃɂ����ās���F�l�c�B�A��5�̉́t����߂�ʒu�ɂ���
�@�\�\���̉��y���Ƃ����ϓ_����\�\
�@�����m���i�����|�p��w��w�@�j
�i2018/6/4�j
���{�_���N���[�Y���y����w���51�����i6��3���i���j�A�����Ɛ���w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://eurhythmics.jp/reikai51info.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��3���i���j13:00�`16:15�i��t�J�n12:30�`�j
���F�����Ɛ���w 120���N�L�O��4B�u�`��
�@�i�����s�������1-18-1�j
�Q����F���1,000�~�A���1,500�~�A�w��500�~
�q�v���O�����r
�T �|�X�^�[���\�@13:00�`13:25
(1) �i�c���ގq�i�L���s���������w�Z�j
20���I�t�����X�ꌗ�ɂ���m�I�Ⴊ������ΏۂƂ������g�~�b�N�̓W�J
�U �������\�@13:30�`16:15
(1) ���c���q�i������w�ʐM����w�@���m�O���ے�/���c���Z����w�j�u�C�M���X�̊w�Z����ɂ����郊�g�~�b�N�̎�e�ƕϑJ�F���y�W���[�i���w�w�Z���y�]�_�x�̃��g�~�b�N�Ɋւ���L�q�𒆐S�Ɂv
(2) �א싧���i���c���Z����w�j�u�W���b�N���_���N���[�Y�́u�o�����X�v�ɂ��āv
(3) ��a�F�i������w�j�u���y�̊w�K�ƒ�������i1898�N�j�ɂ��Ă̌����v
(4) �쐰�q�i������w�j�u�I�n�C�I�B����w�����̏��Ȃ̌����FUniversity libraries Thompson Special Collection ����v
(5) �ÊՐ^���i���c����w/������w�ʐM����w�@���m����ے��j�u�w�_���N���[�Y�E�\���t�F�[�W���x�ɂ����鐔�����Ɋւ����l�@�v
(6) ������i���w�@��w�j�uE.J=�_���N���[�Y�̗��_���䂪���̒��w�Z���y�ȋ���ɗ^�����e���F���a44�N�������w�Z�w�K�w���v�̉��y�Ȃɂ�����̈�u��b�v�̐����𒆐S�Ɂv
���{�_���N���[�Y���y����w��
�����ǁF�������s�ˑq3-21-7�@�d�b��FAX042-575-7270�����C�t
�i2018/5/31�j
���{�������|�w���42����i6��2���i�y�j�`6��3���i���j�A�������Ȋw��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://ko-sho.org/page/activity...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��2���i�y�j�E3���i���j
�ꏊ�F�������Ȋw��w�i���{�����s�����u3�|11�|1�j
�@���s������F�͓������w�i�ߓS�����j�@�k��12��
�@�ޗǎs������F����c�w�i��a�H���j�@�X�N�[���o�X15��
��1���ځ@6��2���i�y�j���@D2-605=606����
�E�J��̎��@13��50��
���؎j�l�i��E�������Ȋw��w�j
�E���J�u���@14��00���`16��20��
�u��蕨���|�̈ٗލ��함�ɂ��āv�ɓ��T��i���ۓ��{���������Z���^�[�j
�u�u���k�v�̒a�� �\�s�ׂ��錾�t�Ƃ��̎v�z�\�v�^�珹���i�k��B�s����w�j
�E����@�@�@16��25���`17��15��
�E������������@�T���q����������̊ԁ@18��00���`20��
��2���ځ@6��3���i���j
�E�������\�@9��00���`11��30��
��1���@D2-605����
�u�����Ɠ��{�ɂ�����s�s�`���̔�r�����v�����H�i���{�@��{�i�@�j�j
�u���b�����ꂽ�̘b �\�ؓc�����́w�V�S�I���{�ނ����Ȃ��x�\�v����ϖ��i������w�j
�u�k�֓��ɂ�����r���v�`���̑S�̑��v������v��Y�i��p�Z����w�j
�u���c�Ĉ�������c���j�� �\�₢�����L����I�[�����ȏ�̐����\�v���h��i�É���w�j
��2���@D2-604����
�u�C�i�E�̗썰�̏z�� �\�k�C���A�C�k�̌������|����\�v����ȁi��t��w�i�@�j�j
�u�k�C���A�C�k�������|�ɂ݂�J���X�_�̐��i�Ɩ��́v���c��āi�A�C�k���������فj
�u�l�i�_�̏K�����l���� �\�A�C�k�E���N�̗ޘb���肪����Ɂ\�v�k�����Y���i�k�C����w�j
�u���N��������̎�҂ɓ`��������{�́u���ԂƂ�v�v粉��c�i���u�Б�w�i��j�j
�E�V���|�W�E���@12��30���`16��00��
���@D2-605=606����
�u���[�J���Ȃ��̂̐������ѕ� �\����ɂ�����l�`�V��̍ĕ������\�v
�p�l���[�F
�u���J�҂̐g�̂Ɛl�`�V�� �\���k�ɂ�����I�V���_���߂����ā\�v�R�c���q�i�O�O��w�j
�u��t���̌p���ɂ݂�l�`�V��̍ĕ����� �\���g�؋�܂킵�̎���\�v�X�c�ǐ��i���m��w�j
�u�X�e�B�O�}�̃V���{������A�C�f���e�B�e�B�̃C�R���ց\���g�؋�̍Đ��ߒ��\�v�I�v�i���s���ؑ�w�j
�R�����e�[�^�[�F�e�n�Łi���s��w�j�E �R��u�T�i�}�g��w��w�@�j�A�i��E�i�s�F�I�v�i���s���ؑ�w�j
�E��̎��@16��00���@�떓�b��i���ꍑ�ۑ�w�j
��3���ځ@6��4���i���j
�u��a�̌������|�E�܌��M�v�̌����v �t�B�[���h���[�N
�ߓS�͓������w�����o�X���[�^���[���i9��40���j�`�ߓS�E�i�q�ޗljw���U(16��00��)�\��
�i2018/5/30�j
���{�����w��2018�N�x�S�����i6��29���i���j�`7��1���i���j�A�_�ˏ������q�w�@��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jstr.org/project/pro01_2018...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F
�E6��29��(��)�F �؍������w��ɂ�錤�����\�E�p�l��
�E6��30��(�y) �E7��1��(��)�F �u���E���\�E�p�l���E���E���h�e�[�u��
�ꏊ�F�_�ˏ������q�w�@��w
�i��657-0015�_�ˎs���������R��1����2-1�j
�q�v���O�����r
��6��29���i���j
�Z�N�V����A�F�ߑ㉉���@13:30�`15:00�@1221����
�E�����J�i�����w�j�u�|�p���̒��N���ƂƉ����q�����r�㉉�v
�E�������f�i���R��w�j�u������p����݂��؍��ߑ㉉���̗l���̉ۑ�v
�E���l�R�i�������j�u�A���n�ڏZ���ۂƋߑ㉉���F�ߑ㏉���̓��{�l�E���N�l�̊���ڏZ���ۂƊ؍��̋ߑ㌀�ꕶ���̌`���v
�Z�N�V����B�F�������_�@13:30�`15:00�@1232����
�E�A����i�[����w�j�uFrom Modern Drama of Enlightenment to Postmodern Drama of Sublimity�v
�E�A����i�[����w�j�uTranscultural Phenomenon of "Crisis of Masculinity" in Anthony Shaffer's and Harold Pinter's Sleuth�v
�E���{���ȁu�����{�����Ɍ�����؍��l�̕\�ہv
�Z�N�V����C�F�������w�@15:30�`17:00�@1221����
�E������i������w�j�u�؍��������ۂɂ����ĉ����Ɗϋq�̗͊w�I�W�Ɋւ���l�@�v
�E�͜��T�i������w�j�u�`�������̌���I�Ȍċz�v
�E�S�p�Łi�؍��|�p�����w�Z�j�u�����ꉉ���̔��w�Ɗ؍������̕��䉻�헪�����v
�Z�N�V����D�F���̑��@15:30�`17:00�@1232����
�E�����P�i�؍��|�p�����w�Z�j�u�n�敶���̎�e�ƒn�挀�c�̒E�n�扻�F�J���W���}���i�N���s�j�����i�̎���𒆐S�Ɂv
�E�A�G���u�Ӑ}���ꂽ�q�S���r�Ɓq���ҁr�̋�ԁF���m�M���b�f�ދY�Ȃ𒆐S�Ɂv
�E�����M�i�؍��|�p�����w�Z�j�u���{�ߑ��y���v�Ɖ�y�ǂ̐ݗ� �v
�������_�@17:10�`18:00
��6��30���i�y�j
��u��(1)�@10:30�`12:00�@213�勳��
�E�v�����i���M���q��w�Z�Z�������|�p��w�j�u�X�g�[���[�E�e�[�����O�iStory Telling�j�ƕ����~�G�I�����s�b�N�J�����v�|��F�c���q�i�k�đ�w�j �ʖ�F���T�j�i����w�@���j
�p�l��(1)�@13:00�`15:00�@724����
�E�u������₢���������v
���c�h��Y�i�c���`�m��w�j�A�j�L�^���q�i�c��`�m��w�j�A�O��i�c��`�m��w�j�A�Ό��M�i�c��`�m��w�@���j�A�{�����i�i�c��`�m��w�@���j
�������\�@13:00�`15:00�@722����
�E����ؑ�i�������q��w�j�u�}���e�B���E�u�[�}�[�ƃn�r�}����F�w�u���C�ꉉ���ւ̃r�W�����v
�E�^�ߔe���q�i�����w�n�挤�����j�u�c�����A��10 �N(1972-1982)�̉���̕����� �ۂƕ���|�p�i�`���|�\�ƌ��㌀�j�v
�E�Ö،\�q�i���s�w����w�j�u�x���i�E�n�X�E�q���[�X�g���̋Y�Ȃɂ݂鑽 �������l��̏ے��Ƃ��Ắu���v�̖����v
�������\�@13:00�`15:00�@721����
�E�����Ђ���i������w�@���j�u�~���[�W�J���w�}���[�E�A���g���l�b�g�x�ɂ����镪�g�F�}���[�ƃ}���O���b�g�̊W���v
�E�������D�q�i����c��w���������فj�u�q������r���z���āF��ˉ̌��ƃA�_�v�e�[�����v
�E�����[�i������w�j�u�n�C�E�A�[�g�ƃ}�X�E�J���`���A�̂͂��܂ŁF���{�̃~���[�W�J���čl�v
�؍������w����{��Z�b�V�����@13:00�`15:00�@725����
�E�������i�؍��|�p�����w�Z�j�u������ݓ��R���A�����������v
�E���^�Ɂi�|��Ɓj�u�qGod Bless Baseball�r�̃A���S���[�����v
�E�^�P�p�i���{���ە����������j�u1910�N����E���s�E����̌��ꋻ�s�����v
��u��(2)�E���E���h�e�[�u���@15:15�`17:50�@213�勳��
�E��u���F�ї��ÍF�i�����Y�p��w�j�u����ɂ��́u��O�v�Ƃ͉����H �����ٌ���̃e���g�ŋ����肪����Ɂv
�E���E���h�E�e�[�u���u���㉉���ɂ�����n�C�E�A�[�g�A��O�����A�T�u�E�J���`���[�̋��E���v�i��F�e��q�p�i�_�ˏ������q�w�@��w�j
���D�i������w�j�A���R���Y�i�Ռ��w�����q��w�j�A�����q�i�\�E���|�p��w�j�A�ї��ÍF�i�����Y�p��w�j�A�ʖ�F���^�Ɂi�|��Ɓj
��7��1���i���j
�p�l��(2)�@10:00�`12:00�@724����
�u�������ۂƂ��Ă̒n��i�f�l�j�����̉\���v
�{���N��i�����o�ϑ�w�j�A�ܓ����q�i�����w�j�A��ؗ��f�q�i�ҏW�ҁE���C�^�[�j
�������\�@10:00�`12:00�@722����
�E�e�r�������i�ޗǑ�w�j�u吐�K�Y���o�V�F�C�N�X�s�A�����F�w�ԈႢ�̊쌀�x�i2006�N�j�𒆐S�Ɂv
�E�R�薾�����i���{��w�j�u�l�X�g���C�̉��Z�p�Ɩ@�̈�̕ϓ��ɂ��āv
�E�����_�q�i������w�j�u�w�e�[�o�X�E�����h�i Tebas Land �j�x (�Z���q�I�E�t�����R��)�ɂ�����_�b�Ƃ̋Y��v
�������\�@10:00�`12:00�@721����
�E�H�����p�i�V����w�j�u�V�����w���蒉���x�����j�F�s�F�����̈ʒu�t���̍Č����𒆐S�Ɂv
�E�����a���i�w�Z�@�l���É��w�@���É����w�E�����w�Z�j�u�\�y�̑�O���F�~�ᗬ�̊����𒆐S�Ɂv
�E�ɓ��^�I�i������w�j�u�吳���ɂ�����u�ԊO�ȁv�����Ƃ��̓W�J�F�u�w�ȁv�lj��ɂ�����V�������_�̓o��v
����E�͒|�����@13:00�`14:30�@213�勳��
�E�͒|�܁F�R�c�a�l
�E����܁F�x�^���q�A������
�V���|�W�E���@14:45�`16:45�@213�勳��
�u���{�`�������ƕ������ہv�i�� : ��������i�����w�j
���䋦�O�i�����w���������ٖ��_�����j�A�������q�i�����w���������فj�A�����O�i����w�j
�i2018/5/29�j
���x�w���23���ጤ����i6��9���i�y�j�A�V����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.danceresearch.ac/reikai...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��9���i�y�j10�F00�`17�F00�i�\��j
���F�V����w �[�V���L�����p�X�i�ޗnj��V���s�[�V����1050�j
�@�@JR������y�ыߓS�ޗǐ��V���w�i�o�X��8���j
���e�F
�P�j��ጤ����F��ʌ������\
�Q�j�����i��ʌ��J�j�F�u��y�E���y�ɂ݂���{�̉�v��y�E���y�̎����ƍu��
���{��ጤ����̎Q����͖����ł��B�܂��A�ߌ�̗����͈�ʌ��J�Ƃ��Ă��܂��̂ŁA���U�����킹�̏�A�����̊F�l�̎Q�������҂����Ă��܂��B
�q�v���O�����r
��t�J�n�F10�F00�i2����1�K 2���������j
��ʌ������\�F10:30�`12:30�i2�K22A�����j
�E���c�����q�i�����ё�w�j�u�V���x�^���ɂ����鑼�Ґ��v
�E������S�i�Q�n�������q��w�j�u���@�i�L�����[�ȕ��x�̃��t���[�~���O�F�V���[�l�b�h�E�q���[�Y�Ɗ_���x�̋����v
�E�����ߓގq�i�_���X�����F�_���X�h���}�g�D���N�j�uNoh to Trio A�F�C���H���k�E���C�i�[�ƘV���̃_���X�h���}�g�D���M�[�v
�����F14:00�`17:00�i�����V���}���ّO�A9���قӂ邳�Ɖ�فj
�E��y���t�ƃ_���X�p�t�H�[�}���X�u�z�V�y�v
�@�@�V����w��y���ƓV����w�n��_���X��
�E���y �����́u���ˉ��v�ƉE���́u�[�\���v
�@�@�V����w��y��
�E�u���F�����_�i�i�V����w���_�����j�u��y�ɂ݂��v
�i2018/5/28�j
���m���y�w����{�x����104���ጤ����i2018�N6��2���i�y�j�A���ۊ����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/higashi...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��2���i�y�j14:00�`16:10
���F���ۊ����w H402�����i��w�{��4�K�j
�@�L�����p�X�}�b�v�F http://www.icu.ac.jp/about/docs...
�@�A�N�Z�X: http://www.icu.ac.jp/about/access...
�q���m�_�����\�r
1.�u1930�N��̓������y�w�Z�ɂ������ȋ���Ɓu�̋ȁv�n��\�ߑ���{���y�j�ς̍č\�z�ɂނ��ā\�v���Ґ^���i�����Y�p��w��w�@�j
2.�u�G���w�I�y���]�_�x����сw�I�y���x�ɂ݂�I�y���̎�e�ߒ��ɂ��āv���Ð�ˎq�i�����̐����q��w��w�@�j
3.�u�u���特�y�v�Ƃ����p��ɂ��Ă̗��j�I�l�@�\����������吳���𒆐S�Ƃ��ā\�v�R�{�^�I�i������w��w�@�j
�i��F�}�b�g�E�M�����i���ۊ����w�j
�i2018/5/22�j
��w�@������i�����j���J�Â��܂�
������5��26���i�y�j�ɁA�����ő�w�@��������J�Â��܂��B�{�w�̋��E�����ꓰ�ɉ�A�{�w�̋���E�����̓��F������̊T�v�A�C����̐i�H���ɂ��đ��k�������܂��B
��w�@�ւ̐i�w�����l���̕��A�{�w�̎��g�݂ɋ�����������̕��A�Ȃ��Ȃ���W�܂�ɂ������ƂƎv���܂��B���y�R�[�X���܂߁A�e�R�[�X���狳�����Q�����܂��̂ŁA���s���̓_�����C�y�ɂ����k���������B

��z�����w ��w�@������y�������z
����30�N5��26���i�y�j13:00�`16:00�y�������z
���F�T���V���C���V�e�B ���[���h�C���|�[�g�}�[�g�r��5�K
�@�R���t�@�����X���[��4�E5�i�����s�L����j
�����̑��ɓ����Ɩ��É��Łu��w�@���w���k��v�𐏎��J�Â��Ă��܂��B����ɂ��Ă� ������ �ł��ē����Ă��܂��̂ł������������B
���\���݁E���₢���킹
�E��z�����w���L��
Tel025-521-3626 / Fax025-521-3627
�E���y�R�[�X ��w�@������S��
Tel025-521-3514 / MAIL: tamamura [at] juen.ac.jp
��������\��̕��͎��O�ɂ������K���ł��B���L�����N�́u�y������zWeb�\���݂͂�����v���炨�\���݂��������B�������A�\�����݂Ȃ��ł��Q���ł��܂��B
�i2018/5/21�j
�I�y���^���y��������5���������i2018�N5��19���i���j�A����c��w�j
������̏��ł��B
������HP�͂�����
www.waseda.jp/prj-opera-mt/next.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N5��19���i�y�j16:30-18:30
���F����c��w ����c�L�����p�X3����406���K��
�@���L�����p�X�}�b�v�Fhttps://www.waseda.jp/top/access...
���e�F�V���|�W�E��
��ځF�J�^���[�i�E���[�O�i�[���o�s�t�B�f���I�t�����y���ނ��߂�
���\�ҁF�����p�A�V�c�F�s�A�X������
�T�v�F������5��20�����瓌���̐V��������Ńx�[�g�[���F���̃I�y���s�t�B�f���I�t�̐V���o�������n�܂�B ���o��S������̂̓J�^���[�i�E���[�O�i�[�i1978�`�j�B��ȉƃ��q�����g�E���[�O�i�[�̑\���ɂ��Č��o�C���C�g���y�Ց��ēł���A ������̃h�C�c�̃I�y�����o�Ƃ̂Ȃ��ł��A���̐V���o����ɑ傫�Ȓ��ڂ��W�߂���ʂȐl���ł���B���O�l���A���̐��n�� �s�j�������x���N�̃}�C�X�^�[�W���K�[�t�i2007�N�j�Ɓs�g���X�^���ƃC�]���f�t�i2016�N�j�����o���傢�ɕ��c���������ޏ����A���̏t������ �x�[�g�[���F������Ȃ����B��̃I�y���ɒ��ށB������@��Ɂs�t�B�f���I�t�ƃJ�^���[�i�E���[�O�i�[�̉��o�ɂ��čl����̂������ �V���|�W�E���̎�|�ł���B
�@�S�͎̂O�̕ƕ҂����ɂ�铢�_����\�������B�܂��A�h�C�c�̉��y�����A���ɂ��̕������f�B�A�Ƃ̊W����Ƃ��� �����p�i���{��w�j���s�t�B�f���I�t�̍�i�T�v�Ǝ�e�j�ɂ��āA�����ŁA����̃I�y�����o�𗝘_�I�ɕ��͂��Ă����V�c�F�s�i����c��w�j�� �ߔN�̒��ڂ��ׂ�����́s�t�B�f���I�t���o�ɂ��āA���ꂼ��Љ�������ŁA�w�I�y���n�E�X���琢�E������x�i2013�N�A������w�o�ŕ��j �̒��҂ł���X������i������w�j���A���[�O�i�[��i�ɉ����ās���G���c�B�t�i2008�N�j�A�s���X�v�l�t�i2010�N�j�ق��̃J�^���[�i�E���[�O�i�[�� �ߋ��̉��o��i��U��Ԃ�ޏ��̉��o�̓������l�@����B����́s�t�B�f���I�t�͉ʂ����āu���炩�ɖ苿�����R�ւ̎^�́v �i�V��������z�[���y�[�W�̏Љ���j�ɂȂ�̂��B���_�ł͗\�z����҂������A�J�^���[�i�E���[�O�i�[���o�s�t�B�f���I�t�̌�����l�X�� �p�x���猟���������B
�i2018/5/18�j
�|�\�j�������55����i2018�N6��10���i���j�A���u�Џ��q��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w�����HP�͂�����
http://www5b.biglobe.ne.jp/~geinoshi...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��10���i���j10��20���`17��30��
���F���u�Џ��q��w���o��L�����p�X ������S014����
�e�[�}�F�q���ƌ��r�̓W�J�ƌp��
�q�v���O�����r
����ʕ�
�E�u���{��������p�ɂ�����\����v���~����
�E�u��{���i�������l�v�ѓ���F��
�E�u�u�ʂ���́v�l�v�R�H������
���V���|�W�E���u�q���ƌ��r�̓W�J�ƌp���v
���
�E�u�w���ƕ���x���{�̔����Ɓq���ƌ��r�v�������]��
�p�l����
�E�u�����O���ɂ�����Ӑl�̌|�\�v�ҍ_�a��
�E�u��������̔��i�@�t�̊����ɂ��āF����j������v��؍F�f��
�E�u�ߐ��E�ߑ�̕��ƌ��̋���̏�ƌ��̕ϗe�v�E�c���q��
�f�B�X�J�b�V�����@
�i2018/5/17�j
�����|�\�w���169�����i2018�N5��26���i�y�j�A����c��w���������فj
�w��E������̏��ł��B
���w�����HP�͂�����
http://www.minzokugeino.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N5��26���i�y�j�ߌ�2���`�i�ߌ�1��30���J��j
���F����c��w���������ك��N�`���[���[��6����3�K318����
�@�@�m�n�}�nhttp://www.waseda.jp/top/assets/uploads...
���Q����200�~�i����łȂ��������Q���ł��܂��j
�u�����̂ƌ|�\���H�F�S���肩�猩��ɐ���_�y�v
���\�ҁF��F��
�i��F�U�،�@�R�����e�[�^�[�F����
�q���₢���킹��r
�����|�\�w����ǁi���T�Ηj�� �ߌ�1���`4���j
��169-8050�@�����s�V�h�搼����c1-6-1 ����c��w���������ٓ�
TEL03-3208-0325�i���ʁj Mail�Foffice[at]minzokugeino.com
�i2018/5/16�j
���{���y�\���w���16��i�܂�߁j���i2018�N6��9���i�y�j�E10���i���j�A�L�������w����w�j
�w��E������̏��ł��B
�{�R�[�X�����̈����A��w�@���̔ё��@�g���������\�����܂��B
���w�����HP�͂�����
www.music-expression.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��9���i�y�j�E10���i���j
�ꏊ�F�L�������w����w�����L�����p�X
�@�i�L���s������撷����3����5-1�j
�Q����F�w���5,000�~
�@�����Q�� ���3,000�~�^1���A�w���w��2,000�~�^1��
�v���O�����F
�E6��9���i�y�j
12:00�`�@��t
13:00�`�@�J��@13:00�`
13:20�`�@��u���E���N�`���[�R���T�[�g
15:40�`�@����
16:50�`�@�T����
19:00�`�@���e��
�E6��10���i���j
9:40�`�@���ȉ�iA�`G�^1�`10�j
�J��F�u�����Ց��ہv���t�F�L�������w����w�a���ۃ`�[��
��u���F���c�G�i�i�L�������w����w���C�����j
�@�u���y�͂����Ƀq���V�}��`���Ă������v
���N�`���[�E�R���T�[�g�F�u�����̋L���Ɖ��y�v
�@�T�픚�̌��Ɖ��y�@�U�������Ɖ��y�@�V���펍�ƍ�ȉ�
�T�����F����S�����������������A�n��̉��y�Ƃ������āA���ʂ̘b��E�e�[�}�ɂ��Ęb���������ԁBA��Ȃ̃T�����AB�w���̃T�����AC���̃T�����AD�\���t�F�[�W���̃T�����AE�nj��Ŋy��̃T�����AF�s�A�m�̃T�����AG���{���y�̃T�����AH���y�\���ƎЉ�̃T����
�������\���F
�E���������Y�u�O�P�W�̑n�슈���ɂ�����푈�̌��̈Ӗ��v�i���ȉ�A4�A10��11:30�`12:10�j
�E�㓡�O�u�����͐��F���g���ĔE�ъ��v�i���ȉ�A8�A10��14:50�`15:30�j
�E�ё��@�g�u���X�@���Y�̃X�g���[�N�t�@�Ɋւ��鋳�ގj�I�����F�e�Ŋy��̗��K�@�ɒ��ڂ��āv�i���ȉ�C8�A10��14:50�`15:30�j
�i2018/5/15�j
���w������318�����\��i2018�N5��26���i�y�j�A���s��w�j
������̏��ł��B
���w�����HP�͂�����
http://www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N5��26���i�y�j�ߌ�1��30�����
���F���s��w �g�c��L�����p�X�l�ԁE���w�����ȓ��n����u�`��
����ʂ̕��̌䗈�������R�ł��i�Q����s�v�j�B
�q�������\�r
�u�����O�̃s�A�m�Ƒt�Ȃɂ����鎞�Ԃ̕ϗe�v
�� �ہi���s��w�j
�u�C���[�W�̎��ݐ��Ɣ��������F
�W���x�[���E�V�����h���w�z���͂Ɣ����x���߂����āv
�F�����B�N�i���s��w�E���{�w�p�U������ʌ�����DC�j
�i2018/5/11�j
���w������30�N�x��1����i2018�N5��26���i�y�j�A�����w�j
������̏��ł��B
���w�����HP�͂�����
http://www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F5��26���i�y�j14��00���`16��30��
�ꏊ�F�����w 7����731����
�@�A�N�Z�X�E�}�b�v http://www.seijo.ac.jp/access/
�@�L�����p�X�E�}�b�v http://www.seijo.ac.jp/about/map/
�q�������\�r
�E�u�J���t�H���j�A����̃}���E���C�v
�ؐ��痢�i�����w�j
�i��F���������i�i������w�j
�E�u�ЊQ�Ǝq�ǂ��I�����F�{�V�����́u���̖��O�Y�v���߂����āv
���싱���i�����w�j
�i��F�O�R�I�v�q�i��ʑ�w�j
�i2018/5/10�j
�|�p�n��w��������E�����҃V���|�W�E���u�����̃A�[�e�B�X�g�E�����҂͂ǂ̂悤�ɃL�����A��z���Ă����悢�̂��H�v�i2018�N5��26���i�y�j�A�����Y�p��w�j
������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
diversity.geidai.ac.jp/2018/04/sympo2018/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F5��26���i�y�j15:00-17:30�i14:30�J��j
���F�����Y�p��w���Z�n ���p�w��������1F��1�u�`��
�@�@�i�����s�䓌�������12-8�j
���ꖳ���E�\���s�v�A����F�撅180��
�q�v���O�����r
�EPart1 ��u���@15:00-15:45
�u���A�����̊���Ɍ����ē`���������Ɓv
���J�T�q�i�L���X�^�[�^�����Y�p��w�����E�_�C�o�[�V�e�B���i�����j
�EPart 2 �p�l���f�B�X�J�b�V�����@16:00-17:30
�u�|�p����ɂ����鏗���̃L�����A�\�z���l����`����Ǝ��H�̌��ꂩ��`�v
���c������i��������p��w���{��w�ȋ����j
���R���q�i���q���p��w�|�p�w���A�[�g�E�f�U�C���\���w�Ȓ��E�����j
���c�֎q�i�������y��w�����j
���q�m���i�˕��w����w���y�w�������j
�F�q���q�i�����Y�p��w��w�@���ی|�p�n�������Ȓ��j
�����~�q�i�����Y�p��w���y�w���y���ȋ����j�ȏ�A�\����
�i��F���{���Îq�i�����Y�p��w���w���j
�i2018/5/9�j
�|�p�w�֘A�w��A����13��V���|�W�E���u�|�p�Ƌ��{�F�|�p�͋��{���肦��̂��H�v�i2018�N6��2���i�y�j�A�c��`�m��w�j
������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://geiren.org/news/2018/20180602.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
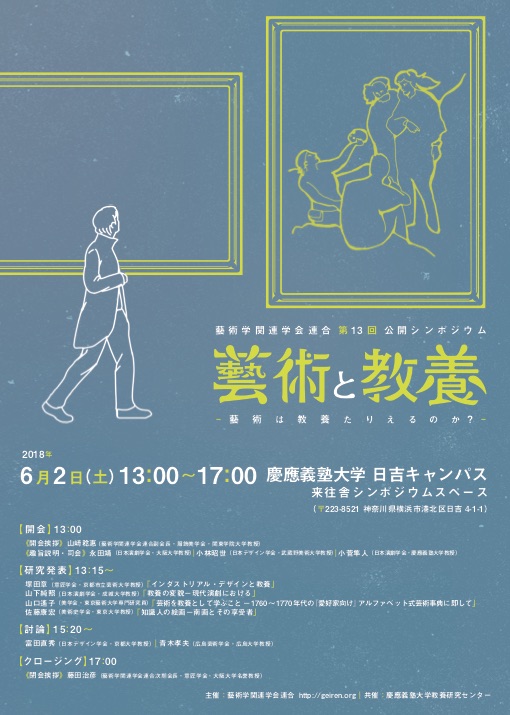
�����F2018�N6��2���i�y�j13:00-17:00
�ꏊ�F�c��`�m��w ���g�L�����p�X�����ɃV���|�W�E���X�y�[�X
�@���ꖳ���^���O�\�����ݕs�v
�q�v���O�����r
�J��@13:00
�E���A�@�R�薫�b�i�|�p�w�֘A�w��A������E�������w��j
�E��|�����E�i��@�i�c���i���{�����w��j�A���я����i���{�f�U�C���w��j�A�������l�i���{�����w��j
�������\�@13:15�`
�E�u�C���_�X�g���A���E�f�U�C���Ƌ��{�v�˓c�́i�ӏ��w��j
�E�u���{�̕ϖe�F���㉉���ɂ�����v�R�����Ɓi���{�����w��j
�E�u�|�p�����{�Ƃ��Ċw�Ԃ��ƁF1760�`1770�N��́w���D�ƌ����x�A���t�@�x�b�g���|�p���T�ɑ����āv�R��ꡎq�i���w��j
�E�u�m���l�̊G��F���Ƃ��̋���ҁv�����N�G�i���p�j�w��j
���_�@15:20�`
�E�x�c���G�i���{�f�U�C���w��j�A�؍F�v�i�L���|�p�w��j
�N���[�W���O�@17:00
�E��A�@���c���F�i�Y�p�w�֘A�w��A��������E�ӏ��w��j
�i2018/5/8�j
���{���y����w��ߋE�n��2018�N�x��1��n����i2018�N5��26���i�y�j�A�����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://���{���y����w��.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N5��26���i�y�j13:30�`17:30
���F�����w����w�����y��
�q���Ƙ_���r
�E����F���i���s���q��w�j�u�z�X�s�X�ɂ����鉹�y�Ö@�����F�Ɨ��^�z�X�s�X�ł̎��H��Ɋ�Â��āv
�E���R��q�i�����w�j�u�q�ǂ��̍s�������y�ł��Ȃ������݁F�c�����̐����K���ɏœ_�����Ăāv
�q�C�m�_���r
�E���c�����i�����w��w�@�j�u���w�Z���y�Ȃɂ����鎙���̓��I����͂̊l���ߒ��ɂ��Ă̌����v
�E�����i���s�����w��w�@�j�u���y�Ȏ��Ƃɂ����鋦���I�Ȋw�K�̔��W�I�l���F���ʖ��̐����ɒ��ڂ��āv
�q������\�r
�E�����v从q�i�����w��w�@�j�u�h�C�c�̏����w�Z�����{���ɂ����鉹�y�ȋ���F�m���g���C�������F�X�g�t�@�[�����B���Ɂv
�E���㌒�u�i���ɋ����w�j�u�����{���̎��_����w�Z�̉��y�����U��Ԃ�v
�������w����w���ւ̃A�N�Z�X
JR�ΎR�w�����2�n���̃o�X������A�o�X�^�[�~�i������p�ɂɔ������Ă��܂��B�ΎR�w����e�o�X�X�g�b�v�܂ł̏��v���Ԃ͖�10���B
�E����o�X2�ԁE4�Ԃɏ�ԁA�����O�o�X��ʼn��ԁA����֓k��7��
�E����o�X52�ԁE53�ԁE54�Ԃɏ�ԁA����吼��o�X��ʼn��ԁA����֓k��0��
�i2018/5/7�j
��w�@��������J�Â��܂�
������5��12���i�y�j�A�����26���i�y�j�ɁA��w�@��������J�Â��܂��B�{�w�̋��E�����ꓰ�ɉ�A�{�w�̋���E�����̓��F������̊T�v�A�C����̐i�H���ɂ��đ��k�������܂��B
��w�@�ւ̐i�w�����l���̕��A�{�w�̎��g�݂ɋ�����������̕��A�Ȃ��Ȃ���W�܂�ɂ������ƂƎv���܂��B���y�R�[�X���܂߁A�e�R�[�X���狳�����Q�����܂��̂ŁA���s���̓_�����C�y�ɂ����k���������B
��z���̉�ł́A�w���h�ɂ��͂��ߑ�w�������w����c�A�[�Ȃǂ�����܂��B���̋@��ɂ��Б������^�т��������A�w���̗l�q�������ɂȂ��Ă��������B

��z�����w ��w�@������
����30�N5��12���i�y�j13:00�`16:00�y��z���z
���F��z�����w�i�V������z�s�R���~��1�j
����30�N5��26���i�y�j13:00�`16:00�y�������z
���F�T���V���C���V�e�B ���[���h�C���|�[�g�}�[�g�r��5�K
�@�R���t�@�����X���[��4�E5�i�����s�L����j
��12���́A�k���V�����u��z�����v�w�Ƒ�w�L�����p�X�Ԃ��������}�o�X���^�s���܂��B�ڍׂ� ������ ���������������B
�����̑��ɓ����Ɩ��É��Łu��w�@���w���k��v�𐏎��J�Â��Ă��܂��B����ɂ��Ă� ������ �ł��ē����Ă��܂��̂ł������������B
���\���݁E���₢���킹
�E��z�����w���L��
Tel025-521-3626 / Fax025-521-3627
�E���y�R�[�X ��w�@������S��
Tel025-521-3514 / MAIL: tamamura [at] juen.ac.jp
��������\��̕��͎��O�ɂ������K���ł��B���L�����N�́u�y������zWeb�\���݂͂�����v���炨�\���݂��������B�������A�\�����݂Ȃ��ł��Q���ł��܂��B
�i2018/5/1�j
���{���y�w����{�x����40����^���m���y�w����{�x����279���ጤ����i2018�N5��26���i�y�j�A�_�ˑ�w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N5��26���i�y�j14:00�`17:00
���F�_�ˑ�w�l�Ԕ��B���w������
�@�ߍb��2�L�����p�X C101����
�@�n�}: http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access...
���e�F���v���y��܋L�O�u��
�P�D�E�c���q�i�����쉹�y��w�����j�u���Ɓi���ȁj�̉��y�w�I�𖾂Ǝ�����ւ̓`���v���W�F�N�g�F����������H�ցv
�Q�D�t�B���b�v�EV. �{�[���}���i�V�J�S��w���y�Ȃ���уJ���b�W�A���[�g�E�B�q�E���[�[���o�[�K�[ ���_���j��M�����B�n�m�[�t�@�[���y������w�q�������j "Lifted Up from Earth at the Very Moment of Death": Music beyond Itself
�i2018/4/26�j
�\�y�w���17����i2018�N5��19���i�y�j�E20���i���j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.nohgakugakkai.cside.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N5��19���i�y�j�E20���i���j
�ꏊ�F����c��w ����L�O�u���i���吳��O���ԁA27���ْn��2�K�j
�����ꖳ���E���O�\���s�v
5��19���i�y�j��t�J�n�i12��30���j
�E��\���A�i13���j�\�y�w���\ �O��q
�E�����u���p�H�|�Ɣ\�y�v�i13��05���`17��30���j
��|�����@�������u��
�u���u���{�G��j�ɂ�����\�y�̉e���v�Γc���玁
�u���u�\�œǂ݉������G�ӏ��v���c�Č���
�u���u�`���ꂽ�\���������v����ގ�
�S�̓��c�@�Γc���玁�E���c�Č����E����ގ�
�@�R�����e�C�^�[�F���ь��@�i��F�������u��
�E���e��i18���`20���j����� 4000�~��
���c�q�Ɂi����c��w����c�L�����p�X���O�j
5��20���i���j��t�J�n�i9��30���j
�E�������\�i10���`11��30���j
�u�c���˂̔\�y�v�����a����
�u�q�|��r�̍\���Ɖ��o�v���c�M�ꎁ
�u�a������{�u�ؘZ�ʁv�̐��i�ƕ\�����v���ѐ瑐��
�E���x�݁i11��30���`13���j
�E����i13���`13��30���j
�E�g�[�N�Z�b�V�����s�w�Z�ŋ�����\�E�����t�i13��45���`15��30���j���F26���فi��G�L�O�^���[�j302�����@�i��F�O��q��
�u���l�\�y���ł̎��g�݁v������V��
�u����ɂ����鋳�������̍u���A�w�Z�K��̌���v�L�V�v�� �@�@ �@�@�@�@�@�@�@
�E�g�[�N�Z�b�V�����s�ϋq�ȂƍŐV�Z�p�\�ς�����\�y���̊ӏ܊����߂����ā\�t�i13��45���`15��30���j ���F26���فi��G�L�O�^���[�j502�����@�i��F���R���Y��
�u�����z�M�Ƃ���𗘗p������H��̎��g�݁v�ϐ��쐳���E�w�퐳��
�u�����\�y���̎����̎��g�݁v���їm����
�E�u���i15��45���`16��45���j
�u�w�{�̖{���Z���ɂ��āv�|�{���v��
�i2018/4/25�j
��16��n�D�i�����t�H�[�����i2018�N5��12���i�y�j�A���s�V�������z�[���j
������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.cdij.org/shikohin/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
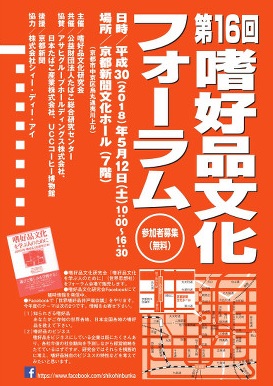
�����F2018�N5��12���i�y�j10:00�`16:30�i�J��F9:45�j
�ꏊ�F���s�V�������z�[���i���s�s�G�ۊۑ����߂��j
�����ꖳ���i�v�\���݁j
�v���O����
�E����29�N�x���������������\
�r�ؗ��i��s��w�����l���Ȋw�����ȁj
�u�N�ƉƂ̉c�݂���R�����C���h�l�V�A�����蕶���v
�ɓ��吶�i�}�g��w�l���Љ�Ȋw�����ȁj
�u�������ɂ������O�̖����̏���Ǝ��v�v
���ԗ����i���k��w ���Ȋw�����ȁj
�u�������L�쒬�̐l�ƃ^�o�R�̎�ϓI�Ӗ������鐶�����v
�����R�����i����w���w�����ȁj
�u�n�D�i�Ƃ��Ẳ��y�R���e���c�F���l���y��i������Ɂv
�������i�ꋴ��w����Љ���ȁj
�u��c�H���Ɩ��㕶�l�̒��ȁF�]�˕��l�̐����n�D�ɂ��āv
�E�L�O�u���u���܃f�U�C���Ƃ̈́���KYOTO Design Lab�̎��݁v
����F�N�i���s�H�|�@�ۑ�w���w���E�H�|�Ȋw�����ȋ����EKYOTO Design Lab. ���{���g���[���j
�E��u�n�D�i���f�U�C������v
��쐣�v�����i�b���w�����j
�E�������_
��쐣�v�����i�b���w�����j�A���c�S���i���������w�����ُy�����j�A���r��q�i�\�a�c�s������p�يْ��A�N���G�C�e�B�u�E�f�B���N�^�[�A����Ǖi�A�h���@�C�U���[�E�{�[�h�j�A���c�����i���ɐ쏗�q��w���_�����j�A���{����i���ɐ쏗�q��w�����j�A�֓����i���s���ؑ�w�����j
���\�����݁E�₢���킹�� ������
�i2018/4/24�j
�������y��w�������y������2018�N�x���J�u��No.1 ���y�h�L�������^���[�u�`���[�~���y�c���s���I�v��f��y�сu�~�����}�[���y�����u���v�i2018�N5��16���i���j�A�������y��w�j
�u���̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.minken1975.com/kouza_exhibition...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N5��16���i���j
�@�~�����}�[���y�����u���F16:30�`17:30�i16:00�J��j
�@�u�`���[�~���y�c���s���I�v��f��F18:00�`20:00
�ꏊ�F�������y��wJ�كX�^�W�I
���ꗿ�F���ꖳ��
�\�����݁F�\��s�v�B�����撅���̂�����ƂȂ�܂��B
����F100��
�l�Ɛl�Ƃ��Ȃ��A���_����Ă�~�����}�[�̓`�����y�u�T�C���i�T�C�����C���j�v�̊y�c�ɖ��������h�L�������^���[�f��̏�f��ł��B�~�����}�[�����A�A�j���[�n���̑��ň�܂�Ă����l�Ɖ��y�Ƃ̉c�݁B�y�퉉�t�ҁA�x���A�������ҁA�ϋq����̂ƂȂ��Č`�������|�\��Ԃ̖��͂ɔ���܂��B�����āA�f��𐧍삵���ΒJ���j�ɂ��u�~�����}�[���y�����u���v���J�ÁB�`�����d���邱�̍��ŁA���m�����Ƃ��Z�����Ȃ���Ɠ��̉��y�V�[����z���Ă������̉ߒ����A�n���A���j�A�����ȂǗl�X�Ȕw�i�ƏƂ炵���킹������܂��B
�E���y�h�L�������^���[�u�`���[�~���y�c���s���I�v
�B�e�E�\���F�ΒJ���j�@��ށF������āA�㓡�C�g
�h�L�������^���[ 2017�N ���{ 116��
�~�����}�[�ꉹ���E���{�ꎚ��
�i2018/4/23�j
�����c�ۂ��E���E�ۂ�20���N�L�O���t��i2018�N5��5���i�y�E�j�j�A���[�W�����v���U��z�j
�Â��̏��ł��B
�������cHP�͂�����
http://purety.jp/pocoapoco/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
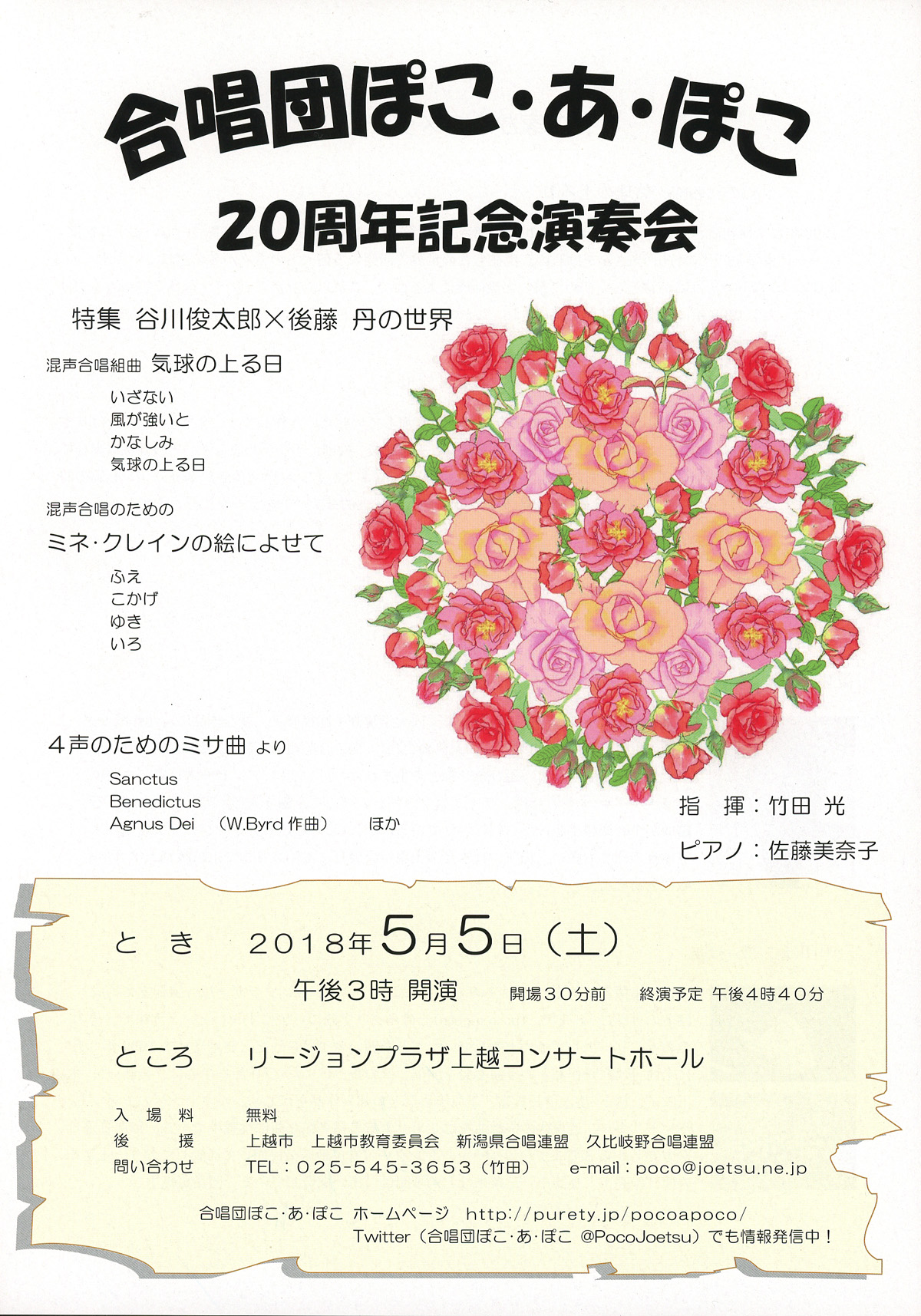
�����F2018�N5��5���i�y�j�ߌ�3���J��
�@�J��30���O�A�I���\��ߌ�4��40��
�ꏊ�F���[�W�����v���U��z�R���T�[�g�z�[��
���ꗿ�F����
���W �J��r���Y�~�㓡 �O�̐��E
�E���������g�� �C���̏���
�@�@�����Ȃ��^���������Ɓ^���Ȃ��݁^�C���̏���
�E���������̂��߂� �~�l�E�N���C���̊G�ɂ悹��
�@�@�ӂ��^�������^�䂫�^����
�E�S���̂��߂̃~�T�� ���iW. Byrd��ȁj
�@�@Sanctus / Benedictus / Agnus Dei�@�@�ق�
�w���F�|�c��
�s�A�m�F�������ގq
�㉇�F��z�s�A��z�s����ψ���A�V���������A���A�v���썇���A��
�⍇���FTEL025-545-3653�i�|�c�j�AE-mail: poco[at]joetsu.ne.jp
�i2018/4/20�j
��������z���� �l�`��ڗ��u�R����v�v�i2018�N4��21���i�y�j�E22���i���j�A���c���E�فj
�Â��̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
https://blog.goo.ne.jp/ningycyathemis...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
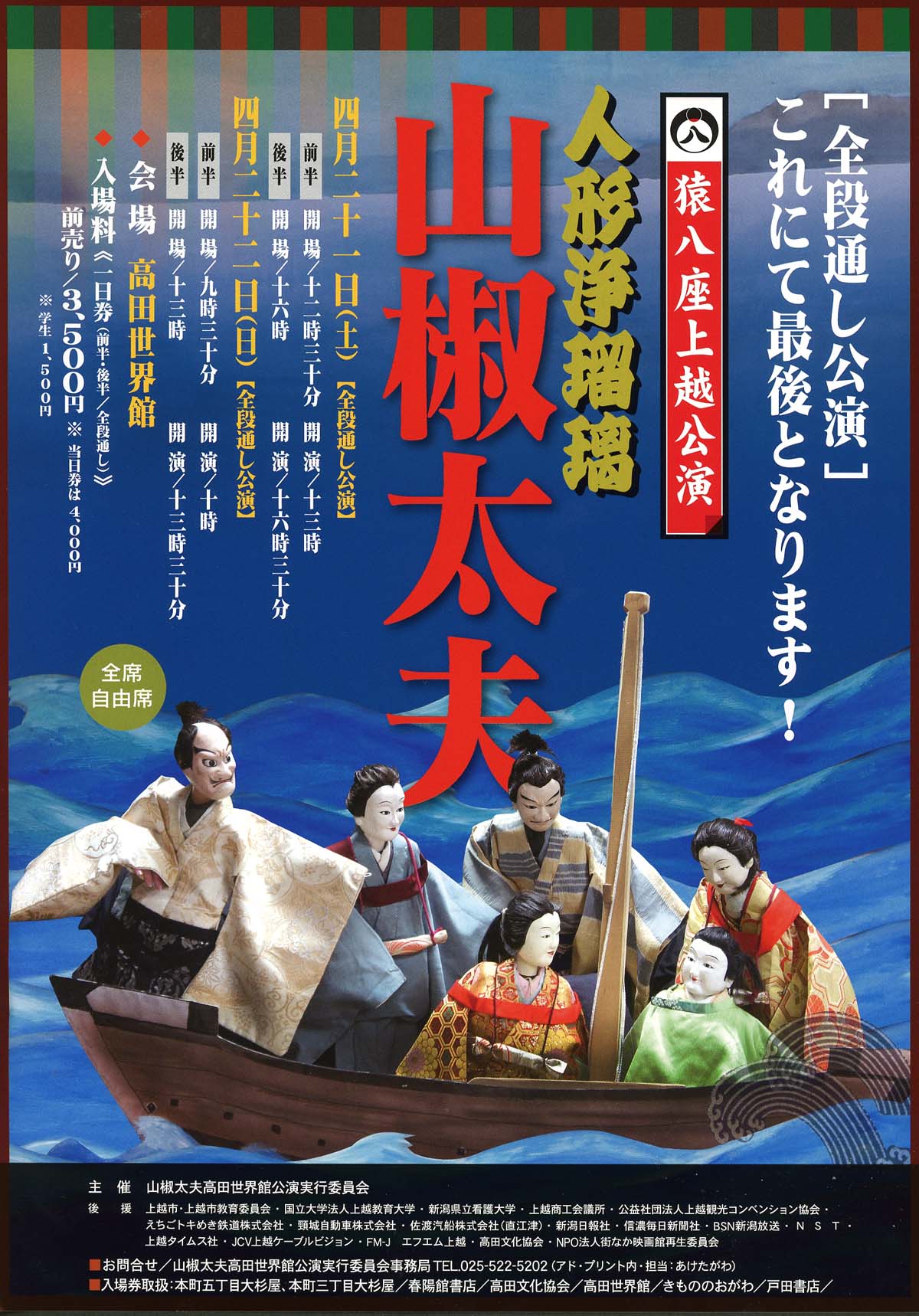
�E�����F2018�N4��21���i�y�j�E22���i���j
�@�@21���c�O��13���J���A�㔼16��30���J��
�@�@22���c�O��10���J���A�㔼13��30���J��
�E�ꏊ�F���c���E�فi��z�s�{��6�j
�E���ꗿ�i������F�S�i�ʂ��j�F�O����3,500�~
�@�@��������4,000�~�A�w��1,500�~�@�S�Ȏ��R��
�E�`�P�b�g�戵���F�{���ܒ��ڑ吙���A�{���O���ڑ吙���A�t�z�ُ��X�A
�@�@���c��������A���c���E�فA�����̂̂�����A�˓c���X
�E���⍇���F�R�����v���c���E�ٌ������s�ψ������
�@�@TEL025-522-5202�@�S���F����������i�A�h�E�v�����g���j
�i2018/4/17�j
�y���w���99����i4��20���i���j�A�����Y�p��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www1.odn.ne.jp/~gakugeki...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��20���i���j
�@�ߌ�6��30���`8��30���i�\��j
���F�����|�p��w���y�w��5-301��
�@JR���^��J�w���� �k��10��
�@�n���S���w���ԓk��15���A���Éw���ԓk��10���@
�E�C�m�_���u�F�����i�̉��y�\���|�ߓc���𒆐S�Ɂv�]���݂�����
�E�ƏЉ�u�w�䉮�ܔԑg�T�x���߂����āv���S����������
�i2018/4/16�j
���{�����w��m��r������������i2018�N4��14���i�y�j�A�����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jstr.org/project...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��14���i�y�j�ߌ�3��15���`5��
�ꏊ�F�����w3����3F���c��
�@http://www.seijo.ac.jp/access/index.html
�@3���ق́A���傩�璆��ɐi��ō����̌����ł��B
�u���F�������ǁu��������̂ƌ����Ȃ����́v
�u���v�|�F�M���V�A�ߌ������ۂɂǂ̂悤�ɏ㉉���ꂽ���ɂ��Ă͔���Ȃ����Ƃ���������܂����A��{�I�ȃ��[���Ƃ��Č���̋�ԓI�����������Ƃ͊m�����Ǝv���܂��B���Ȃ킿�ϋq�����邱�Ƃ̂ł���̂̓R���X�̈ʒu����I���P�[�X�g���[�Ɣo�D�������o���肷��X�P�[�l�[�Ɍ����Ă����Ƃ������Ƃł��B���̊O�̐��E���ϋq�����邱�Ƃ͂ł��܂���B���̂��Ƃ͏������̂悤�Ɍ��ꂾ����}�̂Ƃ����W�������ƌ���I�ɈقȂ�_�ł��B���Ƃ���Ƃ����`���������Ȃ��M���V�A���ɂ����Ă͈�x��̐ݒ肪���܂�R���X���܂ތ����l���̌��鐢�E�Ɗϋq�̌��鐢�E�͊�{�I�ɓ���ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A���̋�ԓI����͌��t�ɂ���ĕ⊮����Ă��܂����B�����Œ��ڗ����܂�肪�������邱�Ƃ͖w�ǂ���܂���ł������A�g�҂̕Ƃ����`�ɂ�蕑��̊O�ŋN���������������t�ɂ���ĕ����̐l���Ɗϋq�ɓ`�����A�܂����䗠����̐��ɂ���ĊԐړI�Ɏ������Î������Ƃ�����������Ȃ��炸�p�����Ă��܂����B�������o�I�ł��낤�ƌ���I�ł��낤�Ɨ^��������͕���Ɗϋq�Ȃŋ��L�����Ƃ�����������������Ă����Ǝv���܂��B�������A���Ƃ��Č��t�ɂ���ĕ����ɂ��̑��݂��w������Ă���ɂ�������炸�ϋq�ɂ͌����Ȃ��ꍇ������܂��B���邢�͂܂��t�Ɋϋq�ɂ͎��o�I�Ɍ����Ă���ɂ�������炸�����̔o�D�ɂ͌����Ă��Ȃ��A���邢�͕ʗl�Ɍ����Ă���Ƃ����ݒ�̏ꍇ������܂��B����͂���Ӗ��ł͏�ɏq�ׂ��M���V�A���̏㉉��̊�{�I���[�������E���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B����͂��̓_�ɂ��Ă������̍�i�����グ�ċ�̓I�Ɍ������Ă݂����Ǝv���܂��B
�i2018/4/13�j
�������w���30�N�x4�����i2018�N4��21���i�y�j�A�ŋ���w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.bukkyoubun.jp/studies/2018.htm
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N4��21���i�y�j14���`17��35��
���F�ŋ���w ����L�����p�X1-418�i1����4�K�j
�@�@�@�i���s�s�k�掇��k�ԃm�V��96�j
�V���|�W�E���u�u�������̃Z�J���h�X�e�[�W�ցv
�J��̎��@���Z
������
�E��|�����E���\�ҏЉ�@�t�c�~��i����w�@��w�j
�E�u�����ƍu���F�w�@�ӗ֍u���x���N�_�Ƃ��āv�ĉ����T�i��t��w�j
�E�u��c�̏�y�M�ƕ����F�u���𒆐S�Ƃ��āv��~暁i���J��w�j
�E�u�w�_�_�u���x�Ɛ_�y�E�Օ����E�F�u�u�������̃Z�J���h�X�e�[�W�v�̂��߂Ɂv���D��i�ŋ���w��w�@���m����ے��j
�p�l���E�f�B�X�J�b�V�����@�i��E�t�c�~��
��̎��@�ΐ쓧�i�c��`�m��w�j
���e��i18���`�j �ŋ���w��1�H���i1���ْn��1�K�j
�i2018/4/12�j
����c��w�I�y���^���y��������4���������i��170��I�y��������j�i2018�N4��14���i�y�j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������������T�C�g�͂�����
http://www.waseda.jp/prj-opera-mt/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��14���i�y�j16��30���`17��30��
���F����c��w ����c�L�����p�X 3����
�@���L�����p�X�}�b�v�Fhttps://www.waseda.jp/top/access...
�@�����ƂȂ鋳����4��6���ȍ~��HP���ł��m�点�������܂��B
���e�F�I�y���^���y���̃L�[���[�Y�@��10��
���\�ҁF���F�M
��ځF���o�Ǝ��
�v�|�F�V�F���[���o�s���H�c�F�b�N�t�̍l�@��ʂ��āA�I�y����i�̉��o�Ƃ��̉��߂̕��@�ɂ��Ę_����B
���F����
�Q���\���݁F�ǂȂ��ł����Q�����������܂��B
�i2018/4/11�j
�R�L�E��蕨�������417����i2018�N4��29���i���j�A�R�w�@��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://gunki.sakura.ne.jp/katsudou.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��29���i���j13:00�`17:00�i�\��j
���F�R�w�@��w �R�L�����p�X
�@�����r���i������������E���j10�K��18��c��
��ʁFJR�R����A���}���A������̓�����a�J�w�
�@�{�v����ʂ̏o�����k����10��
�@�n���S��\�Q���w�B1�o�����k����5��
�q���\�ҁr
�E���R�M�ގ��u���d���̖@�����߂����āv
�E�H���ꌛ���u���ƒ��������Ɠ}�X�`�����n��Љ�̍\�����������ā`�v
�q�����ǂ��r
�E���ݕ��̏������o���܂���̂ŁA���萔�ł����e���ł��p�ӂ��������B
�E����ȊO�̕��i�����ҁE�w���j�̗��������}�������܂�
�E�I����A���e���\�肵�Ă���܂��B
�E���ł̔��\�҂��W���Ă��܂��B���\������]�̕��́A���ψ��܂ł��m�点�������B
�i2018/4/10�j
���������w�����ّ�12�㒆���n�挤�����N�`���[�V���[�Y������i2018�N4��20���i���j�A�������j�����w�����فj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.minpaku.ac.jp/research...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��20���i���j15�F00�`17�F00
�ꏊ�F���������w�����ف@��6�Z�~�i�[��
��ʌ��J�i�Q�������^�v���O�\���s�v�j
��ځF�q����Ƃ��Ă̎��\����C�����ɂ����鎍�l�W��̖�����
�ҁF�Z�g���b�N�E�}�k�[�L�A�[��
�@�@�i�}�b�M����w�C�X���[���w�������j
�g�p����F�p��i���ʖ�͂���܂���j
���₢���킹�Fkenjikuroda[at]idc.minpaku.ac.jp
�@���������w�����ٌ��㒆���n�挤�����_
�i2018/4/9�j
���m���y�w���x����70���ጤ����i2018�N6��9���i�y�j�A���ꌧ���|�p��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://tog.a.la9.jp/okinawa/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N6��9���i�y�j14:00�`16:00
�ꏊ�F���ꌧ���|�p��w �����L�����p�X�t�y���u�`��
�@�i�t�y���z�[��2�K�j�\��
�Q����F����E�����Ƃ��ɖ����i�\��s�v�j
�E�������\1 �������ށu��O�̉���ɂ�����{�y���~�x��̏����`����{������є��d�R�����ɂ��ā`�v
�E�������\2 ��Éx�q�u����̂��́E���̌p���ɂ��āv
�Вc�@�l���m���y�w���x��
��903-8602���ꌧ�ߔe�s������1-4
���ꌧ���|�p��w���y�w�� �����������C�t
TEL/FAX098-882-5016
�i2018/4/6�j
�Y�\�j������4�����i2018�N4��13���i���j�A�n�[�g�s�A���s�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://www5b.biglobe.ne.jp/~geinoshi/reikai.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��13���i���j18:00�`20:00
�ꏊ�F�n�[�g�s�A���s 3�K�����o��
�i�A�N�Z�X�Fhttp://heartpia-kyoto.jp/access/access.html�j
���\�ҁF�ђˌb���l��
���\�^�C�g���F�C���Ə����u�e���`�d�����v�ɂ���
�i2018/4/5�j
�w���y����w�x��47����2���i���{���y����w��A2018�N3���j
�w�p���ŐV���̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://���{���y����w��.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�q�����_���r
�E�u�\�̊w�K�v���O�����̊J���y�ю��H�F�{�錧���s��ђn��ɓ`���u�t�����v�̗w���j�Ƃ��āv�c���ɂ����@1
�E�u�����t��DVD�Đ����t�ɂ�鉹�y���掞�ɂ�����蔏�q�����̉�͔�r�v����L�q�@13
�E�u���������ɂ����鎙���Ԃ̊W���\�z�Ɍ��������y�����̑Ή��Ɋւ���l�@�F�X�y�C���E�����V�A�B�ɂ�����C���^�r���[������ʂ��āv�ˌ���@25
�E�u20���I�����̃h�C�c�ɂ�������{�̊w�Z���́FR.�����Q��G.�J�y�����ɂ����V�C��ҁw���w���́x��ꊪ�̖|��E�ҋȂɏœ_�Ăāv�B�{�M�q�@37
�q�_�l�r
�E�u�q�����ȉ��y�r�̎��H�I�T���F2�̃��[�N�V���b�v��ʂ��āv�������l�E���c���F�E�O�c�ꖾ�@49
�q���]�r
�E����_��w���؉��y����W�j�����F���{�l�̊؍��E���N�\�ۂƉ��y�x�i�ē��^�j57
�E��c�j���w�u�`�F���j�[30�ԁv�̔閧�F���K�Ȃ͐i������x�i�~����\�q�j59
ISSN:0289-6907
���s���F����30�N3��31��
���s���F���{���y����w��
�@�����ǁF�����s������s�{��5-38-10-206
�@TEL&FAX042-381-3562�@Mail:onkyoiku[at]remus.dti.ne.jp
�i2018/4/4�j
�w���y�w�x��63��2���i���{���y�w��A2018�N3���j
�w�p���ŐV���̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://www.musicology-japan.org/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�q�_���r
�E���q�D���q�u��q�Y�s���ό����ȁt�Ɓs��䶗������ȁt�̐����ߒ���r�F�uCampanology�����v�̕��͂𒆐S�Ɂv61
�E�R���^�G�q�u�w���}���E�V�F���w���ɂ��V���[�x���g���߁F�����s�̌��e�u�V���[�x���g�E�u�b�N�v���肪����Ɂv78
�E�i��ʑ��u19���I�㔼�̃p���E�I�y�����ɂ�����o���G���t�ҁF�t�����X���������ًy�уI�y�����}���ق̎����Ɍ�����ԁv94
�E���ہu�����O�s�s�A�m�E�f�B�X�^���X�t�̕��́F�\���̏����ƕs�m�萫�A�W�����E�P�[�W����̉e���v110
�E�������m���u���i�[�h�E�}�C���[�ƃj���[�E�~���[�W�R���W�[�̊W�ɂ��Ă̈�l�@�F�W���[�t�E�J�[�}���́w���y���n�l����x�ɂ�����u��]�v�Ƃ̔�r��ʂ��āv128
�q���]�E�Љ�r
�EToru Mitsui �� �wMade in Japan: Studies in Popular Music�x�i��{�����j143
�E�W���i�T���E�X�^�[�����A���썎�u�E���q�q���Y�E�J�����a��w�������Ă���ߋ��F�����Đ��Y�̕����I�N���x�A�J�����a�E���썎�u�E���c�T�咘�w�������f�B�A�j�x�i�n�ӗT�j145
�E���ؐ��i���w�I�y����20���I�F���̂܂����ցx�i������j149
�EOlivia Bloechl, Melanie Lowe, and Jeffrey Kallberg �ҁwRethinking Difference in Music Scholarship�x�i�����~�q�j151
�E�����r�Y���w��Z���I���{���R�[�h�Y�Ǝj�F�O���[�o����Ƃ̐i�U�Ǝs��̔��W�x�i�H�g�N���j153
�E������q���w�����O �����ȉƂ̏ё��x�i�F�J���q�j155
�EDavid Beach, Su Yin Mak �ҁwExplorations in Schenkerian Analysis�x�i���c�h�q�j157
�E�����Y�p��w�����}���يďC�w��O�����R�[�h���y�G���L�������x�i�����m��Y�j159
�E�X���q���w�I�y���b�^�̖��J���F�I�b�t�F���o�b�N�Ɠ��{�ߑ�x�i���쏇�q�j160
ISSN:0030-2597
���s���F����30�N3��15��
�ҏW�E���s�F���{���y�w��
�@�����s���c��ѓc��3-3-3�����r��303
�@TEL03-3288-5616
�i2018/4/3�j
���{���y�w����{�x����50���ጤ����i2018�N5��12���i�y�j�A�R�w�@��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://www.musicology-japan.org/east/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
���� : 2018�N5��12���i�y�j13�F30�`16�F30
�@���J�n���Ԃ��ʏ�ƈقȂ�܂��̂ŁA�����ӂ��������B
�ꏊ : �R�w�@��w�R�L�����p�X7����2�K720����
�i��F�ߐ{�P�F�i�R�w�@��w�j
���e�F�C�m�_�����\5��
�P�D�u���[�c�B�I�E�N�������e�B�́s�O���h�D�X�E�A�h�E�p���i�b�X���tOp.44�čl�F���y�ƁA���ƉƁA����҂Ƃ��Ă̊������猩�邻�́u���l���v�̈Ӗ��v���֎����i�����|�p��w��w�@�j
�Q�D�u�V���p���́s12�̃G�`���[�h�tOp.10�����Op.25�ɂ�����u�����v�F10�x�����ƈ�E�I�\���Ƃ̊W����v�э����i�����쉹�y��w��w�@�j
�R�D�u�����������ɂ������{�E���y�E�U�t�̑��ݍ�p�F�s�W�[���t�ɂ�����u�x��v�̗��`���Ƃ��̋�v�����o���}�i�����Y�p��w��w�@�j
�S�D�u�̌n�I���t���_�Ƃ��Ẵ��[�}���̃t���[�W���O���_�F�a���_�y�є��ߘ_�̓����v���Z�X�𒆐S�Ɂv�r��F��i�c��`�m��w��w�@�j
�T�D�u�o���g�[�N��ȁs�s�A�m�E�\�i�^�tBB88��3�y�͂̌����v�ؑ��D��i�����̐����q��w��w�@�j
�i2018/4/2�j
�����Y�p�w���34����i2018�N4��21���i�y�j�E22���i���j�A�ь����p�فj
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://ethno-arts.sakura.ne.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��21���i�y�j�E22���i���j
���F�ь����p�فi���R�s�k��ۂ̓�2-7-15�j
�@JR�V�������R�w�������
�@���d�o�X���d�����s �����O���ԓk��3��
�@�F��o�X���ˉw�O�s�E�l��_�s �����O���ԓk��3��
�@�s���d�ԓ��R�s �����ʉ��ԓk��7��
�e�[�}�F�����Y�p�Ɠ`���Y�\
�ߔN�A���`��Y�Ƃ��Đ��E��̂��ƂŒ��ڂ������`���Y�\�́A�e�X�̓Ǝ�����ۂ��A�X�̗l����ێ������܂ܘA�Ȃƌp������Ă��邪�A������Y�p�Ƃ��Ă̂������̎��Ⴉ��A�����I�E���j�I�E�Љ�I�R���e�N�X�g�̒��ő��������A���̌���ɂ�����Ӌ`�ɂ��čl�@����B
�q4��21���i�y�j�r
10:30�` ��t�J�n
11:00�`12:00 �e�[�}�֘A���\
�E�u�w�����S���`�����y�x�������p��Ɋւ���l�@�v�}�n�o���E�T�E�K�Q�����i���y�w�j
�E�u���m�������O���[�o���ȃA�[�g�V�[���ɖ|��v�����m�Y�i���y�j
13:00�`15:45 �V���|�W�E���u�\�y�ɂ�����`���̈Ӗ����l����v
�E��|���� �����O�i�����w�j
�E��u���u�ω��������Ă����\�F���̏����v�V�앶�Y�i�\�y�����j
�E��1�u�\�ʂ̉��O�F�l���̕ω��Ɗm���v���s�גj�i�\�ʑŁj
�E��2�u�]�ˎ���̑喼�̐����Ɣ\�F���R�ˎ�E�r�c�j���̎�������ƂɁv���e���i�|�\�j�j
�E��3�u�`��������Y�̕ۑ��Ɗ��p�F����̏�ł̈������܂߂����{�ɂ����铮���v�R�{���I�i���y�w�j
16:00�`16:30 ����
16:30�`16:40 ��15��ؑ��d�M�ܖ����Y�p�w�����
17:00�`17:30 ���ʌ���I �����_�y�i���H�_�y�琬��j
17:30�`18:00 ���ʌ���II ���y�i�����m�Y�j
�q4��22���i���j�r
9:30�` ��t�J�n
10:00�`11:00 �e�[�}�֘A���\
�E�u�����ԂƖ����F���{�E��p�E�؍��̊��������ʂ��āv���ёP���i�����ԕ����j�j
�E�u�������x�ƈ��q���F�`���|�\�Ɩ����Y�p�v���ʊG���q�i�|�p�w�j
11:00�`12:00 ��ʔ��\
�E�u���L�V�R��Z���E�B�`���[���Љ�S������ю��G�̕ϑJ�Ƃ��̖����v�R�X���l�i�����w�j
�E�u�D��Ƒ����̂��ƂȂ݂��`���u�����I���摜�v�E�A�e�}�����n��Z�������̎�����v�{�J�T�q�i�����j
13:00�`15:45 ��ʔ��\
�E�u�V���s���y�̌���I�ȓW�J�F�R���{���[�V������i�{���̌��ꂩ��v�ÎӖ��ߎq�i���y�w�j
�E�u��^���ۂƃg�D�ɕt����ꂽ��̂���O�����v�R�{�G�q�i���y�w�j
�E�u���B�[�_�w�L���X�g����x�ɂ�����G�N�t���V�X�F�ϗe�^�W�J����u���v�s�ׁv�㌎�đ��i�����\���_�v
�E�u�������ɂ�����u�C���h�v�\�ۂ̐����F���W�f�U�C�����߂����āv������G�i�f�U�C���_�j
�E�u���Ɣ��p���t���ƃV���[�E�B���h�[�����v�|���K�G�i�f�U�C���_�j
�^�c�g�D�F�ь����p�ف@�����Y�p�w���34������s�ψ���
��700-0823 ���R�s�k��ۂ̓�2-7-15
TEL086-223-1733�@FAX086-226-3089
E-mail: taniichi[at]hayashibara-museumofart.jp
�����s�ψ����F�J�ꏮ (�ь����p�ْ�)
���Q���v�̂� ������
�i2018/3/29�j
�w��z�����w�����I�v�x��37��2���i2018�N3���j
�{�w�����I�v�w��z�����w�����I�v�x�̍ŐV���i��37����2���j�����s����܂����B�{�R�[�X�����̋ʑ��̘_�e���f�ڂ���Ă��܂��B
�E�ʑ� ���u�s�����t�͂Ȃ��O������Ȃ̂� : ���ނƂ��Ă̎O�����̒����ɂ��āv�i�w��z�����w�����I�v�x��37��2���A2018�N3���A621-631�ŁAISSN:0915-8162�j
�����{�w�����}���ك��|�W�g�� ��ʂ��Ė{���̉{�����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��BPDF�t�@�C���ł̃_�E�����[�h���\�ł��B�i���|�W�g���Y���y�[�W�� �������j
�i2018/3/28�j
���m���y�w����{�x����103���ጤ����i2018�N4��7���i�y�j�A�����̐����q��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://tog.a.la9.jp/higashi/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��7���i�y�j14:00�`17:00
�ꏊ�F�����̐����q��w ���ʍu�`��2����102��
�@�A�N�Z�X�Fhttp://www.ocha.ac.jp/help/accessmap.html
�@�������Z�̍ۂ͐g���ؖ������������̏�A����������p���������B
�q���Ƙ_�����\�i����2�j�r
�P�D�u19���I�����̃A�C�������h�ɂ����郆�j�I���E�p�C�v�X�̉��t�FO'Farrell's Pocket Companion for the Irish or Union Pipes�̑������ɒ��ڂ��āv���ウ��q�i�����Y�p��w�j
�q�C�m�_�����\�i���̂Q�j�r
�Q�D�u�o���g�[�N��ȁs�s�A�m�E�\�i�^�tBB88 ��3�y�͂̌����v�ؑ��D��i�����̐����q��w��w�@�j
�R�D�u�F�����i�̉��y�\���F�ߓc���𒆐S�Ɂv�]���݂����i�����Y�p��w��w�@�j
�S�D�u1920�`30�N��̒����ɂ����鐼�m���y�o�ŁF�h���a�ƒ��؊y�Ђ𒆐S�Ɂv�A�ŗ�i�����Y�p��w��w�@�j
�T�D�u�]�˒����̎�w�҂ɂ�鉹�y�����ᔻ�Ɖ����h�q�v����D�q�i�����Y�p��w��w�@�j
�U�D�u���{�ɂ�����K�������̊����Ɋւ����l�@�F���̕ϑJ�ƌ��͂����ƂɁv���c�v���i�������y��w��w�@�j
�i��F���R �����q�i����������w���u�t�j
�i2018/3/23�j
���y���_�������22�����i2018�N4��14���i�y�j�A�������y��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
https://sites.google.com/site...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N4��14���i�y�j
�@13:30�`17:00���i13:10�`��t�J�n�j
���F�������y��w5����219����
�Q����F���\1,000�^�w��\500
(1) ���ËӁi�d�C�ʐM��w�j
�u�y�ȋL�q����MusicXML��p�����y�ȕ��͂̎������v
(2) �y�������i�������y��w�C�m�ے��j
�u�h�r���b�V�[�s�O�t�ȏW��t���q�͗t�r�̊y�ȕ��́v
(3) Fati Fehmiju�i�������y��w���m�ے��j
�u�R���s���[�^�[���y�ւ̃|���X�^�C���Y�������̉\���v
���\�҂̓s���ɂ��A���e���ꕔ�A�ύX�ɂȂ�ꍇ���������܂��B
���s���ȓ_���������܂�����A���[���܂��͓d�b�ɂāA����܂ł���������B
���₢���킹�F���y���_��������x����\ ����N��i����̂Ă�j
konno.tetsuya[at]kunitachi.ac.jp
�i2018/3/22�j
���{���y�w����x����122���ጤ����i2018�N3��31���i�y�j�A���m������w�E���m�����|�p��w�T�e���C�g�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://www.msj-chubu.org/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N3��31���i�y�j13:30�`16:30
�ꏊ�F���m������w�E���m�����|�p��w�T�e���C�g�L�����p�X
�@���m���Y�ƘJ���Z���^�[�@�E�C���N������15�K
�i���m�����É��s�����於�w4����4-38�j
�@http://www.winc-aichi.jp/
�y����t�H�[�����z
2017�N�x�̑��Ƙ_������ю��Z�n�C���_���i���m�O���ے��j�̏Љ�
������V�i���m�����|�p��w���y�w���j
�{�N�x�A���m�����|�p��w���y�w������щ��y�����Ȃɒ�o���ꂽ�_������A����4���Љ�܂��B�i�e�_���ɂ��ẮA���M�҂����\���܂��B�j
�q���Ƙ_���r
�E�A����Y�u�N�k�[�g�E�j�[�X�e�b�h�̍�����i�����F�����t����������i�𒆐S�Ɂv
�E�����D�ԁuG. Ph. �e���}���̃I�y�������F�n���u���O�ŏ㉉���ꂽ��i�̊y�ȕ��͂���̍l�@�v
�q���y���������C���_���r�i���m�O���ے��j
�E���⏮���i���Պy��̈�j�u�W�������t�B���b�v�E�����[�@�N�����T����i�����鑕�����̍l�@�F�����[�ɂ�鉹�y���_�̎��_����v
�E�����Ք��i���y��̈�j�u�H��琡�u�q���y�̂��߂̎O�y�́i�g���v�e�B�[�N�j�r�F����E�]�p�O��̔�r�v
�y�������\�z
1. ���m�_�����\�@���R��i���m�����|�p��w��w�@���y�����Ȕ��m����ے� ���y�핪��j�u�C���@���E���B�V���l�O���c�L�[�̌��y�l�d�t�Ȃɗp����ꂽ�l�����Z�@�\�l�����ɂ����@���̌`���v
2. ��엲�i����w�@��w���_�����j�u���y�w�ƃn�C�f�b�K�[�O��v
�i2018/3/19�j
���{�w�Z���y������H�w���12��k���x�����i2018�N3��25���i���j�A����s�ߍ]���𗬃v���U�j
�w��E������̏��ł��B
���w��HP�͂�����
http://www.jassmep.jp/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N3��25���i���j13:30�`16:20�i��t13:15�j
�ꏊ�F�ߍ]���𗬃v���U���C��1�i�ߍ]�������Ί�4F�j
�i����s����88�Ԓn�ATEL076-260-6722�j
�Q����F�����@���w��̉���łȂ��Ă����Q����������
�E13:30�`14:00�@�͋[����A�u����炵�����ɂ������y����`�ӏ܂ƕ\�����ւ�点�ā`�v���c�K�q�搶�i�ΐ쌧����s���c���w�Z�j
�E14:00�`14:25�@�������\B�u�`�����������ʂ��Ĉ琬�����������E�\�́v������q�搶�i�����w�������w�Z�j
�E14:25�`14:50�@�������\C�u�}�����o�A���T���u���́u���y�Â���v�̎��H�I�����`�C���^�[���b�L���O�̉��y�̎d�g�݂������ā`�v���c�T�q�搶�i�����w�������w�Z�j
�E14:50�`15:05�@�x�e
�E15:05�`15:30�@�������\D�u���k�̓���ł̉��y�̌��������ꂽ���Ɠ��e�̍\�z �`���w����ΏۂƂ����A���P�[�g���ʂ���`�v�|�V���Ⴓ��i�����w����w�����ȉ@���j
�E15:30�`15:55�@�������\E�u���w�Z�ɂ����鉹�y�n�D�ɒ��ڂ������Ƃ̈Ӌ`�Ɖ\���v�֓������搶�i���䌧�I�]�s�����H���w�Z�j
�E15:55�`16:20�@�������\E�u���y�ȋ���@�Ɋւ��錤���`�͋[���Ƃɑ���u�S���I���ʁv�Ɓu��b�I�Ȕ\�́E�m���v�Ƃ̔�r���`�v���]�w���搶�i���ő�w�j
���I����A�ߍ]�������ΊقPF �J�t�F�E�A���R�E�����J�[�g�Œ��b������܂��B
�i2018/3/17�j
��30��\�y�t�H�[�����i�\�y�w������j�u�ߑ�̉��\���(2)���܍l����u�O�n���\�v�v�i2018�N3��21���i���E�j�j�A�卂���w�Z�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://www.nohgakugakkai.cside.com/nohgakuforum.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N3��21���i���E�j�j13���`17���i�J��12��30���j
���F�卂���w�Z��u�`���i�_�ˎs����招��k��8-5-1�j
�@��JR�_�ː��u�Z�g�v�w���ԁ@���֓k����10��
�@����_�d�S�u����v�w���ԁ@�k�֓k����15��
�Q����F500�~�i������j�i�\�y�w�����͖����j
�@�����O�\�����ݕs�v�B�ǂȂ��ł����Q�������܂��B
�ߑ�ɓ���A���{�l�̊C�O�ڏZ���n�܂�ƁA�V���Ȓn��Ŕ\�y����������悤�ɂȂ�܂����B�C�O�̓��{�l�Љ�ł͈��D�҂��W�܂�A�n��ɂ���ẮA�\�y�t�ɂ�������\����̌��݂Ȃǂ��s���Ă��܂��B���ɁA����̏I��Ŏp���������u�O�n�v�₻�̎��ӂ̔\�y�E�ɂ��ẮA�ߔN�������i�W���A�V���Ȏ��_�ő��������@�^�����܂����܂��B����150�N���}�������N�A�u�O�n���\�v�𒆐S�ɁA�ߑ�ɂ�����C�O�ł̔\�y�����ɂ��čl�������Ǝv���܂��B
�E��1���F��u���u�u�O�n���\�v�Ƃ͉��������̂��F�������k���i�����F�j�̎���𒆐S�Ɂv�����������i�卂���w�Z���@�E���J��w���u�t�j
�E��2���F�u�ߑ㒆���ɂ�����\�y����F��C�E�k���E�V�ÁE���v�����a�����i���É����w�Z�E�����w�Z���@�j
�E�g�[�N�Z�b�V�����F�����������A�����a�����A�R�����e�C�^�[�G���~�����i��ˎR��w�������j�A�i��G�����O���i����w�y�����j
�⍇���F�卂���w�Z�i��\�jTEL078-411-7234�@�S���G�����i�Ȃ����܁j
�����L���[���ł����₢���킹������܂��B
�\�y�t�H�[������p�A�h���X�Fnohgaku_forum[at]zoho.com
�i2018/3/16�j
�s�s���������t�H�[�����u�q���̍��r�̕������H�\���f�B�A�ƕ\���v�i2018�N3��18���i���j�A���s����w�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/UCRC/archives/5398
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
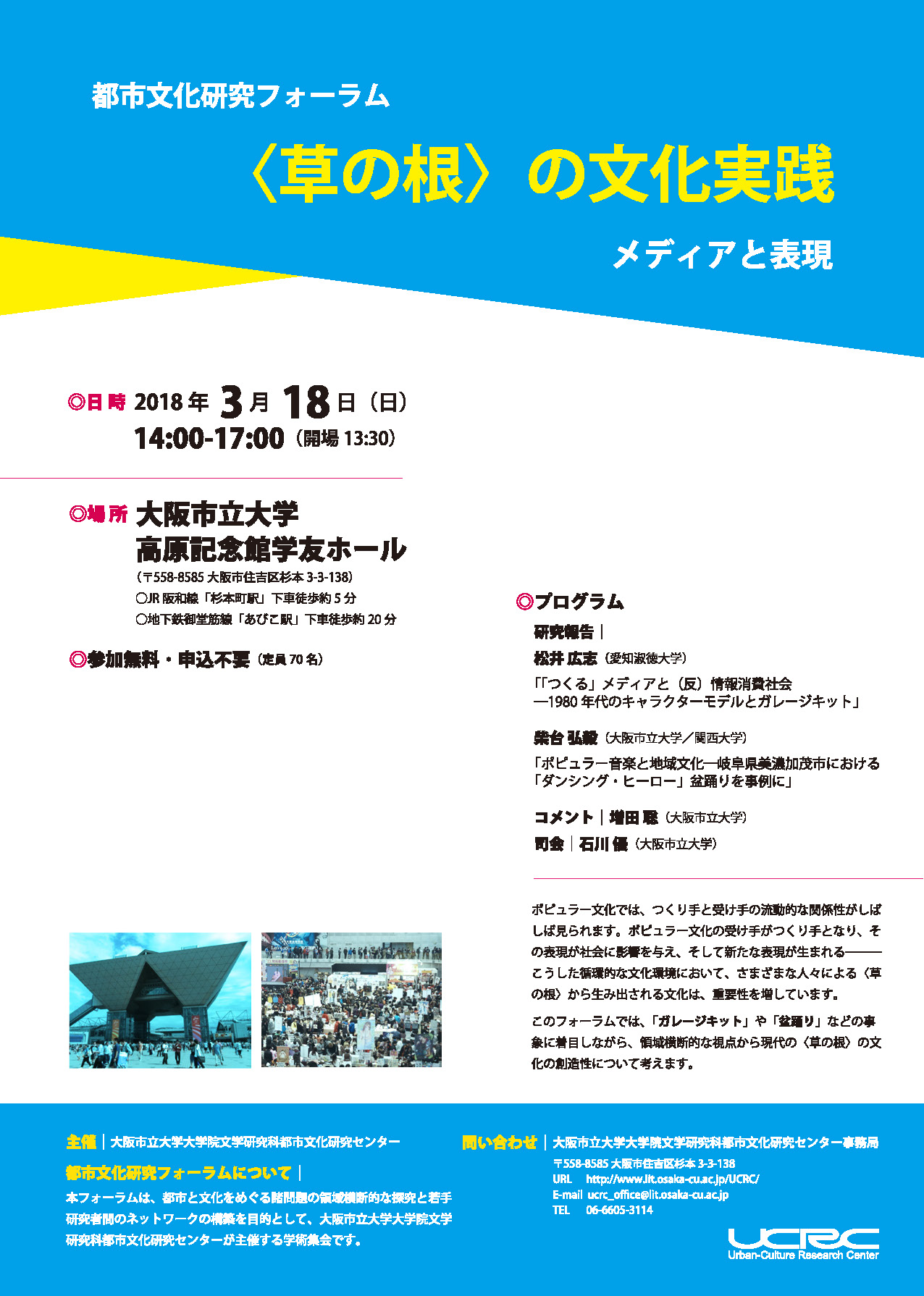
�J���F2018�N3��18���i���j14:00-17:00�i�J��13:30�j
���F���s����w�����L�O�يw�F�z�[��
�i��558-8585 ���s�Z�g�搙�{3-3-138�j
��JR��a���u���{���w�v���ԓk����5��
���n���S�䓰�ؐ��u���т��w�v���ԓk����20��
��ÁF���s����w��w�@���w�����ȓs�s���������Z���^�[
���Q�������E�\���s�v�i���70���j
�|�s�����[�����ł́A�����Ǝ�̗����I�ȊW���������Ό����܂��B�|�s�����[�����̎肪�����ƂȂ�A���̕\�����Љ�ɉe����^���A�����ĐV���ȕ\�������܂��\�\���������z�I�ȕ������ɂ����āA���܂��܂Ȑl�X�ɂ��q���̍��r���琶�ݏo����镶���́A�d�v���𑝂��Ă��܂��B���̃t�H�[�����ł́A�u�K���[�W�L�b�g�v��u�~�x��v�Ȃǂ̎��ۂɒ��ڂ��Ȃ���A�̈扡�f�I�Ȏ��_���猻��́q���̍��r�̕����̑n�����ɂ��čl���܂��B
�q�v���O�����r
�E�F����L�u�i���m�i����w�j�u�u����v���f�B�A�Ɓi���j������Љ�\1980�N��̃L�����N�^�[���f���ƃK���[�W�L�b�g�v
�E�F�đ�O�B�i���s����w�^����w�j�u�|�s�����[���y�ƒn�敶���\�����Z���Ύs�ɂ�����u�_���V���O�E�q�[���[�v�~�x�������Ɂv
�R�����g�F���c ���i���s����w�j
�i��F�ΐ� �D�i���s����w�j
�q�s�s���������t�H�[�����ɂ��ār
�{�t�H�[�����́A�s�s�ƕ������߂��鏔���̗̈扡�f�I�ȒT���Ǝ�茤���ҊԂ̃l�b�g���[�N�̍\�z��ړI�Ƃ��āA���s����w��w�@���w�����ȓs�s���������Z���^�[����Â���w�p�W��ł��B
�q���₢���킹�r
���s����w��w�@���w�����ȓs�s���������Z���^�[������
��558-8585 ���s�Z�g�搙�{3-3-138
E-mail�Fucrc_office[at]lit.osaka-cu.ac.jp
TEL06-6605-3114
�i2018/3/15�j
��z�����w�~��z������� ��5��t�̓��ʉ��y�u���i2018�N3��24���i�y�j�E25���i���j�A��z������فj
3��24���i�y�j��25���i���j�̓���ԁA���N���u��z�����w�~��z������كR���{��� �t�̓��ʉ��y�u���v���J�Â���܂��B
������{�R�[�X�̋������o���G�e�B�L���Ȋ����o�u����ق��A�w���L�u�ɂ��~�j�u�����s���܂��B���y�̊y���ݕ��ⓤ�m�����A�킩��₷���E���[�����`���ł���Ǝv���܂��B���z�����������B
��z�����w�~��z������كR���{���
��5��t�̓��ʉ��y�u��
����30�N3��24���i�y�j�A25���i���j
���F��z������فi�V������z�s�V����1-9-10�j
�u�`(1)�u���y�͉���\���ł���́H�v�i�u�t�F�㓡�O�j
3��24���i�y�j10:30�`12:00�@���z�[��
���y�́u�̎��v��u����v�ɗ��炸�ɁA����\���ł���̂ł��傤���B��ȉƂ��Ȃɍ��߂����Ƃ����t�Ƃ⒮����͂ǂ��܂ŗ����ł���̂ł��傤���B�l�X�ȋȂ��A��ȉƂ̌��t�����肪����ɂ��Ȃ���𖾂����݂܂��B
�u�`(2)�uF.�V���[�x���g��ȁs�~�̗��t�𗷂���v�i�u�t�F��쐳�l�j
3��24���i�y�j13:30�`15:00�@���z�[��
�F����ƂƂ��ɃV���[�x���g�s�~�̗��t�̐��E������Ȃ��炻�̖��͂ɔ���܂��B
�u�`(3)�u���ɍ�Ȃ�����Ƃ������Ɓ`�w�Z�ł̉��y�����Ǝ���ǂނ��Ɓ`�v�i�u�t�F���������Y�j
3��24���i�y�j15:30�`17:00�@���z�[��
�u���ɍ�Ȃ��邱�Ɓv�̒��ŁA�u���̈Ӗ��E���s�������ʂ��č�Ȃ��邱�Ɓv�ɁA���d�_��u���Ă��b�����܂��B���S�ɂȂ�̂́A�ؓ��n�̎��ɎO�P�W����Ȃ������̂ł��B�Ȃ͕��ՂŖ��邢�ł����A���̓lj��ɂ͉��s��������܂��B�w�Z�ł̉��y�����̏�����ؓ��n�̎������ʂ��Ă���Ƃ��������̂ŁA�����ɂ������炩�d�_��u�����ƍl���Ă��܂��B
�u�`(4)�u�s�A�m��i���猩�郍�x���g�E�V���[�}���v�i�u�t�F����r��j
3��25���i���j10:30�`12:30�@���z�[��
�h�C�c�E���}���h�̊���ƌ��Ȃ���Ă���V���[�}���́A�����̒i�K�ł̓s�A�m�Ȃ̑n��ɐ�S���A���X�̖��삪���܂�܂����B�V���[�}���̎v�z�ƃs�A�m��i�̊ւ��ɂ��ĒT���Ă��������Ǝv���܂��B
�u�`(5)�u���Ƌ�Y�̓`�����y�`�ߑ���{���y�j�́w�����x�`�v�i�u�t�F�ʑ����j
3��25���i���j13:30�`15:00�@���z�[��
�`�����y�̗��j�͋��̘A���ł����B���ɖ����`���a�̎���A�����鐼�m���y�̔g�ɗ����������ׂ����y�Ƃ����͕������܂����A���̉ߒ��ł́u���A����Ȃ��̂��c�H�v�Ƃ������m�����ݏo����邱�Ƃ��B�m��ꂴ����{���y�j�́u�����v�ɃX�|�b�g�āA�`�����y�̈ӊO�Ȉ�ʂ��Љ�܂��B
�u�`(6) ���ʍu�`�i�u�t�F��z�����w���y�R�[�X�w���L�u�j
3��25���i���j15:30�`17:00�@���z�[���i�\��j
�㋳�剹�y�R�[�X�̊w�����A�����̌����̐��ʂ����ă~�j�u������悵�܂��B���e�͌�����\�B���y���݂ɁI�@�����̍u���͖����ł��B
���w���u�`�̃^�C�g���Ɠ��e���ȉ��̂Ƃ��茈�܂�܂����B�i3/21�j
�u�`(6)�u�N�ł��ȒP�IiPad�ō�Ȃ��悤�v
�{�u���ł͑S����iPad��z�z��Garage Band�Ƃ����A�v�����g���āA�Q���҂̊F����ɉ��y�Â����̌����Ă��炢�܂��BApple Loops�Ƃ����A���炩���ߘ^�����ꂽ�t���[�Y��t����ׂĐ�\�肷�邱�ƂŁA���y�m���̂Ȃ����ł������x�̍�����i����邱�Ƃ��ł��܂�!! ���̋@��ɁA�w���B�ƈꏏ�ɉ��y�Â����̌����A�M�������̃I���W�i���Ȃ�����Ă݂܂��B
��u�`�P�b�g�F�e�u���F�e500�~�@5�u���Z�b�g���F2,000�~
�v���C�K�C�h�F���[�\���`�P�b�g�iL�R�[�h�F32097�j�A�Z�u���C���u��
��ÁE�₢���킹�F��z������ف@TEL025-522-8800
�i�x�ٓ�������9:00�`17:00�j
�i2018/3/5�j
���{�������y�w���7�����i2018�N3��24���i�y�j�A�������y��w�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://s-jfm.org/2018...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
��N���{�������y�̋��މ��̃e�[�}���͂��߁A��茤���҂̓�����̌������ʂ̔��\�̋@��Ƃ��Ē蒅���Ă܂���܂�����������̑�V��ڂ��A���镽���R�O�N�R���Q�S���i�y�j�ɉ��L�̗v�̂ŊJ�Â������܂��B����́A�����Ƃ��g�߂Ȗ������y�i���w�E�����|�\�j�ł���h�~�x��h��b��Ƃ��ď����邱�Ƃ��v�悵�Ă��܂��B�����̎Q�������҂����Ă��܂��B
�����G����30�N3��24���i�y�j
���ԁF13:30����17:30�i�\��j
���F�������y��w6����3�K301��
(��190-0004 �����s����s����5-5-1)
���X�P�W���[���F
�E13:00�`13:30�@��t
�E13:30�`13:40�@�J��i�����E�����ψ���ψ����j
�q��1���F�������\�r(�e���\20��+���^5��)
�E13:40�`14:05�@��c�T�u�����s�������w�Z�ɂ�����䂪���⋽�y�̓`�����y�̎�舵���ɂ���(������)�v
�E14:05�`14:30�@�� �i�u���E���w�Z�ɂ����鋽�y�̉��y�̎戵���\����DVD�̊J���\�v
�E14:30�`14:55�@�����֎q�u�n���K���[�̊w�Z����ɂ����Ė������y�͂ǂ̂悤�ɋ������Ă��邩�\�i�V���i���J���L�������Ɖ��y���ȏ��̕��͂�ʂ��ā\�v
�E14:55�`15:20�@�ؓ� ���u�n�}�I���v�_���Ɓ�������r�偄�̐����ƓW�J�\�K�ᕑ�ȁ��l�o���ʼn̂��镨���Ԃ́u���V���v�𒆐S�Ɂ\�v
�E15:20�`15:45�@���c�^�R���u���c�Ï͂ɂ��[�S�A���S�A���Ȃ̊y���o�łƂ��̈Ӌ`�ɂ��āv
�E15:45�`16:10�@�͐����G�u�n�����V�X�e����p�������{���w��ς̍̕��n��̉����v
�q��2���F���r
�E16:25�`16:50�@����h�u�~�x��̏�̓��̊|�������v
�q��3���F�f�B�X�J�b�V�����r
�E16:50�`17:30�@��1���A��2���܂��ĎQ���ґS���ɂ�铢�c
�E17:30�`�@��E�I��
�i���ɂă~�j���e��j
�Q����F����
�Q���\���F���{�������y�w����E�����ψ���i�S���j�ɖ�`��
E-mail:inoinoino[at]muc.biglobe.ne.jp
�i2018/3/4�j
�Y�\�j������3�����i2018�N3��9���i���j�A�n�[�g�s�A���s�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
http://www5b.biglobe.ne.jp/~geinoshi/reikai.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N3��9���i���j18���`20��
�ꏊ�F�n�[�g�s�A���s4�K��4��c��
�i���s�s������|�����ʉG�ۓ���������375�j
���\�ҁF���u�M�V��
���\�^�C�g���F���������ږx�̉̕��ꋻ�s�W�҂ɂ���
��4�����
�ђˌb���l���u�C���Ə����u�e���`�d�����v�ɂ��āv
2018�N4��13���i���j�n�[�g�s�A���s
�i2018/3/3�j
��z�����w��w�@�����C�����ɂ��ЂȂ܂�R���T�[�g�i2018�N3��3���i�y�j�A���c�����I�[�����v���U�j
�{�R�[�X��w�@���ƏC�����̏o�����鉉�t��̂��ē��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/auren-plaza...
http://hand-shake.jp/event/2018/03...
https://chiharu-rosina.jimdo.com/schedules/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N3��3���i�y�j�ߌ�2��00���`�i�ߌ�1��30���J��j
�ꏊ�F���c�����I�[�����v���U �X�^�W�I�i��z�s�{�钬8��1���j
���ꗿ�F1,000�~�i�������z�j
�q�v���O�����E�o���r
�E��c���g�i�s�A�m�E�@1�j
���t�}�j�m�t 10�̑O�t��Op.23���i���t�}�j�m�t�j
�E���g�O�Ɓi�s�A�m�E�@1�j
���z�ȁu�����炳����v�i����N�O�Y�j
�o���[�h��1��Op.23�i�V���p���j
�E���V���i�T�N�\�t�H���E�@1�j
�T�N�\�t�H�����t�ȁi�O���Y�m�t�j
�E���c����i�\�v���m�E�@3�j
�u�����牡���傤�v�i�ʋ{��Y�j
��̌��s��������t�i�V���g���E�XII�j���
�g��ݗl�A�M���̂悤�Ȃ����́h�ق�
�E�Έ�G��i�s�A�m�E�@2�j
�s�A�m�ȏW�s�����̒�����i����j�t�i�㓡�O�j���
�u�ᖾ����v�ق�������
�E�������͂邩�i�I�[�{�G�E�@3�j
�s3�̃��}���X�t����2�ԁi�V���[�}���j �ق�
�E���X��t�i���]�\�v���m�E�C�����j
�u�����Ȃ��v�i���c�O�Y�j
�̌��s�T���\���ƃf�����t�i�T�����T�[���X�j���
�g���Ȃ��̐��ɂ킽���̐S�͉ԊJ���h�ق�
�����t�Ȃ͕ύX�ɂȂ�ꍇ���������܂��B���炩���߂��������������B
�v���C�K�C�h�F�I�[�����v���U�A��z������فA��t�y��
�`�P�b�g���\���⍇���F���y�G���낶�ȍH�[
�@TEL080-5447-4204�@Mail:chiharu.rosina[at]gmail.com
�i2018/3/2�j
���w������317�����\��i2018�N3��17���i�y�j�A�L����w�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
http://www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N3��17���i�y�j�ߌ�1��30�����
�ꏊ�F�L����w���L���L�����p�X�w�m���2�K���Z�v�V�����z�[��
���u�w�m��فv�́A�Ԃǂ��r�k���A�T�^�P�������A���z�[���ׂ̗�A�Ŋ�o�X��iJR�����w���j�́u�L�咆�����v�ł��B
https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/higashihiroshima
�EJR�����w�i�R�z�{���j���A�o�X�u�L����w�v�s�A��20���i280�~�j�A�^�N�V�[��15���B
�EJR���L���w�i�R�z�V�����j���A�o�X�u�L����w�v�s�A��15���B
���V�����w����̃o�X�{���͑�������܂���B�����ӂ��������B
�E�L����`�A�R�z�����ԓ��𗘗p����B
�����\�̏ڍׂ́A��L�̍L����w�z�[���y�[�W�����Q�Ƃ��������B
�q�������\�r
�u�������̓��{�ɂ�����q�l�`�r�ς̕��w���\����������p�����Č����\�v�����L�V��i�L����w�j
�q���ԍZ���E�V���|�W�E���r
�u�l�`���邢�̓q�g�K�^�ianthropomorphos�j�̖��́\�l�`�E�����E�t�B�M���A���̋��E���z���ā\�v
�p�l���X�g�F���їm�i���u�Б�w�j�A�{�c��u�q�i���������w�j�A���쏇�q�i���|�p��w�j
�i��F�؍F�v�i�L����w�j
����ʂ̕��̌䗈�������R�ł��i�Q����s�v�j�B
���w��������
��606�]8501�@���s�s������g�c��{����
���s��w��w�@�l�ԁE���w�����ȉ��c���i��������
E-mail: w-office[at]bigakukai.jp
�i2018/3/1�j
���{���q��w���w������w�����Ȋw�p�𗬊��V���|�W�E������S�ɂ����鎂�q���F��̌n����i2018�N3��13���i�j�A���{���q��w�ڔ��L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
www.jwu.ac.jp/unv/faculty_department/humanities...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
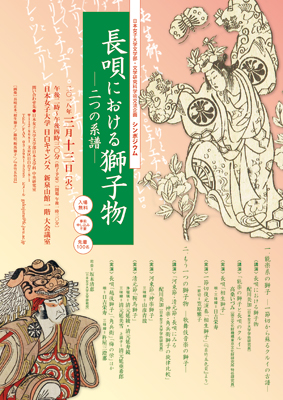
�����F����30�i2018�j�N3��13���i�j
�@14�F00�`16�F30�i�J��F13:30�j
���F���{���q��w �ڔ��L�����p�X �V��R�و�K���c��
�����ꖳ���E���O�\�����ݕs�v�E�撅100��
1.�\�y�n�̎��q�F��ߐ���h��N���C�̌Õ�
�E�u���u���S�ɂ����鎂�q���v�z������i���{���q��w�w�p�������j
�E�u���u�\�y�̎��q�ƒ��S�̃N���C�v���K���Â݁i�����������@�\�������������������C�������j
�E���� ���S�u�������q�v�S�E�O�����F���g�h��
�E���� ��ߐؕ������t�u�������q�v�i�w���|�ܐF�L�x���j��ߐF�}����q
2.������̎��q���F�̕��ꉹ�y�̎��q
�E�u���u�͓��߁E�����߁E���S�ɂ݂�_�y�E�p���q���q�̐�����r�v�z������i���{���q��w�w�p�������j
�E���� �͓��߁u�_�y���q�v�O�����F�R�F�g
�E���� �����߁u�Ɣn���q�v��ڗ��F���������E�����������A�O�����F����������A�㒲�q�F����������Y
�E���� ���S�u�z�㎂�q�v�u�p���q�v�u�~�̉h�v�ق� �S�F���g�h���A�O�����F�n���O����
�i��F��{���b�m���{���q��w���w�������n
���₢���킹��F
���{���q��w���w�����{���w�Ȓ���������
��112-8681�����s������ڔ���2-8-1
TEL/FAX03-5981-3522�@E-mail�Fgakujutu[at]fc.jwu.ac.jp
�i2018/2/27�j
��20��\�y�Z�~�i�[ �V���|�W�E���u�ȐS�`�S�E�Ȑg�`�g�F�u���U��`���郏�U�v�Ƃ͉����H�v�i2018�N3��12���i���j�A�@����w�s���J�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://kyoten-nohken.ws.hosei.ac.jp/info...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
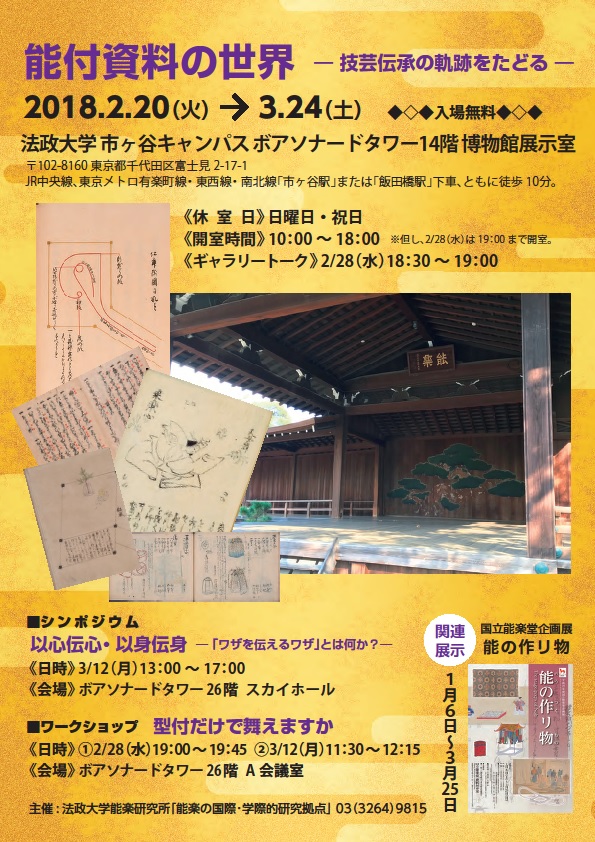
�u�\�̋Z�|�`���v��傫�ȃe�[�}�ɁA�V���|�W�E���Ǝ����W���A���[�N�V���b�v���v�悵�܂����B�g�̌|�p�ł���\�́A�ǂ�Ȗ��l��肪�����Ă��A�`�Ƃ��Ďc�邱�Ƃ͂���܂���B�������Ă͏����Ă������G�Ȑg�̏����A�������琶�܂�錾���Ɍ����ʖ��͂́A���������ǂ̂悤�ɓ`������Ă����̂ł��傤���B
�����W���ł́A����₻�̃^�C�~���O���������߂��^�t�A���q�e�p�[�g�̕��ł��隒�q�t�A�ȗ��ȕ��䑕�u�ł���샊���̐��@���L�����샊���t���X�̌Î����̂ق��A�G�}�E�ʐ^�E���擙�A�\�̕�������`���邽�߂ɍH�v���ꂽ�ߑ�ȍ~�̃��f�B�A���Љ�܂��B
�V���|�W�E���ł́A�����������܂��܂Ȏ����ɂ��ď������`���̗l�Ԃ��T�ς���ƂƂ��ɁA���ۂ̌m�Â̏�ɂ�����w���̏o�����E�~�ߕ��A�w���ɂ��ǂ��u��B�v���邩�ȂǁA�t��Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̖����l���܂��B�܂��A���[�N�V���b�v�ł́A�^�t�⑫���}�Ȃǂ̏��łǂ̂��炢������̂��A�t���̎w���ŕ����ꍇ�Ƃ̈Ⴂ�������Ă݂����Ǝv���܂��B
�����F3��12���i���j13�F00�`17�F00
���F�@����w�s���J�L�����p�X �{�A�\�i�[�h�^���[26�K�X�J�C�z�[��
���\���s�v�E���ꖳ��
�E�P�u�\�̋Z�|�`���F��|���������˂āv�R����q�i�@����w�\�y�����������j
�E�Q�u������������ߓ`����Z�p�F�^�t�̋@�\���l����v�[�V��]�i�@����w��w�@���m����ے��j
�E�R�u�Z�|�`���ɂ����邱�ƂƐg�́F�f�l�m�ẪR�~���j�P�[�V�����͂���v���R���Y�i�Ռ��w�����q��w�y�����j
�E�S�u�q�ϓI�ȓ��앪�͂���݂����U�`�B�̗v���i�哇���m�Ẫf�[�^�܂��āj�v�їe�s�i�@����w���w���S���w�ȍu�t�j
�E�T�u���l�̌m�ÁE�f�l�̌m�Áv�哇�P�v�i�V�e���쑽���\�y�t�j�A������@�R����q
�E�U�@�S�̓��_
���: �@����w�\�y�������u�\�y�̍��ۥ�w�ۓI�������_�v
���₢���킹��F�@����w�\�y������
�@��102-8160 �����s���c��x�m��2-17-1
�@TEL03-3264-9815�@FAX03-3264-9607
�i2018/2/26�j
�u��l�̂��߂̕��m�����͂��߂��A���̍��̂��b���B�\�ޗNJG�{�w�ی�����x�w��������x�ƕ��ȁ\�v�i2018�N3��1���i�j�A�������s�������݃z�[���j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
www.nishogakusha-u.ac.jp/news...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
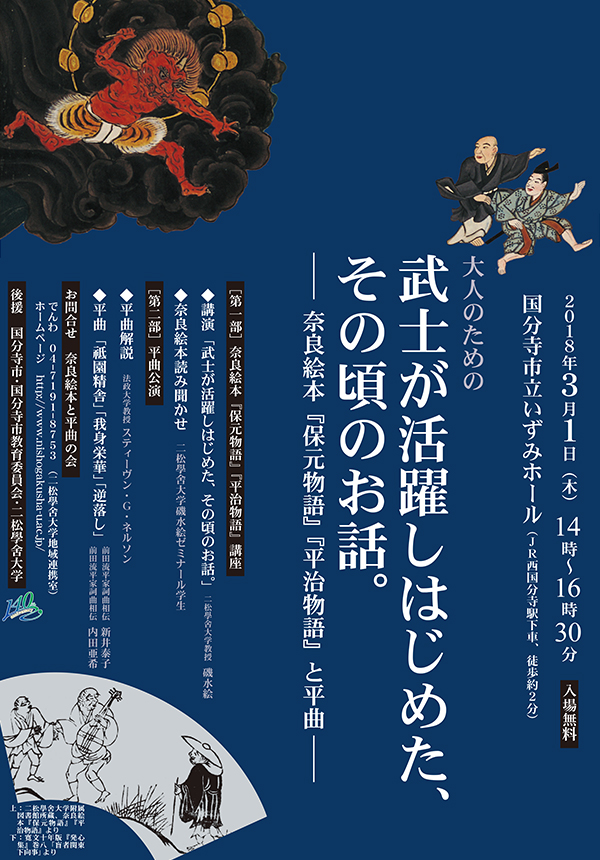
�����F2018�N3��1���i�j14:00�`16:30
���F�������s�������݃z�[���iJR���������w���k����2���j
���\���s�v�E���ꖳ��
��ꕔ�@�ޗNJG�{�w�ی�����x�w��������x�u��
�E�u���u���m�����͂��߂��A���̍��̂��b�B�v
�@�{�q��w���w������ �鐅�G
�E�ޗNJG�{�ǂݕ�����
�@�{�q��w�鐅�G�[�~�i�[���w��
��@���Ȍ���
�E���ȉ��
�@�@����w���� �X�e�B�[�����EG�E�l���\��
�E���ȁu�_�����Ɂv�u��g�h�v�u�t�����v
�@�O�c�����Ǝ��ȑ��`�@�V��q�E���c���G
��ÁF�ޗNJG�{�ƕ��Ȃ̉�i�{�q��w�㉇�j
���₢���킹��:�{�q��w�n��A�g��
�@TEL04-7191-8753
�i2018/2/25�j
�V���|�W�E���u���{�I������ԂƂ͉����v�i2018�N3��10���i�y�j�A�����|�p����j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
http://www.saitama-u.ac.jp/seminar...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
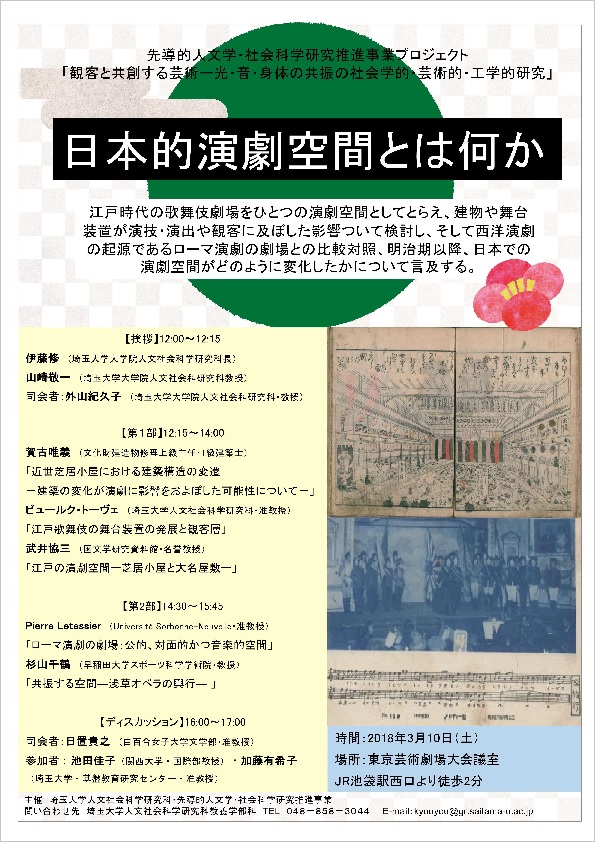
�]�ˎ���̉̕��ꌀ����ЂƂ̉�����ԂƂ��ĂƂ炦�A�����║�䑕�u�����Z�E���o��ϋq�ɋy�ڂ����e���ɂ��Č������A�����Đ��m�����̋N���ł��郍�[�}�����̌���Ƃ̔�r�ΏƁA�������ȍ~�A���{�ł̉�����Ԃ��ǂ̂悤�ɕω��������ɂ��Č��y����B
�����F3��10���i�y�j12:00�`17:00
�ꏊ�F�����|�p������c���iJR�r�܉w�������k��2���j
�ΏہF�ǂȂ��ł��Q���ł��܂�
���A�@12:00�`12:15
�E�ɓ��C�i��ʑ�w��w�@�l���Љ�Ȍ����Ȓ��j
�E�R��h��i��ʑ�w��w�@�l���Љ�Ȍ����ȋ����j
�E�i��ҁF�O�R�I�v�q�i��ʑ�w��w�@�l���Љ�Ȍ����ȋ����j
��ꕔ�@12:15�`14:00
�E��×B�`�i�������������C���㋉��C�E1�����z�m�j�u�ߐ��ŋ������ɂ����錚�z�\���̕ϑJ�F���z�̕ω��������ɉe��������ڂ����\���ɂ��āv
�E�r���[���N�E�g�[���F�i��ʑ�w��w�@�l���Љ�Ȋw�����ȏy�����j�u�]�ˉ̕���̕��䑕�u�̔��W�Ɗϋq�w�v
�E����e�O�i�����w���������ٖ��_�����j�u�]�˂̉�����ԁF�ŋ������Ƒ喼���~�v
��@14:30�`15:45
�EPierre Letessier (Universite Sorbonne-Nouvelle �y�����j�u���[�}�����̌���F���I�A�ΖʓI�����y�I��ԁv
�E���R��߁i����c��w�X�|�[�c�Ȋw�w�p�@�����j�u���U�����ԁF�I�y���̋��s�v
�f�B�X�J�b�V�����@16:00�`17:00
�E�i��ҁF���u�M�V�i���S�����q��w���w���y�����j
�E�Q���ҁF�r�c���q�i����w���ە������j�A�����L��q�i��ʑ�w��Ջ��猤���Z���^�[�y�����j
�₢���킹��F��ʑ�w�l���Љ�Ȋw�����ȋ��{�w���W
TEL048-858-3044�@E-mail:kyouyou[at]gr.saitama-u.ac.jp
�i2018/2/21�j
�V���|�W�E���u�n��n����₢�����F�n��n���w�̊m���Ɍ����āv�i2018�N3��3���i�y�j�A�k��B�s����w�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
https://www.kitakyu-u.ac.jp/events/detail/3619.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
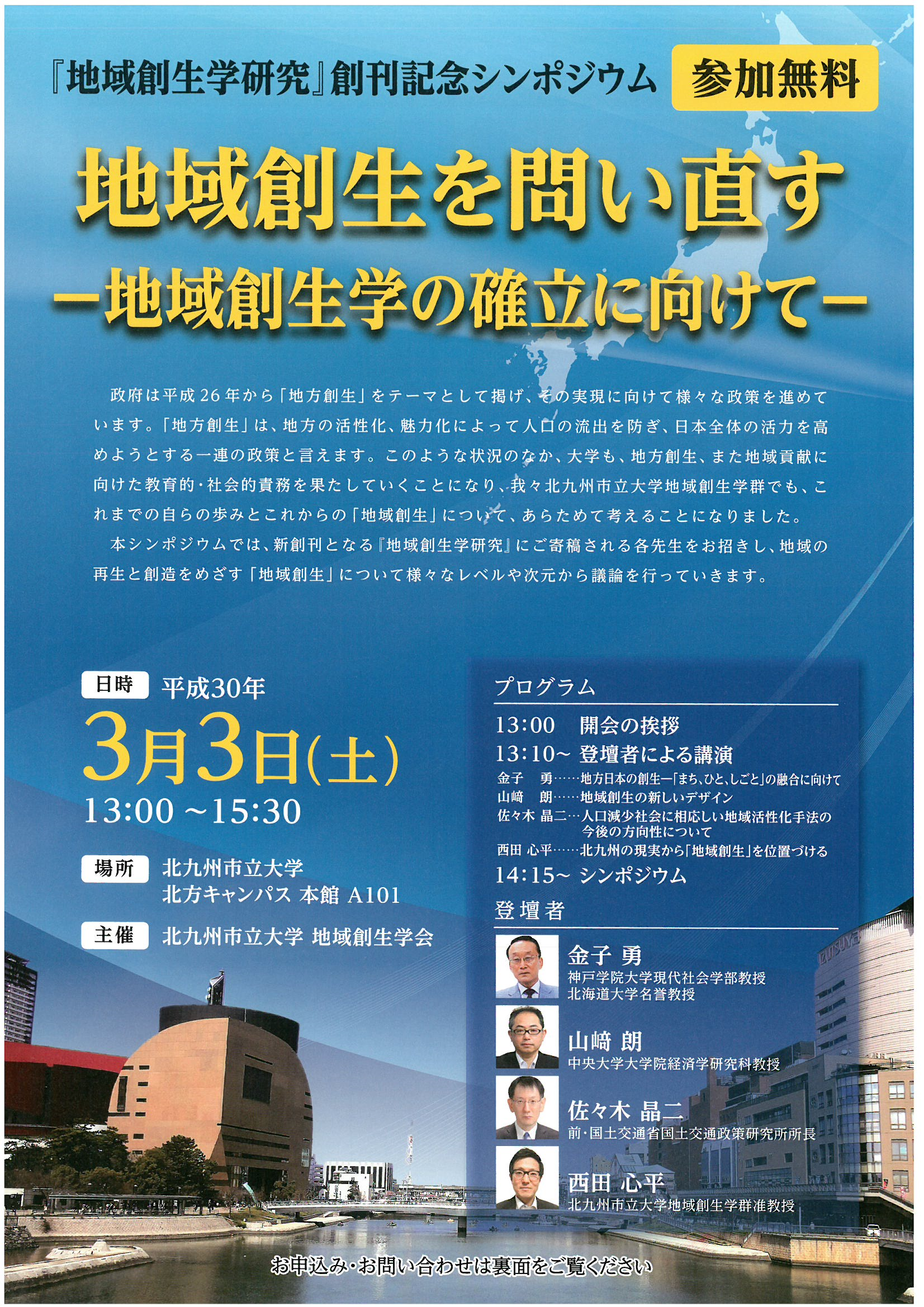
���{�͕���26�N����u�n���n���v���e�[�}�Ƃ��Čf���A���̎����Ɍ����ėl�X�Ȑ����i�߂Ă��܂��B�u�n���n���v�́A�n���̊������A���͉��ɂ���Đl���̗��o��h���A���{�S�̂̊��͂����߂悤�Ƃ����A�̐���ƌ����܂��B���̂悤�ȏ̂Ȃ��A��w���A�n���n���A�܂��n��v���Ɍ���������I�E�Љ�I�Ӗ����ʂ����Ă������ƂɂȂ�A��X�k��B�s����w�n��n���w�Q�ł��A����܂ł̎���̕��݂Ƃ��ꂩ��́u�n��n���v�ɂ��āA���炽�߂čl���邱�ƂɂȂ�܂����B�{�V���|�W�E���ł́A�V�n���ƂȂ�w�n��n���w�����x�ɂ���e����鏑���搶�����������A�n��̍Đ��Ƒn����ڎw���u�n��n���v�ɂ��ėl�X�ȃ��x���⎟������c�_���s���Ă����܂��B
�����F����30�N3��3���i�y�j13�F00�`15�F30
�ꏊ�F�k��B�s����w�@�k���L�����p�X�{��A-101
�Q����F����
�q�v���O�����r
13:00 �J��̈��A
13:10�` �o�d�҂ɂ��u��
�E�_�ˊw�@��w����Љ�w������ ���q�E���u�n�����{�̑n���F�u�܂��A�ЂƁA�����Ɓv�̗Z���Ɍ����āv
�E������w��w�@�o�ϊw�����ȋ��� �R���N���u�n��n���̐V�����f�U�C���v
�E�O�E���y��ʏȍ��y��ʐ��������� ���X�؏��u�l�������Љ�ɑ��������n�抈������@�̍���̕������ɂ��āv
�E�k��B�s����w�n��n���w�Q�y���� ���c�S���u�k��B�̌�������u�n��n���v���ʒu�Â���v
14:15�` �V���|�W�E��
���O���\�����݁F e-mail��������FAX�Łi�P�j�����O�A�i�Q�j�����A�i�R�j�A����������肭�������B�q���\���݁Y�F2��28���i���j�܂Łr�������̂��Q�����\�ł����A�Q���ґ����̏ꍇ�͂��\���݂̕���D�悳���Ă��������܂��B
�E���[���A�h���X�@rd-siryou[at]kitakyu-u.ac.jp
�EFAX093-964-4085
�i2018/2/20�j
���{���y����w���29�N�x���k�n����i2018�N3��10���i�y�j�A�X���̐��Z����w�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
http://���{���y����w��.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N3��10���i�y�j14:00�`18:00
���F�X���̐��Z����w3109����
�q�������\�r
�P�u���y�Ȃɂ����鐫�I�}�C�m���e�B�ɔz���������������F������ �ւ̃C���^�r���[��������v�O�ڑ�i�{�鋳���w4�N�j
�Q�u���o��Q���ɂ�����q�������Ɓr����ՂƂ������y����v�O�菃�b�i�O�O��w��w�@����w������1�N�j
�R�u�N�w�ւ̉���F���y����ɂ����錾�t�̈Ӌ`(����)�v�O�c�ꖾ�i�O�O��w��w�@�n��Љ���Ȍ�����m�ے��j
�S�u�|�p����̃G�R���W�[�F���ݍ�p�iinteraction�j������� �icorrespondence�j�ցv�������l�i�O�O��w��w�@�n��Љ���Ȍ�����m�ے��j
�T�u���ʎx���w�Z�̉��y�����̉ۑ�Ƃ��̉����Ɍ��������Ǝ��H�̕v���}�m���i�O�O��w����w���������ʎx���w�Z�E�O�O��w��w�@�n ��Љ���Ȍ�����m�ے��j
�U�u���y����̔ފ݂ւ̂܂Ȃ���(��) �F���y���炪����邱�ƁC �����邱�Ɓv�������i�����w�|��w�A����w�@���m�ے��j
�q�g�[�N�E�Z�b�V�����r
�V �Q���҂ɂ�鉹�y������l���鎞��
�����I����C���e����J�Â��܂��̂ő������Q�����������B
���₢���킹��F
��030-0961 �X�s�Q��2-6-32
�X���̐��Z����w ��t�C��
TEL017-741-0123�i�����j
E-mail�Fshuchiba[at]aomori-akenohoshi.ac.jp
�i2018/2/19�j
�w�u�v�l�́v��������{���F��z�����w����̒�3�x�i2018�N1���A��z�����w�o�ʼn�j

���ҁF��z�����w��
���s�F��z�����w�o�ʼn�
�����F�i�c����i���j�o�ŕ�
���s���F����30�N1��31��
�艿�F�{��2,000�~�{��
ISBN�F978-4-9906685-9-4
�{���́A�������k�́u�v�l�́v���琬���邽�߁A�{�w�ł͂ǂ̂悤�Ȏ��Ƃ��s���A�w�������������A���E�ɏA���w���ɐg�ɂ������悤�Ƃ��Ă���̂��A���̋�����H�̎p��{�w�������ʂɏЉ�A���H���|�[�g�̌`�ł܂Ƃ߂����̂ł���B(��)�{�w�́A�����Ƃ��Ă̐�含�̍��x�������߂��鍡���A�䂪���̋����{���̒��S�I�Ȗ������ʂ����ׂ��A�����{���@�\�𒅎��ɍ��߁A�䂪���̊w�Z����S�̂̎��̌�������[�h���Ă��������ƍl���Ă���B�������k�́u�v�l�́v����Ă邽�߂̎w�������������ƂȂ�w���ɏC�������悤�Ƃ���{���H���܂��A�����Ƃ��Ă̐�含�̍��x����}��A�����{���@�\�����߂邽�߂̈����Ƃ��Ď��{�������̂ł���B�i�u�܂������v���j
������A���A���J�삪���y�Ȃ̐߂̎��M��S�����Ă��܂��B�i��1�́u�e���ȁE����v�j
15. �u21���I���������߂̔\�́v�́u�v�l�́v���琬����̏�����F�C�^���A�ÓT�̋ȁsSebben, crudele�t�i���Ƃ���Ȃ��Ƃ��j�̎��H����i��쐳�l�j
16. �u21���I���������߂̎����E�\�́v�́u�v�l�́v���琬����C���[�W�`���F���w�Z2�N���̉��y�Ɓu���ڂ���v�i�K���قȂݍ쎌�^���V�g����ȁj�̎��Ǝ��H���Ɂv�i����S�i�j
17. �u21���I���������߂̔\�́v�̎v�l�́v���琬�����y����F���t�̎w���ɑ���w�����H���Ɂv�i���J�쐳�K�j
�w�����@�F�t�z�ُ��X�iTEL025-525-2530�j�A��z�����w���X�iTEL025-521-3644�j�A�i�c����iTEL025-523-4452�j�A�y��Amazon�ōw���ł��܂��B
�i2018/2/16�j
���w������29�N�x��5����i2018�N3��3���i�y�j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
http://www.bigakukai.jp/activity...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N3��3���i�y�j14��30���`16��30��
�ꏊ�F����c��w����c�L�����p�X26���فi��G�^���[�j1102����
�@�V�h�搼����c1-6-1
�@�������g���������E����c�w���ԓk��5��
�@�s�o�X�w02�i�w�o�X�j���c�n��w���� ���吳�剺�Ԃ���
���ꏊ���A��N�ƈقȂ�A�ˎR�L�����p�X�ł͂Ȃ����߂��C��t���������B����c��w����c�L�����p�X����킫�A��G�u�������̃^���[�ɂ��鋳���ł��B
�������\�F
�E�����V�i�����w�j�u�v������l�ԁ\�\ �W�����W���E�f�E�L���R�s�q�ǂ��̔]�t�̔h����i�ɂ��āv
�i��F���j�q�i����c��w�j
�E����q�q�i�k����w�j�u�t�����X�I�a���a���̈�f�ʁ\�w�����L���[���E�~���W�J���x1905�N�n������ǂ݉����v
�i��F��p��i�����w�j
�i2018/2/15�j
���c����\�v���m�E���T�C�^���i2018�N2��24���i�y�j�A���c�����I�[�����v���U�j
�{�R�[�X��w�@���ɂ�鉉�t��̂��ē��ł��B
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
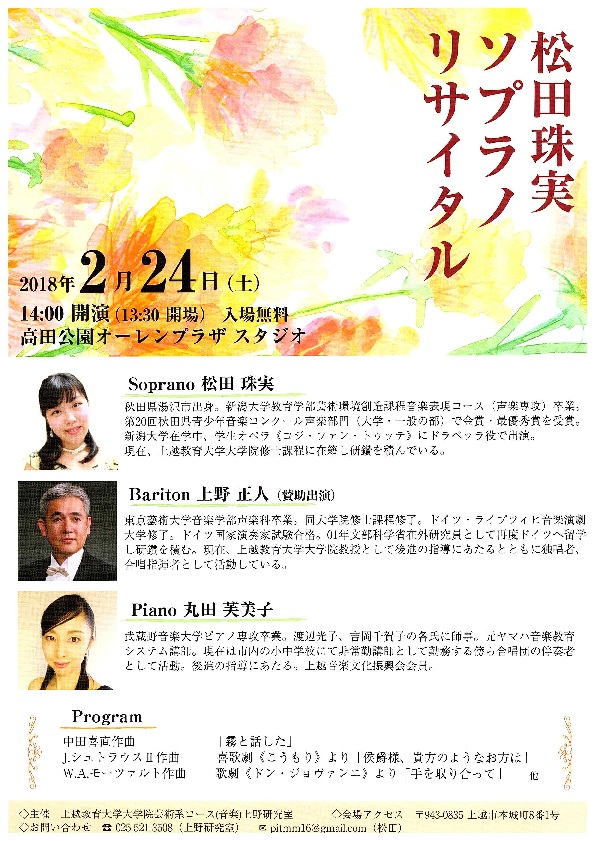
�����F2018�N2��24���i�y�j�ߌ�2��00���`�i�ߌ�1��30���J��j
�ꏊ�F���c�����I�[�����v���U �X�^�W�I�i��z�s�{�钬8��1���j
�@�����ꖳ��
�EProgram:
���c�쒼�u���Ƙb�����v
J.�V���g���E�XII ��̌��s��������t���u��ݗl�A�M���̂悤�Ȃ����́v
W.A.���[�c�@���g �̌��s�h���E�W�����@���j�t���u�����荇���āv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�E�o���F
���c����iSoprano�j
��쐳�l�iBariton�j���^���o��
�ۓc�����q�iPiano�j
��ÁF��z�����w��w�@�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j
���⍇���FTEL025-521-3508�i��쌤�����j�A
�@pitmm16[at]gmail.com�i���c�j
�i2018/2/14�j
������w�����Ȋw�������t�H�[���� ���J�����u����u���C�n���̌|�\�ƕ����F�r��Ƃ��̎��Ӂv�i3��10���i�y�j�A������w���É��L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
����Î҃T�C�g�͂�����
https://www.chukyo-u.ac.jp/research/ics/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N3��10���i�y�j13:30�`17:00
���F������w���}�e�z�[�� �����L�����p�X0����2�K
�i�n���S������E���ߐ��u�����v�w���ԁA5�ԏo������k��1���j
�E�u���É��r��Ƃ��̎��Ӂv
�u�t�F�[�J�厁�i����c��w���������ُ��ٌ������A������w�����Ȋw�������y�����j
�E�u���m�̍Ղ�ƌ|�\�v
�u�t�F�S���G�����i�����|�\�����ƁA������w���w�����u�t�j
�₢���킹��F
������w�����Ȋw�������@TEL052-835-7111�i��2142�j
�T�|�[�g�E�v���X�����ǁ@TEL090-9209-0385
�i2018/2/13�j
���{�w�Z����w����J������u2030�N�̊w�Z��������������V�������ƂƊw�с`�q�ǂ��E���t�E�n��̊w�т��Ȃ��`�v�i2��18���i���j�A���{��w�x�͑�L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
http://www.jase.gr.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N2��18���i���j13��30���`16��30���i��t13���`�j
�ꏊ�F���{��w���H�w���x�͑�L�����p�X �����̐��Z��C502����
�i�����s���c��_�c�x�͑�1-8-14�j
�iJR�u�䒃�m���v�A�n���S�u�V�䒃�m���v�u�䒃�m���v�e�w���ԁj
���̂˂炢�ƃv���O�����F
�@2017�N�ɗc�t���E���w�Z�E���w�Z�E���ʎx���w�Z�̐V�w�K�w���v�̂���������A�w�Z����ɂ����āu��̓I�őΘb�I�Ȑ[���w�сv�𐄐i���邱�Ƃ�����܂����B�q�ǂ����m���Z�\���l�����邾���ł͂Ȃ��A�\���s�\�Ȍ����̉ۑ�Ƀ`�������W���邽�߂̎���I�Ŏ����I�Ȋw�т��A�w�Z����Ŏ��g�ނׂ��d�v�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȋw�т��������邽�߁A���t�Ɗw�Z�ɂ͕s�f�̎��Ɖ��P�����߂��Ă��܂��B�܂��A2012�N�̒����R�̓��\�ȍ~�A�u�w�ё����鋳�t���v������A����ψ�����w��n�擙�Ƌ������Ȃ���A���t���w�Z�ł̎��H��ʂ��Ċw�ш炿�Â��邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B����A�l�H�m�\�iAI�j�������y���A���q������i�s����ɂƂ��Ȃ��A�Љ��d���݂̍���⓭���������łȂ��A�w�Z����̐��x��g�D�A���e����@���傫���ϗe���邱�Ƃ��\������܂��B�������A���̍������Ƃ����߂ċ��t���w�тÂ��邱�Ƃ͕��ՓI�ȉۑ�ł����A�����ŋ��E���̒����ԘJ���⑽�Z���ɂ��A���t���\���Ɋw�Ԏ��Ԃ��m�ۂ���Ă���Ƃ͂�����A�V�����ۑ�ɑΉ����邽�߂Ɋw�Z����͍���ɒ��ʂ��Ă����܂��B�����ŁA�{���J������ł́A�q�ǂ��Ƌ��t�ƒn��̊w�т��Ȃ����Ƃɂ���āA����̎������߂���Ƃ⎎�݂ɂ��ĕ����肢���A2030�N�̊w�Z��������������V�����w�тɂ��Ă̈ӌ��������s�������Ǝv���܂��i���̍ہA�V�w�K�w���v�̂ɑΉ����邽�߂̕���̒�ĂɂƂǂ܂炸�A�ᔻ�I�n���I�Ȍ����Ƌc�_���s����Ɗ���Ă��܂��j�B ���J������ł��̂ŁA�ǂȂ��ł��i�w����łȂ��Ă��j�Q���ł��܂��B�ӂ���āA���Q���̂قǁA�ǂ����A��낵�����肢�������܂��B
�i�e�[�}�͉���j�F
�E���ꂩ��̐V�����w�� �V�c�����i��q��w�j
�E�����I�Ȋw�K����Ȃ���w�� �{���^���q���i��s��w�����j
�E���E���A�g�ɂ��w�� ���X�ؑP�����i�x�m�s���g����O���w�Z���j
�@�w�蓢�_ �x��[�K���i��t��w�j
�₢���킹��F���c�F�I
�ikuroda_y[at]penta.ge.cst.nihon-u.ac.jp�j
�i2018/2/7�j
�c���x�E���䍹�� Duo Concert�i2018�N2��12���i���E�j�j�A��z�����w�u���j
�{�R�[�X��w�@���ɂ�鉉�t��̂��ē��ł��B
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N2��12�� �ߌ�2���`�i�ߌ�1��30���J��j
�ꏊ�F��z�����w�u���i�V������z�s�R���~��1�j
�o���F�c���x�iMezzo Soprano)�A���䍹��iSoprano�j
�@�Έ�G��A��c���g�iPiano�j
�����ꖳ��
�v���O�����F
�EF.�V���[�x���g�u�����v
�EG.�r�[�[ �̌��q�J�������r��萔�Ȕ���
�E�㓡�O�搶�E�[�~���ɂ��Ϗ���i�@��
��ÁE���⍇���F
��z�����w��w�@�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j
TEL025-521-3508�i��쌤�����j
�i2018/2/6�j
���{�w�Z���y������H�w�� �����x�����i2018�N2��11���i���j�A���J�s�������U�w�K�Z���^�[�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.jassmep.jp/index.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N2��11���i���j13���`16��30��
�ꏊ�F���J�s�������U�w�K�Z���^�[ 503���C��
�i���J�s���������Z���^�[���F���J�s�ᏼ��2-104�j
JR���J�w�i����j�A���S���J�w�i����j����k��3��
�i�w���D����X���[�v�ɂĒ����A��p���ԏꂠ��j
�^�C���e�[�u���F
13:00�@�͂��߂̉�i12:45�`��t�j
13:10�`14:20�@���������͋[����
�@���ƎҁF��،��i�搶�i���C���w�Z���@�j
�@�P�����F�����ƕω��������ās������ϑt�ȁt�𖡂킨��
14:20�`14:35�@�x�e
14:35�`16:10�@���������͋[���Ƃɂ��Ă̌𗬁E�܂Ƃ�
16:30�@�I���E�Еt��
16:40�`�@���e��
���e�F���w�Z1�N����ΏۂƂ����ӏ܂̊w�K��z�肵�Aⶂʼn��t�����s������ϑt�ȁt�ɂ��āA���y����������ƒ����āA�O���[�v�ő��k���Ȃ���}�`�y��������܂��B�����āA�e�O���[�v�̐}�`�y���ɂ���F��`�ɂ��Ėⓚ�����Ȃ���A���y�̂ǂ̍\���v�f���ǂ���������������L���Ă����܂��B�����āA�Ō�Ɋe�X�����̉��y�̖��킢���]���ɂ܂Ƃ߂܂��B
�A����F���I�S�q�i�����x�������j
E-mail: yukoharmony[at]yahoo.co.jp
�i2018/2/5�j
���m���y�w���x���@��69���ጤ����i2018�N2��18���i���j�A���ꌧ���|�p��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/okinawa...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N2��18���i���j14:00�`16:00
�ꏊ�F���ꌧ���|�p��w �����L�����p�X�t�y���u�`��
�@�i�t�y���z�[��2�K�j
�Q����F����E�����Ƃ����ꖳ���i�\��s�v�j
���e�F�������\
�E���g����
�u���ꌧ�ɂ����鎂�q���̗��j�Ɠ`��
�@�@�\�Y�Y�s�̎��q���𒆐S�Ɂ\�v
���A�������\1��
���₢���킹�F�x���ψ��i���S���j���c�b��
TEL080-3055-5668 Mail: okadaemy[at]edu.u-ryukyu.ac.jp
�i2018/1/31�j
�w�p���ʌ��J�V���|�W�E���u�k�Е����ɂ����閯���|�\�̖����ƌp���v�i2018�N2��10���i�y�j�A�S�R���q��w�j
�w��E������̏��ł��B
���ڍׂ͂�����
https://www.tohoku.ac.jp/japanese...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
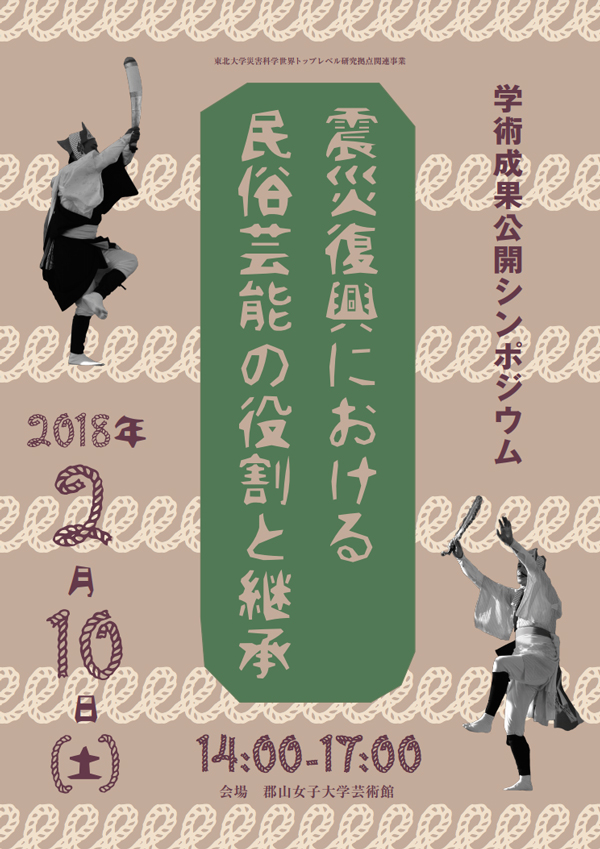
�����{��k�Ќ�A�n��Љ�ɓ`����Ă��������́A��Ў҂̓���I�ȕ�炵�������ǂ��ꏕ�ƂȂ��Ă��܂����B�{�V���|�W�E���̖ړI�́A�k�Е����ߒ��ɂ����閯���|�\���̖����ɂ��āA�����Ă��̂��߂ɒn��E�s���E��w���ǂ̂悤�ɋ��͂ł��邩���l���邱�Ƃɂ���܂��B�������s���▯���|�\�ۑ��c�̂̊�����U��Ԃ�Ȃ���A�n��̖����ɂ��čl�@���܂��B
�����F2018�N2��10���i�y�j14:00�`17:00
���F�S�R���q��w�|�p�فi�A�N�Z�X�j
�v���O�����F
��|�����F�t�B�[���h�ЊQ�l���w���߂�����
�@�@�@���q�_���i���k��w�j
��ꕔ�F�������̖����|�\
�E�b��1: �����|�\�̕����́\�c�A���x��������
�@�@�@����q�q�i�S�R���q��w�Z����w���j
�E�b��2: �k�Ў��ɂ����閯���|�\�̗�
�@�@�@�{�������i�Q�]���������E�������y�|�\�ۑ���j
��F�����|�\�Ɩh�ЁE�k�Е���
�E��3: ������������n�敶��
�@�@�@���J����i���k���j�����فj
�E��4: ���`������Y�̖h�ЂƂ����l����
�@�@�@�v�ۓc�T���i�����������������j
�������_�F�R�����e�[�^�[: �������i�S�R���q��w�Z����w���j�E�ؑ��q���i���k��w�j�@�i��: �R���r�i�R����w�j
��ÁF���k��w�ЊQ�Ȋw���ی������E�S�R���q��w
���ÁF���k��w���k�A�W�A�����Z���^�[
�₢���킹��F
�@���ɂ��āF�S�R���q��w ����q�q t.ueno[at]koriyama-kgc.ac.jp
�@���e�ɂ��āF���k��w ��ΘЍ� yuka.oishi.d3[at]tohoku.ac.jp
�i2018/1/30�j
��17�������w�t�H�[�����u���N�̏j�Ձ\�c�I2600�N�E����100�N�E����150�N�\�v�i2018�N2��11���i���j�A������w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/CR/forum...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
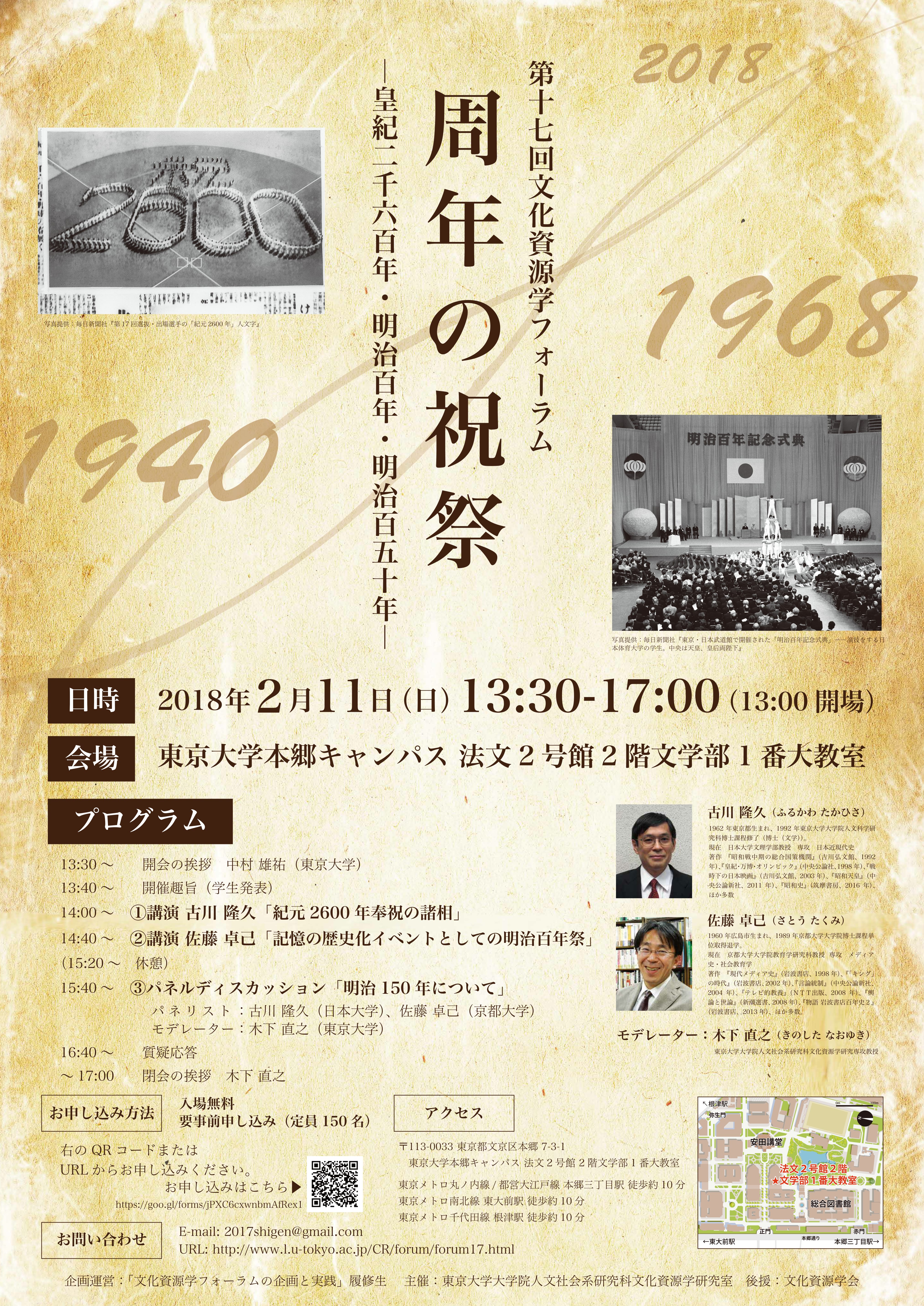
�����F2018�N2��11���i���j13:30�`17:00�i13:00�J��A��t�J�n�j
���F������w�{���L�����p�X�@��2����1�ԑ勳���i�����n�}�j
��ÁF������w��w�@�l���Љ�n�����ȕ��������w������
�㉇�F���������w��
���E�^�c�F�u���������w�t�H�[�����̊��Ǝ��H�v�[�~���C��
����F150�� �i�v�\�����݁@���ꖳ���j
�J��|�F
�@����30�N�i2018�j �́A �������N�i1868�j����N�Z���Ė�150�N�ɓ�����B���{�́u�����ȍ~�̕��݂�������Ɉ₷���Ƃ�A�����̐��_�Ɋw�сA���{�̋��݂��ĔF�����邱�Ƃ́A��Ϗd�v�Ȃ��Ɓv�Ƃ��A�u����150�N�v�֘A�{��̐��i�Ɏ��g��ł���i���@�z�[���y�[�W�u�u����150�N�v�Ɍ������֘A�{��̐��i�ɂ��āv�j�B
�@�ߋ��̎�������ڂ���s���́A ���N�Ƃ����ߖڂŎ��{����Ă����B �Â��͏@���I�Վ��▯���I�V��Ɋ�Â��čs���A �ߑ�ȍ~�͍��̐����ʂȃ��f�B�A����đ�K�͂Ɏ��{�����悤�ɂȂ����B �����͗��j�I�Ȏ����ɋL���^�L�^�����L����s�ׂ�ʂ��āA���Ƃ̂Ȃ�������߂��苤���̂ւ̋A���ӎ������߂��肵���B
�@���j��U��Ԃ�ƁA��̌����Ȏ��N�s�����������B���a15�N�i1940�j�u�c�I2600�N�v�ł́A�c���ƍ������Ƃ̃A�C�f���e�B�e�B�����т����A���a43�N�i1968�j�u����100�N�v�ł́A��������� ���_�������Â��ꂽ�B ����������{����̓I�Ɏ��g�݁A �����̗��j�F���Ɋւ����̂ł������B ���ɗ��s���ɋ��ʂ��āA�ߋ��̎����́q�ۑ��r�Ɓq�W���r�Ɋւ�鎖�Ƃ��s���A�u����150�N�v�ł����l�̎{�\�肳��Ă���_�����ڂ����B
�{�t�H�[�����ł́A�u�c�I2600�N�v�u����100�N�v�Ɓu����150�N�v���r���A�������N���j���ߋ�����ڂ���s���������ɍs���A ����ɂǂ̂悤�ȈӋ`������̂��ɂ��čl�@����B �߂������A �V�c�ވʂ�I�����s�b�N �E�p�������s�b�N�������J�ÂȂǗl�X�ȍ��ƓI�ȍs���������܂��Ȃ��A�w�ۓI�Ȍ��n����c�_��[�߂����B
�v���O�����F
�E13:30�@�J��@�����Y�S�i������w�j
�E13:40�@�J��|�i�w�����\�j
�E14:00�@�@�u���@�Ð엲�v�u�I��2600�N��j�̏����v
�E14:40�@�A�u���@������ȁu�L���̗��j���C�x���g�Ƃ��Ă̖����S�N�Ձv
�E15:20�@�x�e
�E15:40�@�B�p�l���f�B�X�J�b�V�����u����150�N�ɂ��āv
�@�@�p�l���X�g�F�Ð엲�v�i���{��w�j�A������ȁi���s��w�j
�@�@���f���[�^�[�F�؉����V�i������w�j
�E16:40�@���^������
�@�@��̈��A�@�؉����V
�E17:00�@��@
�\�����ݐ�F���̃��[���܂��̓t�H�[���ɂĎ�t
�E���[���@2017shigen[at]gmail.com
�E�\���t�H�[���@https://goo.gl/forms/jPXC6cxwnbmAfRex1
���₢���킹�F
��17�������w�t�H�[����������
������w��w�@�l���Љ�n�����ȕ��������w��������
Email�F2017shigen[at]gmail.com
�i2018/1/29�j
���m���y�w����{�x����101���ጤ����i2018�N2��3���i�y�j�A�������q��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://tog.a.la9.jp/higashi/regular.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N2��3���i�y�j 13:00�`16:40
�ꏊ�F�������q��w �_�c��c���L�����p�X�{��303�����i�A�N�Z�X�j
���������\��
�P�D�A���n���N�̑��͐�Ɖ̕���
�\�����g�E�q��Ǝs�쉎�V���̈Ԗ⏄�Ƃ𒆐S�Ɂ\
�@���u�P�i�����Y�p��w�j
�Q�D���J�t���Q�G�Β��i�̖ژ^�ɂ���
�@�����O�i�����w�|��w�j
�R�D����̃J�U�t���y����ɂ݂��镜���I�������߂�����
�@���c�͎q�i�����Y�p��w�j
�S�D�f�B�A�X�|���Љ�ɂ�����@���I�|�\�����̓W�J
�\�E�B�[���̃A�����B�[�ɂ��@���V��̕��͂���\
�@��ؖ��ؔ��i�������y��w�j
�i��F�y�c�q�q�i�������q��w�j
�i2018/1/26�j
�w���w�x��251���i2017�N12���A���w��j
�w��ŐV���̏��ł��B
���w������T�C�g�͂�����
http://www.bigakukai.jp/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�E�ɓ����сu�����҂̌o���ɂ��ƂÂ����o��Q�҂̐g�̘_�v�@1
�E��ؘj�u�W���b�N�E�����V�G�[���̌|�p�j�ςƌ���|�p�ւ̊�^�F�w�����I�Ȃ��̂̃p���^�[�W���x�ɂ����郂�_�j�Y���^�|�X�g���_�j�Y���ᔻ�̌����𒆐S�Ɂv�@13
�E�K���Ďq�u�ŌÂ̐���ӔN�`�lj�̃e�L�X�g�����F���[�}�A�t�H���g�D�[�i�E���B���[���_�a���邢�̓T���^�E�}���A�E�f�E�Z�N���f�B�`�F���I�����lj�i������N�\������N�j�v�@25
�E�쑽�������u�k�E�a�E�A���x���e�B�́q�L���̊�r�ƌÑ�G�W�v�g�_�������F�q�_�̊�r�Ɓq�l�̊�r�A�}���̌���Ɖ��߂��߂����āv�@37
�E�]�����u�y���W�[�m��s�K���c�B���Ւd��t�ɂ�����t�����h���G��̉e���F�J�E�h�[���́s�I�Y�t�Ȃǃt�@���E�G�C�N�h�̍��𒆐S�Ɂv�@49
�E�������u�h���}�o�t�`�F�E�W���[�~�C�ɂ݂���I�X�}���鍑�h�[�������X�N�̗l���I�`���̑����v�@61
�E���{�ގ��u�h�K�̕��i��ɂ݂���V���Ȏ��o�F�T�������@�������V�������\�����̕��i��𒆐S�Ɂv�@73
�E�������u�G���I�E�I�C�`�V�J�s�g���s�J���A�t�ɂ�����N�P���Ɓq�H�l�̎v�z�r�v�@85
�E���͋��u���y�͔߂��݂������炷���H�F�L���B�[�̉��y��ɂ��āv�@97
�E���ہu�����O�ɂ����锽���L���̎g�p�@�F������̍�i����̉e���Ƃ��̔��w�̕ω��v�@109
��68����w��S�����i���E���\�v�|�j
���E�������\��\�v�|
�w������E�ҏW��L
�����v�|
ISSN:0520-0926
���s���F����29�N12��31��
�ҏW���s�F���w��
�@���s�s������g�c�����B��46����c�L�O�ٓ�
�@���s��w������̖��������Z���^�[�g��������
����F�q�~����������
�����F���p�o�Ŏ�
�i2018/1/25�j
���J����������u���y����g�̊Ԃ̑��ݍ�p�𑨂���\�\�~���[�W�b�L���O�̊w�ۓI�����v�i2018�N1��27���i�y�j�A���������w�����فj
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.minpaku.ac.jp/research/activity...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N1��27���i�y�j13:00�`18:00
�ꏊ�F���������w�����ف@��4�Z�~�i�[��
��ʌ��J�i�Q�������^�\���s�v�^�撅40���j
�v���O�����F
�E13:00-13:10�u�I�����e�B�𑨂��Ԃ��\�\�~���[�W�b�L���O�ƌ��̊Ԃ���i��|�����j�v���V�L��i�x�R��w�j
�E13:10-13:55�u�����Ƃ��ƂA���炾�Ƃ��Ƃ\�\���Ɛg�̐��v�ёq�`�V�i���{�@��{�j
�E13:55-14:40�u�w�M���Ă���x�ƌ��̂����Ɓ\�\���l�y���e�R�X�e�h�L���X�g���ɂ�����I�����e�B�ƐM�v���V�L��i�x�R��w�j
�E14:50-15:35�u�Ȃ��i�킴�킴�j�̂����킷�̂��\�\�|�������̂̃I�����e�B�v���ۊx�i���s��w�j
�E15:35-16:20�u�̂����ƂƘb�����Ɓ\�\�o���̉̎ŋ��A���W���ɂ����鐺�̗l�����v���숟�q�i�����Y�p��w�j
�E16:30-18:00�@�S���E�������_
���₢���킹�F���������w������ �������͉ۋ������p�W
TEL06-6878-8364�@E-mail:kyodo[at]idc.minpaku.ac.jp
�i2018/1/24�j
�I�y���^���y��������2017�N�x2���������i��169��I�y��������j�i2018�N2��3���i�y�j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://opera-and-music-theatre.jimdo.com...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N2��3���i�y�j 16:30�`18:00
���F����c��w ����c�L�����p�X3����802����
�@���L�����p�X�}�b�v�� ������
�@���Q�������E���O�\���s�v�B�ǂȂ��ł����Q�����������܂��B
���e�F�������\
���\�ҁF�ڈ�����
��ځF�s�j�[�x�����O�̎w�t�ɓ��e���ꂽ�ϋq���\�\���[�O�i�[�̊ϋq�_��1976�N�ȍ~�̏����o�𒆐S�Ɂ\�\
���\�v�|�F
�@�{���\�ł́AR. ���[�O�i�[�̊y���s�j�[�x�����O�̎w�t�i�ȉ��s�w�t�j��1976�N�ȍ~�̏����o�ɂ��āA�ϋq�Ƃ̊W���ɒ��ڂ��čl�@����B���y����i���㉉���鑤�ɂƂ��āA���̏㉉���ϋq�Ƃ̊Ԃɂǂ̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�����ݏo���̂��́A�l������Ȃ����ł���B���[�O�i�[���g���w�I�y���ƃh���}�x�i1851�j���͂��߂Ƃ��钘��ɂ����āA����̊y�������S�ɗ�������邽�߂ɂ́A�ϋq�̎�̐��𑣂��K�v�����邱�Ƃ��咣���Ă���B
�@�������[�O�i�[�̏������ƁA�s�w�t�����[�O�i�[��ނƒ��ڊւ��̂������l���̎�𗣂ꂽ����ɏ㉉���邱�ƂƂȂ����A1970�N��ȍ~�̉��o�Ƃ̌������r�E�l�@����ƁA���҂̕����ϋq���ɂ͑��Ⴊ����A�܂����̂��Ƃ��s�w�t�̏㉉��@�ɂ�����������炵�Ă��邱�Ƃ��킩��B�{���\�ł͂����̑�����A�s�w�t�㉉�̒��ł��f���Ŋm�F���邱�Ƃ̏o����1976�N�ȍ~�̏����o������Ɍ�����ƂƂ��ɁA�����̉��o�����[�O�i�[�́u�Ӑ}�v�Ƃ͈قȂ��@�ł���Ȃ�����A��͂�ϋq�̎�̐��𑣂����̂ł��������Ƃ��𖾂���B
�i2018/1/23�j
��z�����w�|�p�n�R�[�X�i���y�j���ƁE�C�����t��i2018�N1��27���i�y�j�A��z�����w�u���j
������1��27���i�y�j�ɁA2017�N��z�����w�|�p�n�R�[�X�i���y�j���ƁE�C�����t����J�Â��܂��B�w��4�N���A��w�@2�E3�N���ɂ��A����܂ł̌����ƌ��r�̐��ʂ̔��\�ł��B
���t���\����э�i���\������A�l�X�Ȋy��ɂ��Ə��E�Ƒt�A�d���E�d�t�A��l���ł̍��t�ȂǁA���e�����ʂł��B���Ђ����꒸���������E���ڝ�����܂��悤�A���ē��\���グ�܂��B
��z�����w�|�p�n�R�[�X�i���y�j���ƁE�C�����t��
�����F����29�N1��27���i�y�j13���`
���ꕔ�`���V�ŊJ����14���ɂȂ��Ă��܂����A13���J���ł��B���ԈႦ�Ȃ��悤�����ӂ��������B
�ꏊ�F��z�����w�u���@�����ꖳ��
���e�F�w��4�N���A��w�@2�N���ɂ��Ə��A�Ƒt�A��i���\
��ÁF��z�����w�|�p�n������H�R�[�X�i���y�j
���₢���킹�F TEL025-521-3501 hirano [at] juen.ac.jp �i����j
�v���O�����F
�q�C�����t�� ��ꕔ�r
�\�v���m�Ə��@���c����A��c���g�i�s�A�m�j
�E�����ď����́i�q��́j�i�v�b�`�[�j�j
�E�̌��s�C�����A���W�F���J�t��� ����Ȃ��Ɂi�v�b�`�[�j�j
�E�̌��s�W�����j�E�X�L�b�L�t��� ���̂�������i�v�b�`�[�j�j
�\�v���m�Ə��@�匴��b�A�������i�s�A�m�j
�E������̎q��S�i��c���v�^���R���j
�EI�i���j�i�ߍ]���q�^���R���j
�E��z�ȁi���R�m�q�^���R���j
�s�A�m�Ƒt�@��،[�l
�E�p�K�j�[�j�ɂ�����K�ȑ�3�ԁs���E�J���p�l���t�i���X�g�j
�E�p�K�j�[�j�ɂ�钴��Z�I���K�ȑ�3�ԁs���E�J���p�l���t�i���X�g�j
�\�v���m�Ƒt�@���䍹��A�Έ�G��i�s�A�m�j
�E�����牡���傤�i��������^�_�ˍF�v�j
�E�̌��s�t�@�E�X�g�t��� ��̉́i�O�m�[�j
�q���Ɖ��t��r
�s�A�m�Ƒt�@�쓇���k
�E�s�A�m�\�i�^Op.7 ��4�y�� �����g�E�A���O���i�O���[�O�j
�`���[�o�Ƒt�@�잊�K꤁A�����쌪��i�s�A�m�j
�E�`���[�o�ƃs�A�m�̂��߂́s�J�v���b�`���t�i�j���[�g���j
�q�C�����t�� ��r
�J�E���^�[�e�i�[�Ə��@�R�ݎ����A�����쌪��i�s�A�m�j
�E�̌��s�^�������[�m�t��� �A�X�e���A�����𗠐�̂Ȃ�`�ޏ��̋��̓��̐S�͌Ղ����i�w���f���j
�E�̌��s�����[�y�t��� �Ȃ掄��������ʂ��i�W���R���b���A�����쌪��ҋȁj
�E�̌��s�I���t�F�\�I�t��� ���̏�Ȃ��s�K�Ȉ��ɂ��i�|���|���A�����쌪��ҋȁj
�I�[�{�G�Ƒt�@�������͂邩�A��c���g�i�s�A�m�j
�E�Ԏ��v�i�t�����Z�j
�����@�w���F�㓡�O�A�s�A�m�F���A�����F�L�u�����c
�E�����g�ȁs�����₩�Ȃ������t��� ���₯�̂Ƃ��i���݂��q�^�㓡�O�j
�E���������ƃs�A�m�̂��߂́s�M����t�i�J��r���Y�^�����k�j
�i2018/1/22�j
�����|�\�w���167�����i2018�N1��27���i�y�j�A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.minzokugeino.com/meetings.html
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N1��27���i�y�j�ߌ�2���`�i�ߌ�1��30���J��j
���F����c��w���������ك��N�`���[���[��6����318����
�Q����F200�~�i����łȂ������Q���ł��܂��j
�R�E�g�E����s���Ɩ����|�\���߂�����
�E�����q�v�u�`���ꂽ�R�E�g�E����E�R�Ԃ̍Ձ\�]�ˎR���Ձ\�v
�E�����z�q�u���Z�ɂ������R�Ƃ���\���̎�e�̏����\�v
�i��F�U�،�@�R�����e�[�^�[�F����
���ڂ������e�� ������ �Ɍf�ڂ��Ă���܂��B
�i2018/1/18�j
���{�����w�� ���m��r����������1�����i2018�N1��20���i�y�j�A�����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
www.jstr.org/project/pro02...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F����30�N1��20��(�y) 14:00�`18:00
�ꏊ�F�����w 7����731�����i3F�j
�V���|�W�E�����|�X�g�h���}�����F20�N��̎�e�ƌ��؇U��
�E14:00�`14:15�@�͂��߂Ɂ@�R������
�E14:15�`15:00�@���\�P �]�����o�u�A�����J���O���ɂ�����i�|�X�g�j�h���}���_�̓W�J�v
�E15:00�`15:40�@���\�Q �k��獁�q�u�I�y���ɂ�����|�X�g�h���}�����\�N���X�g�t�E�V�������Q���W�[�t�́s�p���W�t�@���t���o�i2004�j���Ƃ��āv
�E15:40�`16:10�@�V���|�W�E����U��Ԃ��ā@�R�����Ɓi�����E�i��j
�x�e10��
�������\
�E16:20�`18:00�@��R��u��c�G���w�����l�Ԃ̏��C�x�ɂ�����A�ߌ��ŏI���Ȃ��w���~�I�ƃW�����G�b�g�x�ƓV�c���v
������A�V�N������˂����e����s���܂��B
����7���ْn�����E���W�i��3,000�~)
�i2018/1/17�j
�����㉉�t��i2018�N1��21���A����s������كA���t�H�[���j
���t��̏��ł��B
�{�R�[�X�����̏�삪�o�����܂��B�w���������c�ɎQ�����Ă��܂��B
�������T�C�g�͂�����
www.artforet.jp/event...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F2018�N1��21���i���j14:00�J���i13:00�J��j
���F����s������كA���t�H�[�� ��z�[���i����s���Β�4��32���j
���z���n�k����10�N���}���A�g�����̃V���{���h�A���t�H�[���ő�㉉�t����J�Â��܂��B����ɂ�鍇���c�ƌ����䂩��̃\���X�g���A�I�[�P�X�g���̉��t�Ƌ��Ɂg����h�̉̐����������܂��B
�o���F�ێR�Õv�i�w���j�A��؈����i�\�v���m�j�A�������q�i�A���g�j�A���R�M��i�e�m�[���j�A��쐳�l�i�o�X�j�A����t�B���n�[���j�[�nj��y�c�A�����㍇���c
�v���O�����F
�E�x�[�g�[���F���@�����y�u�G�O�����g�v����
�E�x�[�g�[���F���@�����ȑ��� �j�Z���u�����t�v��i125
�@�����e�͕ύX�ɂȂ�ꍇ������܂��B
��ÁF����s������كA���t�H�[���@�㉇�F����s�A����s����ψ���
�����F�S�Ȏ��R 1,000�~
�v���C�K�C�h�F����s������كA���t�H�[���A����s�Y�ƕ�����فA�킽����y�탉���t�B�A�Z�u���C���u���i�Z�u���`�P�b�g�j
�i2018/1/16�j
�V�\�z3�����w�V���|�W�E���u����I����ۑ�Ƒ�w�ɂ����錻�E�����̍ċ���\�w�Z����ɂ����锭�B��Q���E�҂̎x����ʂ��ā\�v�i2018�N1��27���A��z�����w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.juen.ac.jp/010pickup...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d

�����F����30�N1��27���i�y�j13:30�`16:40�i��t�F13:00�`�j
�ꏊ�F��z�����w�u�`��201�����i�V������z�s�R���~��1�Ԓn�j
�E13:30�@�J��
�E13:40�`14:20�@��u��
�����Ȋw�ȍ�������Ǒ�w�U���ۋ����{����掺�� ���V�D�����i�\��j
�E14:30�`16:30�@���H���\
�V�\�z3�����w�̑�w�@�C���������w�Z����ɂ����锭�B��Q���E�҂̎x���Ɋւ�����H�I�ȋ���E�����̐��ʂ\����ƂƂ��ɁA��w�ɂ����錻�E�����̍ċ���ɂ��Č����s���܂��B
�E16:40�@��
�ڍׁE�\�����@���F�ʎ��`���V ���Q�Ƃ̏�A���\���݊肢�܂��B
�Q����F���� ���150��
�i2018/1/15�j
�I�y���^���y��������2017�N�x1���������i��168��I�y��������j�i2018�N1��20���A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://opera-and-music-theatre.jimdo.com...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N1��20���i�y�j 17:00�`18:30
���F����c��w ����c�L�����p�X3����809��c��
�@���L�����p�X�}�b�v�� ������
�@���Q�������E���O�\���s�v�B�ǂȂ��ł����Q�����������܂��B
���e�F�������\�@���\�ҁF�V�c�F�s
��ځF�u����I�y�����o�ɂ����镶���I�Q�Ƃ̖��\�\�N���X�g�t�E���C���o�s�e�̂Ȃ����t�i2011�N�A�U���c�u���N���y�Ձj�Ƃ��̔�]�I��e���߂����āv
���\�v�|�F
�@�ÓT�I�ȃI�y����i�̍ĉ��߂Ƃ��Ď�ɍs���錻��̃I�y�����o�ɂ����āA��{��̐ݒ��ǂ݊�����ۂ̃l�^���ɂȂ�̂������I�Q�Ɓicultural references�j�ł���B������f��̏ꍇ�ƈقȂ�A���ꎩ�̂̌|�p�������܂��ɔF�m����Ă��Ȃ��I�y�����o�Ɋւ��ẮA��]�Ƃ̊Ԃł���ʂ̊ϋq�̊Ԃł��A������ǂ����o�������Ƃ����|�p�I�ȑ��ʂ��A���ɓǂ݊��������Ƃ����m�I�ȑ��ʂɑ���S�������B�Z�m�O���t�B�[�≉�Z�w���̎��ł͂Ȃ��A�R���Z�v�g�╶���I�Q�Ƃ̓K�������o��]�������ƂȂ��Ă���B���̌���ɑ��āA���o�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȓ��킪�\���낤���B
�@�{���\�ł́A2011�N�̃U���c�u���N���y�Ղŏ㉉���ꂽ�N���X�g�t�E���C���o�s�e�̂Ȃ����t���ɁA�����I�Q�Ƃ��߂��鉉�o�Ƃ̐헪�ɂ��čl����B��{��̕�������y�w�I�m���܂��Ȃ��瓖�Y��i�̎�e�j�Ƃ��ēǂ݊�����A�ߔN�̋^���w��I�ȃI�y�����o�̌X���ɑ����郍�C�́s�e�̂Ȃ����t�́A�����ꏊ�A�l������肷�镶���I�Q�Ƃւ̗���x�ɉ����Ċϋq���قȂ�̌��ɓ����B���̕��@���A���o�Ƃ̔���������]�ƏƂ炵���킹���o�̍ו��ɒ��ڂ��邱�Ƃŋ�̓I�ɖ��炩�ɂ������B
�i2018/1/13�j
���{���y�w����{�x����39��i�ʎZ390��j���i2018�N1��20���A���u�Џ��q��w���o��L�����p�X�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/asia/msj/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N1��20���i�y�j13:30�`17:00
���F���u�Џ��q��w���o��L�����p�X ������301����
�@���s�s�c�n���S���o��w���ԁA�k��5���B
�@�܂��͋���{���o�����w���ԁA�k��10���i�n�}�j
�P�D�������\
�uS.�[�q�^�[�����鉹�y�I�n����A.�u���b�N�i�[�̎w���@�F F.�G�b�N�V���^�C�����u���y���_�̌n�v�����̍l�@�v�~�ш�q�i��������w�j
�@�A���g���E�u���b�N�i�[�̒�q���l�鏑�ł������t���[�h���q�E�G�b�N�V���^�C���́A�u���b�N�i�[����w���y���_�ɂ��āA�w�A���g���E�u���b�N�i�[�B���y���_�̌n�x�Ƒ肷�錴�e���c�����B�u���b�N�i�[�́A�W�[�����E�[�q�^�[�ɉ��y���_���Ȗ@���t�����A�����e���������Ƃ���A�G�b�N�V���^�C���́u���y���_�̌n�v�����ɂ����āA�[�q�^�[�����鉹�y�I�n���ɂ��ďڏq���Ă���B�����Ŗ{���\�ł͂��̒��q����ɁA(1)�[�q�^�[�������y�I�e���ƁA��q�Ɏc�����e���A(2)�[�q�^�[�̍���Ƃ��Ẵu���b�N�i�[�̎w���@�A�̓�_����������B
�@�G�b�N�V���^�C���������ŁA���̓�_�ɏœ_�����Ă����R�́A�u���b�N�i�[�̉��y���_�̗��j�I�w�i�𖾂炩�ɂ��邽�߂ł������B�u���y���_�̌n�v�{���̓����Ƃ��āA�G�b�N�V���^�C���̓u���b�N�i�[���w�сA��Ȃɐ������A��q�ɋ��������y���_�́A�Ђ��Ă͎������w���_�́A���j�I�ȗ���ɂ�����ʒu�t���m�ɂ��悤�Ɠw�߂��̂ł���B
�Q�D�V���|�W�E��
�u���̌����̐V�W�J�F���j�E���H�E�z���v
�ҁF�֓����i�R����w�E�����j�A�x�j�[�E�g���i�I�[�X�g�����A������w�E�����j�A�֓��T��i����w�j
���_�ҁF���c���i���s����w�j
�@�{�V���|�W�E���ł́A�u���́v�Ə̂���Ă���i�����j���y�Ɋւ�錤���̌���ƓW�]�ɂ��Č�������B���҂̗֓��́A2010�N���Ɂw�n��ꂽ�u���{�̐S�v�_�b�x���㈲�����B���R�[�h�̗w�W�������Ƃ��Ắu���́v�̌`����1970�N�O��ł���A�Ƃ��������̎咣�́A���s���_�ł͂���Ȃ�ɃZ���Z�[�V���i���Ȃ��̂ł������ƍl�����邪�A���݂ł́A������x��ʂɎ�����A�ȑO�Ȃ�u���́v�̌ꂪ�p�����Ă����ł��낤�����Łu���a�̗w�v�Ȃǂ̌������ɂƂ��Ă�����邱�Ƃ�����悤���B����ŁA�u���́v�Ƃ������t���߂��錾���j�I�ȃA�v���[�`���̂����ْ��̘g�g���錤��������Ă���B���������������\������̂Ƃ��āA�֓������i�R����w�j�A�x�j�[�E�g�����i�I�[�X�g�����A������w�j��҂Ƃ��Č}����B�֓����́u���̂̏����v�Ə̂����ȑO�̔���Ђ�́u�f��X�^�[�v�Ƃ��Ă̑��ʂɒ��ڂ��A���{�̍ݗ��̌|�\�����Ƃ̘A�����ɂ��Ă��h���I�ȋc�_��W�J�����w�f��Œm�����Ђ�Ƃ��̎���x�̒��҂ł���A�g�����́A���̃J���I�P�i���^�����ł̃C���e���V���ȃt�B�[���h���[�N�Ɋ�Â����m�_���̒�o���O�ł���B�֓��̖���N�Ƃ��킹�āA�u�|�X�g���́v�Ƃ������ׂ��ɂ������O�̗w�����̉\���ɂ��Č����������B�@
�@���m�̂悤�ɍ֓����̓g���R�E�C�X�^���u�[���̖��w����Łu���߂�̂���v���J��L�����o���������A�g�����̓V���K�|�[���o�g�A�I�[�X�g�����A�ݏZ�ł���B�܂��֓���2017�N�ɔ��N�]���p�ɑ؍݂��A���n�ɂ�����u�����v�̗̉w�i�Ƃ�킯��p��̂���j�Ɋւ��ĐV���Ȓm�����B���������C���^�[�A�W�A�^�����m�I�Ȋϓ_����苭�����ׂ��A�A�W�A�s�s�����w����Ƃ��鑝�c�����i���s����w�j���f�B�X�J�b�T���g�Ƃ��Č}���A�ꍑ�j�I�Șg�g�݂������́i�^���s�́^�̗w�ȁj�����̉\���ɂ��Č�������B
�i2018/1/12�j
���ۃV���|�W�E���u���A�W�A�Ɛ��E�́w�N�̖��́B�x�v�i2018�N1��20���A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/flas...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N1��20��(�y)
�ꏊ�F����c��w�@�ˎR�L�����p�X33����6�K��11��c��
�g�p����F���{��i�ʖ�L��j
��ÁF������w�헪�I������Ռ`���x�����Ɓ@��2�O���[�v�u�|�X�g�R���j�A������̐l���w�A���̍č\�z�\21���I�̓W�J�Ɍ����āv���{���㒆���w��֓��x��
���ÁF����c��w���w�w�p�@�����l���Ȋw�����Z���^�[ ��������u���A�W�A�̐l���m�v�A����c��w�������㕶��������
�v���O�����F
13:00-13:30�@�J��̎��A��|�����i����c��w�E���j
13:30-14:30�@���u���i�����E��J��w�j�ʖ���܂�
�@�u���ꂩ����j���~���F�w�N�̖��́B�x�ɂ�����g�����h�̃A���S���[�v
14:30-15:30�@���́i��p�E������w�j�ʖ���܂�
�@�u�ЊQ�����̂̋L���ƖY�p�F��p�ɂ�����w�N�̖��́B�x�v
15:30-15:45�@�e�B�[�u���C�N
15:45-16:15�@���_�E�}���V�A�[�m�i�J�i�_�E�J�[���g����w�j
�@�u�k�A�����J�ɂ�����w�N�̖��́B�x��e�v
16:15-16:45�@���{��E�i����c��w�j
�@�u��́w���E�^�Z�J�C�x�̋��ԁF
�@�w�N�̖��́B�x�Ɓw���̐��E�̕Ћ��Ɂx�v
16:45-17:00�@�e�B�[�u���C�N
17:00-18:30�@�p�l���f�B�X�J�b�V�����i�i��F���j
18:30-18:35�@��̎��i���j
�i2018/1/11�j
�w���y������H�W���[�i���x��15���i2017�N12���A���{���y����w��j
�w��ŐV���̏��ł��B
�{�R�[�X�����̔���ƒ��J��A��w�@���̔ё��@�g����̘_�e���f�ڂ���Ă��܂�
���w������T�C�g�͂�����
http://���{���y����w��.com/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�q���W1 ���y�n�̕������Ɖ��y����r
�����y�n�̕������̍���T��
�E���W���e�i�j�u���K�͍��Z�ɂ����鍇�������̓W�J�F�w�Z�̋�������R�[�f�B�l�[�g�������H���Ⴉ��v�Ό��T�i�@6
�E���W���e�i�j�u�w�Z�̕������ƒn��̌��ꂪ�Ȃ��鍇�������̎��H��F�v�c�s���g�c���w�Z�������Ɓu�O�����g���E���[�X�E�R�[���v�̊�����ʂ��āv�i�c���q�@11
�E���W���e�i�j�u�����{���ے��̐��t�y�c�̂ɂ�����C�O�����̎��݁F��z�����w���t�y�c�ƍ�����ȍ��ێ����������w�NJy�c�̓���𗬃v���O����������Ƃ��āv�ё��@�g�E���J�쐳�K�@18
�E�u�Љ��艻�����u�������̂�����v�ɉ��y����͂ǂ��Ղނ̂��F���w���y�ђ��w�Z�����Ώے����f�[�^�̕��͂���v�������@26
�E�u���w�Z���t�y���Ɋւ���8�̏����F���ԓI�]�T�Ɛ��I�w���ɗ]�͂�������Âɉ��y�ƌ����������ɂȂ邱�Ƃ�����āv�V�R�����a�@37
�E�u�w�Z����ɂ����鍇�����̎��ԂƂ��ꂩ��̓W�]�F�����E���k���L���Ȏ��Ԃ�Nj����邱�Ƃ����߂āv���m��@45
�E�u���w�Z�́u���ʉ��y�N���u�v�Ƃ́F���l�s�̏��w�Z�ɂ�������H�̌o������v�㓡�r�Ɓ@51
������T�K
�E�u�吳�Ղ̕������ɂ�鉹�y�����̌p���F��茧�Z�c�������c�h���w�Z�̎��g�݁v���q�֎q�@56
�E�u���ꂼ��́u���y����v���Ƃ̈Ӗ��F�����w�@���w�Z�n���h�x���N���C�A�v���{�N���@60
�E�u�����B��̕��Z�ƒn��Ƃ̘A�g����ސ_�y�F�L���������v�����w�Z�|�k���Z�_�y���̎��g�݂���v�����N�s�@64
�E�u���y�w�K���Ƃ��Ă̌y���y���F�я鍂���w�Z�y���y���̎��Ⴉ��v�؉��a�F�@68
�E�u�؍��E���N�̖����|�\�Ƃ̏o��A�����̃��[�c��T��F���s�s�������w���́u�R���A�݂������v��c�O�Îq�@72
�q���W2 �O�D�P�D�Q�Ύ��Ɖ��y����r
�����c������芪�����y�Ƃ��̂������̎p��m��
�E���W���e�i�j�u�����Ɨ{��҂́u��b�v�ɂ�����}�U���[�Y�F�v���\�f�B�̕��͂��猩���鉹�y���v���싱�q�E�R�c�x���@76
�E���W���e�i�j�u�O�D�P�D�Q�̎����I�ȉ��y�\�����珬�w�Z�̉��y�Â���ցv���N�q�E���ѓT�q�E����m���@85
�E�u�O�D�P�D�Q�̎q�ǂ��́q���r�q���y�r�����ƂɊւ�������F�ۈ牀�E�c�t���̉������l����v���c�e�q�@95
�E�u�Q�Ύ��̊y��V�тɂ����郂�m�Ƃ̂������̓����F�y��ւ̃A�v���[�`�̈Ⴂ�ɒ��ڂ��āv�ΐ������]�E����N�q�@104
�E�u�y��ւ̗��H�A���邢�͉��ւ̗U���F���c�����̉��y�I���B�ƃA�t�H�[�_���X�̊w�K�v�ێR�T�@114
������T�K
�E�u�����ۈ�Ƃ��ׂ����F�����̂��ۈ牀�v��v���q�@125
�E�u��������芪�������Ƃ��Ă̕ۈ�҂́u���v�F���z�ۈ牀�v�s��b�@129
�q���R���e�r
�E�i�j�u�w�Z�E���ǂ������̍s���ɂ����鉹�y���쌠�̈����Ɋւ��錟���F�ׂ�₷�����쌠�ی�̖ӓ_�v�����T�E��J�Í��E���v�Ñ���@133
�E�i�j�u�v���X�`�b�N���\�ǂ�p�������Ƃ̎��ہF���̂ɂ��`���I�Ȏw���@��ʂ��āv�R�c����@137
�q�}���Љ�r
�@�i���j
ISSN:1880-9901
���s���F2017�N12��31��
���s���F���{���y����w��
�@�����ǁF��184-0004�����s������s�{��5-38-10-206
�@�@Tel&Fax042-381-3562
�i2018/1/9�j
���ۃV���|�W�E���u�l���m�̖��������߂āF���f�B�A�̍��V�ƒm�̕ϖe�v�i2018�N1��13��(�y) �A����c��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
https://www.waseda.jp/flas...
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
��ÁF������w�헪�I������Ռ`���x�����Ɓu�ߑ���{�̐l���w�Ɠ��A�W�A�������F���A�W�A�ɂ�����l���w�̊�@�ƍĐ��v
�����F2018�N1��13���i�y�j13:00�`18:50
�ꏊ�F����c��w�@�ˎR�L�����p�X36����382-AV����
�q�v���O�����r
�E��ꕔ�F�u���i�i��F���j
13:00�`13:15�@�J���̎��E��|�����i���j
13:15�`14:45�@�G���L�E�t�[�^���u�|�X�g�q���[�}�����E�ɂ�����l���w�̖����F���f�B�A�l�Êw�̎��_����y�ʖ�z�v�gThe Tasks of Humanities in a Posthuman World : Media Archaeological Perspective�h (with consecutive translation)
14:45�`15:00�@�e�B�[�u���C�N
15:00�`15:45�@�h�~�j�N�E�`�F���u���Z�p�ɂ��l���m�̍��V�F�m�\���玩�����̑����Ɍ����āv
�gInnovation of Humanities with Information Technology: From Intelligence Augmentation To Autonomy Amplification�h
15:45�`16:30�@���_�I�u�ό��Ƃ��Ă̓N�w�A���邢�̓_�[�N���[�g�s�A�ɂ��āv�gPhilosophy as a Tourism, or on the Dark Utopia�h
16:30�`16:45�@�e�B�[�u���C�N
�E��F�u�p�l���f�B�X�J�b�V�����v�i�i��F�����^�m�q�j
16:45�`18:45�@�p�l���X�g�F�G���L�E�t�[�^���A�h�~�j�N�E�`�F���A���_�I�A����
18:45�`18:50�@���̎��i�����^�m�q�j
�i2018/1/5�j
���{���y�w����{�x����49���ጤ����i2018�N1��20��(�y) �A�����w�@��w�j
�w��E������̏��ł��B
�������T�C�g�͂�����
http://www.musicology-japan.org/east/
�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d
�����F2018�N1��20��(�y)�@14:00�`17:30
�ꏊ�F�����w�@��w�����L�����p�X2201�����i�A�N�Z�X�j
�i��F�����^��Y�i�����w�@��w�j
���e�F
�q�������\2���r14:00�`15:25
1�D�u����y�v�Ɓu�@�����y�v
�\�A���x���g�E�Q���I���E�V���^�C���̋���y�_
�����N�G�i������w��w�@�j
2�D���ۉ��y�R���N�[���Ɛ����{
�\���m���y���t�����ɂ�����u���x�����v�Ƃ��̔w�i�\
�_�ۉĎq�i���{�w�p�U����^������w��w�@�j
�q�C�V�V�q�搶�u����r�i���ψ�����j15:40�`17:30
�u��z�F���{���y�w��Ǝ��A�����Ď��̐�啪��v
�i2018/1/4�j
�w�u���H�́v����Ă�F��z�����w����̒�2�x�i2017�N12���A��z�����w�o�ʼn�j
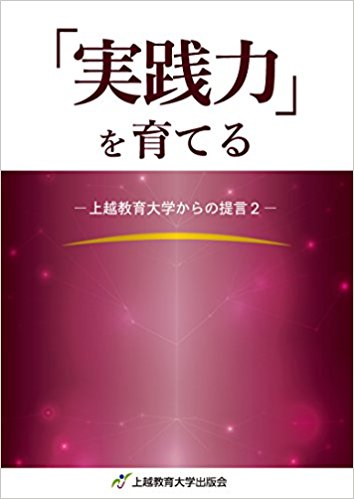
���ҁF��z�����w��
���s�F��z�����w�o�ʼn�
�����F�i�c����i���j�o�ŕ�
���s���F����29�N12��19��
�艿�F�{��2,700�~�{��
ISBN�F978-4-9906685-7-0
�{���́A�u21���I���������߂̔\�́v�̂����́u���H�́v���琬������@�ɂ��čl�@�������̂ł���A�e���Ȃ⋳�E�Ȗړ��̊w�K��ʂ��āu���H�́v���琬���邽�߂̕��@��Ӌ`�A�\���v�f���ɂ��Č������A��̓I�Ȉ琬�菇�A�]���K�����l�����B�{�N6���Ɋ��s�����w�u�v�l�́v����Ă�-��z�����w����̒�1-�x(��z�����w�o�ʼn�)�̑��҂ɂ����邪�A�O���̏����i�K����u�v�l�́v�́u���H�́v�ɂȂ���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��Ȃ��ƍl���Ă����B�l�Ԃ�Љ�̂���ׂ��p�Ƃ̊֘A�Ȃ��ɂ́A21���I���������Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B �u���H�́v�̈琬�����̕��@�ɂ���Đ��A����邱�Ƃ����������Ȃ�A���猻��ɂ����Ė{���͗L�Ӌ`�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��悤�B�{���������̋���ۑ����������[���ƂȂ�K���ł���B�i�u�܂������v���j
������A���A���J��A�ʑ��A���������y�Ȃ̐߂̎��M��S�����Ă��܂��B�i��1�͑�5�߁u���y�F���y�Ȃɂ�����u21���I���������߂̔\�́v�́u���H�́v�̑������v�A87-125�Łj
�w�����@�F�t�z�ُ��X�iTEL025-525-2530�j�A��z�����w���X�iTEL025-521-3644�j�A�i�c����iTEL025-523-4452�j�A�y��Amazon�ōw���ł��܂��B
�i2017/12/28�j
�ߋ��̃j���[�X�͈ȉ��ł��������܂��B
|