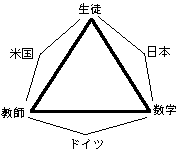
図1:各国の授業で優勢な要因
(Stigler & Hiebert (1999) を参考に布川が作成)
一方、第3回国際数学・理科教育調査では、米国、ドイツ、日本3ヶ国の数学の授業をビデオに撮って分析する、いわゆるビデオ・スタディも行われたが、その結果を踏まえて書かれた本 (Stigler & Hiebert, 1999) が出版された。ここで書かれている日本の授業の特徴を見ると、自分が感じたことと共通する部分がある。そこで本稿では、こうした特徴のいくつかを述べていくことにする。
なお、筆者の参観したのが研究用に計画された41時間の授業のみであり、しかも筆者のつたない英語力で理解した範囲のものであるので、ここで述べることは日米の授業についての一般的な比較や、まして米国の授業の批判を意図するものではない。むしろ異文化の中で改めて浮き彫りにされた、日本の授業の特徴を述べることを試みたい。
2. 授業におけるまとめ
スティグラーとヒーバートは、米国においてはOHPの利用が多いのに対し、日本の授業では黒板の利用が多いとしている (pp. 73-76)。しかし彼らはこれを単に指導に使うメディアの違いと捉えるのではなく、むしろ授業で何が大切にされるのかに関わる、ある種の文化の違いと考えている。米国でのOHPの利用が生徒の注意を一時的に引くために使われることが多いのに対し、日本の黒板の利用は、授業中に出された意見が蓄積されていくことを意図して用いられているというのである。
コブらのプロジェクトにおける授業では、自分たちの開発したソフトウェアの画面がプロジェクタによりスクリーンに映される一方で、ホワイトボードで生徒が自分の考えを説明する場面も多く、日本の授業の形態と近いようであった。しかし、その利用の仕方ということに注意を向けると、スティグラーらの指摘は正鵠を得ているように思われる。自分たちの考えを発表するときに、生徒がホワイトボードにそれを書いたり、あるいは教師がボードにまとめたりしても、別のグループの発表になると、前のものは簡単に消されてしまうのである。また、日本の授業であれば、いくつか出された考えを黒板に残し、さらにそれらを比較したりまとめたりすることで、最後には授業のポイントになる数学的アイデアを、教師が黒板にまとめることが多いであろう。しかし、参観した授業ではそうした流れは見られなかったようである。
こうした黒板の利用は日本人にとっては当然のことであるが、外国人研究者にこのように指摘されると、改めてその良さに気づくことができる。また、スティグラーらのこうした指摘を念頭においてコブらの授業を見ているうちに、いくつかの考えを比較・検討し、そこから数学的アイデアを引き出してくる授業のスタイルは、それら多様な考えを黒板などの上に残しておくことと、密接に関わっているのではないかとも感じた。
3.数学の内容の重視
スティグラーらが米国の授業の分析をするときに指摘することの一つは、比較的容易な問題を1時間の中で数多く提示するということである。日本の授業では、適度な難度をもった問題を1時間に1問から2問提示することが多い。このことを少しキャッチフレーズ化して言えば、日本の授業では数学的な内容が重視されている、と言えるのではないだろうか。実際、スティグラーらは、ビデオ・スタディに参加していたある研究者による、次のような特徴づけを紹介している(図1)。ドイツの授業には教師と数学があり、教師が数学を管理している。米国の授業は教師と生徒のやりとりが多いが数学がない。日本の授業は生徒が数学に携わっており、教師はその両者を媒介している (pp. 25-26)。また、日本の授業は「構造化された問題解決」とも特徴づけられている。
スティグラーらは、この特徴づけが非常に単純化されたものであることを認めながらも、一方で、これが各国の授業のある側面をうまく捉えたものであるとも感じているようである。そして、生徒と数学が大切にされ、教師がその仲介役を務めようとする日本の授業に対して、彼らは一定の評価をしているように見受けられる。つまり、教師が講義をするかのような授業でないと同時に、単なる話し合いや活動になってしまうのではなく、適度なレベルの数学が保証されていることは、算数・数学の授業にとって大切なことであると考えられていると言えよう。
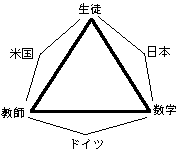
コブらの研究授業では、データの分布と共変 (covariance) を「ビッグ・アイデア」と称して、これにそったデータの分析が目指されていた。また、1つの課題を2〜3時間かけて扱っており、スティグラーらが分析した授業に比べると日本の授業に近い。しかし例えば、データを数学的アイデアに基づいて分析する場面で、教師の側も生徒の側も非常に頻繁に現実場面を参照することが多いために、現実に依拠した直観的な判断が常に現れ、数学的アイデアに焦点を絞りきれないように見えた。したがって、数学により現実場面の理解が深まるという印象も薄い。また、生徒は分布よりも個別のデータ点に注意を向けがちであったが、そこから分布の認識へつなげるための学習活動や話し合いの計画においても、方向性(例えば、分布と見ることでより適切に判断ができるといった経験)は曖昧に感じた。こうした傾向が、第2節で述べたまとめの希薄さと結びつくので、学習された数学的アイデアが何なのかは、一層わかりにくいように感じた。
逆に日本の授業においては、その授業や単元で学習される数学的アイデアが意識されていて、1〜2問の課題についての活動とそれに続く話し合いを通して、そうしたアイデアが生まれるよう計画されていることが多い。この意味で日本の授業では、授業の中で(当該の生徒に適当な)数学が「扱われている」ことが、見えやすくなっていると考えられる(こうした日米の差異のより具体的な姿については熊谷 (1992) を参照。また数学的内容の重要性については両角 (1998) も参照)。
4.知識の価値を伝える工夫
コブらの授業の中で、代表値としてのメジアンを生徒に理解してもらう場面があった。彼らはそれ以前の授業の中で、生徒自身の反射時間を測っていた(落下する棒をつかむというやり方で、各生徒が10回測定)が、そのデータから100個を選び、表の形に整理したプリントを生徒に配った。その表から今度は各生徒が9つのデータをランダムに選び、各自が9つのデータのメジアンを求めた。皆のメジアンを報告させた後、表全体のメジアンを教師が伝えた。両者が比較的一致することで、サンプルのメジアンが全体のメジアンを反映することの理解につなげようとしたものと思われる。しかしこの時点である女の子が挙手し、「一致するのは当たり前、なぜなら先生がその表をコントロールしているのだから」といった意味のことを発言した。
この女の子は、サンプルのメジアンが全体のメジアンと比較的近くなることは認めているのに、メジアンのよさは感じていないように見られる。この授業を参観したときに、日本の優れた実践の持つ一つの特徴が筆者には思い出された。それは、生徒の側に「驚き」が生ずるような工夫がされているということである。例えば、現実と無関係だと思っていた数学を用いて、現実についての情報が得られ、しかもそれが現実のことをより深く理解する助けになりうる、といった経験が、日本の実践には含まれている(例えば、永田, 1999)。あるいは、生徒が「驚く」ような現象を目で見せたあと、その仕組みを数学を使って解明するとか、数学を利用して常識に反するような情報を作りだして見せるとか、作れそうもない図形の面積の公式が、授業の最後にはいろいろアイデアを通して作られる、といった工夫が授業になされていることが多い(布川, 1999)。つまり、日本の優れた実践では、数学的知識の価値を伝える工夫がなされているのである。
上で見たメジアンについての授業でも、例えば、サンプルを調べるだけでデータ全体のことがかなりわかる、という「驚き」を生徒の側に引き起こすことができれば(出口 (1997) の第4章を参照)、数学的アイデアのよさを生徒に感じてもらうことができたのではないかと考えられる。単に数学的内容に関わる活動を取り入れるだけではその価値は伝わりにくいこと、またある種の「驚き」が生ずるような演出を考えることの大切さを、この授業は示しているように感じられた。
5.おわりに
福田 (1993) は、物理と数学が死ぬほど嫌いな高校生の作文を紹介している。彼女の場合、国語、英語、世界史では「外人にこんなことを伝えたいときはなんて言えばいいだろう」「もし自分がこの時代に生きていたらどんな暮らしをしているだろう」と想像(イメージ)が広がるのに、数学ではそれが起こらず、結果的に嫌いになったとされている。よく知られているように、我が国の子どもは、数学を楽しいと思う割合が国際的に見て低い(国立教育研究所, 1997)。もしもこの原因の一端が、福田 (1993) が指摘するように、イメージの広がりに関わるとすれば、単純に算数・数学の内容を削減することでは対処できないと思われる。米国が自国の数学教育の問題点として扱われる内容のレベルの低さをあげ、数学の "存在" を必要と感じているとすればなおさらである。
上で見てきたように、我が国の算数・数学の授業にはいろいろなよい面がある。こうした財産は今後の数学教育においても十分生かしていくべきであろう。一方、授業での生徒の「驚き」を保証することは、一部の実践には見られても、全ての教室で普及しているかは疑問のように思われる。「本当にそんなことがわかるの?」「数学はそんなところにも使えるんだ!」といった驚きを生徒に感じてもらえる授業を1回でも多く含め、イメージの広がりを伴った算数・数学の授業を行うことで、さらに我が国の算数・数学の授業を改善していく余地もあるように思われる。