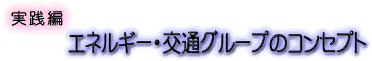(1)新学習指導要領との関係
本実践では、近年、我が国だけでなく世界各地で再評価がなされているLRT(Light Rail Transit)に焦点をあて、日本とアメリカにおける都市の公共交通と環境への配慮について考えることにする。
平成11年に告示された高等学校学習指導要領においては、地理Aの内容「(2)地域性を踏まえてとらえる現代世界の課題」の「イ 地球的課題の地理的考察」の「(ア)諸地域から見た地球的課題」で、次のような扱いが求められている。
「環境、資源・エネルギー、人口、食料及び居住・都市問題を地球的及び地域的視野から追究し、地球的課題は地域を超えた課題であるとともに地域によって現れ方が異なっていることを理解させ、それらの課題の解決に当たっては各国の取組とともに国際協力が必要であることについて考察させる。」
また、同じく地理Bの内容「(3)現代世界の諸課題の地理的考察」の「オ 環境、エネルギー問題の地域性」、「キ 居住、都市問題の地域性 」では、次のようである。
「環境、エネルギー問題を世界的視野から地域性を踏まえて追究し、それらは地球的課題であるとともに各地域によって現れ方が異なっていることをとらえさせ、その解決には地域性を踏まえた国際協力が必要であることなどについて考察させる。」
「居住、都市問題を世界的視野から地域性を踏まえて追究し、それらの問題の現れ方には地域による特殊性や地域を超えた類似性がみられることをとらえさせ、その解決には地域性を踏まえた国際協力が効果的であることなどについて考察させる。」
すなわち、地理A・地理Bのいずれの科目においても、環境問題や資源・エネルギー問題、居住・都市問題を、地球的及び地域的視野から追究して、それらが地域を超えた課題であるとともに地域によって現れ方が異なることを理解させ、解決に当たっては国レベルだけでなく、国際協力が必要であることを考えることが、求められている。
そのため、本実践において、我が国とアメリカ合衆国におけるLRTの復権の状況を考えることは、この新学習指導要領の趣旨に基づくものである。つまり、本実践は、LRTをとおして環境問題、資源・エネルギー問題、居住・都市問題を、日米各国のそれぞれと比較の視野から追究し、それらが両国を超えた課題であるとともに各国によって現れ方が異なることを理解させ、解決に当たっては国レベルだけでなく、国際協力が必要であることを考えるものである。
(2)教材化の意義や教師の教材観
我が国において、現在、都市における移動手段としては、自家用車・バス・電車・地下鉄などが主流である。これらの手段はいずれも整備が整い、生活上欠かせないものとなっている。しかし、これらの交通手段を、環境との関係で考えてみると、いずれも何らかの問題を抱えている。例えば、自家用車やバスは、かつてよりも改善が進んでいるとは言え、その排気ガスがもたらす大気汚染は深刻である。電車や地下鉄については、その沿線での騒音や用地確保、施設整備の際の特に社会環境に与える影響は、さけることのできない問題となっている。このように、現在、都市の交通は環境への影響という側面から、構造的な転換が求められている。そこで、今、このような問題を解決する交通手段として、LRTの再評価が我が国において活発に進められている。
その動きの一端としては、1993年6月より、路面電車のもつ多様な可能性を広く世に問うべくはじめられた「路面電車サミット」に見ることができる。この集まりは当初、路面電車愛好団体のつどいとしての性格が色濃かったが、現在では各路面電車事業者をはじめ、一般市民や行政などの参加も目立つようになっている。第1回の開催地は札幌市で、以後2年おきに、路面電車の走る都市で順番に開かれている。ちなみに、1995年が広島、1997年が岡山、1999年は豊橋で開催された。
我が国におけるLRTの再評価は、実はアメリカでの動向の影響を強く受けている。アメリカでは、自動車会社の圧力もあって、公共交通を保護するのではなく、もっとも自由度の高い移動手段である自動車交通を前提に道路整備を重点とした投資が進められてきた。この結果として、ほとんどの都市の交通は自動車とバスのみに依存するようになったが、1960年代になると、はやくも自動車交通が行き詰まり、その弊害が現われるようになった。具体的には、自動車の集中による都心部の混雑、バスの運行サービスの低下によるトランスポーテーションプアに対する移動の自由の喪失、化石燃料の浪費による資源枯渇と大気汚染、マイカーに起因する犯罪・交通事故の増大、および市域の拡大による都心商業施設の衰退などである。これは、自動車だけに依存してきた都市交通の限界を示すもので、人種問題もからんでヨーロッパより深刻な問題となった。
このような環境下において、早くも1962年に都市大量交通機関の維持や充実の必要性がうたわれたはじめ、1968年に都市の公共交通機関に自動車よりも魅力的なものを創造することが提唱され、主管する部署として運輸省(DOT:Depertment of Transportation)が設立された。これはエネルギー問題と道路混雑の緩和を目的に、道路経済効率の向上を狙った施策という解釈もできるが、いずれにしろ公共交通の必要性を打ち出したことは、自動車中心の交通政策からの一大転換といえるものであった。そして、運輸省の目玉として新しい都市交通システムの開発が始まった。
新時代の路面電車を意味する言葉として、よくライトレールという言葉が使われるが、このライトレールという言葉を、いわゆる路面電車に初めて使ったのは、アメリカの運輸省である。アメリカの都市交通の改善は、当初はコンピュータで制御する新交通システム指向であったが、DPM(ダウンタウン・ピープル・ムーバー)として都心部の再開発を目的にデトロイトとマイアミに建設したものの、あまりにもお金がかかるため、その代わりとして目を付けたのが西ドイツで都市交通機関として改良が進められていた路面電車であった。当時、アメリカにはボストン、ニューアーク、フィラデルフィア、ピッツバーグ、クリーブランド、ニューオリンズ、サンフランシスコの7都市に路面電車が残っていたが、まずボストンとサンフランシスコで近代化のため新しい路面電車の標準車を造るにあたり、古くさいイメージを与えている「ストリートカー」とか「トロリー」という言葉に変わって、新しい言葉を考え出した。それがLRT=「LIGHT RAIL TRANSIT」という言葉であり、その車両であるLRV=「LIGHT RAIL VEHICLE」という言葉であった。
アメリカの運輸省がこの時に定めたライトレールの定義は、新交通システムと違うということで「電動機駆動によって二本のレールの上を走る車両を使用する」という規定もあるが、一番の特徴は「大部分の区間を他の交通機関から分離した軌道を走行する」、すなわち自動車に邪魔されずに走れる交通システム、言い換えれば自動車と共存が可能なシステムということである。日本ではまだ、ライトレールは都市交通機関として位置づけがされていないが、アメリカでは既存の都市鉄道システムの中で、路面電車と都市高速鉄道の中間にあたる中量輸送機関としてしっかりと位置づけられた。
こうして北米では、1978年にカナダのエドモントンに初めてのライトレールが開通し、81年には同じカナダのカルガリーとアメリカのサンディエゴにも新しく開通した。アメリカのライトレールは、当初は走行路の自動車との分離を図った高速路面電車指向だったが、それにちょっと味付けをした。すなわち、新交通システムの開発で行おうとしたコンセプト、都心部での短距離の移動に便利な公共交通システムの機能を兼ねさせようとした。
前述の通り、アメリカの公共交通見直しの最大の理由が、モータリゼーションの進展による都心部の衰退であったわけだが、その再開発を進めるに当たり、一番のポイントとしたのが、車の侵入を禁止し、人中心の商業街路の中に路面電車を走らせたトランジットモールの建設であった。そこに人を集めるだけでなく、モール内の移動手段、すなわち水平エレベーターとしても使えるライトレールは、まさに格好の輸送システムであった。それは目的とした再開発において、都心に人が戻って活性化が図れるという大成功を収めた。また徹底的に合理化・省力化されたシステムである事から、サンディエゴではアメリカとしては大変珍しく、営業経費の90%を運賃で賄える好成績をおさめ、全米のライトレール建設の引き金となった。
こうして、1984年にはバッファロー、1986年にはポートランド、1987年にはサクラメントとサンノゼ、1990年にはロサンゼルス、1991年にはボルチモア、1993年にセントルイス、1994年にデンバー、1996年にはダラスで開業した。
加えて、日本での想像以上に深刻といわれる大気汚染や、道路渋滞による環境の悪化は、ライトレールの導入を早めることになった。サクラメント、ポートランド、そしてロサンゼルスでは、フリーウェイの建設にかえてライトレールを建設する道を選んでいる。それらはまさしく、LRTの復権であった。
以上のようなLRTを取り巻く状況は、日本とアメリカにおける都市の公共交通と環境への配慮について考えるのに、優れた教材となりうる。
註:上記の文章の一部は、「路面電車サミット'97 in OKAYAMA」における「第1分科会:LRT部会」での服部重敬氏の基調講演「なぜいまLRTなのか」を、若干修正したうえで引用させていただいている。
2.授業構想(教授・授業書)
| 「日米におけるLRT(路面電車)復権の理由を探る」 | |
(2)目 的: |
日本とアメリカにおいて、LRTが再評価されている理由を探ることをとおして、環境に対する今後の都市交通の在り方について考える。 |
(3)展 開 |
|
発問・指示 |
学習活動 |
|
|
|||
| ・皆さんは、今日、学校までどのような交通手段を利用しましたか。(皆さんが、都市での移動でよく利用する手段は何ですか。) | T:発問する | |||||
| P:答える | ・徒歩、自転車、車、バス、電車、地下鉄、等々。 | |||||
| ・その中で、車・バス・電車や地下鉄は、なぜ、それを利用するのですか。 | T:発問する | |||||
| P:答える |
・速くて便利だから。
・距離が遠くても快適に移動できるから。 |
|||||
| ・一方で、それらの移動手段には、どんな問題がありますか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・交通渋滞、交通事故、排気ガスによる大気汚染、通勤通学ラッシュ、等々。 | |||||
| ・では、皆さんはこの乗り物は何か分かりますか。 | T:発問する | [1] | ・路面電車、チンチン電車。 | |||
| P:答える | ||||||
| ・この路面電車にどんなイメージを持っていますか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・古い乗り物、運賃が安いけど速度が遅い、等々。 | |||||
| ・では、この乗り物を見たことがありますか。 | T:発問する | [2] | ・路面電車みたいだけど、ちょっと違う?。 | |||
| P:答える | ||||||
| ・これはLRTです。ヨーロッパやアメリカの都市部で近年、導入が進められている乗り物です。 | T:説明する | |||||
| ・実は、日本でもLRTが導入された都市があります。どこでしょうか。ヒントはこの写真です。 | T:発問する | [3] | ||||
| P:答える | ・広島(熊本でも導入されている)。 | |||||
| ・広島は大都市の一つですが地下鉄がないのです。なぜでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・太田川三角州上に都市が形成されたため、地盤が弱く、地下鉄の整備が困難なため。 | |||||
| ・しかし、現在土木技術の進歩で広島のような場所でも地下鉄の整備は可能になっています。それなのに、広島では地下鉄を作るよりもLRTの導入を選びました。なぜ、でしょうか。 |
T:発問する | |||||
| P:答える | ・建設費が格段に安いから。 | |||||
| ・他の理由はないでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・? | |||||
| ・それでは、この問題を日本とアメリカの具体的な事例を検討しながら考えてみよう。 | T:指示する | |||||
|
||||||
| ・この資料は、世界各国と日米のLRT(路面電車を含む)導入都市のリストです。 | T:提示する | [4] | ||||
| ・これを見て各都市の共通点と相違点を考えてください。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・大都市もあれば、それほど大きくない都市もある。先進国もあれば、発展途上国の都市もある。 | |||||
| ・それでは、この都市のうち、アメリカを事例にいくつかを抽出して、その実態を考えてみよう。 | T:発問する | |||||
|
||||||
| ・ピッツバーグは、アメリカの中でも最も早くから路面電車が都市の交通手段として利用されていました。どれくらい前からだと思いますか。 | T:発問する | [5] | ||||
| P:答える | ・資料[5]を見ると、1859年に馬車、1888年にケーブルカー、1890年に電気による路面電車が開通となっています。 | |||||
| ・日本の年号ではどうでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・1859年はまだ江戸時代です。1888年は明治21年、1890年は明治23年です。 | |||||
| ・では、その頃の路面電車の姿を見てみましょう。(数枚の写真を提示する) | T:提示する | [6] | ||||
| ・写真でも分かるように、非常に多くの電車が走り、多くの人々が利用していました。しかし、第2次世界大戦後に、ピッツバーグの路面電車は衰退し始めます。何故でしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・自家用車の普及により、利用者が激減したから。 | |||||
| ・どの位、衰退したかですが、1952年と1985年の路面電車網を比較してみよう。 | T:提示する | [7] | ||||
| P:答える | ・かつてはダウンタウンのほとんどの通りに路面電車が走っていたのに、今は路線が少なくなっている。 | |||||
| ・路線は少なくなったけど、未だに残っています。車があるから、もう路面電車なんていらないのではないでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・そう思うけど、みんなが車を使うわけでもないし、またみんなが車を使って町中に行くと大渋滞で、大気汚染の問題もある。 | |||||
| ・その通りです。ピッツバーグだけでなく、アメリカでは、自家用車の普及に伴い、それ以外の交通手段の見直しが世界でも最も早く進んでいると言えます。 | T:説明する | |||||
| ・ピッツバーグでも、昔と比べると路線は少なくなってけど、色々と見直して路面電車を再び充実させる動きが見られます。どんな点でしょうか。 | T:発問する | [8] | ・資料[8]によると、路線の一部を地下にしたり、併走する道路を走る車の規制を行って、より利用しやすい環境を整えている。 | |||
| P:答える | ||||||
| ・では、ピッツバーグ以外のアメリカの都市の路面電車の状況も見てみよう。 | T:提示する | |||||
|
||||||
| ・サンフランシスコは路面電車というよりもケーブルカーで有名ですが、ケーブルカーも路面電車の一種です。実は、サンフランシスコにはケーブルカーの他にも路面電車があるのですが、調べてみよう。 | T:指示する | [9] [10] |
・資料[9]を見ると、サンフランシスコではケーブルカーの路線以外に、Fラインやミニメトロなど、いくつもの路面電車が縦横に走っている。 | |||
| P:答える | ||||||
| ・ピッツバーグでは、自動車の普及により路面電車はかつてよりは衰退しましたが、サンフランシスコではかつてよりも路線も増えて、発達しています。なぜでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・? | |||||
| ・ヒントはこの地図を見てください。 | T:提示する | [11] | ||||
| P:答える | ・サンフランシスコの地形は垂直方向に入り組んでいるために、他の交通機関や手段と比較しても、最も適しているため。 ・人口規模がピッツバーグと比べて圧倒的に多いために、自家用車以外の手段を用いる人々の数も激減はしなかったため。等々。 |
|||||
|
||||||
| ・サクラメントに、路面電車が開通したのはいつですか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・資料[4]によると、1987年です。同じ年にサンノゼも開通しています。 | |||||
| ・サクラメントは、アメリカの中では近年、LRTを導入した都市の代表となっています。 | T:説明する | |||||
| ・資料を見て、サクラメントのLRTがピッツバーグやサンフランシスコと異なる点はどんな所だと思いますか。 | T:発問する | [12] | ||||
| P:答える | ・路線が郊外にまで延びていて、更に延長工事も行われている。 ・31の駅全てに移動タラップあるいはリフト、スロープがあり、高齢者や障害者への配慮が行き届いている。 ・更に低床車両の導入も予定されている。 ・13の駅がバス輸送サービスを行っている。 ・10の駅では4,020台の駐車スペースを用意した無料パークアンドライドシステムを利用できる。 |
|||||
| ・以上、アメリカにおける路面電車の状況を見てきましたが、これをふまえて、なぜ現在、路面電車が見直されて導入が進められているのか、整理して答えてください。 | T:発問する | |||||
| T:答える | [1]「建設費が安い。」 LRTの建設費は、高架・地上・部分地下、そのシステムにもよりますが、地下鉄をつくるより、安く済む。モノレール や新交通システムをつくるより安く済むという試算も多数出ている。財政の危機が叫ばれる今、市民の税 金を使って行う公共事業は、市民に有効に働かなければ意味がない。高価な地下鉄をつくって、巨額の赤字を抱えるより、実用性の高いLRTをつくった方がいい。 [2]「環境への負担が少ない。」 地下鉄や新交通システムは建設に伴い、多大な自然・社会環境を犠牲にするが、LRTは主に既存の道路・路面に即する形で建設するために負担は小さく抑えられる。また、バスとの比較では排気が全くないという利点がある。 [3]「バリアフリーに低コストで対応できる。」 LRTの利点として、「地上から乗れて便利」という点がある。線路を地上に敷けば、乗り降りは便利であり、何より段差がないので、車椅子の方やお年寄りの方にも乗り降りしやすい交通機関になる。しかし、大都市の交差点では、クルマの通行の妨げになる。それでもいいという街もあるだろうし、それでは困るから、線路を地下や高架にしたほうがいい、と考える街もある。「LRT」というシステムは、それらに対応するフレキシブルな能力を持っており、しかも低コストで対応できる。 [4]「定時性がある。」 バスだと、何時に着くか不安で、特に通勤・通学など、決まった時間までに目的地に着く必要があるとき、困る。電車や地下鉄では、その運行はダイヤ通り行われ、決まった時間に目的地に着くことが出来る。鉄道の仲間であるLRTも、同じメリットを持っている。 [5]「中間性の優位がある」 LRTには他と比較して絶対的に優位という点はないと言える。例えば、自動車の「ドアツウドア」、バスの「路線の緻密さ」、電車の「速さと定時性」、といったものに競合できるLRTの優位点はない。しかし、それらの交通手段は優位点とともに絶対的な欠点も持ち合わせている。LRTは絶対的な優位点はないが、絶対的な欠点も見あたらない。その「中間性」こそがLRTの最も支持される点である。特に都市交通と環境の観点からみると、LRTの中間性は人の利便性と環境との共存といった点でも、その優位点を発揮できるものと考えられる。 |
|||||
|
||||||
|
||||||
| ・ここまで、アメリカを事例にLRTの良さを中心に学習してきましたが、LRTは本当に良いことばかりなのでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・? | |||||
| ・例えば、現在、ミネアポリスでは、LRTを新設する計画と準備、そして一部で建設も始められています。そこである市民の方から聞いたのですが、LRT新設に反対の人々も少なからず存在するとのことです。なぜでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・道路に沿って建設すると言っても、やはり沿線の人々は騒音問題で反対なのでは。 | |||||
| ・騒音に関しては、新しいLRT車両だとほとんど問題にはならないようです。その市民によると、LRT新設で便利になるのが困るというのです。なぜでしょうか。 | T:発問する | |||||
| P:答える | ・もしかして、治安の問題ではないでしょうか。アメリカの都市部ではある程度の収入がある人々は都市部よりも郊外に家を持ちます。そこは、交通に不便でも、というか不便だからこそ治安は良いと聞きます。LRTができて便利になると、その沿線は治安が悪くなる可能性があるから、反対しているのではないでしょうか。 | |||||
| ・その通りです。日本の感覚ではちょっと考えられませんが、便利になると困る人々が多い、というのはアメリカ都市部に特有に問題のようです。 では、こんな観点も視野に入れながら日本のLRTについても考えてみましょう。 | T:説明する | |||||
|
||||||
| ・それでは、日本のLRTについては、皆さんにそれぞれ調べて来てもらいたいと思います。現在、日本の路面電車都市は19です。またLRTの新設が検討されているのは、浜松市・奈良市・尼崎市、そして東京でも計画があります。いずれかを選んで、その実態と課題をレポートしてください。 | ||||||
(4)資料一覧
| [1] | 路面電車の写真(http://www.urban.ne.jp/home/yaman/ を参照) |
| [2] | LRTの写真(http://www.urban.ne.jp/home/yaman/ を参照) |
| [3] | 広島電鉄グリンムーバの写真(http://www.urban.ne.jp/home/yaman/ を参照) |
| [4] |
世界各国と日米のLRT(路面電車を含む)導入都市のリスト (http://www.urban.ne.jp/home/yaman/white.htmを参照) |
| [5] | PAT,Streetcars in the GoldenTriangle 1859-1985,Pittsburgh,Pennsylvania.(英文小冊子) |
| [6] | 資料[5]中の写真(本稿巻末を参照) |
| [7] | 資料[5]中の路線図(本稿巻末を参照) |
| [8] | ピッツバーグLRTの写真(本稿巻末を参照) |
| [9] | サンフランシスコ路面電車路線図 (http://www.transitinfo.org/cgi-bin/muni/map/systemを参照) |
| [10] | サンフランシスコ地図(鳥瞰絵地図または地形図) |
| [11] | サンフランシスコLRTの写真(本稿巻末を参照) |
| [12] | サクラメントLRTの写真とHP (本稿巻末及び http://www.sacrt.com/を参照) |
参考引用URL
| ・ | 「路面電車サミット'97 in OKAYAMA」における「第1分科会:LRT部会」での服部重敬氏の基調講演 「なぜいまLRTなのか」(http://www.urban.ne.jp/home/yaman/okayama.htm) |
| ・ | 大阪市立大学インターネット講座における西村弘氏の講義「クルマ社会の都市と交通」 (http://www.hosp.msic.med.osaka-cu.ac.jp/koho/vuniv99/lectnish.htm) |
| ・ |
北海道大学LRTとまちづくりの勉強会HP (http://home4.highway.ne.jp/%7Em-takuya/LRT/index.html) |
| ・ | 環境週間東京都実行委員会・東京都主催「環境問題を考える都民のつどい」における東京大学森地茂氏の 講演「東京における自動車利用のありかた」 (http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/koho/tudoi_03.htm ) |
| ・ | サンフランシスコのMunicipal Railway (Muni)のHP (http://www.ci.sf.ca.us/muni/) |