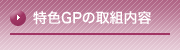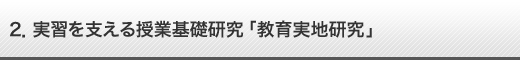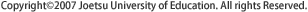授業基礎研究「教育実地研究II」の実際 2005年 春~夏
|実習前全体指導|実習後全体指導|学習指導案個別検討会|アンケート結果|成果と課題|
観察実習前の全体指導
学部3年生は,5月30日からの1週間,観察実習に取り組みます。そこで,5月25日に次の(1)~(3)について全体指導を行いました。
(1) 形成できる技術と困難な技術
「授業を観察分析する技術」,「学習指導案を作成する技術」,「授業を運営する技術」,「授業を自己評価する技術」のそれぞれにおいて,実習で形成できる技術と形成が困難な技術とがあることを説明しました。実習中は形成が困難と思われる技術の習得にも積極的に挑戦してほしいと激励しました。また,授業を観察する際は,三つの目(子どもを見る目,教材を見る目,授業運営を見る目)をもって臨んでほしいことを話しました。
そして,9月12日から3週間行われる本実習までの流れと学習指導案作成の課題(細案を二つ作成すること)を伝えました。
(2) 研究期間における教材研究の進め方
観察実習終了から本実習開始までの4か月が学部3年生にとっての研究期間となります。この期間を有効に活用してもらうために,次の事項について指導しました。
-
○教材研究の進め方 ― 小学校社会科を例に ―
- 学習指導要領で,学習の目標と内容を確かめる。
- 教科書や指導書を読んだり,年間指導計画を見たりして,単元の構成(流し方)の概略を把握する。
- 児童が興味を引く教材,熱中できる教材,ダイナミックな活動ができる教材はないか,創意を発揮して考える。
- 授業に役立つような資料を集めたり,学習対象となる人に聞き取りをしたり,教材・教具を作ったりする。
- 学習の流れを書いてみる。
- 学習指導案を書く。
- 再度吟味し,修正していく。
- 授業の準備をする。
- ○教材研究の方法
- 視聴覚教材を探す。
- 校区や見学場所を歩いて事前調査を行う。
- 資料を収集して,教材として生かす。
- 先行実践等からアイディアに富んだ教材,魅力ある教材を発掘する。
- 教材となる動植物を飼育・栽培する。
- 自作教具を製作する。
- 事前練習・実習・実験を行う。
- ○教材研究に対する考え方
- よい授業をするには,教材研究が欠かせない。
- 教材研究は,教員採用試験の最大の勉強である。
- 教育実習での努力は,教師になっても生き続ける。
(3) 観察参加のポイント
学部3年生は,1年次において小規模小学校・特別支援学校・附属中学校の観察・参加実習,2年次において幼稚園観察・参加実習を経験しています。しかし,3年次の秋の本実習で担当する学級を観察するのは初めてです。観察参加のポイントとして,次の6項目について指導しました。
- ○その学級・教師の授業スタイルを見よ
- 活動型,作業型,講義型,問答型,討論型,複合型など,様々なスタイルがある。
- ○授業の骨格を見抜け
- 授業のよしあしは,教材と発問・指示とに規定される。
- ○教師の微細技術を抜き出せ
- 指名や板書など,教師のちょっとした行為にも意味がある。
- ○子どもの実力を診断せよ
- 書く力はあるか,話す力は育っているか,自分が授業をするつもりで見る。
- ○「記録簿」の例
- 子どもの言動や教師の行為が分かるように書く。
- ○個別指導をせよ
- 全て観察に終わるのでなく,授業中にも子どもとかかわる。
|実習前全体指導|実習後全体指導|学習指導案個別検討会|アンケート結果|成果と課題|
観察実習後の全体指導
学部3年生の観察実習を終えた翌週の6月8日,5教科(国語・社会・算数・音楽・体育)の学習指導案作成について全体指導を行いました。 ここでは,算数の学習指導案作成について指導した14項目を列挙します。
- ○教材研究
- 教材を十分に理解し,解釈しているか。
- 取り上げる単元の系統性(9年間の学習の中の位置付け)を把握しているか。
- 「こういう授業をしたい」「この単元を通して子どもたちにこんな力をつけたい」という信念(思い)が固まってきているか。
- ○本時のねらい
- ねらいは明確になっているか。
- ○課題(問題)
- 子どもが興味・関心,問題意識をもてるようになっているか。
- ○提示の仕方
- 問題そのものを提示するのか。具体的な活動 を通して問題化していくのか。
- 導入課題と関連する既習事項をどのように想起させるか。
- ○児童の実態
- 本時の課題を解決するために必要な既習事項を洗い出したか。
- 既習事項について,一人一人の状態を把握したか。
- ○教具の準備
- 子どもが使用する物は,使いやすさ等に配慮したか。
- 安全上問題はないか。
- 教育機器の利用は考えてみたか。
- ○反応の予想と手だて
- 子どもの多様な反応を十分に予想したか。
- 多様な反応に対応する手だてを様々に考えたか。
- 子どもの考えをどのような順番で学級全体に取り上げるのか。
- ○子どもにさせたい活動
- どの場面でどのような操作をさせたいのか。
- どの場面でどのような話合いを仕組むか。
- 学習形態をどうするか。
- ○発問
- 発問を吟味したか。
- 教えることと考えさせることとの区別がついているか。
- 授業の山場を想定しているか。
- 授業の山場に向けて,子どもを揺さぶる準備はあるか。
- 学習内容を整理する場面が必要かどうかを考えたか。
- ○板書の計画
- どのようなことを,どのような順に,黒板のどの位置に書くのか。
- 子どもの多様な考え(記入させた用紙)を,黒板のどの位置に紹介するのか。
- ○時間配分
- 子どもが考える時間,発表に要する時間,全体で考える時間,まとめる時間等の配分を考えてあるか。
- ○机間指導の準備
- 子どものつまずきを具体的に予想し,手だてを複数用意したか。
- 課題解決が早く終わる子どもには,どのように対処するか。
- 必要に応じて,座席表への記入準備はできているか。
- ○評価
- どの場面で評価するのか。
- どのような方法で評価するのか。
- どのようになっていればよいのか。
- ○最後に
- 授業者の主張が伝わるものになっているか。
- 自分が創った学習指導案になっているか。
ここに示した14項目を解説した後に,複数の教科書分析による教材研究の仕方を例示しました。小学校1年の算数の単元「たしざん(2)」を例にして,6社から発行されている教科書を実際に分析した一覧表を示し,教科書分析から見えてくる「教材研究の視点」について解説を加えました。
表1. 6社の教科書分析表の一部| A社 | C社 | |
| 導入場面 | 絵 さつまいも 問題文 |
絵 牧場 問題づくり |
| 合併・増加 | 合併 | 増加2つ 合併1つ |
| 登場する数値 | 8と7 | 5と3 9と3 7と9 |
| 「5」の意識 | さつまいもの絵 ブロック図 |
ブロック図 |
| 導入の特徴 | 加数分解 被加数分解 |
問題づくり 既習の計算の登場 |
| ブロック図 | 横置き | 縦置き |
|実習前全体指導|実習後全体指導|学習指導案個別検討会|アンケート結果|成果と課題|
学習指導案の個別(グループ別)検討会
学部3年生は6月17日までに,国語,社会,算数,理科,生活の中から一つを選択し,学習指導案の細案を作成して提出しました。また,6月24日までに音楽,図画工作,家庭,体育,道徳,学級活動の中から一つを選択して,学習指導案の細案を提出しました。こうして,学生は2種類の学習指導案を提出しました。提出された学習指導案の総数はおよそ340部になりました。
附属小学校の教員も参加し,これらの学習指導案をすべて読み,朱を入れ,一つ一つの学習指導案に対しておよそ15分程度の個別,あるいはグループ別検討会を実施しました。ねらい達成のための指導構想や付けたい力,指導方法等にかかわって指導し,学生自身の課題を明確にできるようにしました。更に,これらの指摘を基に学習指導案を修正することを課し,2回目の個別指導で再度指導しました。検討日は,学生の研究期間内の6月22,29日,7月6,13日,8月31日,9月1,2,7,8日の9日間です。
検討会の際に,次のような問い掛けをすると,返答に困る学生が少なくありませんでした。
- この単元の学習を通して,どのような子どもになってほしいと考えているのか。
- 児童の実態では,このように書いてあるが,これらの傾向をどのようにしてつかんだのか。
- 展開部分で,最も工夫したところはどこか。
- この部分では,実際にどのような発問をするつもりか。
- 予想される子どもの反応として,他に考えられないか。
- この方法で子どもが活動できないとき,次の手としてどのようなことを考えているか。
学習指導案は全体的に次のような傾向が見られました。
- ○単元設定の理由
- 教材観として,本単元についての記述はあるが,これまでの単元や今後学習する単元とのかかわりについて言及しているものは少ない。また,この単元の学習を通して,「このような子どもに育てたい。」という信念の伝わってくるものが少ない。
- 児童の実態として,一般的な実態を記述していて,実習する学級の実態になっていない場合がある。
- ○展開の角度
- セールスポイントになる部分,工夫した部分の記述が見られない。
- 単元の指導計画を説明するだけになっている。
- ○評価
- 評価の計画において,何をみて評価するのかが書かれていない。
- ○本時
- ねらいが具体的でないものがある。
- 展開の視点にセールスポイントがほしい。
- 展開では,発問が具体的でないもの,予想される児童の反応が曖昧なもの,手だてに欠けるものが見られる。
|実習前全体指導|実習後全体指導|学習指導案個別検討会|アンケート結果|成果と課題|
アンケート調査の結果
(1) 本実習後のアンケートから
本実習を終えた学部3年生を対象に,10月5日,アンケート調査を行いました。
設問「教育実地研究Ⅱ(3年次:学習指導案の書き方や個別指導)は,指導計画立案や指導場面で生かされたか。」に対して,次のような回答を得ました。
| □1 大いに役立った。 | 52.3%(79名) | 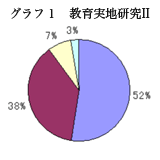 |
| □2 少し役立った。 | 37.7%(57名) | |
| □3 余り役立たなかった。 | 7.3%(11名) | |
| □4 全く役立たなかった。 | 2.6%( 4名) | |
「役立った」と回答した学生は「大いに」と「少し」を合わせると90%になります。 また,「教科指導法で学んだことが,指導計画立案や指導場面に生かされたか。」という設問については,次のような回答でした。
| □1 大いに役立った。 | 19.2%(29名) | 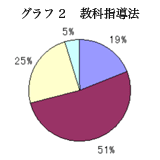 |
| □2 少し役立った。 | 51.7%(78名) | |
| □3 余り役立たなかった。 | 24.5%(37名) | |
| □4 全く役立たなかった。 | 4.6%( 7名) | |
教科指導法が「役立った」と回答した学生は「大いに」と「少し」を合わせると70.9%になります。 多くの学生は,「教育実地研究Ⅱ」及び「教科指導法」で学んだことを指導計画立案や指導場面に生かしていることが分かります。
(2) 算数の学習指導案作成者へのアンケートから
算数の学習指導案を作成した63名の学生に対し,学習指導案を検討した際にアンケート調査(6月22,29日)を行いました。以下はその結果です。
| ・教科書の教師用指導書 | 95.2%(60名) |
| ・本学の教育実習の手引き | 93.7%(59名) |
| ・学習指導要領解説算数編 | 68.3%(43名) |
| ・算数の教科書 | 65.1%(41名) |
| ・学習指導要領 | 36.5%(23名) |
| ・他社の算数の教科書 | 34.9%(22名) |
| ・先輩の学習指導案 | 11.1%( 7名) |
| ・書籍 | 9.5%( 6名) |
| ・学部3年生 | 55.6%(35名) |
| ・学部4年生 | 17.5%(11名) |
| ・実習校の先生 | 11.1%( 7名) |
| ・大学の先生 | 7.9%( 5名) |
| ・大学院生 | 3.2%( 2名) |
| ・児童の実態 | 69.8%(44名) |
| ・教材観 | 52.4%(33名) |
| ・展開の角度 | 49.2%(31名) |
| ・評価規準 | 39.7%(25名) |
| ・展開 | 23.8%(15名) |
| ・展開の視点 | 14.3%( 9名) |
| ・単元のねらい | 12.7%( 8名) |
| ・単元の指導計画 | 12.7%( 8名) |
| ・本時のねらい | 1.6%( 1名) |
9割以上の学生は,学習指導案作成時に「教科書の教師用指導書」と「本学の教育実習の手引き」とが参考になったと回答しています。一方,「学習指導要領」や「学習指導要領解説算数編」が参考になったと回答した学生はそれぞれ4割弱,7割弱程度でした。
また,5割以上の学生は,同学年配属の学生と相談しながら学習指導案を作成しています。
「書きにくかった項目」については,「児童の実態」「教材観」「展開の角度」が上位を占めました。
|実習前全体指導|実習後全体指導|学習指導案個別検討会|アンケート結果|成果と課題|
成果と課題
学部3年生が初めて書いた学習指導案の細案,およそ340部すべてを読むことによって,授業を構想する力の現状が大まかながらも把握できました。このことが最も大きな成果です。また,教育実地研究Ⅱ(3年次:学習指導案の書き方や個別指導)が,指導計画立案や指導場面に役立っていたと認識している学生が9割いることから,教育実地研究Ⅱそのものが評価されていることも成果の一つと受け止められます。
しかしながら,学生が作成した学習指導案の全体的傾向及びアンケート調査から,次のような課題も見えてきます。
- 少人数指導の拡充
学習指導案検討会は個別(グループ別)に実施した。「教材研究の仕方」や「学習指導案の書き方」は全体指導で行った。よりきめ細かな指導を行うために,これらの指導も少人数で行うことができるかどうかを検討したい。 - 学習指導案細案の提出数
本年度は二つの学習指導案細案の提出を課した。次年度は学部3年生の他に,教育職員免許取得プログラム院生の学習指導案も同時期に点検することになる。提出すべき学習指導案を「二つ」とするか「一つ」とするかを検討したい。 - 教育実習の手引きの改訂
9割以上の学生が参考にしていた本学の「教育実習の手引き」はA4版サイズ,145ページである。服務・勤務など概括的な内容が多く,学習指導案の書き方は簡略となっており,しかも作成から数年を経過している。これを徐々に改訂していきたい。 - 参考資料の充実
学習指導案を作るうえで参考になりそうな書物等の資料を充実させていきたい。