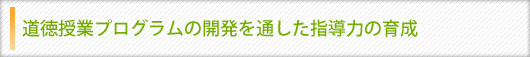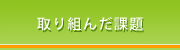
開発プログラムの概要(平成17年度第1学年)
■プログラムの概要
学級担任との初回打ち合わせ時に、提供できる授業内容を数種類提示した。研究発表会の際に配布された資料に、年間計画と主題配列表が含まれていたことに対する配慮であったが、授業内はすべて大学研究チーム側で決するという合意に至った。そこで1 年生部会で話し合った結果、現職院生天野が提案した第1〜3 回の授業の内容で行う方針が決められた。第4 回についてはそれまでの流れとともに、それぞれの院生の修士論文の方向性から興味の持てる内容が出てきた場合につめることとした。
結果的には特段の提案はなされず、第4 回も現職院生天野の提案で内容が決定した。それら授業内容の概略は以下の通りである。それらは事前に学級担任に学習指導案の案として提出し、承認を得たことを付言しておきたい。
表 授業内容の概要
| 実践回 | 時数等 | 内容の概要 |
| 第1回授業 | (事前授業)1 | どんな一字を選んだのか、仲間との発表・質問による交流 |
| (本授業)2 | 自分の人生の「これまで」「これから」を漢字一字で表現する「書」 | |
| (事後授業)2 | 自分の「一字書の作品」にあった飾りつけを行い、思いを語る発表会 | |
| 第2回授業 | 1 | いのちと規則のモラルジレンマ対話 |
| 第3回授業 | 1 | 悩む仲間に声をかけるモラルスキルトレーニング |
| 第4回授業 | 1 | 左右対称性から自分の身体を見つめなおす |
■4 回の授業における抽出生徒の学びのねらい
表 授業ごとの抽出生徒分析場面
| 授業回数 | 抽出男子A分析場面 | 抽出女子B分析場面 |
| 第1回事前 | ・選んだ一字を発表する仲間の話を十分に聞くことができるか | ・自分が選んだ一字を仲間に対して素直に説明できるか |
| 第1回 | ・仲間による一字書製作の様子を共感的に見ることができるか | ・一字書を自分が選んだ理由に素直に向き合って製作できるか |
| 第1回事後 | ・友人が自分の作品について説明するのを十分に聞くことができるか | ・学級全員の前で、自分の一字書について話すことができるか |
| 第2回 | ・ジレンマ対話で自分が話していないときに、仲間と指導者の対話を十分に聞くことができるか | ・指導者に対して自分の考えを素直に述べられるか |
| 第3回 | ・仲間が発表した声がけスキルを共感を持って見ることができたか | ・仲間の前で自分が考えた声がけを素直に発表できたか |
| ・スキルトレーニングであつかう、悩みを抱えた2人の生徒の「悩み」の内容は、抽出生徒の抱える問題を反映させ、再構成したものである。そこから自分に対する気づきなどについて、授業ワークシートへの記入からも分析する | ||
| 第4回 | ・悩みを抱える周囲の人の存在に気づくことができるか | ・悩みも含めた自分を見つめ直すことができるか |
開発プログラムの概要(平成17年度第2学年)
■2年生学級の事態
2年生は15名であるが、1名が長期欠席状態である。小集団で人間関係が固定しているという特徴は、1年生とも共通する点である。
■2年生部会の構成員
主として下記の4名が授業運営に関わった。
| 氏名 | |
| 安保 惟子 | 学卒院生 |
| 久保田 雅樹 | 現職研究生 |
| 林 泰成 | 大学教員 |
| 矢川 咲子 | 現職院生 |
■プログラムの概要
2年生の実践は、自尊感情を高めることをねらいとして4時間のプログラムを組んだ。ただし初回の授業は、1学年の書の授業に合流することとした。その理由は、「これまでの自分」「これからの自分」を1文字の書で表現するという活動は、まさに自尊感情を高める活動であると判断したためである。
| テーマ | |
| 第1回授業 | 自分のこれまで、これからを一字書で表現してみよう。 |
| 第2回授業 | 自分自身を見つめ直そう(構成的グループ・エンカウンター) |
| 第3回授業 | あなたもわたしもカウンセラー(傾聴訓練) |
| 第4回授業 | あなたならどうする?(ペープサートによるロール・プレイ) |
第2回目は、自尊感情を育み、人間関係を作るのに効果があるとされている構成的グループ・エンカウンターのエクササイズから、「四面鏡」を実施することにした。第3回目は、傾聴訓練のごく初歩的なものを実施することにした。これは、聞き上手になるというだけでなく、きちんと話を聞いてもらえたときの気持ちよさを生徒たちに体験させることが第一のねらいであった。というのは、自尊感情を高めるには、受け入れられ体験が必要だと考えられるからである。第4回目は、天使と悪魔のぺープサートを用いて、心理的な葛藤場面を体験させるエクササイズを行う。これは、道徳的な判断力をつけるためではなく、ありのままの自分の思いを表現することで、自己受容を促すためである。
■評価
このプログラムの効果を測定するために、事前/事後に、自尊感情テストを実施する。
全授業をビデオ撮りし,質的な分析を行う。