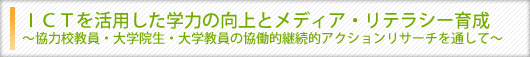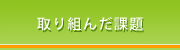
取組実績と課題
4. <メディア・リテラシー育成>についての協働の経緯
ICTを活用したメディア・リテラシーの育成を総合的な学習の時間の授業の中に位置づけて取り組んできた。平成17年度は環境教育,平成18年度は食育を題材とした授業の中に受け手を意識した情報の発信や表現・コミュニケーションを意識した学習活動を組み込み,チームティーチングやティーチングアシスタントのかたちで協働に取り組んだ。
(1)単元名
「自然大好き!げんきっ子」〜自然とともに生きる生き方をみんなに伝えよう〜
(2)単元の目標
身近な自然環境の様々な問題に興味をもち、調べたり取材したりする中で、自然環境を守るために自分たちのできることを考え、伝えたい情報をビデオで発信することができる。
(3)単元について
児童は、国語の単元「ニュース番組作りの現場から」で、ニュース番組作りの仕組みを知り、情報を発信するためには、内容や伝え方に相手を意識した工夫が必要であることを学んだ。また、社会の単元「放送局のはたらき」では、放送局を実際に見学した。資料を調べたりした中から、たくさんの人々の手で情報が「正確に、早く、分かりやすく」伝えられることを学んだ。
総合学習では、児童は「自然大好き!げんきっ子」をテーマに、身近な自然環境に関して学習を進めてきた。それらを学ぶ中で、人々の暮らしが大きな影響を与えていることに気付くことができた。そこで、生き物の命である川や水が、人々の暮らしの中で汚されている現状や地球温暖化の問題、地域の自然環境を課題として追求することにした。活動を進めていく中で、地域の人や専門家、関係する会社の人々等、様々な人との関わりが必要である。人々の意見を生かした教材や資料を上手に集める工夫も必要である。そして、集めた資料やデータから自分たちが伝えたいことを映像化するために考えることになる。また、自分たちが実際にできる勝度を考え、自分たちの考えの入った提案性のあるニュース番組作りを目指す。時間を3分と決め、ニュース番組形式にすること、「伝えたいこと」をしっかりと短いビデオの中で、伝えるように工夫する。
(4)単元の指導計画(全20時間)
| 事項 | 時間 | 活動内容 | 支援 |
| 1.課題をもつ | 3 | ○総合的な学習の時間の活動で、自然環境とふれあってきたことから、学習課題をもつ。(1) ・川の水質調査から考えること ・自然教室での体験から考えること ・身近な自然環境問題から考えたこと |
・自然の中での体験したことを振り返る資料を提示する。 |
| ○身近な自然環境問題について調べてみたいことについて話し合う。(1) ・「川の汚れ」汚れの原因、家庭排水について ・「ゴミの問題」ゴミの分別、粗大ゴミ、ゴミの捨て方 ・「地球温暖化」温暖化の原因と対策 ・「エコについて」エコに関わっている活動 |
・図書館活用 | ||
| ○課題について調べる方法・取材方法を考える。(1) ・図書館の資料・本,インターネット ・地域の人、関係の会社の人に、メール、電話、直接話を聞く、取材など |
・コンピュータ活用 |
||
| 2.追求する | 13 | ○課題別グループごとに調査活動をする。(3) ・取材するための方法や手順を確認する。 ・調べた内容をどのようにまとめていくか考える。 |
|
| ○調査した結果から必要な資料を作成する。(3) ・調査したデータを整理編集する。 ・調査結果について考える。 |
|||
| ○調査した結果から必要な資料を作成する。(3) ・調査したデータを整理編集する。 ・調査結果について考える。 |
|||
| ○ビデオ編集の仕方を学習する。(1)※ ・ビデオの取り込み方 ・文字の入れ方 ・つなぎ方 |
|||
| ○資料をもとに、ビデオを撮影する。(2) ・班毎に役割分担を行う (プロデューサー、アナウンサー、カメラマン) ・3分間で伝えたい内容をシナリオにする。 ・正確にわかりやすい内容になるように撮影する。 |
・ビデオ編集の操作を教わる | ||
| ○ビデオ編集を行い、ニュース作りをする。(2) ・撮影したビデオを用いて編集する。 ・必要な文字、効果音等を入れて、見やすい映像を作る。 |
・伝えたいことを表現する方法を援助する。 |
||
| ○ニュース番組を完成する。(1) ・情報に間違いはないか、見やすいニュースになっているか確認する。 |
|||
| 3.振り返る | 4 | ○身近な自然環境問題について振り返る。(2) ・自分たちの課題が明確にニュース番組として表されているか確認する。 |
|
| ○発表会を行う。(2) ・互いの番組について学年全体で情報交換しあう。 |
※上越教育大学の大学院学習臨床コース情報教育分野の大学院生が学習支援を行う。